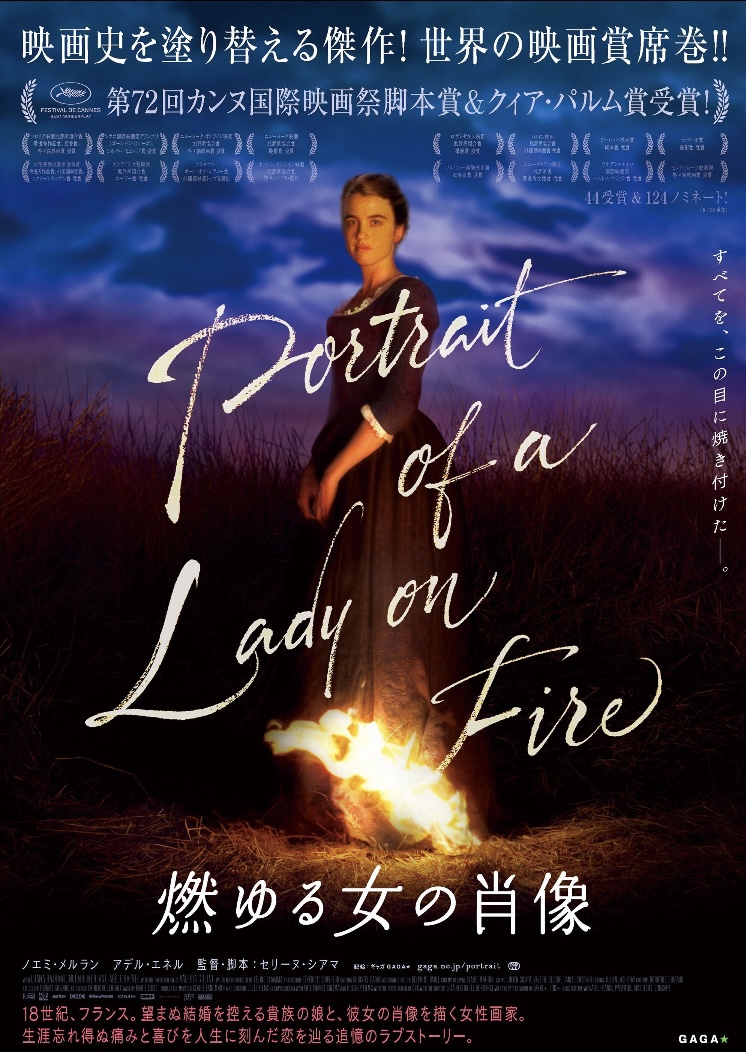みなさんこんにちは。ナガと申します。
今回はですね映画『火口のふたり』についてお話していこうと思います。

ロマンポルノの脚本として活躍し、最近は監督も務めるようになった荒井監督。
年末になると、彼が編集を担当している「映画芸術」のぶっ飛んだ年間ベスト・ワーストランキングが発表されて、映画ファンの間でも賛否両論になる光景は珍しくありません。
ただ、個人的に脚本力には定評があると思っていますし、2017年の『幼子われらに生まれ』なんかは称賛に値する内容と思います。
一方で、荒井監督作品で一番知名度が高いのは、実は『海を感じる時』ではないかと思っています。
おそらくこの作品が結構『火口のふたり』と似たテイストだと思いますし、「オシャレAV」としてもなかなかのものなので、意外と男性諸君は興味本位で見たことがあったりするんじゃないかと思います。
そんなR18指定対象にもなっている本作を早速鑑賞してきました。
本記事は作品のネタバレになるような内容を含む感想・解説記事となっております。
作品を未鑑賞の方はお気をつけください。
良かったら最後までお付き合いください。
目次
『火口のふたり』
あらすじ
賢治と直子はかつて身体を重ねる関係だったが、賢治が結婚することになり、その関係も終わってしまった。
その後、賢治は結局妻と上手くいかなくなり、最後は自身の浮気が原因で離婚する運びとなる。
それから数年が経過したある日、賢治は父親から直子が結婚するので故郷の秋田に戻って来いという知らせを受ける。
両親も既に暮らしていていない実家に戻ると、そこに直子がやって来る。
結婚後の新居のための家電購入に付き合わされるという何気ない要件だったが、2人は思わず身体を重ねていた頃の関係を思い出してしまう。
そしてその夜、直子は彼を「今夜だけ、あの頃に戻ってみない。」と誘い、2人は数年ぶりに身体を重ねる。
忘れていた快感が蘇り、2人は激しく求めあうのだが、翌朝になると、その関係は再び終わってしまった。
しかし、家に戻り1人でいると、賢治は直子を抱きたくて居ても立っても居られなくなり、そして再び彼女の家に向かうと、身体を求めた。
直子は、夫が結婚式のために自宅に戻って来る数日の間だけ一緒にいても良いという条件を出し、2人は再び「あの頃」に戻っていくのだった・・・。
スタッフ・キャスト
- 監督:荒井晴彦
- 原作:白石一文
- 脚本:荒井晴彦
- 撮影:川上皓市
- 照明:川井稔 渡辺昌
- 編集:洲崎千恵子
- 音楽:下田逸郎









基本的に脚本としてクレジットされることが多いので、監督として映画に携わっている機会はそれほど多くないであろう荒井晴彦さん。
彼が監督を務めた『この国の空』は結構賛否両論あった印象ですが、個人的にはそれほど悪い印象はなかったですね。
戦時中に身体を激しく求めあうような情熱的な恋に落ちる男女の物語を描いていて、戦争映画としてはかなり斬新な切り口でした。
今作『火口のふたり』は題材的には近いところがあるので、荒井監督の得意分野だと思います。
その他の撮影、照明、編集、音楽等のスタッフ陣も『この国の空』から継続して起用されていて、荒井監督のお気に入りが集結したという感じなんでしょうか。
ただあの作品を作り上げたスタッフ陣ということは、濡れ場描写については定評があるということでしょうし、その点では期待が持てる陣容だと思います。
- 永原賢治:柄本佑
- 佐藤直子:瀧内公美









『アルキメデスの大戦』や『居眠り磐音』など今年に入ってからも話題作に継続的に出演している柄本佑さん。
そんな彼が、今作では濡れ場全開のR18指定映画に挑みます。
ちょうど『居眠り磐音』で共演していた松坂桃李さんも昨年『娼年』という映画に出演していて、全編濡れ場みたいな内容だったので、ある種の登竜門だったりするのかな?とも思いました。
そしてヒロインを担当するのは、瀧内公美さんですね。
主演を務めた『彼女の人生は間違いじゃない』という作品で大胆な脱ぎっぷりを見せてくれた女優ですが、今回さらに脱ぎっぷりがエスカレートしてますね。
その少し陰がある雰囲気が体当たり的な演技に良い方向に働いていて、不思議なエロスを感じさせる稀有な女優でもあると思います。
より詳しい情報を知りたいという方は、映画公式サイトへどうぞ!!









『火口のふたり』感想・解説(ネタバレあり)
荒井監督らしさ全開の物語
今作『火口のふたり』を見て、とにかく荒井監督らしさ全開だなと思いました。









『この国の空』については良い脚本が書けたのに、それを監督してくれる人が見つからなかったということで荒井さんが自らメガホンを取ったという経緯があるようです。
そして今作『火口のふたり』は、『この国の空』にプロットもテーマも非常に似ています。
『この国の空』は戦時中に深い関係に落ちてしまった一組の男女の物語なんですが、彼はこれについて「戦争が終わって嬉しくないと思った女の子を撮りたかった」と述べています。
もちろん戦争に賛美的な映画を撮りたいという意図ではなく、戦争がそうさせてしまったという形で反戦的なメッセージには繋がっている作品です。
それを現代を舞台にした物語に落とし込んだのが『火口のふたり』という作品ですし、戦争が震災(ない富士山噴火)に置き換えられています。
今作も、2人の関係性というのは直子の夫が家に戻ってきた瞬間に終わりを迎えてしまいますよね。









血の通った人間というよりも、どこか無機物的な印象を与える「自衛隊」という言葉は、彼らにとって身体関係のフィニッシャーとして君臨しています。
2人は終わってしまうと分かっているからこそ、「あの頃」に戻り、必死に身体を求めあいます。
彼らは「富士山の火口」の写真に象徴される「あの頃」の幸せな日々を刹那的な時間の中で永遠に過ごそうとするのです。
しかし、時間は刻一刻と迫り、そして夫が家に戻って来る日がやってきます。
そんな折に、富士山の噴火の予兆が現れ、彼女の夫は極秘任務のために結婚式を延期し、家を離れていきます。
終わりを迎えたはずの2人の関係ですが、「自衛隊」が再び遠ざかったことにより、三度「あの頃」を取り戻す機会を得ます。
そして2人は、白黒写真に鮮明に刻み付けられた、建物の間の小さな路地で野外プレイに及びます。









2人が野外プレイに及んでいる最中に、塾帰りの少年少女に路地を覗かれてしまい、賢治は恥ずかしくなって、行為を終わらせて、その場から去ろうとします。
このシーンは確かに2人の関係性の変化を予期させるシーンです。とりわけそれを印象づけるのが「子供」という存在だったところにも注目すべきかもしれません。
その翌朝、富士山は噴火してしまいます。富士山が噴火すると、火口が斜面の別のところに新たに作られるんだと語る2人。
日本が未曽有の大災害に襲われる中、2人は身体を重ねます。
そしてこの映画の最後に2人は「中出し」つまり子作りのためのセックスに及ぶことになります。
その少し前に、賢治が「中出し」の可否を尋ね、それを笑いながら直子が拒否するというシーンがありました。
つまり、本作のラストで2人の関係性は確かに変化しています。
富士山の美しい姿が崩壊し、そして新たに火口が作られるが如く、2人はかつて心中した火口から飛び出し、新たな火口へと飛び込まんとしているのです。
荒井監督は『この国の空』のインタビューの中で次のように語っていました。
爆弾でいつ死ぬか分からない中での里子のロストバージンの話です。彼女には“終戦から始まる戦いがある”ということです。
(『この国の空』荒井晴彦監督インタビューより引用)
きっと富士山が噴火するなんて事態が起こらなければ、直子は自衛隊勤務の夫と子をもうけ、不自由なくささやかな幸せを享受する人生を送ることができたでしょう。
しかし、噴火が起こってしまい、東京の首都機能は停止してしまい、日本は未曽有の危機に晒されることになりました。
そこで、2人は「噴火から始まる戦い」を迫られることになるわけです。
これまではただひたすらに後ろを振り返って「あの頃」を取り戻そうとしていた2人ですが、路地裏での野外プレイが中断させられたが如く、2人はもう「これから」を見つめなければならない段階にいました。
日本が混乱し、首都圏では多くの人が命の危険にさらされる中で、2人は子供をもうけるための行為としてのセックスに及びます。
それはまさに2人が「未来」を見据えたことの象徴であり、同時に日本全土に「死」のイメージがつきまとう中で高らかに「生」を叫ぶ行為なのです。
震災映画としてのコンテクスト
荒井監督は先ほども指摘したように『この国の空』では、戦争という題材を選びました。
そしてそれを今度は震災に置き換えて、現代の男女の物語として作り替えたとも言えるでしょう。
東日本大震災以降、それを題材にした映画はたくさん作られていますが、どの映画もその向き合い方は微妙に異なります。
とりわけ『この国の空』で、ヒロインの里子が「戦争が終わってしまうと、同時に終わりを告げる恋」に落ちてしまうというプロットが戦争賛美に繋がるという批判にさらされたわけですが、今作も見方によれば、同じような批判ができてしまいます。
つまり、賢治と直子の関係というのは、日本が富士山噴火という未曽有の災害に襲われたからこそ続いたものであり、2人がその関係を臨むことが、災害に対して好意的な目線にも取れるというわけです。
今作を見ていると、震災に絡めたいくつかの印象的なセリフがあります。
特に個人的に印象的だったのは、「被災者になったふりは出来ても、被災者にはなれない。」というものです。
これがすごく胸に突き刺さったんですが、やっぱり私たちは未曽有の大災害がどこかで起きていて、その映像を見ていたって自分がそこにいたかのように想像することはできても、当事者になれるわけではありません。
被災者の悲しみや苦しみを想像することはできても、その感情を自分のものにすることは決してできないんです。
荒井監督は常に映画は無力だと語っています。それは反戦映画がいくら作られようと、戦争が無くならないのと同じです。
そんなフィクションとして震災を後世に伝えていく必要があるという映画の役割と、そして映画というメディアに監督が感じている無力感がぶつかり合っているようなそんな印象を受けました。
彼は『この国の空』のインタビューの中で次のように語っていました。
「戦争が終わるのを望まない女もいた、そのこと自体が戦争がもたらす不幸だ」
(『この国の空』荒井晴彦監督インタビューより引用)
こういう言葉を読むと、本作もすごく逆説的にリアルを描いていたんじゃないかと思うんです。
確かにフィクションとしては、震災に立ち向かう映画、誰かに共感性を示し、助け合うようなテーマが「震災映画」のコンテクストにふさわしいのは明白です。
ただ荒井監督は、フィクションとしてあえて、リアルを志向し、震災を前にしても何もすることができない多くの人々の中から1つのサンプルを映画化したようでもあります。
最後に賢治は自分の「身体の言い分」に従って本能のままに生きようと決意します。
それに加えて、彼らの身体の関係が続けられるのも、大災害のおかげであるというのもに皮肉が効いています。
「被災者になったふりは出来ても、被災者にはなれない。」のであれば、私たちはそれを傍観する立場から本能のままに生きていくしかないという無力感と退廃的な雰囲気を監督は本作のラストに閉じ込めました。
しかし、彼の本当のメッセージは逆説になっているはずです。
私たちは、当事者になれなくたって、被災者に共感的になり、何か行動を起こさなければならないはずです。
ただ、私自身も含めて結局は自分の生活こそが大切なのであり、本当に自分たちが同じ立場に置かれるまでは決してその苦しみを想像できないのです。
そういう私たち自身が震災に対して抱えている無関心や無力感を『火口のふたり』という作品は突き付けてくるような鋭さがありました。
震災映画としては斬新でかつ、とても鋭い切り口になっていたと思います。
おわりに
いかがだったでしょうか。
今回は映画『火口のふたり』についてお話してきました。
鑑賞前は「オシャレなAV 」だとか何とか言っていましたが、テーマや震災に対する向き合い方はすごく誠実だと感じました。
また、ロマンポルノを長らく手掛けているスタッフ陣の作品ということで、濡れ場は素晴らしい出来栄えですね。
これを映画館で見られるというだけでも、すごく価値があると思いました。









今回も読んでくださった方、ありがとうございました。