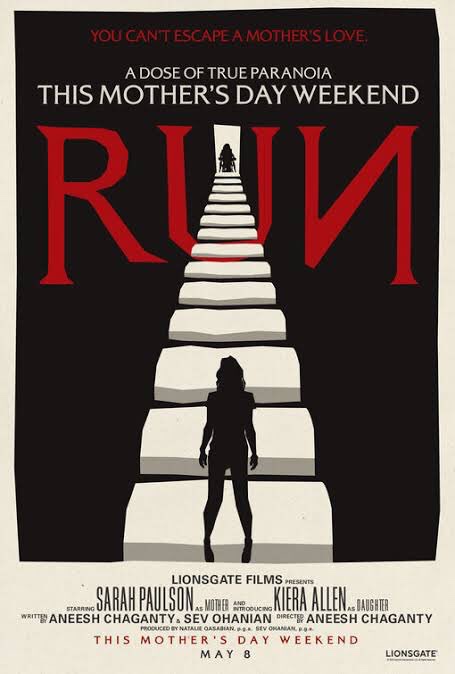みなさんこんにちは。ナガと申します。
今回はですね映画『ジョーカー』についてお話していこうと思います。

ベルリン国際映画祭にて最高賞にあたる金獅子賞を受賞し、多くの人の心を掴み、そして賛否両論を巻き起こしている問題作『ジョーカー』。
映画本編を見た今となっては、なぜ本作が、というよりもたった1本の映画がこれほどまでに社会に鮮烈なインパクトを与えたのかが痛いほどに理解できます。
この作品はアメリカという国ないし土壌があったからこそ生まれた作品だといっても過言ではありません。
『ジョーカー』という作品が生まれる背景を考えるにあたっては、アメリカという国がどういう経緯で生まれたものなのかという点から語っていく必要があるでしょう。
それほどまでにアメリカという国の本質と現状を浮き彫りにした問題作と言える今作を、今回は徹底的に解剖していきたいと思います。

















本記事は作品のネタバレになるような内容を含む解説・考察記事となっております。
作品を未鑑賞の方はお気をつけください。
良かったら最後までお付き合いください。
『ジョーカー』
あらすじ
大都会で大道芸人として生きるアーサーは暗い社会の中で人々に笑いを届けようと「ピエロ」として街頭や施設で活動していた。
しかし、ゴッサムは疲弊しており、死の衛生局がストライキへと突入したことで街は荒れ果て、腐臭を漂わせていた。
毎日のように街ではパトカーが行き来し、貧困のどん底で暮らす者たちは暴力の狂気へと身を落としていった。
アーサーはそんなゴッサムで何とか「ピエロ」として活動を湯づけていこうとするが、ギャングの子供たちからの暴力の憂き目にあうなど、厳しい現実を突きつけられる。
さらに護身用にと同僚から手渡された拳銃を小児病院の子供たちの前で落とすという事故を起こしてしまい、仕事を解雇される。
それに追い打ちをかけるように、彼の心の支えになっていた市のカウンセリングや薬品の処方も終わってしまう。
そんな絶望に打ちひしがれながら自宅へと向かう電車に乗り込んだアーサーは、3人のエリートビジネスマンたちに絡まれ、暴力を振るわれる。
その時、彼の中で何かが崩壊し、咄嗟に懐に忍ばせていた拳銃で3人を撃ち殺してしまう。
さらに精神を病んだ母ペニーは、市長選に立候補した大富豪トーマス・ウェインが、アーサーの父であるという妄言か現実か分からないことを口にするようになる。
現実と虚構の渦の中で確かに、アーサーの中で何かが大きく変わろうとしていた・・・。
スタッフ・キャスト
- 監督:トッド・フィリップス
- 脚本:トッド・フィリップス スコット・シルバー
- 撮影:ローレンス・シャー
- 美術:マーク・フリードバーグ
- 編集:ジェフ・グロス
- 衣装:マーク・ブリッジス

















トッド・フィリップス監督は、やはり全米で大ヒットしたコメディ映画『ハングオーバー!』で有名ですよね。
ただ彼のフィルモグラフィーを見て見ると、『全身ハードコア GGアリン』のように薬物による幻覚と狂気に苛まれた人間の姿を描いた作品があります。
そういう意味では、彼は確かに今作『ジョーカー』に向けて自身のキャリアを積み上げてきたのかもしれません。
撮影には、先日公開された『GODZILLA キングオブモンスターズ』や『ハングオーバー!』シリーズで知られるローレンス・シャーが起用されました。
編集のジェフ・グロスも過去にトッド・フィリップス監督とタッグを組んだ経験があり、かなりスタッフ的にはコメディ映画寄りな陣容となっています。
- アーサー・フレック/ジョーカー:ホアキン・フェニックス
- マレー・フランクリン:ロバート・デ・ニーロ
- ソフィー・デュモンド:ザジー・ビーツ
- ペニー・フレック:フランセス・コンロイ
- ギャリティ刑事:ビル・キャンプ
- バーク刑事:シェー・ウィガム
- トーマス・ウェイン:ブレット・カレン

















主演のホアキン・フェニックスは特異な経歴の持ち主だと思います。
『グラディエーター』や『サイン』、『ウォーク・ザ・ライン/君につづく道』など話題作に次々に出演し、アカデミー賞やゴールデングローブ賞などでも高く評価されました。
しかし、後に義弟ケイシー・アフレックのドキュメンタリー映画『容疑者、ホアキン・フェニックス』に出演するためだと判明しますが、突然の歌手転向やメディアでの奇行で注目と批判を浴びました。
そこから何とか俳優へと復帰し、『ザ・マスター』や『インヒアレント・ヴァイス』などで再び高く評価されるようになりました。
こういう俳優としては狂ったキャリアを歩んできた彼だからこそジョーカーにふさわしいとも言えるのではないでしょうか。
また、大物コメディアンのマレーを演じたのは、ロバート・デ・ニーロです。
彼が今作にこのような役どころで出演するのは、アメリカンニューシネマの傑作『キングオブコメディ』の影響です。
彼がこの作品で演じたルパード・パプキンという幻想と現実の境界があやふやな男が、おそらく時を経て、今作『ジョーカー』の役どころにリンクしているのでしょう。
より詳しい情報を知りたいという方は、映画公式サイトへどうぞ!

















『ジョーカー』解説・考察(ネタバレあり)
建国時から続くアメリカのDNA
『ジョーカー』という作品を読み解いていくためには、アメリカという国の歴史と社会をある程度解体していく必要があるように思います。
本作におけるジョーカーという狂気のキャラクターを生み出したアメリカという土壌にどんな背景や現状があるのかを理解しておくことは非常に重要です。

















もちろん世界史の教科書でも触れられている部分ではあり、イギリス本国から移民した人たちが作り上げた国だというのが一般的に知られている情報でしょう。
そこを深く探っていきますと、まず16世紀の終わりにイングランド王室で働いていたリチャード・ハルクートという男がアメリカ大陸についての様々な報告書を読み、そしてアメリカ大陸に幻想を持つようになりました。
彼は北アメリカ植民の熱烈な唱道者となり、「北アメリカ大陸には金銀やその他宝石が山ほど眠っており、先住民が住んでいるものの彼らは従順でしかも人口密度は少ない」などととにかく事実を確認もせず妄想だけで報告書を作り上げていきました。
それが敬虔なプロテスタントであり、冒険家でもあるウォルター・ローリーの目に留まり、彼は旅行・探検・植民目的での新世界(アメリカ大陸)への航海を敢行しました。
では、ウォルター・ローリーの派遣した探検隊はどうなったのかと言うと、結局2度にわたって大陸に送り込んだものの全滅という惨状でした。
それでも彼は、2度の失敗にも関わらず、イングランド国内では、アメリカ大陸は黄金都市エルドラドであるという幻想を吹聴し、それを宣伝するために本を執筆したりもしています。
これがイングランドからアメリカ大陸への移民の発端であり、しかもそれが極めて虚構や幻想に裏打ちされて行われたものであることが明かされています。
その後、国を挙げての移民が推進されるなんてこともありましたが、悉く失敗に終わっており、それにも関わらず、国内では「アメリカ大陸=楽園」という幻想に憑りつかれる人が後を絶たないという異常な事態でした。
哲学者のフランシス・ベーコンは当時のアメリカ大陸に対する熱狂と現実を鋭く分析しており、以下のように述べました。
人間の知性は、いったんある意見を採用すると(一般に受け入れられている意見であれ、自分が賛同できる意見であれ)、ほかのあらゆるものを引っ張り出して、その意見を擁護するようになる。それを否定する重要な事例がいくつも見つかったとしても、それを無視・嫌悪するか、何らかの違いを持ち出して除外・拒絶する。こうした巧妙かつ悪質な態度により、先に採用した意見の権威が損なわれないようにしているのである。
こうして虚構と幻想に取りつかれた人が新世界へと熱狂し、現実がどれほど悲惨なものであれど、移民・植民を推し進める状況が続きました。
そしてその後、キリスト教が1つのキーワードとなってきます。
イギリスでは当時、イギリス国教会と呼ばれるプロテスタントの一派が主流になり、カトリックを圧倒するようになりました。
しかし、同じプロテスタントの中にも、体制派となった国教会に異を唱える派閥がありまして、それが俗に言うところの「ピューリタン」と呼ばれる人たちでした。
「ピューリタン」は、バカ正直などの意味で蔑称的に使われていた言葉で、国教会側の人間が、嘲笑的に用いていました。
彼らは、国教会の信徒よりも自分たちの方が信心深いのであると信じており、国教会の意見には一切同意を示さず、仮にそれが極めて合理的なものであったとしても虚構に基づいた難癖をつけて否定するという有様だったと言われています。
そういう行動の結果としてイギリス国内ではピューリタンに対する風当たりが強まり、どんどんと居場所がなくなっていきます。
結果的にイギリス国内での暮らしに絶望した、ある種の狂気的なカルト集団とも言えるピューリタンたちが、ご存知「ピルグリム・ファーザーズ」として北アメリカ大陸にやって来ることとなりました。
彼らは以前に金や宝石目的で派遣されていた探検隊とは異なり、純粋に宗教的な狂気と幻想を抱いて移民してきました。
生活を改善したいですとか、金銀を発掘して富を得たいなどという現実的な野望を持っていたわけでなく、ただ「北アメリカ大陸=神の国」であるという根拠のない幻想を信じて海を渡ったのです。
ここまで少し映画『ジョーカー』の話からは逸れる形にはなりましたが、アメリカの建国に纏わる狂気と幻想のお話をしてきました。
カート・アンダーセンは自身の著書の中で、アメリカがこういった経緯で建国された国であることが、確かに国のDNAとなっており、現代にも脈々と受け継がれているのだということを語っています。
アメリカにおいては幻想や虚構が、現実と同等ないしそれ以上の価値を持って当たり前のように「現実」として存在していると言うのです。
幻想と現実から読み解く『ジョーカー』
『ジョーカー』という作品は、『キングオブコメディ』や『タクシードライバー』といったアメリカンニューシネマの作品に多大な影響を受けています。
とりわけ前者の影響は色濃く、本作もじつに幻想と現実の境界線というものをぼやかしていく方向へと物語が突き進んで行きます。
本作の舞台となったゴッサムとそしてTVショーの関係を見てみましょう。
(C)2019 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved TM & (C) DC Comics
ゴッサムでは衛生局の職員のストライキによりごみが散乱し、貧困層は暴力的になり、毎日のようにパトカーのサイレンが鳴り響くという異常な事態に陥っています。
しかし、テレビをつけて見ると、そんな現実をコメディショーの中で虚構の出来事のように語り、笑いに変えてしまうマレー・フランクリンというコメディアンがいます。
トーマス・ウェインという富豪の男は、自分が市長になるためにメディアでショーを展開しています。
自分は富豪の育ちでありながら、貧困層の痛みが分かるし、だからこそ貧困に苦しむ人たちを救うために市長になるんだという自身のキャラづけをして、ゴッサム市民から受け入れられようとしています。
つまり、今のゴッサムの現実を自分の選挙戦というショー(虚構)の中の一部に取り込んでいるわけですよ。
このように、ゴッサムには危機的な現実の光景が広がっているにもかかわらず、多くの人たち、とりわけ中産階級以上はTVから放送される虚構と現実の区別がつかなくなり、いつしか虚構が現実を超越していきます。
この映画で1つ印象的なシーンがったとすれば、ピエロのお面をかぶった暴徒たちが押し寄せているにもかかわらず、上流階級の人間たちはそんなことに見向きもせず、チャップリンの『モダンタイムス』を見ていたという場面でしょうか。

















外の世界には苦しい現実、貧困、暴力が広がっているにもかかわらず、そんなものには見向きもせず虚構や幻想ばかりに傾倒し、いつしか現実を喪失していくのです。
また、トーマス・ウェインは、「我々の社会からの落第者」のことを「ピエロ」だと呼称しました。
これも現実に存在し、貧困と絶望の中で暴力に走る人たちのことを嘲笑的に「ピエロ」と呼称したわけですが、先ほどお話した「ピューリタン」の話に通じるところがありますよね。

















そうして、虚構や幻想にかまけて現実を見ようとしない、体制派たちに向かってピエロのお面をつけた市民が反旗を翻します。
これはまさに虚構に対する虚構の反乱とも言えますし、幻想しか見ようとしない体制派に対して幻想の世界の産物である「ピエロ」が抵抗するという構図でもあります。
しかし、アメリカ建国史の一連の出来事からも分かる通りで、反体制派の「ピエロ」たちが現実を見ているかと言われればそうではありません。
彼らもまた自分たちこそが正しいのであり、体制派は悪であり、自分たちを搾取しているのだという幻想に踊らされているに過ぎません。
もはやそこに現実と虚構の境界線など微塵も存在していません。
このように映画『ジョーカー』の中で描かれるゴッサムの世界観は、先ほどお話した現実と虚構が同等の価値を持つアメリカのDNAに強く裏打ちされたものなのです。
また、本作の主人公であるアーサーという人物も幻想と現実の境界線を行き来している人物です。
カレは、精神的に病んでおり、向精神薬を服用していることもあってか幻想と現実の区別がついていません。
これは『キングオブコメディ』の主人公であるルパード・パプキンと同様なのですが、アーサーはテレビから流れるコメディショーに自分を投影して妄想したり、見知らぬ隣人が自分の恋人であると錯覚したりしていました。

















完全に彼自身の虚構が現実を超越してしまっており、向精神薬の効果が切れて、ふと現実に立ち返ったときに「ソフィーが恋人である」という事実が幻想でしかなかったことが浮かび上がってきます。
このシーンはまさしくチャップリンの『街の灯』へのオマージュであり、これを幻想や虚構であると位置づけたうえで現実との乖離性を浮かび上がらせるという興味深い演出になっています。
『街の灯』のラストでは、刑務所から出た浮浪者の男はかつて1,000ドルを手渡して目の手術の援助をした少女に再会します。
そして薔薇の花と小銭を手渡した時に、その少女は浮浪者の男が自分を救ってくれた恩人なのだということに気がつきます。
しかし、『ジョーカー』においてアーサーは雨に打ちひしがれ、自分が一番苦しい時に頼った恋人が自分のことを知ってくれてすらいないという悲劇に見舞われます。
『街の灯』のような物語は幻想や虚構でしかなく、現実はもっと厳しいものであるということがここで突きつけられたように思います。
そして彼はゴッサムシティを取り巻く幻想の象徴とも言えるマレー・フランクリンのショーに呼ばれることとなります。
ジョーカーというアンチ・クライスト
(C)2019 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved TM & (C) DC Comics
アーサーはマレー・フランクリンのショーというまさにゴッサムの虚構の中心へと足を踏み入れます。
そして彼は、マレーを手にしていた拳銃で撃ち殺し、その様子を生放送で公開するという蛮行に及びます。
まさに上流階級の人間たちのための上品なコメディ番組という幻想を、彼自身の狂気的な幻想で塗り替えて見せたのです。

















それを考えて見た時に、貧困と絶望にあえぐ人々のために、富裕層の目を覚まさせようとしたというもっともらしい理由が真っ先に思いつくのですが、明らかにジョーカーの行動理念とは一致しません。
では、なぜ彼はマレーを殺害しなければならなかったのかと言うと、それは全て自分自身のためです。
彼が母親を殺害するに至った経緯を思い出してほしいのです。
アーサーは母親を信じていますし、自分のことを育ててくれた彼女のことを心から愛していました。
しかし、信じていた母の愛は全て幻想でしかなかったことが判明してしまいます。
彼は養子であり、しかも自分は母とそして父によって虐待されており、その際に脳に障害を負い、笑いが止まらなくなったのだということが分かるのです。
その事実に絶望した彼は、母親に対して激しい憎悪を覚え、病室で殺害してしまいます。
人は最初から最後まで不幸であれば、きっとそれが不幸なのだと気がつかないままで生きていくことができます。
しかし、アーサーは自分が母親から愛されているのだというハッピーな「幻想」を一度見てしまったんですよね。
そんな幸せな幻想を見せられてしまったがばっかりに、彼はそれを失うことに深い絶望と悲しみ、怒りを感じたわけです。
クリストファーノーラン監督の『ダークナイト』を思い出してみてください。
この作品において、ジョーカーはハービーデントというゴッサムの正義のアイコンを悪の道に叩き落すことで、私たちが信じる幻想がいかに脆く壊れやすいものなのかということを示しました。
つまりアーサーないしジョーカーは自分に期待をさせ、生ぬるい幻想を見せる存在に対して激しい怒りを覚え、それを壊すことで自分は初めて現実に生きることができると考えたのではないでしょうか。
そして自分の母親を殺害したのと、全く同じ理由で、自分に幻想を見せながらも、その実は自分のことを嘲笑っていたマレー・フランクリンという男を殺害します。
先ほど長々と書いたアメリカという国の成り立ちの中で、キリスト教の中のピューリタンと呼ばれた人たちが建国のパイオニアになったことをお話しました。
アメリカという国の根底には、建国当初からキリスト教という幻想への信頼があります。
それはピルグリム・ファーザーズを初めとするピューリタンたちが「北アメリカ大陸=神の国」だと信じて、苦難を承知で何の合理性も計画もなく移住してきたことからも明白です。
フランスの哲学者ジョルジュ・バタイユは、キリスト教というものの性質について自身の『反キリスト教徒の心得』の中で次のように語っています。
キリスト教は、現実と理想とをわけ隔てていた深淵の上に架けられた橋である。救済の福音の諸神話、すなわち、神の子の受肉と、十字架上の死による原罪のあがないとは、哲学が虚ろなままに放置してきた空隙をみたした。
(中略)
こうして、キリスト教の「真実」は、他に類を見ない信念の力を具えて、うむを言わさないものとなったのである。
(ジョルジュ・バタイユ『反キリスト教徒の心得』より引用)
この指摘が非常に的確で、まさしくキリスト教が現実と虚構の境界を崩壊させる方向へと働いた結果が見事にアメリカの建国の経緯にも繋がっています。
本作のアーサーの設定には父親がいないというものがあり、その点でペニーが聖母、アーサーがイエスキリストなのではないかと想起させるように仕向けてあります。
しかし、実際は彼は養子であり、母親は聖母などという言葉からは程遠い人間であったことが判明します。そしてアーサーは母親を殺害するわけです。
この一連の行動が既にアンチクライスト的なのですが、そこに先ほどまで語ってきた「幻想の否定」というコンテクストが重なって来ることで、その意味合いが一層増していきます。
ジョーカーはカリスマ、王、神、イエスではない
さて、ここまでの解説から、ジョーカーとは何者なのかという核心に自分なりの考察を加えていこうと思います。
先ほど、ジョーカーというキャラクターが極めてアンチクライスト的に作られているということを、アメリカの建国史との関連や彼自身の設定の中で指摘しました。
本作のラストで、ジョーカーは乗せられていたパトカーに暴徒化した市民が運転する救急車が激突して意識を失います。
しかし、ピエロのお面をかぶった市民たちは、彼の復活を願い「立て!」と祈り続けます。
すると、彼は意識を取り戻し、車の上に立つと、いつものようにステップを踏み、踊り始めるのでした。
この光景が明らかにイエスキリストの復活を想起させるように作られているのが、また憎い演出なのですが、これが大きなミスリードだと感じました、
本作のラストが、仮に悪のカリスマジョーカーが誕生し、反体制派の人々の王になるという話なのであれば、それは明らかにジョーカーというキャラクターの存在意義と矛盾を生じます。
なぜなら、ジョーカーは幻想や虚構を信じることに裏切られたという悲劇を経験したキャラクターだからです。
そんな彼が、悪のカリスマとして君臨し、自分が悪のイエスキリストになり、反体制派の人々を導いていくなんて明らかに矛盾しているわけですよ。
しかも、彼は冒頭に自分同様の貧困層のギャングから暴力を振るわれるという経験をしているわけですから、そんな人たちの味方をするはずがないじゃないですか。
(C)2019 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved TM & (C) DC Comics
トッド・フィリップス監督はその辺りをきちんと理解したうえで終盤の2つのシーンの構成を実に巧妙に作り上げています。
まず、反体制派の人々がジョーカーを「悪のキリスト」だと崇めるシーンは、アメリカという国に対する痛烈な皮肉でもあります。
幻想や虚構に現実と同等の価値を見出して信奉するアメリカの根底に組み込まれたDNAは、仮に1つの大きな幻想や虚構が潰えたとしても終わることはないのだということを示しているように思えます。
つまり幻想と虚構ばかりを見て、現実を見ない富裕層を批判し、それらを打倒しようと動き出した反体制派の貧困層とて、結局は「ジョーカー」という幻想に踊らされるだけなのです。
彼らはカートアンダーセン氏が指摘した「狂気と幻想のファンタジーランド」としてのアメリカから抜け出すことはできていません。
しかし、ジョーカーは違います。それは彼だけがお面や装飾品ではなく、直接顔や髪をピエロ仕様にしてあるというギャップに現れています。
彼は幻想が幻想にすぎないのだということを知っています。そしてもはや幻想を信じるということをするつもりもありません。
ただ、彼はそんな幻想に裏切られた自分自身という悲劇をも自分の一部として取り込んでしまっているのです。
彼を崇め奉る人は現実と幻想の区別がついておらず、仮面をかぶり、そんな虚構が現実と等価値なのだと信じています。

















そしてトッド・フィリップス監督が実に巧妙だったのが、2つ目のアーサーが精神病棟に収容されて、カウンセリングを受けているシーンです。
このシーンが実にコメディ的であり、寓話的であるからこそ、私たちは、その直前に見せられていた「悪のカリスマ」「悪の王」「悪のイエスキリスト」という幻想を綺麗に裏切られるのです。

















そしてそんなジョーカーをキラキラとした目で見つめていた自分がいることにハッと気づかされ、恐ろしくなります。
本作『ジョーカー』が恐ろしいのは、私たちの誰もがジョーカーになる可能性を炙り出したことではありません。
そこを描きたいのであれば、終盤のジョーカーが群集の中心で踊るシーンは、ジョーカー自身の視点のアングルにするはずです。
しかし、この映画は踊る彼の姿を群集の背後から捉えています。視点は群集側にあるということです。
つまり今作が恐ろしいのは、誰もがジョーカーという幻想を信奉する可能性を秘めているという恐ろしさを突きつけたからなんです。
アメリカという国が、ピューリタンたちのキリスト教への狂信的な信奉から生まれた国であるように、もしかするとジョーカーのような「悪のイエスキリスト」的立ち位置のアイコンが登場すれば、人々は同様に信奉するのではないかという恐怖は確かに存在しています。
今、アメリカではまさしく幻想の流布が進み、人種や経済格差による分断を必死に覆い隠そうとしています。
先ほどバタイユの言説を引用して、キリスト教が現実と幻想の溝を埋めたからこそ多くの人に受け入れられたという点を指摘しました。
しかし、アメリカにはもはやそのキリスト教の幻想すら届かない領域が生まれてきているのかもしれません。
近年注目されているホームグロウンテロリズムは、アメリカ国内で生まれ育った人が、イスラム系過激派組織の思想に惹かれ、テロ活動を行うようになるというものです。
また国内でも、例えば2017年に白人至上主義者の行進とそれに反対するデモが衝突するという印象的な事件がありました。
しかし、こうした国内の人種的な分断をポリティカルコレクトネスという幻想で覆い隠し、アメリカは多様な人種の統合と社会進出が進んでいるのだというアピールをしています。
そういう状況になっているからこそ、今『ジョーカー』という映画は求められていたのだと思います。
というよりも本作のラストでアーサーが「理解できないよ。」なんて言っていましたが、そんな本来なら「理解されえない」はずのジョークが現実のものとして理解されてしまう可能性があり得る状況に、近年になってきているんだと思います。
ジョーカーは何者でもありません。ただの狂人です。
しかし、周囲の人々が彼に幻想を投影し、信奉することで彼は「悪のカリスマ」にでも「悪の王」にでも、そして「悪のキリスト」にでもなり得るのです。
彼は言わば「器」であり、本来であれば空っぽのままなのに、それを見た人が自分自身の不幸や怒り、狂気を勝手に詰め込んで、拠り所にしているだけなんだと思います。
そんな幻想に囚われ、信奉してしまう可能性を孕んだアメリカという国の狂気を本作は見事に描き出しています。
ギルバート・アデア氏の『ポストモダニストは二度ベルを鳴らす』という著書の中に収録されている「湾岸戦争は本当に起こっているのか?」というコラムの中にこんな面白い表現がありました。
これは筆者がパリのカフェでコーヒーを飲みながらボードリヤールの著書『湾岸戦争は起こらなかった』を読みながら、その本の結末に反感を覚えた場面での出来事です。
そのとき、ある事件が起こった。気もそぞろにページをめくったときに、白いリンネルのジャケットに赤ワインをこぼしてしまったのだ。赤い染みができるのを見て慌てふためき、ちょっとのあいだ戦争も海鵜も、何万人という死者もどうでもよくなったことを、私は告白する。
染みというのはそういうものだ。ほんの小さな存在なのにいきなりそこだけが極端なクローズアップになり、その途端、世界は―染みができる前の世界は―思っていたほどに醜く嫌な場所ではなかったように思わせてしまう。今や対処すべき相手は、遺憾ながら、この世界と染みの両方になってしまったからだ。
(ギルバート・アデア『ポストモダニストは二度ベルを鳴らす』より引用)
この一節を読みながら、私は映画『ジョーカー』のラストシークエンスを思い出しました。
精神病棟の白い廊下を歩いていく彼は、その床に血の赤色のような足跡をペタペタとつけて歩いていきます。
この時につけられた彼の赤い足跡というものが、不思議とギルバート・アデア氏が指摘した「染み」のコンテクストに重なるように思えます。
だからこそ今作は、ジョーカーという存在が生まれたことによって、「染み」ができてしまった世界を映画の中で私たちに見せてくれていたのかもしれません。
「染み」が出来てしまった後に、それを何とかして消そうとしても、その「染み」は広がるだけで、仮に薄くなったとしても元に戻ることはなく、そんな薄汚れた現実を日常として生きていくことしか望めません。
ジョーカーが私たちの世界に血塗られた足跡で「染み」をつけてしまう前に、何ができるのだろう?と考えてみる必要があります。
私たちは、この映画を見ながら一瞬だとしてもジョーカーという狂気に魅了されたという事実を忘れてはならないのです。
『ジョーカー』公開を巡りアメリカで起きている騒動
アメリカでは、映画『ジョーカー』公開を巡りトラブルが起きていました。
万が一の事態に備え、ロサンゼルス市警察や米陸軍が警戒態勢を強化し、一部の映画館ではマスクやフェイスペイントなど上映中の仮装を禁止する措置を取るなど物々しい雰囲気になっています。

















アメリカでは2012年に映画『ダークナイトライジング』が公開された際に、コロラド州オーロラの映画館で銃乱射事件が起こり、多数の死者を出したのです。
今も記憶に新しい、凄惨な事件だったのですが、犯人は『バットマン』シリーズのヴィランであるジョーカーに憧れており、犯行時には「俺はジョーカーだ。」と叫んでいたとも言われています。
彼が犯行前に数千発の銃弾を購入していたこともあり、アメリカの銃社会に問題提起する大きなきっかけにもなりました。
何だかこの事件と今回の『ジョーカー』の公開時の騒動を思うと、アメリカという国には幻想と現実の境界がないという言説もあながち間違っていないように思えます。
もちろんこの事件を起こしたのは、たった1人ですから彼を中心にして国民性を断定するのは暴論です。
それでも、映画の中の幻想と現実が交錯し、大きな事件が起こったり、警察や陸軍が出て行く事態になるという状況そのものがアメリカを象徴しているようにも感じられます。
そしてこういう状況が現実にあるからこそアメリカという国で映画『ジョーカー』が生まれたことへの必然性があります。
見ておくとよりた楽しめる関連作品
記事の最後に、映画『ジョーカー』とセットで見ておきたい作品を7作品、優先度が高い順にご紹介してみようと思います。

















①『ダークナイト』
王道ですが、やはり見ておくと良いと思います。
クリストファーノーラン監督の『バットマン』シリーズの2作目で、これを見ておけばバットマンの背景やジョーカーの行動原理などのざっくりとした背景知識は予習できます。
とりわけ今作『ジョーカー』に登場する彼と『ダークナイト』に登場する彼には、通じる点も多いですので、見終わった後に理解が深まるのではないかと思います。
また、今回は子供の状態で少しだけ登場した後のバットマンになる少年ブルースウェインがヒーローとしてゴッサムシティに立ち上がる姿が描かれているのは、この1つ前の『バットマン ビギンズ』になるので、こちらも併せて見ておいても良いかもしれません。
②『タクシードライバー』
アメリカンニューシネマを代表する1作であり、ポストモダン映画の代表作の1つでもあります。
ロバート・デ・ニーロ主演のこの作品は、『ジョーカー』に様々な面で影響を与えています。
というよりも本作は、『タクシードライバー』を邪悪な形で焼き直したかのような展開を見せます。

















どうしようもない70年代のアメリカ社会のどん底で燻り、現実と幻想の境界を行き来するアーサーとトラヴィス。
それぞれが下した決断の違いやそれに対する社会の反応の違いを比較しながら見てみると、非常に面白いと思います。
③『キングオブコメディ』
この記事でも何度かタイトルを挙げましたが、やはり今作に最も影響を与えた1作と言えるのではないかと思います。
一番わかりやすいところから言うと、この映画を見ておくと、『ジョーカー』においてマレーという大物コメディアンをロバート・デ・ニーロが演じている点にすごく興味深さを感じることができます。
またアメリカの現実と幻想の入り混じる社会観を見事に表現した作品ですので、これを見ておくことで、本作におけるゴッサムシティの世界観にもすんなり入っていくことができるのではないでしょうか。
当ブログでもこの作品については個別記事を書いておりますので良かったら読んでみてください。
④『バットマン』(1989)
今作のジョーカーはジャックニコルソンが演じているのですが、少し『ダークナイト』の彼とは雰囲気も違います。
彼が笑顔であり続ける理由や肌が真っ白な理由も、このティムバートン版の『バットマン』では明かされていて、もちろん今回の映画『ジョーカー』とは異なります。
善悪の観念を超越した、とにかく思いつくままに何にも縛られない予測不能の行動を繰り出すジョーカー像というのは、この映画が1つの基準となっているように思います。
『バットマン』というタイトルの映画なのに、肝心のバットマンが地味で、その一方でジョーカーがその狂気っぷりで目立ちまくっているのもこの作品の面白いところです。
『ダークナイト』と合わせて、3作品のジョーカーの描かれ方を比較してみるのも面白いと思いますよ。
⑤『モダンタイムス』
これについては劇中で上映されているシーンが映るんですよね。
ただそれだけではなく、『ジョーカー』という作品に非常に大きな影響を与えている1作です。
チャップリンが製作した資本主義社会に対する痛烈な皮肉を込めた作品ですが、それが現代における格差社会への批判へとコンバートされ、『ジョーカー』の中に落とし込まれているようにも感じます。
また、この作品の中でトラックから落ちた赤旗を拾った主人公が運転手を追いかけていくうちに、気がつくと労働者デモの先頭に立っているというギャグが描かれます。
これは、まさしく本作において、市長の「ピエロ」発言が発端となり、デモが始まったにもかかわらず、たまたまアーサーが格好で事件を起こしていたがために勝手にリンクづけして語られてしまうという点にそっくりです。
1本の映画作品としても非常に素晴らしい名作なので、ぜひこの機会にチェックしてみてください。
⑥『街の灯』
これも先ほどまでの解説・考察の中で少し触れさせていただきました。
とりわけアーサーと隣人のソフィーの関係性に纏わる一連の描写において、この『街の灯』の影響が垣間見えます。
『街の灯』という作品は非常に悲劇的な作品なのですが、今作『ジョーカー』はさらに悲惨です。
比較しながら見て見ると、非常に面白いのではないかと思います。
⑦『カッコーの巣の上で』
精神病棟のシーンなんかを見ていると、思わず想起するのがこの作品ですね。
関連作品として見るべきかと考えた時に、それほど優先度が高くないのは事実ですが、『ジョーカー』の中にこの『カッコーの巣の上で』見ておくとニヤッとしてしまうシーンがあります。
おわりに
いかがだったでしょうか。
今回は映画『ジョーカー』についてお話してきました。
今作が影響を受けた『キングオブコメディ』は当時のポストモダニズム的な気風とアメリカンドリームの幻想を背負って生み出された映画だと思います。
そして今作は、まさにアメリカという国の歴史と現状を見事に反映させ、ジョーカーという狂気的な幻想が多くの人に受け入れられてしまう可能性があることに警鐘を鳴らしました。

















また、今作は後のブルースウェインないしバットマン誕生のきっかけになる出来事を終盤に描きました。
『ダークナイト』のラストを思い出して見ると、ジョーカーはハービーデントという正義の幻想を破壊しようとし、バットマンはその幻想を守り抜こうと自らを犠牲にしました。
そういう意味でも、同じ悲しみや怒りを背負いながらも対立する存在であるバットマンと対比的な幻想の破壊者としてのジョーカー誕生譚として今作は傑作だったと思います。
今作は結末の解釈を巡って様々な議論が巻き起こっています。
ただ『キングオブコメディ』を下地に作られているということからも分かる通りで本作で描かれたことが幻想だったのか現実だったのかという問いに対する回答は闇の中です。
本作で描かれたことはジョーカーによる「ジョーク」だったかもしれないし「リアル」だったかもしれません。
『キングオブコメディ』の結末を巡る議論が今も続いているように、『ジョーカー』の結末を巡る議論もずっと続いていくことになるのだと思います。
今回も読んでくださった方、ありがとうございました。