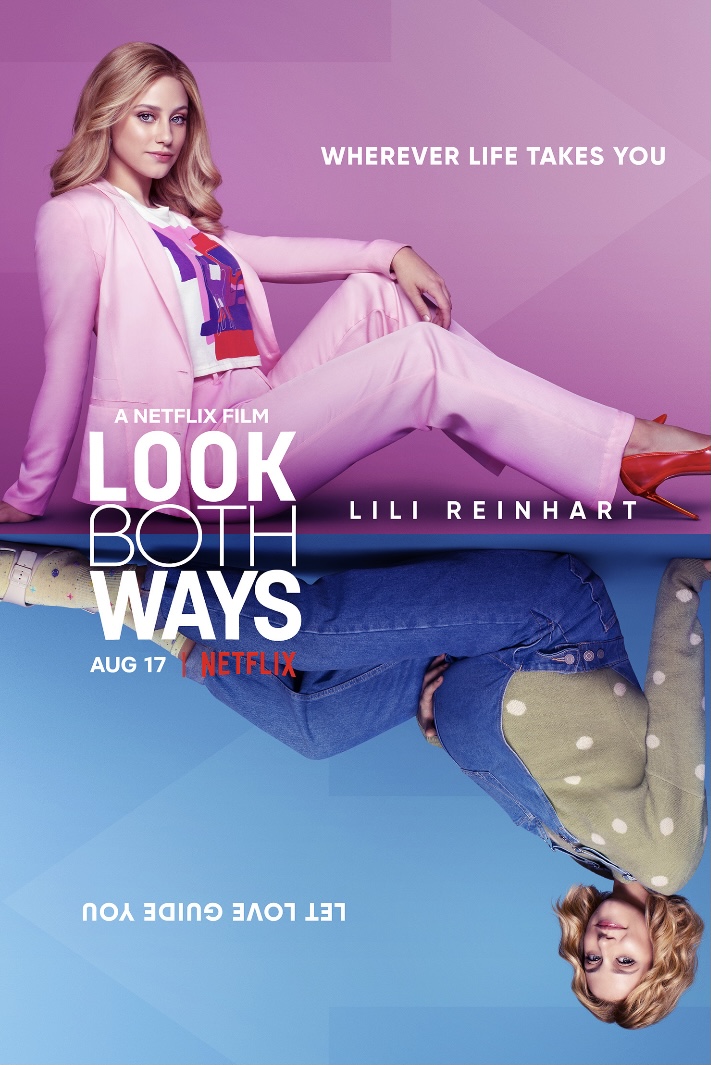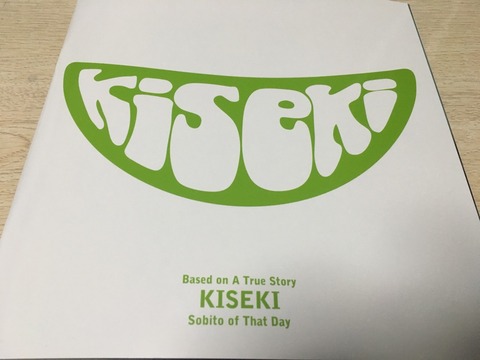みなさんこんにちは。ナガと申します。
今回はですね映画『真実』についてお話していこうと思います。

前作『万引き家族』でパルムドールを受賞し、国内外で高い評価を獲得した是枝裕和監督が、日本ではなくフランスの地で新作を撮影し、ようやく公開を迎えました。
『真実』という作品は、これまでの彼の作品と比較すると、一見非常にシンプルな作りになっているように見受けられます。
直近の『三度目の殺人』や『万引き家族』がかなり展開も派手で、ドラスティックな作りになっていただけに、余計に今作のシンプルさが際立ちます。
しかし、是枝裕和監督というのは、非常に高度で難しいことをサラッとやってのけてしまう凄腕の持ち主なんです。
確かに今作は美しいパリの風景の中で繰り広げられる母と娘のホームドラマと2人の和解を描くというシンプルなプロットではあるのですが、その裏には非常に多層的で複雑な物語構造が存在しています。






ということで、今回は当ブログ管理人が自分なりに解釈した『真実』という作品の奥深さについて語っていけたらと思います。
本記事は作品のネタバレになるような内容を含む解説・考察記事となっております。
作品を未鑑賞の方はお気をつけください。
良かったら最後までお付き合いください。
目次
映画『真実』
あらすじ
自伝小説の出版を控えるフランスの国民的大女優ファビエンヌは、自宅でメディアによる取材を受けていた。
そこに、彼の娘のリュミール、その夫のハンク、彼女の7歳になる娘のシャルロットの3人がやって来る。
彼らは久しぶりの家族団欒を、彼女のパートナーであるジャックの料理を食べながら楽しむ。
リュミールは出版する前に自伝小説の原稿を自分に送るという約束を反故にした母ファビエンヌに不信感といら立ちを募らせていた。
彼女は、その夜『真実』と題された母の自伝小説を読む。
翌朝、自伝小説の内容に強い違和感を感じたリュミールは母親を問い詰める。
その理由の中心にあったのは、ファビエンヌの代わりに自分の母親代わりをしてくれた同じく女優の「サラおばさん」についての記述が一切ないことだった。
さらに同じく自伝小説の中に自分のことが書かれていなかったことに対して、彼女の長年のパートナーであるジャックが憤慨し、家を出て行ってしまう。
リュミールはジャックの代わりに付き人として、母の撮影現場に同行することとなる。
ファビエンヌとサラに纏わる驚愕の疑惑、そしてサラにそっくりな若手女優マノンの存在。
リュミールとファビエンヌは和解に辿り着くことができるのか?
スタッフ・キャスト
- 監督:是枝裕和
- 脚本:是枝裕和
- 撮影:エリック・ゴーティエ
- 美術:リトン・デュピール=クレモン
- 衣装:パスカリーヌ・シャバンヌ
- 編集:是枝裕和
- 音楽:アレクセイ・アイギ






今作『真実』について是枝裕和さんは監督・脚本・編集を担当しています。
彼はテレビのドキュメンタリーディレクター時代から編集まで自分で担当するというのをポリシーにしている様で、フランスに撮影の現場を移したとしてもそれは変わらないようです。
そして彼を支えるスタッフ陣も非常に豪華な顔ぶれとなっております。
『イントゥ・ザ・ワイルド』や『夏時間の庭』などで知られるエリック・ゴーティエが本作『真実』にて撮影を担当しました。
彼は手持ちカメラによる長回しの映像を得意としていて、そのザラザラとした質感の揺れる映像が、母と娘の揺れる心と関係性を表現するうえで非常に効果的だったと言えます。
劇伴音楽には、『草原の実験』などで知られるアレクセイ・アイギが加わりました。
多幸感に満ちたお伽噺のような音楽と、その転調に至るまで非常に見事で、是枝監督自身も絶賛しておられました。
- ファビエンヌ・ダンジュヴィル:カトリーヌ・ドヌーブ
- リュミール:ジュリエット・ビノシュ
- ハンク・クーパー:イーサン・ホーク
- アンナ・ルロワ:リュディビーヌ・サニエ
- シャルロット:クレモンティーヌ・グルニエ
- マノン・ルノワール:マノン・クラベル
- リュック:アラン・リボル
- ジャック:クリスチャン・クラエ
- ピエール:ロジェ・バン・オール






フランスの大女優であるカトリーヌ・ドヌーブとジュリエット・ビノシュが共演しているという圧倒的な華にまずは惹かれますよね。
特に当ブログ管理人は『存在の耐えられない軽さ』や『ポンヌフの恋人』が大好きなので、ジュリエット・ビノシュは大好きです。
そしてアントワン・フークア監督の『トレーニング デイ』やリチャード・リンクレイター監督の『6才のボクが、大人になるまで。』などでアカデミー賞ノミネート経験もあるイーサン・ホークも加わりました。
この豪華すぎる顔ぶれで、繰り広げられるハイレベルな人間ドラマに、もう圧倒されてしまいました・・・。
より詳しい情報を知りたいという方は、映画公式サイトへどうぞ!






映画『真実』解説・考察(ネタバレあり)
是枝監督らしい答え無き物語
是枝裕和監督の作品は、基本的に明確な答えというものを出すということをしません。
映画を見る際に、多くの人がそこに何か「答え」があるのではないかと思って見るわけで、それが作品の中で描かれていないと肩透かしを食らった気分になるわけです。
その点では、映画に明確な「答え」が欲しい人にとっては、彼の作品は受け入れ難さもあるかもしれません。
近年の『三度目の殺人』も『万引き家族』もラストについては疑問を投げかけるような形、答えを明確に示さない形で幕切れています。
彼は『三度目の殺人』の際のインタビューでサスペンス映画ながら誰が犯人なのかを明かさない構成について以下のように述べていました。
狙いですね。主人公の重盛は、はっきりと真実が掴めないままに判決が出て、裁判所を出た後にモヤモヤしていると思うんですね。でも彼も司法のシステムだから、次の裁判に行かないといけないというその主人公の心理を、皆さんにも感じて劇場を出ていただきたかったので、モヤモヤしているのなら成功したのかなって思いますね。
(「映画の時間」より引用)
確かに2時間の中ですっきりと全てのことが明かされて、語られつくしてしまう映画は物語としては非常に優秀です。
しかし、作品の中で明確な答えを出さず、観客に全てを委ねるというのも1つのアプローチであり、この方が見終わった後の余韻に繋がり、長く作品について思いを馳せることになります。
それに加えて、是枝裕和監督にとって映画というものが自分の中で「答え」を模索するためのツールなのだという点も、作品に表れているように思えます。
是枝裕和監督が『万引き家族』のインタビューの際に「家族をどう解釈するか?」との質問に以下のように答えていたようです。
「家族とは何か?という答えを出すためにこの映画を撮ったわけではありません。自分も考えながら撮っているし、登場人物たちも手探りしていると思う。曖昧になってしまうのですが、今回はたぶん、ともに過ごす時間が終わったあと、彼らの中に記憶として残っているものが“家族”なのかなと思った。一緒に暮らすことができなくなってもなおつながっているという意識の中に、見えない形で“家族”が立ち上がってくる。そんな話にしたいと思いました」
(「映画ナタリー」より引用)
この言葉に彼なりの映画観のようなものが透けて見えるような気がしています。
彼はこれまで常に「家族」というモチーフにスポットを当てた映画を撮ってきましたし、もちろん今作『真実』についても家族映画のジャンルに含まれます。
彼が「家族」を題材にした映画を撮り続ける理由は明白で、彼自身が今も「答え」を模索し続けているからです。
そのため、是枝監督の映画を見る際には、何か製作者なりの「答え」を読み取ってやろうというよりは、自分なりに感じたことや見たものから考えてみようという姿勢の方が重要ではないかと個人的には思っております。
『真実』という作品のタイトルは実に皮肉的で、この物語の中で描かれる出来事や語られる思い出は、どれが真実でどれが嘘なのかが実に曖昧に描かれています。
私たちはこの映画を見る際に、「事実」と「真実」が全く別物であるということを知覚しておく必要があります。
「事実」はたった1つであり、起きた出来事そのものを指します。
しかし、対照的に「真実」は1つではありません。
「真実」というのは、あくまでも「嘘偽りのない本当のこと」という意味でしかなく、1つの「事実」に対して、それを見る人の数だけ「真実」があると考えられます。
だからこそ今回の映画『真実』に対しても、多様な解釈があるはずですし、見る人の数だけの「真実」があるはずです。
女優とは何か?という主題を描く
(C)2019 3B-分福-MI MOVIES-FRANCE 3 CINEMA
今作『真実』は紛れもない是枝監督印の家族映画なのですが、まずはその前に「女優とは?」について思索する映画であったことにも触れておこうと思います。
そもそもこの映画は監督とジュリエット・ビノシュが2011年に「女優とは、演じるとは何か?」というテーマで熱く対談したことがきっかけで動き始めた企画だと言われています。
そこに、母と娘の物語という家族映画的なプロットを絡めながら、是枝監督なりの「女優」というものに対する畏怖と敬意を込めたのではないかと感じました。
この映画を見ていて、やはり印象的なのはカトリーヌ・ドヌーブが演じるファビエンヌでしょう。
というのも監督は、間違いなくファビエンヌをカトリーヌ・ドヌーブその人に重ねて脚本を書いているはずです。
初稿段階では、このキャラクターの名前はカトリーヌだったと言いますし、結果的に決定したファビエンヌという名前は彼女のミドルネームです。
そして名前だけではなく、設定についても多くの点で彼女自身の経歴を思わせる部分があります。
例えば、劇中で「セザール賞を2度受賞している」という彼女の女優としての設定が明かされていましたが、カトリーヌ・ドヌーブ自身も『終電車』と『インドシナ』で2度セザール賞主演女優賞を獲得しています。
また劇中でファビエンヌがヒッチコック映画に出る寸前だったと語っていましたが、カトリーヌ・ドヌーブ自身もインタビューで次のように語っています。
「たしかにヒッチコック監督にお会いしました。そしてヨーロッパで撮影の計画があり、脚本もいただいていました。しかし撮影の準備に入る前にヒッチコック監督は亡くなってしまった。出演したかったです。」
(「映画ナタリー」より引用)
このように、現実とフィクションの境界を曖昧にしつつ、『真実』という作品の中に、ファビエンヌという「大女優」のアイコンを成立させることに成功していたと思います。
そして本作は、サラという女優の存在に悩まされながらも女優として活躍してきた母と、そんな母の存在から逃げ脚本家になった娘のドラマが繰り広げられます。
俳優の瑛太がいつかのインタビューで「カメラの前に立つのは怖い。本質がバレるから」なんてことを言っていましたが、ファビエンヌという女優を見ているとその言葉がふと頭をよぎりました。
彼女の本質は弱く、とても嫉妬深い人間です。そして映画の撮影現場に入り、カメラの前に立つと、そんな自分の本質が露呈してしまうことに怯えています。
サラという稀代の女優の才能に圧倒され、さらに彼女に自分の「母」としての役割まで奪おうとしているのではないかと嫉妬しました。
だからこそファビエンヌは自分が「女優」として生きるための「真実」を作り上げなければならなかったわけですよ。
それこそが1冊の書籍として世に発売されることになった彼女の自伝本『真実』でもあります。
彼女は根っからの「女優」であり、それ故に自分の本質を演じて見せていたわけです。
今作『真実』はカメラワーク駆使してそんな「自分」を演じるファビエンヌを巧妙に描き出します。
基本的に『真実』という作品は息が詰まるほどのクローズアップショットを多用していて、人間にかなり寄った近景の映像を中心に構成しています。
しかし、ふとズームアウトし、遠景からのカットに変わることで、これまで見えていたシーンの印象ががらりと変わることがあります。
例えば、ファビエンヌが朝に犬の散歩がてら近所の中華料理店に向かい、食事をするシーンは印象的です。
近景で捉えると、確かに犬と共に優雅に朝食を楽しみに来ている大女優そのものなのですが、引きのカットで捉え、フレームに幸せそうに団欒している家族が映りこんだ瞬間にその印象は大きく変わります。
そこに浮かび上がるのは、彼女の深い孤独です。
本作『真実』は近景と遠景の使い分けをメタ映画的に用いています。
そもそもシャルロットがファビエンヌの家をお城のようだといっていますが、このセリフがフィクションの中の住人としての彼女を浮かび上がらせています。
そして、近景から遠景に移り変わったときに、「映画的なフレーム」を強く意識させるように仕向けてあり、このシーンでも遠景に移った際に、「自分」を演じるファビエンヌというものを強く感じさせられるようになっています。
ファビエンヌは自分の人生という映画の中で生きているんです。
このメタ構造がより一層明確になったのが、後半の夜の喫茶店でのファビエンヌとジャックの会話シーンです。
このシーンでも最初近景で2人の会話を捉えるのですが、後にズームアウトし窓の外から2人を遠景で捉えるカットへと移行していきます。
窓のフレームがそのまま映画のフレームを意識させることは言うまでもなく、そのシーンで話す言葉を彼女が娘に脚本で書いてもらっていたという事実も相まって、よりメタ映画的に機能しています。
彼女にとっては人生も現実も映画の中の世界なのかもしれません。
そして、そんな彼女が恐ろしかったのは、自分がなりたかったけれどもどうしてもなれなかった「サラの再来」と呼ばれる女優マノンでしょう。
弱く、嫉妬深い自分ではなく、常に強く毅然としており、女優としても母としても完璧な自分という「サラ」の亡霊めいたものを自分の本質に覆いかぶせ、彼女は「自分」を演じて生きてきました。
しかし、マノンにちらつく「サラ」の亡霊を見ていると、彼女は自分の正体を暴かれるような気持になるんでしょうね。
これはまさに「カメラの前に立つのは怖い。本質がバレるから」という言葉そのものです。
マノンという女優を介して、彼女はサラを見ていたわけで、そして自分の弱さや醜さを嫌と言うほどに突きつけられます。
そのため、演じることが恐ろしくなり、「女優」という立場から逃げ出してしまいそうになります。
これこそがファビエンヌの「真実」だったわけですが、当然娘のリュミールはそんなことは知る由もなく、母から逃げる形で女優の夢を諦めます。
劇中で『オズの魔法使い』にて弱々しいライオンを演じたリュミールは「ライオンの気持ちが分かっていた」という言及がありましたが、これは彼女自身が弱い人間だったということの表出でもあります。
つまり「弱さ」を偽り、強い自分という「真実」を作り上げるという母のようなことは彼女にはできないということです。
母のようには強くなれない、自分を演じることはできないと悟り、自ら役者の道から退いてしまったのでしょう。
本作『真実』には、是枝監督の「女優」という存在に対する深い敬意の念が表れているように感じられました。
演出家の増見利清は「俳優の人間性と生活すべてが芸術的な成果に直接結びついている」と述べました。
「演じる」ということは自分の本質をさらけ出すことであり、「女優」としての自分を否定されることは、自分そのものを否定されることでもあります。
そういう孤独な世界の中で1人で戦い続け、恐怖と向き合いながらもカメラの前に立ち続ける「役者」ないし「女優」という存在の凄みを監督はこの作品に込めたように思えます。
終盤のサラの服を着たマノンがファビエンヌの自宅から去っていくシーンは、途方もなく美しいです。
彼女は自分の本質を隠すために持ち続けていた「サラ」の亡霊をようやく払拭することができたのでしょう。
ファビエンヌは「弱い」自分のままでカメラの前に立つ勇気を手に入れたのであり、同時に初めて1人の女優として演じたい欲求に駆られたのです。
美しき母と娘の和解の物語
(C)2019 3B-分福-MI MOVIES-FRANCE 3 CINEMA
今作は母と娘の和解を描く物語なのですが、やはり是枝監督らしい巧さが光っていますよね。
この映画の1番盛り上がるシーンと言いますか、「和解」が成立するシーンって実は、2人が抱きしめ合うシーンではないんじゃないかと思うんです。
私が、この映画において最も重要だと考えるシーンは、サラの服を着たマノンがファビエンヌの自宅から去っていくシーンです。
そして『真実』という映画は、すべてのシーンと伏線がこのシーンで結実するように計算されています。
というのもファビエンヌとリュミールはお互いがお互いに相反する「真実」を作り上げ、それ故に関係性が決裂していました。
ファビエンヌが作り出していた真実については先ほどの章で解説した通りです。
そしてリュミールは自分が母親の存在に圧倒され、女優という道から逃げたという事実を作り上げた「真実」によって覆い隠していました。
だからこそ彼女にとっては母ファビエンヌという存在は、育児に無関心で家庭を顧みず、傲慢で自己中心的で、それでいて孤独。そうあってもらわなければなりませんでした。
なぜなら、母がそういう存在であったという「真実」さえあれば、自分が母親から逃げたという事実を覆い隠すことができるからですよ。
それ故に、彼女にとって母の自伝本『真実』は許せないものだったでしょう。
もちろんそこには、サラのことについて触れていないという理由もありますが、それ以上にこれが「真実」なのであれば、自分が母とそして女優から逃げたという事実が明白になってしまうからです。
このように本作で描かれるファビエンヌとリュミールという母娘はお互いに、何かから逃げ、目を背け、そして自分のための「真実」を作り出しているキャラクターなのです。
前者は女優としても母としても自分より優れていたサラという女性の存在から逃げ、後者は大女優として活躍していた母の存在から逃げていました。
そう考えると、自ずと本作のゴールが、2人が1つの「真実」を共有するところにあるべきだという発想に至りますよね。
もっと言うなれば、2人がお互いが作り上げた「真実」を諦めることができれば、再び寄り添うことができるはずだということでもあります。
そして、それが結実したのが間違いなく、先ほど述べたサラの服を着たマノンがファビエンヌの自宅から去っていくシーンです。
前章で解説したように、このシーンはファビエンヌにとって、自分の本質を覆い隠していた「サラの亡霊」から解き放たれた瞬間であり、初めて自分の本質と向き合おうとした瞬間です。
では、リュミールにとってどんな意味があったのでしょうか。
彼女が「サラの亡霊」を見ながら感じていたのは、母ファビエンヌその人だったのではないかと私は思っています。
母は弱く嫉妬深い人間でしたが、サラの存在が消えたことで、まさに唯我独尊な存在へと変貌し、女優としてのキャリアを積み上げていきました。
彼女はそんな母を糾弾しながら、同時に自分自身が「逃げた」という事実を何とかして正当化したいのです。
しかし、母ファビエンヌは映画の撮影の中でマノンとそして彼女の向こう側に透けて見えるサラの存在と向き合おうとしました。
だからこそリュミールも母と向き合う必要性に駆られました。
彼女は、母親が自分を拒んだという「真実」ではなく、自分が弱かったが故に母親とそして女優の道から逃げ出したのだという見たくなかった事実と向き合わざるを得なくなったのです。
だからこそ、あのシーンで去っていくマノンの後ろ姿に、リュミールは「サラの亡霊」を纏い、女優として大成した強い母の虚像を見ていたのでしょう。
2人は「マノンの後ろ姿」という1つの事実を見ています。
そして同時に「自分自身が弱い人間であるが故に逃げだした」のだという1つの「真実」を見ています。
2人の焦点を1人の女性の後ろ姿に交わらせることで、「和解」を視覚的に描くという是枝監督の巧さがこの上なく光ったシーンだったと言えるのではないでしょうか。
また、面白いのが、この後のシーンで、リュミールが脚本を書き、娘のシャルロットにセリフを言わせて、母ファビエンヌを喜ばせるというシーンですよね。
ここで劇中劇の『母の記憶に』のセリフを引用しているのがまたオシャレなんですが、これってまさに「リベンジ」です。
女優として確立された母親に対して、自分の武器である「脚本」を使って、騙し返すという巧妙な演出は、彼女が「逃げ」としてではなく、自分の意志で明確に脚本家という仕事に向き合うことへの決意表明でもあると思います。
和解し、弱さを認め合った2人が、女優として、脚本家として再びそれぞれの人生を歩んでいくのです。
おわりに
いかがだったでしょうか。
今回は映画『真実』についてお話してきました。
事実は1つしかありませんが、真実は無数に存在しています。
それ故に、時に真実は衝突し、人間関係に亀裂を入れてしまうことがあります。
なぜなら多くの人が、自分自身の真実と事実が同じものだという錯覚にとらわれてしまうからです。
しかし、そこで自分自身の真実が相手にとっても同じではないのだと気がつくことができれば、対話が生まれ、和解へと向かうことができます。
真実と事実は異なる、そして真実は1つではない。
このことに気がつくことができれば、人は関係を結び、共に生きていけることができるのだというメッセージを本作から感じました。
是枝監督は本作に関して明確なハッピーエンドを描きたかったと語っていましたが、まさに美しいハッピーエンドだったと思います。
今回も読んでくださった方、ありがとうございました。