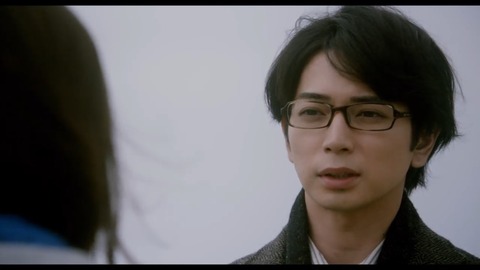みなさんこんにちは。ナガと申します。
今回はですね映画『ブルーアワーにぶっ飛ばす』についてお話していこうと思います。

『TSUTAYA CREATORS’ PROGRAM FILM』は近年受賞作品の映画化が増えてきており、非常に注目されています。
2015年にグランプリを受賞した『嘘を愛する女』、準グランプリだった『ルームロンダリング』はすでに映画化され、劇場で公開されました。
ちなみに今作については箱田優子さんの自伝的な映画でもあり、彼女が自ら「ブルーアワー」の仮題で応募した脚本の映画化です。
しかし、『嘘を愛する女』を長澤まさみさんと高橋一生さんで映画化した時にも思いましたが、この『TSUTAYA CREATORS’ PROGRAM FILM』の映画化作品ってすごく力を入れてくれてますよね。
アマチュアの人が監督作品や自身の脚本を応募できるコンテストで、受賞作品がここまで大切に映画化されるとなると、応募する人も増えてきそうです。
さて、本記事は作品のネタバレになるような内容を含む感想・解説記事となっております。
作品を未鑑賞の方はお気をつけください。
良かったら最後までお付き合いください。
目次
『ブルーアワーにぶっ飛ばす』
あらすじ
30歳でCMディレクターをしている砂田は、不満を抱えながらも何とか日々の仕事に取り組んでいた。
彼女に理解を示してくれる優しい夫もいたが、「自分のことを好きな人が嫌い」だという彼女は、仕事仲間の冨樫と不倫関係にあった。
しかし、仕事現場では責任を押しつけられ、ピエロのように愛想よく気丈に振舞うことに疲れ切っており、酒を飲んでは夜の街をフラフラとしていた。
そんな時、彼女は茨城の実家の両親から、容体がよくなった祖母に会うために帰省して欲しいと告げられる。
帰省の決断ができなかった彼女だが、親友の清浦の突然の提案により彼女の車で茨城へと向かうこととなる。
スタッフ・キャスト
- 監督:箱田優子
- 脚本:箱田優子
- 撮影:近藤龍人
- 照明:藤井勇
- 編集:今井大介
- 音楽:松崎ナオ











冒頭にも書いたように本作は、『TSUTAYA CREATORS’ PROGRAM FILM』で審査員賞を受賞した作品です。
また、箱田優子さんが自分の人生をさらけ出して書いた脚本だということですね。
そんな言わばアマチュアが半自伝的に書いた脚本が映画化された作品が、こんな豪華スタッフに支えられて、映画化されるって単純にすごくないですか・・・。
特に撮影に、今日本で最も勢いがあり、評価されている近藤龍人さんが参加しているんです。
彼は『桐島、部活やめるってよ』や『万引き家族』などの撮影を担当し、高評価を獲得しています。
そして撮影にも『万引き家族』や『見えない目撃者』などで知られる藤井勇さんが加わっています。











他にも音楽にはシンガーソングライターの松崎ナオさんが起用されました。
- 砂田夕佳:夏帆
- 清浦あさ美:シム・ウンギョン
- 玉田篤:渡辺大知
- 砂田澄夫:黒田大輔
- 茨城のスナック店員:伊藤沙莉
- 冨樫晃:ユースケ・サンタマリア
- 砂田浩一:でんでん
- 砂田俊子:南果歩











主人公の砂田夕佳を演じたのは夏帆さんです。
夏帆さんっておしとやかで大人しい役のイメージが個人的には強かったんですが、こういうサバサバとしたぶっきらぼうな役も似合いますね。
そして主人公の親友清浦をシム・ウンギョンが演じました。
元々韓国で大ヒットした映画『サニー 永遠の仲間たち』に主人公役で出演し、そのぶっ飛んだ演技で高評価された女優です。
今年に入って映画『新聞記者』にも出演し、その演技を日本でも認められるなど、韓国だけでなく日本でも活躍しています。
男性キャストも渡辺大知さんや黒田大輔さんなど個性派どころを揃えていて、作品に独特のリズムをもたらしてくれています。
そして、当ブログ管理人的に一番グッときたのは、伊藤沙莉さんが演じた茨城のスナック店員役です。











独特の雰囲気を持つ彼女だからこそ、こういう癖のある役を自分のものにできてしまうんでしょうね。
より詳しい情報を知りたいという方は、映画公式サイトへどうぞ!











『ブルーアワーにぶっ飛ばす』感想・解説(ネタバレあり)
奇妙な「ズレ」を生み出す脚本と編集の妙
『ブルーアワーにぶっ飛ばす』を見ていて、この作品が他の映画を一線を画していると感じたのは、作品の「リズム」なんですよ。
ゆる~いノリで展開していく映画のことをしばしば「オフビート感」と表現しますよね。
ただ「オフビート」ってそもそも「通常とははずれたところに強拍を置く」という意味の音楽用語であって、ただ単にゆる~いノリのことを指しているわけではありません。
その点で、『ブルーアワーにぶっ飛ばす』は完璧な「オフビート映画」だったと言えるのではないかと思います。











まず、基本的に映画を作る際に邦画であれば、日本語のセリフが大半になりますよね。そこに何かひと手間加えてやろうなんて考える人はそれほどいないと思います。
この映画も確かに日本語のセリフしか登場しない映画ですが、極めて意図的に日本語の「音」に違いをつけてあり、作品のリズムを搔き乱します。
- 夕佳が話す比較的標準的な日本語
- 夕佳の両親や地元の人が話す茨城弁
- 夕佳の兄が話す早口で細い日本語
- 清浦が話す奔放すぎる片言日本語











こういう登場人物が話す言葉にアクセントを用意して、観客に作品の持つ独特のリズム感を伝えていくという作品はあまりないように思ったので、その点で今作は新鮮でした。
また、編集を見ていて思ったのは、あえて不自然に見えるように繋げてあるシーンが非常に多かったということでしょうか。
普通、映画の編集って観客に物語を理解させるためにシーン間の飛ばしはかなり慎重に行われますし、どの映像とどの映像を連続させるかなんて細心の注意を払って設計されます。
『ブルーアワーにぶっ飛ばす』は逆に、編集で「観客が意図しないシーン」を繋いできてるんですよ(笑)
ドライブシーンの次にいきなり仏像のクローズアップショットを繋いでみたり、登場人物が眠っているシーンの次に昆虫が裏向きで足をバタバタさせている映像を繋いでみたりと、徹底的に観客の想定しているビートを外してくるんです。
そのため見ている側としては、何だか常に虚を突かれているような感じがして落ち着かないわけですよ。
さらに一番面白いのが、これは物語の根幹をなす設定にも関わっていることですが、シム・ウンギョン演じる清浦だけが、この作品の中で明らかに違うリズムを刻んでるんです。
1番分かりやすいのは、夕佳の家を訪れて、彼女と彼女の母、そして清浦の3人でパックの「お~いお茶」を飲みながら、会話をしているシーンです。
(C)2019「ブルーアワーにぶっ飛ばす」製作委員会
このシーンにおいては、夕佳と彼女の母が物語の針を進めるべく会話をしているわけですが、その横で清浦が全く別のテンポでリズムを刻んでるんですよ。
というのも彼女は2人の会話そっちのけで、お茶を飲んでみたり、部屋をキョロキョロとしてみたり、地元の名産というおつまみを食べて不味いからと吐いて捨てたり、口直しにまたお茶を飲んでみたりとやりたい放題をしています。
つまり夕佳がビート、清浦がオフビートという関係が明確に成立していて、それが同時に存在するというあまりにも奇妙すぎる映像にしあがっているというわけです。
本作『ブルーアワーにぶっ飛ばす』はこういう絶妙な「ズレ」を意識した脚本に仕上げたことで、大きな展開がない物語ながら、観客の注意をそらさせない設計になっています。
見ている側としてはことごとく自分の想定しているリズムを裏切られていくという、独特の居心地の悪さを味わうことになるということです。
「ズレ」を抱えて生きている夕佳
さて、先ほどまでこの映画には、極めて意図的に「ズレ」が生み出されているというお話をしてきました。
実は、この演出上の「ズレ」というものが、物語的には主人公の夕佳が感じている自分と社会の「ズレ」として顕在化しているんですよね。
彼女はCMディレクターの仕事にも上手く噛み合うことができず、田舎に戻っても両親と上手くやっていくことができません。
ただ、夕佳はそのことを自覚していながら目を背けたいと考えていて、それ故に清浦という徹底的に世の中の「オフビート」を貫く偶像を作り出して、自分は世の中のビートと同調していると思い込もうとしています。
確かに清浦というキャラクターは話している片言の日本語からして独特なんですが、田舎に戻るとむしろ夕佳よりも上手く両親との関係を築けていたりするんですよ。
つまり、この作品は清浦という「オフビート」が本来の「ビート」側の存在であることを気がつかせていくことで、本当に「オフビート」の側にいたのは夕佳なんだということを知覚させる構造になっているというわけです。
本作の核となる物語構造は、清浦が夕佳のイマジナリーフレンドだったというところにあります。
そして夕暮れの車の中で、夕佳は自分と社会の「ズレ」から目を背けるために作り出した清浦という幻影を受け入れるのかどうかを迫られるわけです。
清浦というキャラクターを主人公の理想として解釈することもできると思いますが、私はむしろ彼女は清浦という「オフビート」を作り出すことで自分を安心させようとしていたんじゃないかと考えています。
「ぜんっぜん寂しくなくて寂しい」というセリフを彼女が終盤に吐いていましたが、これって寂しいと感じるのが社会の普通なのに、それを感じることができない「ズレ」た自分の存在に寂しさを抱えているということだと思うんです。
だからこそ彼女は、前に進むために自分こそが「オフビート」だったんだと自覚する必要があります。
そんな彼女に清浦が「もともとダサいっすよ。ダセえの最高じゃないっすか。生きてるって感じで。」と告げます。
これは、まさに「ズレ」を抱えて生きるありのままの夕佳の肯定であり、その言葉を聞いて、ようやく彼女は清浦の存在なしで生きていく決心ができるわけです。
「ブルーアワー」は永遠に続かない
本作において登場した1日と始まりに一瞬だけ訪れる静寂の時間として「ブルーアワー」が描かれました。
幼少の頃にその時間帯になると、外に出て駆け回っていた夕佳はその一瞬だけ自分は「無敵」だったと語っています。
そして彼女は今も自分は「ブルーアワー」にいるんだと信じようとしているし、自分は「無敵」なんだと思い込みたいんですよ。
彼女が帰省をする際に、「衰弱した祖母」を見たくないと語っていました。











しかし、彼女はどうしても元気な祖母の姿だけを見ていたいのです。
なぜなら、彼女にとって祖母というのは自分の幼少期、つまり「ブルーアワー」時代の象徴だからですよ。
祖母という存在は自分の中では、あの頃のままなのに、変わってしまった祖母の姿を見てしまえば、自分はもう「ブルーアワー」にいないという現実を嫌でも自覚しなければならなくなります。
だからこそ彼女は「ブルーアワー」時代の元気なあの頃のままの祖母の偶像にすがりたかったのです。
そんな彼女が、病室で祖母と再会し、言葉を交わすシーンは何とも印象的です。
この時に、カメラは祖母の手にクローズアップします。
浮かび上がるのは、「ブルーアワー」時代の血色の良い祖母の手とは対照的な、深くしわが刻まれた力ない祖母の手です。
夕佳は爪を切りながら、そんな祖母の手を見つめ、自分の「ブルーアワー」時代の偶像が壊れていくのを自覚していたはずです。
そうして祖母と再会したことで、彼女はようやく前に進むことができます。
ラストシーンはあえて「ブルーアワー」とは対照的な夕暮れの時間帯で撮影されています。
(C)2019「ブルーアワーにぶっ飛ばす」製作委員会
「夜」が1日の終わりだとするならば、夕暮れとはその終わりに向かって確かに走っていくことを視覚的に明示する時間帯と言えるでしょうか。
振り返るとそこにはまだ「ブルーアワー」があるのですが、夕佳は自分の意志でアクセルを踏み、確かに前に進むのです。
監督・脚本の箱田優子さんはインタビューでこんなことを語っておられました。
「時間を止められない切なさ」を表現したくて、今回脚本を書きました。30歳の砂田は一般的には大人と呼ばれる年齢ですけど、心の中では「自分がこんな歳になるなんて……」と思っているし、親も祖母もどんどん歳をとる。そんな不可逆な時間のなかで自分なりにどう生きるか、という話を書きたかったんです。
人間はいつまでも自分のリズムで無鉄砲に生きていたいと思うのですが、学校に入り、そして社会に入りという成長の中で、いつしか周囲のリズムに合わせながら生きなければならなくなります。
そういう意味では、一たび社会に出てしまえば、もはや「ブルーアワー」に戻ることなど不可能です。
時間を巻き戻すことはできませんし、時間は永遠に前に向かって淡々と進み続けます。
そして私たちはその流れの中で自分の思うようなリズムを刻めないもどかしさを、社会のリズムに合わせなければならない葛藤を抱えながら生きていかなければならないのです。
『ブルーアワーにぶっ飛ばす』という映画には、その「切なさ」が見事に込められています。
そして物語の最後に、夕佳は自分が「オフビート」な存在であることを自覚し、ダサい自分のままで生きていく覚悟を決めるのです。
茨城の片田舎から中古車でアクセルを踏み、東京の街へと戻っていく。
この世界を生きる人間が全員「朝はパン派」だとしても、私は「朝はご飯派で、みそ汁が必須なんだ!」と声高に叫んで生きれば良いとそう思えた夕佳の姿に少しだけ勇気をもらえる、そんな映画でした。
おわりに
いかがだったでしょうか。
今回は映画『ブルーアワーにぶっ飛ばす』についてお話してみました。
この作品は、冒頭にも書いたように「TSUTAYA CREATORS’ PROGRAM FILM 2016」で審査員特別賞を受賞した脚本であるわけですが、正直めちゃくちゃレベルが高いです。











脚本や演出段階で、わざとらしくではなく自然な形で「ズレ」を生じさせるってなかなか難しいと思いますし、絶妙なバランスが求められます。
そういう難しいタスクをこの脚本はいとも簡単げに乗り越えているわけで、そこに近藤龍人を初めとする映像のスペシャリストが集結したわけですから「ハズレ」なわけがないんですよね。
ぜひ多くの人に見て欲しい映画になっていたと思います。
今回も読んでくださった方、ありがとうございました。