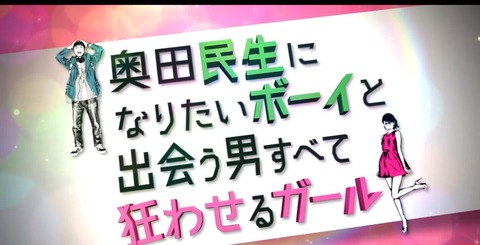みなさんこんにちは。ナガと申します。
今回はですね映画『ひとよ』についてお話していこうと思います。

劇作家の桑原裕子さんが自身の主宰する「劇団KAKUTA」で上演していた題目を今回映画化する運びになりました。
小説版については舞台版を原作として、作家の長尾徳子さんが担当しました。
演劇らしく1つの家という舞台を用いた家族劇になっていて、1つの空間で様々な人間の家族模様が交錯するという面白い構成になっています。
映画の予告編を見た感じでは、ある程度原作からアレンジしてある部分もあるようです。
その点も踏まえつつ、まずは原作本について書いていき、映画版を鑑賞し次第、そちらのレビューも追加していこうと思います。
本記事は作品のネタバレになるような内容を含む感想・解説記事となっております。
作品を未鑑賞の方はお気をつけください。
良かったら最後までお付き合いください。
目次
映画『ひとよ』
あらすじ
稲村家は母こはるとその夫、そして3人の子どもたちで構成されており、タクシー会社を営んで暮らしていた。
しかし、夫は家族に日常的に暴力を働いており、家族としての関係はほとんど崩壊していた。
ある夜、意を決してこはるは子どもたちを守るべく夫を殺害する。
彼女は家に戻ると、子どもたちのご飯の支度をし、「15年後に戻って来る。」と約束し、自首する。
犯罪者の子どもとなった3人の兄弟姉は、世間から白い目で見られ、大企業からの内定を辞退し、夢を諦め、学校で居場所をなくし、苦労しながら成長していく。
そして15年が経ったある日、こはるは突然実家へと戻って来る。
犯罪者の子どもとして苦しみながら15年の月日を過ごした彼らはそんな母の帰還を複雑な心境で受け止める。
あの日、あの夜に閉じ込められたまま人生を歩んできた家族の長い長い夜明けまでの物語が描かれる・・・。
スタッフ・キャスト
- 監督:白石和彌
- 原作:桑原裕子
- 脚本:高橋泉
- 撮影:鍋島淳裕
- 照明:かげつよし
- 編集:加藤ひとみ
- 音楽:大間々昂











当たり映画とハズレ映画を交互に作るという個人的な印象がある白石和彌監督。
前作の『凪待ち』はかなりの傑作だったので、今作はハズレのパターンか?という不安はありますが、気合の入り方からして安心して見て問題ない作品かと思います。
脚本には『ソラニン』『凶悪』『サニー32』などで知られる高橋泉さんが起用されています。











ただ『凶悪』は白石監督の出世作とも言えるものなので、この2人のコンビには期待と不安が入り混じりますね。
撮影・照明には瀬々監督作品で知られる鍋島淳裕さんとかげつよしさんが起用されており、人間の苦悩や葛藤を深く抉るような映像を期待してしまいます。
編集には白石流を熟知した加藤ひとみさんが起用されています。
音楽には『彼女がその名を知らない鳥たち』で息苦しくも、どこか希望を感じさせてくれる美しい音楽を提供した大間々昂さんが加わりました。
- 稲村雄二:佐藤健
- 稲村大樹:鈴木亮平
- 稲村園子:松岡茉優
- 丸井進:音尾琢真
- 柴田弓:筒井真理子
- 友國淳也:大悟
- 堂下道生:佐々木蔵之介
- 稲村こはる:田中裕子











稲村家の次男である雄二役には、佐藤健さんが起用されています。
実写版『いぬやしき』の時にも強く感じたのですが、佐藤さんは陰のあるキャラクターを演じるのが非常に巧いと思います。
その点で、今作のやさぐれ男の演技にも非常に期待しています。
長男の大樹は、鈴木亮平さんが演じています。大樹というキャラクターは吃りという特性があり、その点で演じるのが非常に難しいキャラクターだと思います。
そこを彼がどう演じ切るのかには、非常に注目です。
そして長女の園子を今の若い世代の女優で最も実力があると言っても過言ではない松岡茉優さんが演じます。
これまで彼女が演じてきたキャラクターとは少し毛色の違う今作の園子ですが、彼女の演技の幅が広がるという意味でも楽しみですね。
脇にも豪華俳優陣が起用されていますが、1つ注目なのは大悟さんですね。
彼の演じる友國淳也というキャラクターはいわゆる田舎のやくざ者ですが、堂下に献身的に尽くします。
こういった少し異業種的な演者が混じることで、作品に思わぬ化学反応を生むことがあるので、その点でも期待が持てます。
より詳しい情報を知りたいという方は、映画公式サイトへどうぞ!











映画『ひとよ』感想・解説(ネタバレあり)
様々な家族が1つの空間で交わり合う特異性
『ひとよ』という作品を鑑賞した際に、個人的に面白さを感じたのは、1つの空間の中で複数の家族の物語を描くという試みです。
1つの家と1つの家族を描く作品は数多くありますが、今作は少しそれとは毛色が違います。
そして何と言っても面白いのが、そのキャラクターの配置の仕方ですね。
もちろん作品の中心になるのは、稲村家であり、息子たちを守るために夫を殺害したこはるがキーパーソンとなります。
彼女が車で夫をひき殺したことで、兄弟は大きなトラウマを背負うこととなりました。
とりわけその最たるものが、自分たちが親になるという決断をできなくなってしまったということだと思われます。
特に大樹と雄二は「父親」というもののイメージが、子どもに暴力的なものということで固定されてしまっており、その亡霊に憑りつかれ、親になるということに対してある種の恐怖感を抱いています。
一方の園子は母親の姿と重なるように人物造形が為されており、ホステスとして働き、暴力的な男とばかり交際し、身体に痣を残しています。
そして、母のこはるは自分の犯した罪を決して正当化するわけではないのですが、自分にとっては「間違っていない」決断だったと信じています。
そんな稲村家の物語に、大樹と二三子の物語が関連してきます。
過去のトラウマに悩み、それを一人で抱え込み苦しむ彼を、間近で見ながら、自分を構って欲しい、自分に頼って欲しいと考える二三子の物語は1つの見どころです。
またもう1つ重要なのが、堂下の家族の物語ですね。
彼はかつて結婚しており、息子をもうけていますが、その後離婚してしまい、今は息子に会うことすら許されていません。
離婚の理由は彼のアルコール依存や薬物依存にあったようです。
やくざから足を洗い、タクシードライバーとして働き始めた彼ですが、息子が大学に進学するための資金援助を頼ってきたことで、何とか父親としての使命を果たそうと、再び麻薬絡みの仕事に手を出します。
またこはるの友人である弓は、自身のことを嫌い、邪険に扱う認知症の義母を心の底から憎みながらも、献身的に介護を続けています。
こういったそれぞれに問題を抱えた家族が1つの空間で交わり、それぞれの「夜明け」を目指してもがき苦しむ様が描かれるのです。
そしてこの作品において重要なキャラクターになって来るのが、こはるの恩人であるヨシナガという男ですね。
彼は1人だけ片言の日本語を話す特異なキャラクターで家族を持たない風来の身なんですが、そんな人物が1人だけ家族が交錯する空間に紛れ込み、不思議な空気感を漂わせます。
そんなキャラクターたちの全体のバランスをとるのが、タクシー会社の社長進ということになります。
このキャラクターの配置の面白さが、本作の魅力の1つと言えます。
さらに、物語の中で稲村家の面々が、他の家族の物語に両親の亡霊を見ることが、本作の物語の大きなターニングポイントにもなってきます。
雄二は自分の父親を強く嫌悪しているわけですが、そんな彼が自分の息子のために必死に身を粉にして働く堂下の姿を見て、「父親」というものに対して1つの希望を持ちます。
しかし、それが物語の後半で大きく裏切られることとなり、彼にとっての大きな試練となります。
大樹もまた自分たちに暴力を振るい、自分の指に後遺症を残した父親の存在を嫌悪していますが、二三子に対して強く当たってしまう自分の姿が父親に重なり、絶望します。
園子は母親の一件以来、美容師になる夢を諦めてしまっており、ホステスとして働き、暴力的な男との交際を続けています。
それぞれが「両親」の存在に悩まされており、自分や他人にその亡霊を見出し、苦悩と葛藤を重ねているのです。
このように1つの稲村家という家族を描くにあたり、そこに携わる他の家族の存在を絡ませたことで、物語として重層的になり、それが稲村家の面々の「夜明け」に繋がっていく点も構成として見事だと思いました。
失われた家族がその輪郭を取り戻すまでの長く特別な一夜
(C)2019「ひとよ」製作委員会
本作の中で最も印象的だったのが、次の一節です。
「あの夜・・・。」
あの夜と繰り返す堂下の声が、すすり泣きになって途切れていく。
「自分にとって、特別なだけで、他の人からしたら、何でもない夜なんですよ。」
「でも、自分にとって特別なら、それでいいじゃない。」
(『ひとよ』より引用)











稲村家は15年前に母が父を殺害するという衝撃的な事件が起こり、その時から完全に時が止まってしまっていました。
その結果として「犯罪者の子ども」というレッテルを貼られた子どもたちは苦難の道を歩むこととなります。
そんな子どもたちの前に現れたのは、15年前と何ら変わらない様子の母こはるでした。
当然、彼らは自分たちが苦しんだにも関わらず、何事もなかったかのようにケロリと返ってきた母の姿に困惑しますよね。
自分たちだけが苦しみを背負っていたんじゃないかという怒りにも似た気持ちを強く感じているのは、とりわけ雄二でしょう。
しかし、こはるは罪を犯したことを認め、正当化するわけでもなく、それでも自分があの夜に下した決断は間違っていなかったと言い切るのです。
それはまさに、子どもたちを守るんだという母の覚悟でもあります。
世間的に見れば、母親が取った「殺人」という行為は決して許されるものでもありませんし、どんな事情があろうと理解されるものでもありません。
彼女を擁護するような記事が出舞ったとしても、それは決して覆らないことです。
ただ、彼女が望んでいるのはそういうことではありません。
自分だけでも「あの夜」が正しいと思えていれば、それでいいのだと思い込むことです。
しかし、大樹や雄二は、どうしてもそれが正しかったとは思えません。
それでも彼らは自分や他人に父親の亡霊を見る中で、母親の決断に対して理解を示すようになります。
大樹は二三子に対して強く当たってしまう自分の姿が父親に重なり、ショックを受けますが、苦しんでいる自分を見かねて「余計なおせっかい」を焼こうとした彼女を受け入れるという行為を通じて、こはるを理解します。
そして雄二は、自分たちの父親の姿に重なる堂下という男を痛めつけることで、自分の行動と母親の行動を重ね、彼女に対して理解を示そうとします。
彼らは、少しずつ母親と同じ思いで「あの夜」のことを捉えられるようになっていったのです。
そして物語のラストに、彼らが苦悩と葛藤の中で過ごした「あの夜」が夜明けに向かって動き始めます。
母の両目から涙が吹きこぼれた。
開いた足はそのままだが、体の形が変わっていた。
だらりと脱力した腕につられて両肩は前に下がり、背は骨のつぶれた老婆のように丸まって、ひょこりと顎が突き出てしまっている。母は、もう母の形を保てなくなっていた。
(『ひとよ』より引用)











3人の子どもたちは、互いに母の決断に対して理解を示し、そして歩み寄ろうと努力します。
そしてその結果として、「あの夜」のイメージのままで帰ってきたこはるという存在は確かに崩れ去ってしまうのです。
きっと彼らが取り戻したかったのは、とりわけこはるが取り戻したかったのは、15年前から何も変わらない家族の暮らしの延長線だったのかもしれません。
それは、彼女が夫を殺害した直後に、料理を作りだめしてから自主に向かったという行動にも表れていると言えます。
しかし、確かに父親が殺害され、母親が逮捕されたことで子どもたちの人生は大きく変化してしまいました。
もはや彼らに、あの事件がなかった人生は考えられないほどに変化してしまったのです。
だからこそ、彼らは15年前から変わらない様子で帰還した母親に強い違和感を覚えました。
ただ、それはこはるの覚悟であり、不安や恐怖を拭い去るための仮面でもあったわけです。
3人の子どもたちは、物語の果てに、ようやく彼女が背負ってきたものの重さを理解し、そしてそれを「家族」として共に背負っていくことを「覚悟」できました。
それまで、なぜ母親が犯した罪に自分たちが振り回されなければならないんだと「他人事」のようだった彼らがようやく「あの夜」を共通理解として「特別」だったんだと確認することができたからです。
「母の形」が崩れていくというのはつまり、「家族の形」が崩れていくということでもあります。
彼らが15年前に築き上げていた「稲村家」というものは、もはや跡形もなくなってしまったのかもしれません。
それでも彼らは、変わってしまった母親を支え、その覚悟を共に背負うことで、新しい「稲村家」の形を作っていくことでしょう。
稲村家が苦しんだ長い長い夜が、その物語の最後に確かに「明けて」いくカタルシスに涙が止まらなくなります。
震災のコンテクストを反映した作品
本作のインタビューを読んでいると、原作者の桑原裕子さんが本作『ひとよ』を著した時のことについて次のように綴られていました。
桑原が『ひとよ』の脚本を執筆したのは、2011年の夏。東日本大震災を受け、自分にできることをしようと突き進み、稽古場で芝居に没頭する日々を送っていた時だという。世間では「絆」「復興「再生」という言葉が絶えず飛び交うなか、それは一体どうすればできることなのか、不安や無力感や行き場のない想いと、どう向き合えばいいのか。自分の存在が誰かの心を救うことは出来るのか。さまよう問いに答えを見つけられないまま描いたのが、『ひとよ』なのだそう。
白石監督の作品は前作の『凪待ち』も強くポスト震災の雰囲気を感じる作品になっていましたが、それに引き続いて今作『ひとよ』も震災のコンテクストを背負った作品と言うことになります。
とりわけ本作は、ある「一夜」に起きた母が子どもたちを守るために夫を殺害するという事件が、「家族」の形を大きく変えてしまうという物語になっています。
そして彼らは懸命にその「一夜」がなかったかのように生きようとしますが、世間はそれを許さず、彼らは「殺人者の子ども」というレッテルを背負い、苦悩しながら人生を送ることとなります。
この物語の展開を鑑みると、まさに稲村家に起こった事件ないし「一夜」は、日本にとっての東日本大震災に重なるようにも思えますね。
先ほど引用したセリフは震災のコンテクストで読み解くと、また違った意味合いを持っているようにも感じられます。
「あの夜・・・。」
あの夜と繰り返す堂下の声が、すすり泣きになって途切れていく。
「自分にとって、特別なだけで、他の人からしたら、何でもない夜なんですよ。」
「でも、自分にとって特別なら、それでいいじゃない。」
(『ひとよ』より引用)











今年公開された映画で『火口のふたり』という作品があったのですが、この中で「被災者になったふりは出来ても、被災者にはなれない。」というセリフがありました。
『ひとよ』におけるこはるのセリフは、まさしくこのセリフに重なります。
きっと被災した人たちにとっての「あの日」は、そうでない人には推し量りがたいものでしょうし、それによって壊れてしまった街、生活、人生、命、その何もかもが元に戻ることはありません。
それでも生きていくしかない、そして生きていればいつか「あの夜」から抜け出し、夜明けを迎えることができる。
桑原裕子さんは、壊れた家族の再生の物語の中に、壊れてしまった日本の、そして被災者の人々の再生への希望を見ていたように思います。
兄弟たちが力強く、朝焼けの中で、家族の形を結び直し生きていこうと決意する様に涙が止まらなくなるのは、心の底からの強い「生」への渇望を感じるからなのかもしれません。
淡々とした文字列に感情を宿らせた白石監督の才覚
正直に申し上げると、実は個人的には小説版はそれほどハマらなかったんですよ。
何と言うか無機質な台本を読んでいるような感じがして、最初から最後まで気持ちが乗らず、取り立てて印象に残る場面もありませんでした。
しかし、映画版を見ると、この物語はかくも奥深くて、それでいてエモーショナルなのかとハッとさせられました。
白石監督の作品って基本的にバランス感覚が非常に優れていて、さらに言うと、きちんと映像的な見せ場を用意している点も非常に映画監督として秀でた点だと思います。
まず、白石監督は基本的に真面目なんですよね。
ですので、シリアス路線の映画でしかもそこに時折ユーモアを交えるというシリアス:ユーモア=9:1~8:2に近い作品であれば、抜群の出来栄えを誇ります。
しかし、コメディ路線でそこにシリアスを混ぜようとするという逆転現象が起こり始めると、クラスの優等生が懸命にボケようとしているような痛々しさが漂ってきて、作品の出来もそれに比例して下降します。











今回の『ひとよ』に関して言うなれば、シリアス:ユーモア=8:2の白石監督的黄金比で作品が構成されていたように思いますし、そういったユーモアが作品のリズムにアクセントを加えていました。
また、静の演技と動の演技のバランスも非常に素晴らしくて、彼の作品はよくある邦画大作のように、とにかく大袈裟に演技をさせるといった悪手を取ることはありません。
本作で特に際立っていたのは、個人的には松岡茉優さんに思えました。
確かに映画を撮影するにあたってセリフはある程度準備されていることともいますが、彼女が演じた園子は時折、素で飛び出したような「つぶやき」的な発言をするんです。
特にそれが物語に関係しているわけではないんですが、その何気ない「つぶやき」があることで園子という人物が確かに意思を持って生きていることがスクリーンを越えて伝わってきました。
こういった静かな作品にリアリティをもたらすための静の演技を白石監督は作品の中で積み重ねていきます。
そして、作品のクライマックスでせき止められていた感情を一気に爆発させ、演技を静から動へと転じさせるのです。
このバランス感覚の良さがやはり白石監督の良さだと思いました。
さらに、彼は映像で魅せるという点においても非常に秀でた手腕を持っています。
個人的に唸ったのは、終盤のタクシーを衝突させるという演出とラストで家族4人で写真を撮影するという演出です。
この2つはどちらも原作には存在しないシーンで、映画版オリジナルだと言えます。
まず、タクシーを衝突させるシーンですが、これは言わば平行線のままで交わろうとしなかった母と子の物語がダイナミックに交錯するという演出ですよね。
子供の頃は見失って追いつくことができず、大人になっても雄二は自分の家族のことを週刊誌に書くなど他人事のように考えていました。
そんな彼がアクセルを踏み込み、自らの意志で母の物語と交錯することを決断したのです。
また、後者の写真撮影については、これは「家族のカタチの変容」を視覚的に表現したものと言えます。
作中でしきりに稲村家の5人が映った写真が登場しましたが、ラストで彼らは「変化」を受け入れ、前に進むことを決断します。
そんな変化を2枚の写真で視覚的に表現してしまおうとする白石監督のセンスも光っていたと思います。
原作と時点ではそれほど傑出した内容でもなかった本作を、視覚的な雄弁さと絶妙なバランス感覚で傑作に仕上げたという仕事ぶりに感動しました。
おわりに
いかがだったでしょうか。
今回は『ひとよ』についてお話してきました。











何と言うか良くも悪くも舞台の脚本チックな内容なので、登場人物の説明が特にないままに、たくさんのキャラクターの名前がポンポンと繰り出されるので、正直誰が誰だかを把握するのに時間がかかります。
その点では、非常に舞台向きな作品だと思いますし、もっと言うなれば、映画向きな作品とも言えます。
白石監督は前作『凪待ち』でも閉塞的な田舎で繰り広げられる壊れた家族の物語を見事に描き切っていたので、今作『ひとよ』の映画版にはかなり期待が高まります。
今回も読んでくださった方、ありがとうございました。