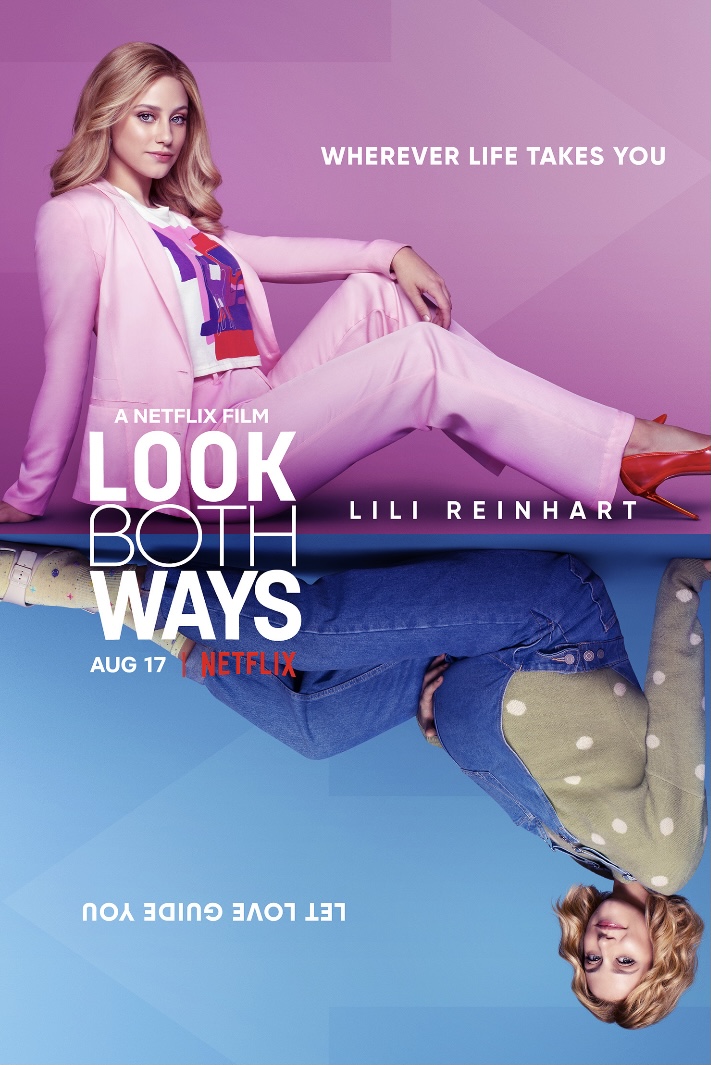みなさんこんにちは。ナガと申します。
今回はですね映画『アイリッシュマン』についてお話ししていこうと思います。

本作『アイリッシュマン』は製作会社が逃げ出すほどの超大作で、予算もとんでもない金額だったと言います。
しかも極めつけはその上映時間でして、何と200分超え。3時間30分近い作品になっているのです。
とは言っても近年の代表作である『沈黙』や『ウルフオブウォールストリート』も3時間近い映画だったので、そう考えると彼にとってはスタンダードなのかもしれません。
ただ、この作品が劇場向きなのか、Netflix向きなのかという問いに答えを出すのは難しいですね。
前者だと集中して見ることができる一方で、連続して鑑賞することになり体力的に厳しい感がありました。



















ただNetflixで見るとなると、4時間弱の時間をパソコンやテレビ、スマホ等を見つめて過ごすことになるわけで、それはそれで進度いですよね。
結局は、本作が5〜6の章に分かれた作品という感じなので、家で話が切れたところで休憩を入れながら見るのがベストでは?が私の回答です。
それほど力んで見るような作品ではなく、比較的緩めな内容なので、マイペースに見るのが良いでしょう。
さて、本記事は作品のネタバレになるような内容を含む解説・考察記事となっております。
作品を未鑑賞の方はお気をつけください。
良かったら最後までお付き合いください。
目次
『アイリッシュマン』
あらすじ
1975年にアメリカで後に最も有名な未解決事件の1つとなるホッファ失踪事件が起きる。
なぜ、彼は失踪し、殺害されたのか?誰が事件を手引きしたのか?
FBIは内偵を裏社会に忍ばせ、犯人を数名のところまで絞り、徹底的な捜査を続けたが結局のところ犯人を確定させることはできなかった。
そんな時、事件について1人の男が口を開く。
それがジミー・ホッファの親友であり、ラッセルに仕え、裏社会で暗躍したフランク・“アイリッシュマン”・シーランという男だった。
フランクは自分自身の人生への救済を求めるが如く、事件の真相を語る。
それは、彼自身がホッファの「家にペンキを塗った(殺害したという意味)」という衝撃的な事実だった。
元々精肉店で働く普通の心優しき男だった彼が、なぜ、裏社会と繋がり、そしてあの失踪事件を手引きすることとなったのか。
1人の男の人生の栄枯を淡々と描く超大作となっている。
スタッフ・キャスト
- 監督:マーティン・スコセッシ
- 脚本:スティーヴン・ザイリアン
- 撮影:ロドリゴ・プリエト
- 音楽:ロビー・ロバートソン
- 編集:セルマ・スクーンメイカー



















まず監督のマーティン・スコセッシは言わずもしれた名匠ですよね。
アメリカンニューシネマの黄金期を支えた旗手であり、『タクシードライバー』や『キングオブコメディ』のような傑作を連発しました。
またギャング映画も多く手掛けており、『グッドフェローズ』は特に高く評価されています。
そして脚本には『シンドラーのリスト』で知られるスティーヴン・ザイリアンが加わりました。
伝記映画にはめっぽう強い監督ですし、ニューシネマの傑作や多くのギャング映画も手掛けているので、『アイリッシュマン』には最適な人物の1人と言えるでしょう。
また撮影・編集にはスコセッシ作品には欠かせないセルマ・スクーンメイカーとロドリゴ・プリエトですよね。



















- フランク・シーラン:ロバート・デ・ニーロ
- ジミー・ホッファ:アル・パチーノ
- ラッセル・バッファリーノ:ジョー・ペシ



















まさかのギャング映画を支えてきたこの3人が揃い踏みするというとんでもなく豪華な映画に仕上がっております。
まず、言わずも知れたギャング映画のキングたるロバート・デ・ニーロですね。
『グッドフェローズ』はもちろん『ワンスアポンアタイムインアメリカ』や『ゴッドファーザー』にも出演するなど、名実ともにハリウッドを代表するギャング映画俳優ですよね。



















そして『ゴッドファーザー』シリーズでおなじみで、『カリートの道』などにも出演する大御所アル・パチーノも今作に出演しております。
またこちらも『ワンスアポンアタイムインアメリカ』や『グッドフェローズ』で知られる名優ジョー・ペシがラッセル役での出演となっております。
そんな映画である『アイリッシュマン』は栄華を誇ったギャングたちの静かな最期を描いており、この3人の名優のキャリアが終盤に差し掛かっていることも相まって妙にエモーショナルな一作になっています。



















ギャングエレジーたる本作を、ぜひ彼らが活躍していた過去の名作と共に味わっていただきたいと強く感じる次第です。
『アイリッシュマン』解説・考察(ネタバレあり)
とんでもなく難しいことを簡単そうにやり遂げる
マーティン・スコセッシ監督の凄みは、やっぱり3時間30分というとんでもない尺の映画をいとも簡単に成立させてしまうことなんだと思います。
『アイリッシュマン』の原作については当ブログ管理人も読んではみたんですが、正直に申し上げると、それほど起伏が大きい話でもなくて、さらに言うと、エモーショナルでもありません。
これはあくまでも、フランク・シーランという1人の男の告白の物語なのであって、クライムサスペンスのようなハラハラとする緊迫感があるわけでもなく、至極淡々と進んでいくんですね。
さらに言うと、長時間に及ぶ伝記映画であるため、とにかく登場人物が多いんですよ。
様々な勢力が出てきますし、登場人物の相関図も物語が進行するにつれて複雑化していきますし、さらに言うと『アイリッシュマン』は3つの時系列で物語を並行的に進行させるというトリッキーなことをやっています。
シーランの老人ホームでの告白、ホッファ失踪事件直前、そして彼の過去の回想と3つの物語が流れていき、それを斜めに読んでいくかのようなスタイルになっておりました。
原作の構成は、冒頭にホッファ事件のことについて触れられて、その後は時系列通りという感じだったんですが、映画はより物語構造を複雑化させている印象を受けます。



















ただ、そんなほとんどの映画監督に務まらないであろう困難なタスクを誰にでもできるかのような軽いノリで、サラッと仕上げてしまうところにマーティン・スコセッシ監督の卓越した手腕が光っています。
まず、彼は人間関係というものは、物語そのものではなく映像が観客に伝えていくのだということを熟知しています。
例えば、シーランがホテルのタオルクリーニング業者を襲撃しようとして、ラッセル・バッファリーノの呼び出しをくらうシーンがありましたよね。
このシーンを見て見ますと、次のようなカメラワークと人物配置になっています。
(映画『アイリッシュマン』より引用)



















このシーンは、端的に言えば、シーランがラッセルたちに脅されている状況であるわけですが、そういう物語的なコンテクストを知らなくても映像だけで人物の関係が透けて見えませんか?
手前に映るラッセルたちは影になっており表情が見えません。
しかもフレームに収まりきらないほど大きな存在なのに、対照的に画面中央のシーランは距離的に遠くにいるわけで、そのために幾分小さく映っており、照明によりその表情が伺えます。
こういった映像だけでサラッとその人物が置かれている状況や、人物と人物の関係性を説明できてしまうスキルを持っているからこそ、マーティン・スコセッシ監督は複雑な設定や関係性を無意識的に観客に理解させてしまうわけです。
さらに言うと、この冒頭のシーンに近い状況を作品の後半でも描いていて、それがトニー・プロとホッファの会談のシーンにあたるのですが、今度は逆にシーランがビッグボス的な立ち位置に座っており、カメラワークもそれを意識させます。



















もう1つ印象的なシーンだったのは、ホッファをついに殺害現場となる家に連れて行くという局面の一幕です。
(映画『アイリッシュマン』より引用)
この3人はそれぞれ向かって右側にホッファ殺害のことを知っているサリー、手前には何も知らないチャッキー(ホッファの息子)そして後部座席にフランクが座っています。
まずその状況を3人の表情や顔の向きで何気なく仄めかしている点も驚きですが、それに加えて、このシーンで重要なのは、フレームを3人の人間で埋め尽くしていることだと思います。
これからホッファを車に乗せようという局面にもかかわらず、彼が乗車するスペースはフレームアウトしているんですね。
では、どのタイミングで彼の乗車スペースを映し出すのかと言うと、フランクのいる後部座席に視点が映った瞬間です。
(映画『アイリッシュマン』より引用)
小説にも書かれていましたし、この一連のシーンにおけるホッファの警戒する素振りを見ても明らかなのですが、百戦錬磨の彼はそんな簡単に罠にはまるような男ではありません。
しかし、それでもなお彼は自分を殺害現場へと連れて行くための車に乗り込んでしまったのかと言うと、それはフランクの存在があったからなんですね。
この映像は実にそんなホッファが車に乗り込んでしまうに至った心理的な安心感を見事に表現しているとは思いませんか?
「問題ない」「安心しろ」と語るように小さくうなずき柔和な表情を浮かべるフランクは少し奥行きをもって配置されており、彼とホッファの間にはホッファが座ることになるであろうスペースが映し出されているのです。
こういうカメラワークと人物配置で、警戒していたホッファが車に乗り込んでしまうまでの一瞬の心情の変化と機微を見事なまで表現しているんですね。
こういうカメラワークと編集をサラッとやって、登場人物の心理や関係性を視覚的に表現してしまうのですから、もう脱帽ですよ。



















それを聞くと、これほど高度で難しいことを作品の中で断続的に行っているのに、「普通過ぎる」という感想を引き出してしまうマーティン・スコセッシ監督の凄さに改めて驚かされます。
いわば、彼はフィギュアスケートで言うなれば、前人未到の5回転ジャンプを何度も繰り返し飛んでいるのに、観客はその凄さにイマイチピンと来ていないという状態なわけですよ(笑)
3時間30分の尺がある映画なので、もちろんシーン単位で語るならば、もう語りたいことは山ほどあるわけですが、今回は予告編にも登場していて、個人的にも印象的だったものをいくつか取り上げました。
また撮影もそうですが、編集も卓越していて、3つの時系列をシームレスに繋いでおきながら、観客に特に大きな混乱を引き起こさない技術は驚異的と言えます。
そして照明も非常に素晴らしいものになっていて、例えばフランクのキャリアの序盤には、先ほどの引用したシーン(フランクがラッセルらに呼び出される場面)もそうですが、白色系の「朝日」を思わせる照明が多用されています。
一方で彼がキャリアの晩年を迎える頃になると、照明が落日の頃を思わせるようなオレンジ色が多用されるようになります。



















(映画『アイリッシュマン』より引用)
まさに太陽が地平線の方に沈む時間帯を思わせる照明の使い方であり、偉大な男の人生の晩年を強く印象付けます。
さらに言うと、その後の彼の「告白」のシーンでは、自然光による白色光が凄く印象的に用いられています。



















(映画『アイリッシュマン』より引用)
先ほどの、人生が少しずつ終盤へと向かって行くかのような夕日の色ではなく、もはや「死」の臭いに憑りつかれている様で、それでいて「平穏」に辿り着いたかのような自然光が見事に機能しています。
このように『アイリッシュマン』はマーティン・スコセッシ監督の円熟した技術を見せつけられるような見事な1作だったと思います。
辿り着くのは栄枯必衰と信仰への帰依
マーティン・スコセッシ監督の作品において、キリスト教というのは1つの大きな主題です。
彼自身もカトリックの司祭を目指していたというほどに敬虔なカトリック教徒なのですが、その作品を見てみると、キリスト教社会に疑念を呈するような作品も目立ちます。
前作である『沈黙』も遠藤周作の原作の映画化であり、そもそもの原作がキリスト教社会に議論を呼んだとも言われています。
そして彼とキリスト教の関係を語る上で避けては通れない映画は、もちろん『最後の誘惑』でしょう。
キリスト教社会で大きな議論を巻き起こし、一部地域では上映の中止が決まり、製作期には脅迫状が届いたりするなど、とんでもない抵抗を受けながら公開された1作です。
物議を醸したのは、マグダラのマリアと普通に結婚して、多くの子どもをもうけ、人間として死ぬという誘惑があったという解釈が作品の下地にあったことです。
このように彼の作品では、常にキリスト教との向き合い方というのが、主軸の1つに据えられてきたわけです。
そして面白いことに『アイリッシュマン』という作品においても「キリスト教」ないし「信仰」というものが印象的に描かれています。
本作の中で描かれたキリスト教観を紐解くと、実はそれが『最後の誘惑』の頃からの変わらない思いに裏打ちされていることが伺えます。
彼はかつて『最後の誘惑』についてこんなことを話しておられました。
もしもこの世にキリスト教がなく、神と自分しかいないと仮定しよう。そういうレベルで私はこの映画を作りたかった。
(中略)
教会に行き、告白を行い、教会の建物の中でキリスト教の考え方に耳を傾ける。しかし一歩外に出れば、拳銃が生活を支配している。それじゃあ、そんな世界で人はどうやって良きクリスチャンとして生きていくのか?
こういったテーマのすべてが長い間私の中で渦巻いていて、『最後の誘惑』においてようやくあるひとつのかたちに到達した。
(『スコセッシ・オン・スコセッシ』より引用)
彼が元々、司祭になろうとしていたというのは、有名な話です。
彼が生まれ育ったリトルイタリーではギャングと教会が力を持っており、そんな環境で育ったからこそ、彼は神父の人生や説教に心を打たれたのです。
しかし、結局、彼は神父への道を諦めて、大学に通うことになります。
そして彼は映画を撮る中で、徐々に協会から足が遠のいていき、カトリック教会のイエスに対するあまりにも妄信的な賛美に対して疑問を感じるようになっていました。
まさにそんな時に『最後の誘惑』という作品を手掛けることになったわけですね。
そしてこの撮影の中で、彼は自分自身のキリスト教との向き合い方について考え、そして1つの答えに辿り着いたと言います。
祈りというものは普通の日常生活の中と関わっているのだろう。自分の家族と関わる中で、つまり子供をどうやって育てるかとか、妻とどうやってうまくやっていくかといった、そういうことのなかで神は見出されるものなのだろう。祈りの真の意味は現代ではそんなところにあるのかもしれない。
(『スコセッシ・オン・スコセッシ』より引用)
教会という場所に縛られない、街や通りにも信仰の端緒は散りばめられているのだという考え方に彼は辿り着いたのです。
そしてその後の作品でも、常にキリスト教観は問われ続けていたと思いますが、やはり前作の『沈黙』はかなり彼の中でも大きな試みの1つだったと思います。
この作品は西洋的な父性に基づくキリスト教信仰と、日本に根付いた母性に基づくキリスト教の対比を描き、日本にやって来た司祭たちが受難の中で、自身とキリストを重ねながら、信仰の意味を深く考える作品です。
作中で、ロドリゴという宣教師が、受難の果てに「踏み絵」を迫られます。
この時、銅板に描かれたイエスは彼にこう語りかけるのです。
「踏むがいい。銅板のあの人は司祭に向かって言った。踏むがいい。お前の足の痛さをこの私が一番良く分かっている。踏むがいい。私はお前たちに踏まれるため、この世に生まれ、お前たちの痛さを分かつため十字架を背負ったのだ。」
(『沈黙』遠藤周作より引用)
フェレイラという先に日本で棄教していた宣教師がいました。
彼はこの行為について「今まで誰もしなかった一番つらい愛の行為」なのであると述べました。
つまり、ロドリゴは西洋の境界的なキリストに背きましたが、それと同時に何か別の信ずるものを手に入れたのはないかと考えられます。
このような神の不在の中で自己の信仰の在り方を問い続ける作品だからこそ、マーティン・スコセッシ監督は『沈黙』という小説の映像化に踏み切ったのだと考えられます。
神は教会の中にも、聖書の中にも、そして銅板にも描かれておらず、自分がただ信じたいように信じるものなのであり、形式に縛られる必要はないのだということです。
そんなマーティン・スコセッシが、『アイリッシュマン』という作品に惹かれるのは至極当然だと私は原作を読みながら感じました。
なぜならこの作品の主人公であるフランク・シーランという男に、彼は絶対に惹かれると思うからです。
フランクもまた幼少の頃から厳格なカトリックの家で育ったわけですが、彼は戦争を経験し、そこで暴力性に慣らされてしまい、更にはラッセルと関係を持ち、裏社会へと足を踏み入れたことで、家族や信仰を蔑ろにし始めるのです。
そして彼は初めて「ペンキを塗る仕事」をして以来、人が変わってしまいます。
一線を越えて新たな世界に足を踏み入れたおれには、もう土曜日に懺悔することも、日曜日にメアリーと教会に行くこともなくなった。すべてが変わった。
(『アイリッシュマン』チャールズ・ブラントより引用)
彼は信仰というものからおおよそ距離を置いてしまうんですね。
そして彼は裏社会で暗躍し、多くの重要人物から信頼される地位を築いたわけですが、そこにホッファ失踪事件という人生最大の出来事が起こります。
自分の恩人を自らの手で抹殺することになるというあまりにも残酷すぎる事件を経験することになるのです。
しかし、当然このことを誰にも話すわけにはいきませんし、彼はただ自分の中で抱え込むことしかできませんでした。
なぜなら、彼がホッファ失踪事件の真相をすべて語ってしまえば、芋づる式に多くの裏社会の人間が検挙されるわけで、更には自分の家族にも多大な迷惑をかけることとなります。
彼は自分が抱え込んでいるものの大きさを知っていますし、同時にそれに対するとてつもなく大きな罪悪感を誰にも共有することもできずにただ1人で背負っていたのです。
そんな彼が人生の晩年に救いを求めたのは、自分がかつて蔑ろにし、いつしか距離を取るようになっていた「キリスト教」でした。
彼はキリスト教の信仰を取り戻し、そして自分の行いを悔い、赦しを求めるようになりました。
『アイリッシュマン』という作品は、そもそもチャールズ・ブラントがフランク・シーランという男にインタビューをしたことで生まれた小説であり、そこには彼の「告白」が綴られているわけです。
人生の最後の最後に、彼は自分が犯した最大の罪の「告白」をし、赦されたいと切に願ったんですね。
彼が終盤に、自分の人生を回顧しながらチャールズに語った言葉が何とも印象的です。
彼はいくつかの事柄に対して悔恨の情を示し、仕事をしたあとは「正しいことをしたのだろうか」と自問自答していたと語った。
(中略)
「おれの仕業だとされていることを実際すべてしていたとして、同じことをもう一度しろと言われても、おれはしない。」
(『アイリッシュマン』チャールズ・ブラントより引用)
フランクという男は確かに善性を持っていたのかもしれませんが、戦争での狂気的な経験が彼の中で何かを狂わせてしまったかのように感じられます。
しかし人生の最後に、彼は信仰に帰依し、自分の人生を遡る中で、その行いの多くを悔いているのです。
もちろん彼が多くの人を殺害してきたという事実が覆ることはないですし、それが罪であるということには変わりありません。
それでも、そんな形で辿り着く信仰としてのキリスト教があるのだという点は、間違いなくマーティン・スコセッシの興味を引く題材であったと言えます。
彼は自分がホッファを殺害したと語っていますが、決して自分以外の人を貶めることを望まず、あくまでも自分がやったのだということだけを明かしています。
その点で、彼がチャールズ・ブラントのインタビューに応じたのは、単なる暴露のためではなく、彼が赦しを乞うための「告白」なんですね。
そういう意味でも彼が為した真実を明るみに出すという行為は、ある種の信仰なんですよ。
フランクが物語の最後に辿り着いた「安らぎ」の境地とは、一体どんなものだったのか。人生の最後の最後に辿り着く、信仰の境地とはどんなものなのか。
形式的なものや伝統的なものに縛られたものとしてではない、心の底から溢れ出るように生まれた「信仰」の1つの形が、まさに描かれていたようにも感じられました。
フランクが開け放ったドアが意味したものとは?
(映画『アイリッシュマン』より引用)
原作は、基本的に対談をベースにした小説になっているので、物語としての明確な幕切れはないのですが、映画となるとそうはいきません。
しかし、マーティン・スコセッシ監督は、見事にこの壮大な3時間30分にわたる物語を完結させています。
とりわけ多くの人が注目するのは、本作のラストでフランクが神父にドアを開けておいてくれと頼むシーンでしょう。



















まず、ドアを開けたままにするという行為は、実は映画の比較的序盤にも登場しています。
それは、フランクがホッファと同じホテルに泊まるシーンなのですが、この時にホッファが自分の寝室のドアを少し開けたままにして眠りにつくんですね。
明確にその意図が語られるわけではないですが、これはおそらくドアが開いていることで、彼を襲撃しようとしてやって来た資格がいた場合に何か罠があることを警戒させようとしているのではないでしょうか。
ドアが完全に閉まっていると、相手は逆にホッファは警戒を解いていると思うでしょうし、完全に開いた状態だと狙われ放題です。
その点で、彼なりの合理的な保身術の1つだったのかもしれません。
このシーンが序盤で描かれているからこそ、ラストシーンで彼がドアを少しだけ開けたままにしたのは、フランクなりのホッファへの哀悼と謝罪の意なのかもしれません。
ただ、私はこのシーンがそれだけを意味しているとは思いません。
このラストシーンにおける扉というのは、フランクの心の扉を表現しているように思います。
つまり、少しだけドアを開けたままにするというのは、彼が長年心の内に閉じ込め続けてきたホッファ殺害の秘密を誰かに打ち明けたがっていることを表しているのです。
ホッファを殺害する際に、彼は無人の家に誘い込み、そして彼を殺し、その家の扉を閉めて逃走しました。
きっと彼は、あの時彼にとってすごく大切だったものを「扉」の向こう側に閉じ込めて来てしまったのでしょう。
だからこそ、彼はあの日、あの場所で自分が閉じ込めて来てしまった思いを解き放ち、そして赦しを請いたいと切に願っているのです。
そして、もう1つは、やはり自分の娘に対しての思いの表出なんだと思います。
フランクは彼なりの愛情で家族を守ってきたつもりでいましたが、彼の好戦的で暴力的な様はむしろ家族を苦しめてしまっていました。
老いた彼は、必死に4人の娘たちとの関係を結びなおそうとしますが、上手くいきません。



















それでも彼は、家族と娘たちと話したいのです。
ラッセルをはじめとしたかつての戦友たちは老いてこの世を去り、家族から距離を置かれている彼は孤独そのものです。
自分で自分の入る棺桶を購入し、自分が入る墓地の予約をするなどしている様は見ていて哀しくなるほどです。
だからこそ、彼が少しだけドアを開けているのは、彼が娘たちに対していつか自分と話していくれることを待っているという意志表示なんですよね。
これまで物語の中心にいたフランクが扉の隙間から垣間見えるちっぽけな存在になっているという演出ももの悲しさを助長しています。
あの原作を咀嚼して、このラストシーンを用意しようと思い至る監督は、きっとマーティン・スコセッシくらいのものでしょう。
おわりに:ギャングたちの晩年
いかがだったでしょうか。
今回は映画『アイリッシュマン』についてお話してきました。
本作の監督を務めたマーティン・スコセッシも、そしてメインキャラクターを演じたロバート・デ・ニーロらもキャリアの晩年に差し掛かっています。



















まず今作のメインキャスト3人はアメリカのギャング・マフィア映画を代表する3人と言っても過言ではありません。
暴力を武器に、裏社会で暗躍し、政治や経済を動かしてきたのが、ギャングたちであり、本作『アイリッシュマン』においても政治にギャングたちが及ぼした多大な影響が描かれました。
しかし、そういった暴力の時代は「アウトオブデイト」になり、ギャング映画というジャンルそのものが衰退しつつあります。
だからこそ、今ギャング映画を代表するスターたちが、自身の人生に幕を引くかのような人物を演じることが1つの大きな「終わり」を感じさせてくれます。
あの時代が終わってしまったのだという切なさと、そして監督やキャスト陣のキャリアが晩年に差し掛かっているという悲しさも相まって、終盤の展開は非常にエモーショナルになっていると言えます。
どんなに繁栄したものも、どんなに栄光を掴んだ者も、時間の流れと共にスクリーンの中央から端へと追いやられていき、「過去のもの」となっていきます。
どんなものにもいつしか必ず「終わり」の時がやって来るんですね。
もっと言うなれば、今作の製作段階で監督自身が予算的に厳しいということで、配給会社から見放されているんですが、映画界の状況も変化していて、ギャング映画に大規模な投資をすることも難しくなっています。
監督自身もいつしか自分の映画人生に幕を引かざるを得ないわけで、「終わり」の到来は避けられないもののはずです。
そういう意味で考えると、『アイリッシュマン』という作品は、ギャングたちが自らの「引き際」について考える映画でもあります。
引き際を見出せず、親友に引導を渡されたホッファのような人物もいれば、自ら身を引いて信仰に帰依していったような人物もいます。
そんなギャングたちの様が描かれるからこそ、マーティン・スコセッシやロバート・デ・ニーロ、アル・パチーノらの映画人生への「幕引き」を妙にリアルにイメージしてしまい、涙が溢れました。
少しずつ画面中央からフレームの外へと近づいていくラストカットのフランク・シーラン。
まさにスクリーンの中心にいたスターたちが少しずつフレームアウトしていく様を見せつけられたかのような印象でした。



















作品の出来も素晴らしいことながら、そのあまりのエモーショナルさに冷静には見られない作品でもあったと思います。
今回も読んでくださった方、ありがとうございました。
関連記事



















ちなみに後者には、「チームスター」やホッファなど、本作に繋がる要素も登場するので必見です。