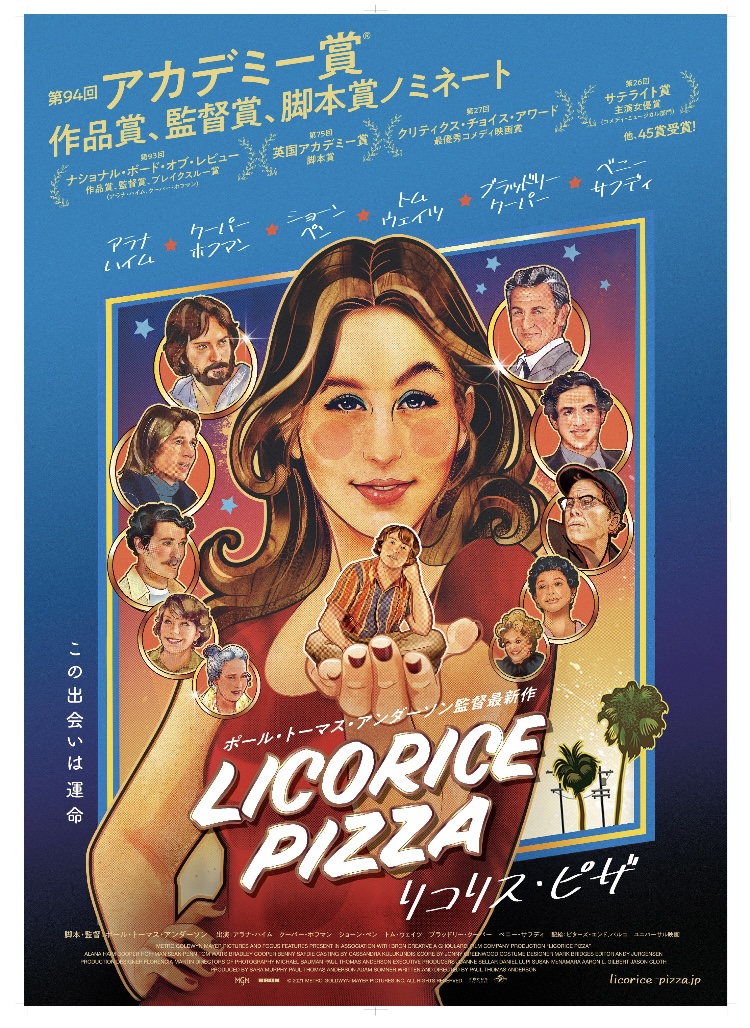みなさんこんにちは。ナガと申します。
今回はですね『マチネの終わりに』についてお話していこうと思います。

予告編の蒔野聡史(福山雅治さん)がかなり気持ち悪いということで話題になっていましたが、まあ基本的にセリフに至るまで原作通りです。
大人のラブストーリーというイメージで認識されているように思いますが、個人的にはリチャード・リンクレイター監督の『ビフォア』シリーズやディミアン・チャゼル監督の『ラ・ラ・ランド』を思い出す内容でした。
何気ない会話を重ねて、お互いに惹かれ合っていくという恋愛の描き方は個人的に大好きなので、その点で嫌いなはずが無い作品でしたね。
一方で、『ラ・ラ・ランド』を思い出させる内容でありながら、真逆に近いことをやってのけるという「愛の狂気」にも震えました。
第2回渡辺淳一文学賞受賞を受賞した作品で、発売以来多くの人に読まれ、そして映画化の運びとなりました。
予告編の気持ち悪いイメージが先行しがちですが、個人的には小説を読みながら終盤ボロボロと泣きました。
そんな作品について今回は余すところなく語っていきたいと思います。
本記事は作品のネタバレになるような内容を含む感想・解説記事となっております。
作品を未鑑賞の方はお気をつけください。
良かったら最後までお付き合いください。
目次
『マチネの終わりに』
あらすじ
サントリーホールでの演奏を終えたクラシックギタリストの蒔野聡史は、偶然演奏を聞きに来ていたジャーナリストの小峰洋子と出会う。
その夜のコンサートで、会場の聴衆を惹きつけたのは、アランフェス協奏曲だったが、彼が会心の出来だと感じていたのは、アンコールで演奏したブラームスの間奏曲第2番イ長調だった。
そんな中で小峰洋子はたった1人、ブラームスの間奏曲第2番イ長調が良かったと言ってくれたのだ。
懇親会で2人は語り合い、お互いの波長が合うことを確認しながらも、彼女にフィアンセがいることもあり、その夜は特に何も起こらないまま別れた。
洋子はその後、バグダッドに取材に向かい、蒔野は日本からスカイプやメールで連絡を取っていた。
そんなある日、バグダッドの彼女が宿泊していたホテルでテロ事件が起こる。
幸い、彼女は一命をとりとめるも、その出来事が心に大きなトラウマを植えつけてしまうこととなる。
蒔野はマドリードでコンサートを開催することとなり、その際にパリに住む洋子のもとを訪れる予定を立てる。
蒔野は彼女に再会し、気持ちを抑えることができなくなり、彼女に愛を告白し、フィアンセとの結婚を止めようとする。
洋子はその求めに応じたかったのだが、迷いが生じ、マドリードのコンサートの後に、再びパリを訪れた際に返事をすることにしたのだった。
揺れ動き、すれ違う2人の恋愛譚は、どんな結末を迎えるのか・・・?
スタッフ・キャスト
- 監督:西谷弘
- 脚本:井上由美子
- 撮影:重森豊太郎
- 照明:中村裕樹
- 編集:山本正明
- 音響効果:大河原将
- 音楽:菅野祐悟









監督を務めたのは西谷弘さんで、まあ福山雅治さんと織田裕二さんを撮るならこの人!みたいなイメージがありますね。
主に『ガリレオ』シリーズの演出や監督を担当していた方であり、その一方で『アマルフィ』みたいな映画も撮っていて、正直典型的なジャパニーズドラマ演出が目立つ印象です。
脚本の井上由美子さんは『昼顔』シリーズで有名ですね。作品性にはマッチした人選だとは思いますが、こちらもテレビドラマっぽさが漂わないかどうかは心配です。
そして撮影の重森豊太郎さんは昨年、『生きてるだけで、愛』の撮影も担当し、素晴らしい映像で魅せてくれました。









そういう意味でも原作『マチネの終わりに』のイメージにすごく近い撮影監督なので、個人的には期待大です。
最後に、個人的に大きな期待を寄せているのが、音響監督の大河原将さんです。
というのも彼は映画『ちはやふる』や『見えない目撃者』といった音響が素晴らしい作品をこれまで世に送り出してきた監督なんです。
本作は、言うまでもなく音楽が重要な作品です。その点では、音をどうコーディネートするかで作品の印象が大きく変わります。
そこに実力派のスタッフをつけてくれたことで、音楽映画としても期待が持てますね。
- 蒔野聡史:福山雅治
- 小峰洋子:石田ゆり子
- リチャード新藤:伊勢谷友介
- 三谷早苗:桜井ユキ









主演を務めるのは、福山雅治さんですね。
この年齢でセクシーで華がある俳優となるともう彼しかいないような気もしますね。やっぱり予告編を見ていても画になります。
そしてヒロインを演じるのが石田ゆり子さんです。
もう彼女は原作のイメージにハマりすぎなんですよね。50歳でありながら、ナチュナルで飾らない美しさがある何とも品のある女優です。
より詳しい情報を知りたいという方は、映画公式サイトへどうぞ!









『マチネの終わりに』感想・解説(ネタバレあり)
本作が描いた大人の恋愛とは何か?
(C)2019 フジテレビジョン アミューズ 東宝 コルク
本作『マチネの終わりに』という作品を評する言葉として、しばしば「大人の恋愛」というものが見られます。
確かにこの作品の中で描かれるのは40歳付近の男女の恋愛譚ですから、単純に年齢的な問題で大人な恋愛ということはできるかもしれません。
あとはやはりリチャード・リンクレイター監督の『ビフォア』シリーズを思わせるような会話劇の中でお互いを理解し合っていくというプロセスもそうでしょうか。
ただ、それだけで本作が「大人の恋愛」を描いているという本質を表現できてはいないように感じます。
その正体を探っていたのですが、その中で気がついたのは、以下の2つのポイントです。
- 相手ではなく自分に求める恋愛であること
- 業(罪)を背負う恋愛であること
まず、若者の恋愛というのは、とにかく相手に求める傾向にあります。
それは相手の身体性、感情の独占などとにかく相手に対して多くを求め、そしてそれが自分の期待を解離することで、相手への失望を深めていくというケースが少なくありません。
しかし、『マチネの終わりに』という作品が描くのは、蒔野と洋子がとにかく相手にではなく、自分に対して多くを求め、それ故に距離を縮めたり、すれ違ったりする様です。
本作の記述の中にそれを象徴する一節があります。
結局、自分が人生を共にすべきは、あなたではなかったという、その偽らざる実感を。・・・せめてそれが、彼のためだと信じられるのであれば、自分は彼を愛しているが故に、彼との恋愛を断念できるのではあるまいか。
(『マチネの終わりに』より引用)









もちろん当ブログ管理人も、恋愛となったときに、愛ゆえに断念できる何て綺麗ごとを想像することはできません。
しかし、それが出来てしまう蒔野と洋子に私たちは何だか「大人っぽさ」を感じてしまう者なのだと思いました。
冒頭に蒔野が一方的に、洋子に対して一方的に婚約破棄を迫る場面がありましたが、後に彼はあの時、もっと自分の具体的な恋愛観や結婚観、現在の生活水準や収入などを明かしたうえで、婚約の破棄を提案すべきだったと後悔していました。
2人はお互いに相手のことを求めながらも、求めるが故に相手ではなく自分に求めてしまうというそんなジレンマを抱えながら相手と向き合っています。
そしてもう1つ私が強く感じたのは、本作が描いた恋愛というものが「業(カルマ)を背負う恋愛」であったというものです。
本作の序文の中で、平野啓一郎さんが2人の恋愛の出会いを「暗い森の中へと迷い込む」ことと表現しています。
これはダンテの『神曲』の書き出しでもあります。
そういう意味では、2人の恋愛というものが「業(罪)を背負って地獄を巡るようなもの」なのだと解釈することができるかもしれません。
洋子は蒔野と結ばれるために、自分のフィアンセとの婚約を破棄するという業(罪)を背負いました。
三谷早苗は、蒔野と結ばれるために、洋子に対して偽のメールを送信するという形で業(罪)を背負いました。
そして蒔野は、物語のその後に洋子と結ばれるために、早苗と自分の子どもを手放すという業(罪)を背負うのでしょう。
彼らは同時に自分自身が背負った業(罪)に伴う罰を受けています。
愛する人と共に生きる道を選ぶために、彼らは自分が何かを捨て、そして業(罪)を背負おうとするのです。
きっとこれは私たちにはできないことだと思いますし、理解できないことなんだと思います。
下世話な描き方をすれば、これはただの「浮気」であり「不倫」なのですが、そこに芸術的な装飾を施し、「大人の恋愛」として昇華させてしまうところに平野啓一郎さんの手腕が光っています。
自分を捨ててでも、業(罪)を背負ってでも共に生きたいと願い、それを現実にしてしまう。
私たちには理解できないし、到底できない、でもそれが美しく見えてしまう、見せられてしまう。
そこにこそ本作『マチネの終わりに』は浮気小説、不倫小説とはなく、「大人の恋愛」を描いたラブストーリーとして評される所以があるように感じています。
戦場で音楽は何の意味を持つのか?
『マチネの終わりに』という作品は、ジャンル的には間違いなく「ラブストーリー」なのですが、私は「芸術」とは何かを考えさせてくれる作品でもあったと思います。
とりわけ本作は、蒔野という1人のミュージシャンが音楽と向き合っていくという筋でも非常に深い作品なんですね。
まず、冒頭の蒔野の心情の吐露の中にこんな一節があります。
きっともう、自分の演奏も聴いてはいないだろう。そもそも、内戦状態の今のバグダッドで、クラシックギターのバッハなんかに、一体何の意味があるだろうか?
(『マチネの終わりに』より引用)
これは、彼がイラクのバグダッドへと向かい、連絡が取れなくなってしまった洋子を思っている時の心情です。
戦争という大きな脅威と不安に対して、音楽ができることなどなく、芸術は現実世界の悲劇に対して徹底的に無力なのだと彼は打ちひしがれています。
しかし、現地にいた彼女は彼が思っていたよりもずっと音楽に救われていたんですよね。
ホテルにテロリストたちがやって来て、不安と恐怖でどうしようもない経験をした後に、彼女は、音楽に身を任せて全てから解放されようとしていました。
そして、パリで再開した2人の間にはこんな会話がありました。
「俺は洋子さんのメールを読みながら、イラクで一体、俺の音楽に何の意味があるんだろうって、やっぱり考えた。カラシニコフの銃弾が飛び交う世界で、俺のバッハに、どれほどのありがたみがあるのかって。」
洋子は、その言葉をすぐにきっぱりと否定した。
「わたしは、実際にバグダッドで蒔野さんのバッハの美に救われた人間ですよ。」
(『マチネの終わりに』より引用)
戦場で芸術にできることって何なのかって考えた時に、やっぱりひと時でも「人間らしさ」を取り戻させてくれることなのかな?と私は思っています。
そういう私の芸術観に大きな影響を与えたのは、当ブログではたびたびご紹介させていただいている岡真理さんの『アラブ、祈りとしての文学』ですね。
彼女は、この著書の中で難民として生きるパレスチナ人たちやアウシュビッツで死を迎えようとするユダヤ人たちが「文学を必要としていた」という点を指摘し、文学は「人間として正気を保つために、言い換えれば人間が人間としてあるために存在する」と述べました。
そう考えた時に、洋子との出会いと言うのは、蒔野にとっても音楽の意味を再考させられる大きな出来事だったのではないかと思います。
そして本作の中で彼の音楽観に大きな影響を与えたのが、ジャリーラというイラク出身の女性との出会いです。
蒔野は再びパリを訪れた際に、祖国から亡命し、洋子の家に滞在していたジャリーラに自身の演奏を聞かせてあげたのでした。
その際に彼は、音楽の力というものを痛感していたようです。
快活になってゆくジャリーラの様子に、蒔野は自分が携わってきた音楽というものの力を再認識させられた。
こういう境遇でも、人は、音楽を楽しむことができるのだった。
(『マチネの終わりに』より引用)
彼は、こうして音楽というものが人間にとって大きな救いになるということを実感していきます。
確かに芸術には現実を変えることはできません。しかし、ひと時の「人間らしさ」を取り戻させてくれるのです。
だからこそ、彼は物語の後半に東日本大震災が起こった際にもライブを中止することはありませんでした。
この行動でバッシングも浴びることとなりましたが、それでも音楽にできることはあるはずだと信念を持ち、人々の「救い」になろうとしたのです。
こういった蒔野という1人のミュージシャンの音楽に対する考え方の変遷という視点で捉えても、本作は非常に深い作品だと思います。
マリアとマルタのエピソードについて
(C)2019 フジテレビジョン アミューズ 東宝 コルク
劇中で聖書に登場するマリアとマルタのエピソードが運用されていました。
すると、マルタという女が、イエスを家に迎え入れた。彼女にはマリアという姉妹がいた。マリアは主の足もとに座って、その話に聞き入っていた。マルタは、いろいろのもてなしのためせわしく立ち働いていたが、そばに近寄って言った。「主よ、わたしの姉妹はわたしだけにもてなしをさせていますが、何ともお思いになりませんか。手伝ってくれるようにおっしゃってください。」主はお答えになった。「マルタ、マルタ、あなたは多くのことに思い悩み、心を乱している。しかし、必要なことはただ一つだけである。マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはならない。」
(ルカによる福音書 10章38―42節)
このパートに関しては、多くの議論があります。
なぜ、せわしなくイエスのために働いているマルタがとがめられて、イエスの話を聞いているだけのマリアが受け入れられるのかという大きな疑問点を孕んでいるからです。
これについて考える時に、私は「愛のカタチ」というものを表現した一節なんだと強く感じさせられました。
何が言いたいのかと言いますと、マルタにとっては「いろいろのもてなしのためせわしく立ち働く」ことがイエスに対する愛情の表出なのであり、対照的にマリアにとっては「足もとに座って、その話に聞き入る」ことが彼に対する愛情の表出だったんです。
つまり「愛のカタチ」というものは人それぞれであるにも関わらず、マルタは自分の方が「正しい愛のカタチ」なのだと主張して、それをマリアに押しつけようとしたわけです。
イエスがこれを見て、マルタを咎めたのは当然と言えるのではないでしょうか。
劇中でマルタに重なる存在である三谷早苗は、まさに洋子に対して自分こそが蒔野に対する正しい愛情を示しているのだと主張して見せました。
だからこそ早苗は結局マリアになることはできなかったのかもしれません。
蒔野と洋子が選び取った結末を考察
(C)2019 フジテレビジョン アミューズ 東宝 コルク
本作の中で一番議論が分かれるのは、おそらく「ラストシーンのその後」ですよね。
ただ個人的には結構明確な結末だと思っています。というのもやっているのは『ラ・ラ・ランド』と真逆のことですよね。
『ラ・ラ・ランド』の結末について、後藤護氏がその批評「『ラ・ラ・ランド』と青の神話学」の中で谷川渥氏の『鏡と皮膚――芸術のミュトロギア』を引用し、解釈していました。
他者の眼差しは、距離を世界に到来させるのだ。この強いられた距離を否定しようとすれば、彼は彼自身の眼差しによって彼女の眼差しを超越するほかはない。そのとき相手の眼差しは眼という対象・・に変貌する。要するに、サルトルによれば、眼差しの交差は、相手を対象と化す相互メドゥーサ的な営為にほかならない。目合まぐわいは、サルトルにあっては、永遠に実現不可能な愛の合体のメタファーとなる。
(『鏡と皮膚――芸術のミュトロギア』より引用)
当ブログでも『ラ・ラ・ランド』の記事を書きましたが、やはりこのラストは2人が「あり得たかもしれないIFの世界」をブルーナイトに閉じ込め永遠にしたんだと思います。
叶わないからこそ美しく、夢の中の世界に閉じ込めるからこそその色が褪せることなく、永遠に輝くのです。
一方で、『マチネの終わりに』という作品はそうはなりません。
2人がコンサートの会場で見つめ合い、そして蒔野が彼女のために1曲弾いたところで幕切れていたならば、『ラ・ラ・ランド』と同じだったと言えるでしょう。
しかし、この作品はコンサート後に2人が再会し、言わばよりを戻すことを予感させるところまで描き切るんですよ。
この時点で、「相手を対象と化す相互メドゥーサ的な営為」たる眼差しの交錯の段階を超え、「永遠に実現不可能な愛の合体のメタファー」とはほど遠い結末を演出します。
ただ、原作を著した平野啓一郎さんはこの結末になることを小説の序章で語ってくれています。
彼らの生には色々と謎も多く、最後までどうしても理解できなかった点もある。私から見てさえ、二人は遠い存在なので、読者は、直接的な共感をあまり性急に求めすぎると、肩透かしを喰らうかもしれない。
(『マチネの終わりに』より引用)









蒔野と洋子が選ぶ物語、ないし結末は、私たちには「理解できないし」それでいて「共感を求めると肩透かしを喰らう」わけですよ。
つまり、彼らはやっぱり『ラ・ラ・ランド』的に、過去を永遠の中に閉じ込めて、別れを選ぶのではなく、復縁を選ぶのだと思いました。
そもそも本作を通底するテーマの1つに「過去は変えられる」というものがあります。
これは、過去に起きたある出来事というものは固定化されたものではなく、思っているよりもずっと繊細で脆いものであり、ちょっとした印象1つで180度変わってしまうこともあるということです。
だからこそ2人は、確かに5年前の「過去」を塗り替え、そして現在を選び取るんですよ。
もちろんこの結末に対しては、賛否があるでしょう。
というのも蒔野は自分のことを献身的に支えてくれた妻とその子供を捨てて、再婚する道を選ぶことになるからです。
しかし、私たちは他人の恋愛話は「どうでも良い」でしょう。
なぜなら恋愛ってあくまでも恋人同士の共通言語なのであって、第三者が聞いたところで何とも思えないからですよ。
だからこそ、私たちは蒔野と洋子が選ぶ物語を結局のところ理解することは難しいのだと思います。
ただこの共感のできなさこそが、『マチネの終わりに』という作品をよりレベルの高いものにしてくれていたように個人的には感じました。
時系列を公開年・月に合わせた映画版
まず今回の映画版はラストの時系列を映画が公開される2019年11月に合わせるという非情に洒落た演出を施してくれています。
これもかなり意味があると思っていて、要はイラクのバグダッドというイメージは少し現代のテロ事情から考えると、過去のものになりつつあって、とりわけ近年テレビで国境を越えてニュースになるのは、ヨーロッパやアメリカで起きるテロ事件です。
そしてヨーロッパの中でも特にテロ事件が多発しているのがフランスです。
劇中で船で爆破テロが起きたり、報道メディアにテロリストが突入したりという事件が描かれましたが、これは2015年のシャルリーエブド襲撃事件やフランス同時多発テロを想起させます。
『マチネの終わりに』という作品がそもそも2015年の初頭にスタートした作品であるため、取材等の事情を鑑みても、フランスでのテロ事件を作品に反映させることは難しかったのだと思います。
ただ、映画版を製作するにあたって、イラクのバグダッドでの事件からフランスでのテロ事件にシフトしたことで、非常に「現代性」が強くなり、観客がイメージしやすい作品になったのではないかと思います。
昨年、『検察側の罪人』という作品の映画と原作を比較した際にも思ったのですが、映画版を作るにあたって、作品の世界観を現代に近いものにアップデートするというアプローチは意外と重要です。
同作は司法の世界を描いた作品ですが、同じく時間軸をより最近に変え、その中で司法制度の変化にも微妙に対応させたうえで物語を構築しなおしました。
そういう意味でも、『マチネの終わりに』は地味ではありますが、細かいところにまでこだわった作品であるということが伝わってきます。
もう少し見せずに頑張って欲しかったか・・・。
(C)2019 フジテレビジョン アミューズ 東宝 コルク
邦画大作なので、基本的に万人に伝わる映像によるストーリーテーリングが求められるので、本作の映像が語り過ぎだと批判するのは、少しズレるような気もします。
ただ『マチネの終わりに』という作品は、かなり説明的な描写を排除して淡々と映像を見せようと努めてくれていたように思うんです。
例えば、蒔野と洋子の会話のシーンだって、下手な人が演出すれば、余計なナレーションを入れたり、心の声的な演出を入れて「説明」しようとすると思うんですね。
本作は、その辺りについては『ビフォア』シリーズさながらに、ひたすら役者の演技に託し、淡々と会話を積み重ねるという手法を貫いてくれた印象でした。









噴水を囲む円状の道を舞台装置として選び、2人がすれ違いそうになる様を演出しつつ、ラストカットで、お互いが交わる方向へと歩いていく静かなカットで幕切れを迎えました。
こういったカットが非常に耽美的で、洒落ていたんですが、その一方で個人的にもう少しそこは・・・というシーンもありました。
まず、個人的には描いて欲しくなかったのは、早苗がニューヨークでの復活コンサートに向かう前に、蒔野を見送るシーンですね。
もちろん原作には存在しないシーンですが、ここで彼女が蒔野に「あなたの好きにしてよいから。」と伝えるのです。
これはかなり余計なシーンだったというか、言ってしまえば観客の感動を誘うための描写でしかなかったように思います。
早苗の決意は、ニューヨークのコンサート会場で、蒔野の立つステージから1人ボーっと観客席を眺めていたシーンで語らずとも分かります。
また、見送りのシーンを入れるとしたら、いつも通りのトーンで見送るくらいでよかったと思いますし、今生の別れのようなウェットさをあからさまに漂わせるセリフは必要なかったと思います。
あとは、ラストのマチネの最後の一曲で蒔野と洋子の視線が交錯するシーンですが、ここの観客席を舐めるようにして映していき、その最後に洋子が映るというカットが究極にダサいのです。
このシーンで『幸福の硬貨』を選曲しておいて、洋子がいないという可能性は考えられないわけですから、もっとスマートな演出で描いて欲しかったですね。
全体的に映像の美しさやスマートさが、街並みや風景の美しさに依存しすぎている印象を受けてしまったので、カメラワークの中でもう少し「魅せるショット」があれば、作品の質が上がったのではないかと思います。
おわりに
いかがだったでしょうか。
今回は『マチネの終わりに』についてお話してきました。
個人的には恋愛小説なんて・・・という気持ちで読み進めていたのですが、どんどんと2人の物語に惹きつけられ、終盤は思わず涙してしまいました。
ただ本作の結末だけはどうしても美しくないし、理解しがたいのですが、そこにこそ『マチネの終わりに』という作品で平野啓一郎さんが描きたかったものがあるように感じました。
私たちは現実と未来を変えられると自負していますが、思ったよりも過去に縛られていて、それが故に現実と未来を変えることができないと感じてしまうケースが多々あります。
しかし、過去というものもまた「変えられる」のだとすれば、より多くの選択肢がありますし、そうなれば私たちは「選ばなかった世界」を選ぶことができる可能性だってあるのです。
蒔野が洋子を選ぶのであれば、それは身勝手で独善的で、最低な決断でしょう。
それでも2人に結ばれて欲しいと思ってしまう、思わされてしまうこの小説の妙に、読み終わってから非常に驚かされました。
恋愛映画・恋愛小説なんて・・・と侮らずにぜひ、多くの人に鑑賞して欲しい作品です。
今回も読んでくださった方、ありがとうございました。