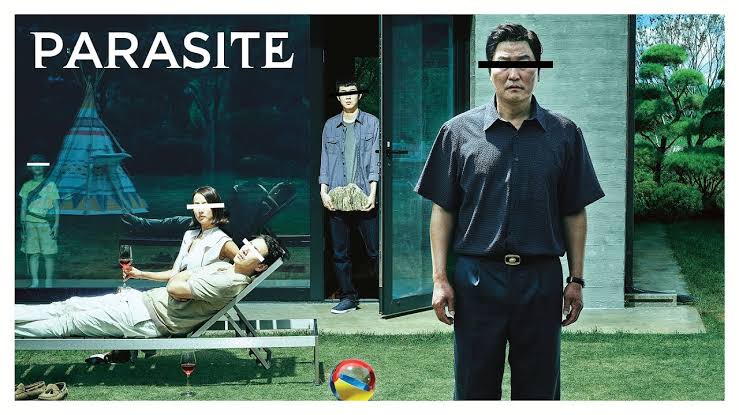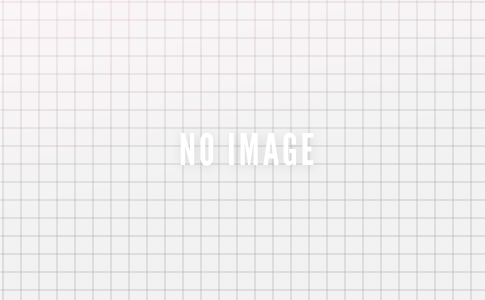みなさんこんにちは。ナガと申します。
今回はですね映画『1917 命をかけた伝令』についてお話していこうと思います。

物語的な部分がどうしても描きこめないタイプの作品ではあったので、その部分で『パラサイト』と比較すると、分が悪かったような気はします。
公開前から、日本ではなぜか「全編ワンカット」という触れ込みを宣伝していたのですが、本作は、「全編ワンカット」ではなく「全編ワンカット風」です。
まあ、映画を観たら、どこを編集で繋いであるのかは割と分かりやすいので、気がつくと思いますけどね。
つまりワンシーンワンカットでいくつかのユニットに分けたものを撮影して、それを編集の跡を残さないようにきれいに繋いで1本の映像にしたのが、今作『1917 命をかけた伝令』であるということです。



















全編ワンカットでこういった戦争体験(テロ事件体験)を描いた作品と言えば、『ウトヤ島、7月22日』がありますね。
どうしても全編ワンカットを見たいんだ!という方は、こういった作品をチェックするといいと思います。
ただ、後ほど述べますが、全編ワンカットには、やはり大きな弱点があり、本作『1917 命をかけた伝令』は「ワンカット風」というスタンスを取ることでそれを見事に克服しています。
さて、ここから少し掘り下げて作品について語っていきたいと思います。
本記事は作品のネタバレになるような内容を含む解説・考察記事となっております。
作品を未鑑賞の方はお気をつけください。
良かったら最後までお付き合いください。
目次
『1917 命をかけた伝令』
あらすじ
トム・ブレイク上等兵とウィリアム・スコフィールド上等兵は、上官に伝令の命を受ける。
2人に課されたのは、連合国軍の前線へと走り、明朝のドイツ軍への突撃を中止して欲しいという内容だった。
危険な任務ではあったが、トム・ブレイクは自分の兄が前線にいるということで、何とか家族を救うべく任務を遂行することを決断する。
空撮によると、ドイツ軍は退却したと見せかけて砲兵隊を揃えて待ち構えており、連合軍の突撃を待ち構えていたので、一刻の猶予もなかった。
連合軍の前線があるクロワジルの森へと向かうには、ドイツ軍が仕掛けたトラップや塹壕、そして占領下にあるエクーストという町を抜けていかなければならない。
それでも2人は、1600人の命とそして自分の家族の命を救うべく走り続けるのだった・・・。
スタッフ・キャスト
- 監督:サム・メンデス
- 脚本:サム・メンデス クリスティ・ウィルソン=ケアンズ
- 撮影:ロジャー・ディーキンス
- 美術:デニス・ガスナー
- 衣装:ジャクリーン・デュラン デビッド・クロスマン
- 編集:リー・スミス
- 音楽:トーマス・ニューマン



















まず、監督を務めるのが『アメリカンビューティー』で映画界に激震をもたらし、その後も『007 スカイフォール』などのエポックメイキングな作品を世に送り出してきたサム・メンデスです。
後ほど解説しますが、サム・メンデスは元々舞台演出家としてそのキャリアをスタートさせているので、映画もどこか演劇的な匂いや構図を残しています。
そして今回のワンカット風映像と戦争譚の融合は、まさしく彼が演劇と映画の融合を追求する中で生まれた1つの極致とも言えます。
さらに、撮影にはハリウッドを代表する撮影監督の1人であるロジャー・ディーキンスが加わりました。
『ノーカントリー』や『007スカイフォール』そして『ボーダーライン』など、とんでもない映像を常に撮り続け、しかも同じスタイルにこだわるのではなく、常に自身をアップデートさせ続けているところには脱帽です。
今作では舞台演出風のカメラワークも織り交ぜ、更にはワンカットの弱点とも言える映像の単調さを見事に克服するなど、作品に多大な貢献をしています。
美術・衣装には、デニス・ガスナーと本年度アカデミー賞受賞のジャクリーン・デュランらが加わり、軍服に徹底にこだわり、そして当時の戦場をリアルに再現しました。
全編ワンカット風に見せるために苦心したであろう編集には、リー・スミスがクレジットされています。



















視覚効果賞ってSF映画が受賞することが多いんですが、今回は戦争映画である『1917 命をかけた伝令』が受賞しました。
何がすごいって、どこからが実写でどこからがCGなのかが、あまりにもシームレスに融合していて判別できないというところだと思うんです。
しかもワンシーンワンカットで撮影されているので、余計にどうやって撮ったんだ!?なカットが映画を見ていると、散見され、驚きの連続でした。
そして、劇伴音楽には、もう語るまでもなくこれまでも素晴らしい音楽を世に送り出し続けてくれたトーマス・ニューマンです。当ブログ管理人は『ロード・トゥ・パーディション』のサントラを聞くと、今でも涙が止まりません。
- ウィリアム・スコフィールド上等兵:ジョージ・マッケイ
- トム・ブレイク上等兵:ディーン=チャールズ・チャップマン
- スミス大尉:マーク・ストロング
- ブレイク中尉:リチャード・マッデン
- エリンモア将軍:コリン・ファース
- マッケンジー大佐:ベネディクト・カンバーバッチ



















主人公のウィリアム・スコフィールド上等兵を演じたのは、『はじまりへの旅』や『マロ―ボーン家の掟』などで知られるジョージ・マッケイです。
そしてもう1人の主人公であるトム・ブレイク上等兵を『ゲームオブスローンズ』で注目されたディーン=チャールズ・チャップマンが演じます。
脇を固める上官役には、マーク・ストロング、コリン・ファース、ベネディクト・カンバーバッチなど英国の名優たちが勢ぞろいです。
撮影秘話を聞くと、ベネディクト・カンバーバッチの出演シーンが遅く、それでもいつ撮影の順番が巡って来るかわからず、スケジュールをキープしておく必要があり、そのために多額の給料を支払っていたということがあったようです(笑)






































『1917 命をかけた伝令』解説・考察(ネタバレあり)
全編ワンカットの弱点を克服したNEOワンカット映画として
ヴィム・ヴェンダース監督は、映画においてカットをすることで「映画内時間」と「観客に流れる時間」の間にギャップを生めば生むほど、観客の心は映画から離れてしまうのではないかと危惧していました。
全編ワンカット映画というのは、ある種の究極の没入感を生むための演出で、まさしく「映画内時間」と「観客に流れる時間」が一致します。
しかし、そもそもワンカット映画は撮影や準備に相当な時間がかかりますし、どうしても舞台演出的な要素が強まり、映画としての完成度は落ちてしまうという傾向が見られます。
少し前に話題になったドイツ産の140分ワンカット映画である『ヴィクトリア』は予算の都合で、全3回しか撮影できないことが分かっていたようです。
そのため最初に今回の『1917 命をかけた伝令』と同様に、シーンごとのワンカットの映像を撮影し、それを編集で綺麗に繋いだものを保険として用意したうえで、全編ワンカットの撮影に挑んだようです。
確かに観客と映画の中でヴィクトリアという少女が経験した「時間」がぴったりとリンクするため、見る側としては臨場感を感じるのですが、どうしても演出的物語的な制約を強く受けてしまった印象を否めません。
ワンカットで撮影するとなると、演出も撮影も登場人物主体というよりも、撮影方法主体で考えなくてはならなくなってきます。
舞台的にこの場所でこの位置からは登場人物を撮れない、また動線的な問題でカメラワークがある程度限定されてくるのも事実でしょう。
そして、ワンカットで撮影することの最大の難しさは、映像的な緩急をつけることが難しい点です。
時間の流れが制限され、さらに2時間程度の人間の行動範囲も限られてきますので、映像がどうしても単調になってしまい、観客はそこに退屈さを感じてしまいます。
また、冒頭に挙げた『ウトヤ島、7月22日』が抱えていた問題で、「カメラ=視点」が何を表していて、何に寄り添っていたのかが不明瞭というものが挙げられます。
ワンカット映像は、観客の没入感を高めるための演出ではあるのですが、時間的にも場所的にも体感がそのまま反映されるからこそ、カメラが何を表現しているのかが非常に気になってしまうことがあります。
『ウトヤ島、7月22日』は登場人物に寄り添って撮影するというアプローチ(おそらく観客をあの場にいるかのように錯覚させるため)をとりました。
登場人物が木の陰に隠れると、カメラも同じ動きをし、登場人物が走るとカメラも走り出すのですが、ただこうなってくるとカメラがあの場所に存在しない人間の視点を成しているということになり、何だかノイズに感じられてしまいます。
もう1つこれを回避する方法ということで被写体から距離を置いて「神の視点」で映像を構築するという手法もありますが、これをやると、映像が単調になるという問題が再燃します。
このように全編ワンカットの作品を作り上げようとすると、立ちはだかる壁が多く、どうしても映画としては物足りないものになってしまうことが多いのです。
そこで『1917 命をかけた伝令』はワンシーンワンカットで撮影し、それをシームレスに連結させることで、全編ワンカット映画の弱点を克服した「ワンカット風」映画として世に送り出されました。
舞台演劇と映画の融合を模索したサム・メンデスの手腕
先ほども書きましたが、サム・メンデス監督は、元々舞台演出家でして、彼の舞台である『キャバレー』が映画監督のスティーブン・スピルバーグの目に留まったことで、映画界に進出することとなりました。
そのため、彼の作品には、映画的というよりも演劇的に感じられる演出やカメラワークが散見されます。
例えば、これは『アメリカンビューティー』の頃からそうなのですが、登場人物が会話をしているシーンで、彼は極力カットや切り返しを用いずに撮影しています。
これもまた、観客と登場人物に流れる「時間」を一致させ、時の移ろいと共に変化する登場人物の心情を描き出すための演劇的演出の1つと言えるでしょう。
そんなサム・メンデス監督が映画と演劇の融合としてキャリアの初期から模索し続けていたのが、今回『1917 命をかけた伝令』で実現したワンシーンワンカットの映像でしょう。
思えば、『007スペクター』の冒頭のメキシコシティのカットはワンシーンワンカットで撮影されていましたし、この時既に、今作に向けた計画はスタートしていたのかもしれません。
『1917 命をかけた伝令』を見ていて、非常に面白いのは、まずカメラワークについてです。
ロジャー・ディーキンスの卓越した撮影技術があることはもちろんですが、ここにもサム・メンデス監督の演劇的な視点が見え隠れしています。
今作のカメラワークは、基本的に一貫しているわけではなく、変幻自在にそのアングルを変化させています。
それが何を表しているのかと言うと、おそらくですが本作の撮影的アプローチは、ワンカットという制約がある状態で、普通の映画と同じような撮影をするということだったのではないかと思っています。
『ウトヤ島、7月22日』のように、観客を映画の中の世界にいる1人と錯覚させるような視点を取っているわけでもなく、超然的な神の視点を取っているわけでもありません。
だからこそ多くの人が前情報なしで本作を観ると、おそらくワンカット風の映像だったことに気がつかないのではないかと思うんです。
そこにサム・メンデス監督やロジャー・ディーキンスの追求した映像の魔法が隠されていると思いました。
カットを用いることができない以上、登場人物の心情を強調したり、寄り添ったりといった緩急をつけるのが難しく、さらには戦争映画でありながら広角レンズで今の状況の全体像を映し出せないのもデメリットとしては大きいでしょう。
しかし、『1917 命をかけた伝令』はあくまでも伝令という小さな個の物語を描くことで、その弱点を強みに変えてみせました。
戦争というものが対極的に見てどうなっているのか、ドイツ軍は一体どんな陣形を整えて待ち構えているのか。
そういった戦争の「大きな」情報は一切垣間見えませんが、ウィリアム・スコフィールド上等兵のレイヤーで見ると、ブービートラップや敵兵といった「小さな」戦争の脅威が押し寄せています。
このように、撮影アプローチ的な部分で制約があったとしても、物語的にそれが正当化されるという状況を作り上げたのは巧いですよね。
加えて、伝令としてウィリアム・スコフィールド上等兵という1人の人間の時間をシームレスに追い、カットを使わずとも感情をリアルに描くことに成功しています。
そして、撮影的な部分で一番面白かったのは、時折挿入される舞台演劇的なカメラワークです。
これは冒頭のスコフィールドとブレイクが大きな水たまりを迂回しながら歩くシーンや、スコフィールドがエクーストへと続く壊れた橋を渡るシーンで見られました。
(C)2019 Universal Pictures and Storyteller Distribution Co., LLC. All Rights Reserved.
登場人物を追っていたカメラが突然被写体と距離を置き、俯瞰で捉えるようなショットで、水平移動させながら人物を追っていきます。



















舞台という場所で、登場人物の動きを見せるためには、左右への広がりをいかに用いるかが重要になってきますが、サム・メンデス監督はそういった舞台的視点を本作に取り入れています。
その一方で、エクーストでのスコフィールドの疾走シーンや、彼が伝令を届けるべき第1波の攻撃は始まった戦場を駆け抜けるシーンは、映画の強みでもある奥行きを使った撮影を施されています。
このように、本作はワンカットという制約がありながら、カットを施した一般的な映画と何ら変わりない効果を創出し、加えてそこにサム・メンデス監督の舞台演出家としてのエッセンスを加えることで映像にバリエーションをもたらしています。
もう1点、本作が傑出していたのは、ワンシーンワンカットにすることで、ワンカット映画が抱えていた映像の単調さというジレンマを払拭したことでしょう。
本作の丁度、上映時間的には中間に位置する時点に、スコフィールドが意識を失って時間帯が昼から夜へと転じるという展開がありますが、これは舞台におけるインターミッションを意図していると思います。
舞台演劇は確かに上演が始まると、物語を止めることは許されませんが、唯一インターミッションという形で物語を中断することがあります。
これにより、スコフィールドが意識を失っていた時間を彼が体感していない時間として巧妙にカットし、加えて昼の戦場と夜の戦場という2つの時間を描けるようになったために映像にバリエーションが生まれました。
特に夜のエクーストを彼が失踪するシーンの映像は圧巻と言う他なく、照明弾で照らされては暗闇に包まれ手を繰り返す廃墟の形式や業火に浮かび上がる敵兵のシルエットなど、単純に映像表現として息を飲む場面が多かったです。
(C)2019 Universal Pictures and Storyteller Distribution Co., LLC. All Rights Reserved.



















さらに舞台において、セットが変化していくが如く、彼が疾走している場所の景色も変化していくため、ハイテンポなロードムービーのような味わいすらあります。
こういった視点で紐解いていくと、やはり今作『1917 命をかけた伝令』はサム・メンデス監督が映画と舞台の良さを併せ持つ映像作品をついに完成させたと見るべきではないかと感じました。
最も故郷から離れた場所で故郷に辿り着く物語
ここからは、本作の物語的な部分に焦点を当ててお話していこうと思います。
本作の主人公であるブレイクは家族のことを思っていますし、故郷に帰りたいと強く願っています。
しかし、その一方でスコフィールドは家族の元へ戻ることを恐れているようなのです。



















1916年のソンムの戦いに参加したスコフィールドは、戦場の怖さをよく知っており、安全に行動することで、自分の命を大切にしています。
一方のブレイクは戦場に出た経験に乏しく、大胆で無鉄砲な行動を取ることもあり、スコフィールドとは対照的です。
戦場という故郷からはかけ離れた場所にいるからこそ、人は家族や故郷を強く思わずにはいられません。
戦争という事象を拡大して見てみると、そこには1人1人の人間の家族や大切な人を守りたいという思いがあり、戦争とはその小さな思いの集合体なのだということを実感させられます。
本作は『1917』という壮大なタイトルをつけられながらも、その実は1人の青年にスポットを当てた小さな物語です。
しかし、その1人の物語が戦場に立つ兵士の数だけ合わされば、それは「戦争」になるわけですから、そういう意味でもこのタイトルは憎いと言わざるを得ません。
ただ、任務の序盤でブレイクはドイツ兵士にナイフで刺されてしまい、家族の写真を抱きしめながら、息絶えてしまいます。
では、ここで彼の物語は終わってしまったのかと言うとそうではありません。
ブレイクの故郷を目指す旅は、彼の形見がスコフィールドに託された形で続いていき、前線の兄の下へと向かって行きます。
その度を形容するとすれば、「最も故郷から離れた場所にある『故郷』を目指す旅」とでも言えるでしょうか。
スコフィールドはエクーストを目指して、他の部隊のトラックに乗り込むのですが、このシーンが何とも切なくもあり、本作が『1917』というタイトルを関していることの本質を表している様でもあります。
彼が乗ったトラックには、ブレイクのように戦場でユニークな軽口を叩いて、場を盛り上げている青年がいました。
これまで、淡々とスコフィールドとブレイクの旅路を描き、とりわけ後者が戦場でもユニークな話をして場を和ませ続けていたのが印象的でしたよね。
そんなブレイクが死んだ直後のシーンで、彼に似たような他の部隊の人物が描かれるのは、まさに「戦争」とは主人公2人のような人間の集合体で成されているものであることを仄めかしている様でもあります。
スコフィールドとブレイクは特別なのではなく、あくまでも戦争に内包されたたくさんの個人の1つのサンプルなのだということを表現しているとも言えるでしょうか。
その後の旅路では、ある種の誘惑が待ち受けており、彼は幾度となく心が折れそうになっていました。
そうして旅を続けるスコフィールドはエクーストの街で、女性と1人の乳児が暮らす家に辿り着き、そこで「家族」という温かい誘惑に心を吸い寄せられます。
ここで、改めてスコフィールドと彼の家族について思いを馳せてみると、彼の秘めたる心情が少し浮かび上がって来たように感じました。
重要なのは、彼が爆発した洞窟から脱出したときに、真っ先にある写真を取り出して、その無事を確かめると缶ケースのようなものに入れていた点ですよね。



















彼がなぜ、エクーストの街で出会った親子に吸い寄せられ、そしてあの空間にいることに強い安心感と安らぎを感じているのかを考えてみると、1つの解釈が見えてきます。
スコフィールドは、ソンムの戦いという第1次世界大戦中に最も過酷だったという戦いを経験しています。
だからこそブレイクというキャラクターが家族を助けたいという思いゆえに危険を顧みない行動を取っているのを、彼は嗜めていました。
つまり、スコフィールドは戦争に「家族」という守るべき存在を持ち込むことで、冷静さを欠いたり、不安や恐怖が増長したりしてしまうことを恐れていたのではないかと思います。



















そう思うと、彼にとって家族とは「愛するべきもの」であることに間違いないのですが、同時に戦争という場所においては自分を弱くする存在だと考えているのかもしれません。
しかし、命を落としながらも家族を想い続けたブレイクを間近で見て、そしてエクーストの街であの親子とであったことで、彼の考えは少しずつ変わっていったのでしょう。
自分を冷静でかつ強く保つために遠ざけてきた「家族」という存在。
それでも前に進むために彼は、その幸福の残り香を必死に振り払おうとしていたようでもありました。
さらには、クロワジルの森で、イギリス兵たちが故郷への思いを歌った楽曲に浸っている様子が描かれ、スコフィールドはその歌を聞いて、前に進む気力を喪失しかけましたね。



















ホメロスの『オデュッセイア』にも登場するセイレーンは、歌声で船乗りたちを誘惑し、海の底へと引きずり込む恐ろしい怪物です。
また、このシーンは彼の中にある家族の元へと戻りたいというある種の「弱さ」が極限状態の中で表出したと言えるのではないでしょうか。
そうした数々の誘惑に晒されながらも、彼は最前線へと辿り着き、伝令としての役目を果たします。
さらには、運んできたブレイクの形見を、彼の兄に託すことで、自分の命を救ってくれた恩人を「故郷」に帰すことに成功します。
ラストシーンで、草原に佇み、陽光差し込む中で1人、木にもたれかかり、家族(妻と娘)の写真を見つめるスコフィールド。
まさに「最も故郷から離れた場所にある『故郷』」に彼がたどり着いた瞬間だったと言えるのではないでしょうか。
そして、彼はブレイクという戦争の最中でも愚直に家族を想い、愛し続けた友人を自分の中に取り込み、そして兵士であり同時に父親であるという自分自身を受け入れることができたのでしょう。
そう思うと、本作は家族から最も離れた場所で、家族への愛の深さを知るという物語でもありますね。
聖書的視点から読み解く『1917』
本作を見ていると、実に多くの聖書的なモチーフが目につきました。
今回は『1917 命をかけた伝令』を聖書的な視点から読み解くということで、少しお話させていただければと思います。
まず、登場人物の名前を整理しておきましょう。
主人公となったのは、
- Tom Blake(トム・ブレイク)
- Will Schofield(ウィル・スコフィールド)
の2人です。
まず、Tomという名前についてですが、聖書における「Thomas(トマス)」を真っ先に連想させる名前ですよね。
「トマスによる福音書」というものが聖書にはありまして、キリスト教におけるトマス派内では、トマスは「キリストの双子の兄弟」であると囁かれています。
イエール大学の新約聖書学者、デール・マーチン教授は、「ディディモス・ユダ・トマス(Didymus Judas Thomas)」という名前に注目しました。
イエス・キリストの双子の兄弟であるというディディモス・ユダ・トマス(Didymus Judas Thomas)とは、キリストの十二使徒の一人であるトマスであり、ディディモスはギリシャ語で「双子」を意味し、トマスはセム語ではあるが、ヘブライ語、アラム語、シリア語のいずれでも同じく「双子」を意味するということだ。
(知的好奇心の扉「トカナ」より)
本作『1917 命をかけた伝令』において、トム・ブレイクは確かに兄弟を持つキャラクターとして描かれていましたから、その点でリンクを見出すことができます。
一方のWill Schofield(ウィル・スコフィールド)には、「スコフィールド聖書(The Scofield Bible)」を想起させる名前がつけられていますよね。
面白いのが、スコフィールド聖書が大きく広まっていく契機にもなった、著者サイラス・スコフィールドによる改訂版の出版年が「1917年」であるという点です。
サイラス・スコフィールドが伝道者であり、宣教師であり、更にはスコフィールド聖書によって、契約時期分割主義を広めた人物であることを鑑みると、作中でのスコフィールドの役割に興味深い視点が付与されます。



















さて、『1917 命をかけた伝令』の物語を見ていくと、そもそもは2人で伝令を引き受けたわけですが、面白いのは、2人の関係性です。



















これは冒頭にも仄めかされていましたし、とりわけスコフィールドが「なぜ僕を選んだんだ!?」という趣旨の言葉をブレイクに投げかけていたことから明らかです。
2人はドイツ軍の塹壕でブービートラップに引っかかり、スコフィールドは一時的に視力を失いました。
これについても聖書への言及ではないかと考えられます。
パウロは地から起き上がって目を開いてみたが、何も見えなかった。そこで人々は、彼の手を引いてダマスコへ連れて行った。
彼は三日間、目が見えず、また食べることも飲むこともしなかった。
(中略)
そこでアナニヤは、出かけて行ってその家にはいり、手をサウロの上において言った、「兄弟サウロよ、あなたが来る途中で現れた主イエスは、あなたが再び見えるようになるため、そして聖霊に満たされるために、わたしをここにおつかわしになったのです」。
するとたちどころに、サウロの目から、うろこのようなものが落ちて、元どおり見えるようになった。
(使徒言行録より)
ちなみにパウロというのは、初期キリスト教の使徒であり、新約聖書の著者の一人です。
そして、その後2人は廃墟の近くで植えられていた桜の木を眺めますよね。
桜というのは、キリスト教の世界観でも象徴的な木でして、幼児期のキリストや聖母マリアを描いた宗教画には、時折描かれていることがあります。
この時、2人は「実がついていない」というような話をしていましたが、実は桜の果実(さくらんぼ)は、レオナルドダヴィンチの『最後の晩餐』にも描かれていて、「キリストの血」を表すとされ、受難の象徴とされています。
2人が桜の木を眺めるという描写は、とりわけこれからもたらされる「受難」を思わせる内容なのです。
その後、ドイツ兵をすぐに殺害しようとしたスコフィールドに対して、何とか助けようとしたトム・ブレイクが殺害されてしまうという展開が描かれます。
これが、自分の使徒であるユダに殺害されたイエスを想起させると見るならば、トム・ブレイクは「イエス」的に描かれていると感じます。
また、先ほどブレイクがスコフィールドを選んだという構図が描かれていましたが、ここにもイエスと彼が選んだ使徒の関係が見え隠れしています。
加えて、ブレイクが絶命する際のシーンが非常に重要なのですが、彼が戦場の最前線にいる兄に伝えて欲しいと願ったのは自分の家族への思いを込めた「言葉」でしたよね。



















そうして彼は、「イエス」を想起させるブレイクから「預言」された言葉を伝えるために、そして連合軍の総攻撃を止めるために走り出します。
そんなスコフィールドが経験する最大の葛藤は、マーティンスコセッシが映画化したことで注目を集めた『最後の誘惑』を思わせるような誘惑です。
(C)2019 Universal Pictures and Storyteller Distribution Co., LLC. All Rights Reserved.
ここで牛乳というこれまた聖書的なモチーフが登場しているのも面白いのですが、彼は自分の任務の遂行を前にして、目の前の女性と可愛い赤ちゃんという存在に誘惑され、葛藤していました。



















イエスとマグダラのマリア結婚していたのではないかという研究は為されていますが、『最後の誘惑』という作品では、彼が彼女を取るか、それとも磔刑に処されることで人類を救済する道を選ぶかという選択で葛藤する姿が描かれました。
つまり、彼は目の前の女性と赤ん坊に後ろ髪をひかれているというよりは、その向こうに透けて見えている故郷の自分の家族(妻と娘)の存在に葛藤しているのです。
危険を顧みて、飛び出したらもう故郷の家族には会えないかもしれない・・・そんな誘惑が確かに彼の心の中にはあります。
シーンが飛んで、塹壕から飛び出して彼がノーマンズランドを疾走する場面を見ていきましょう。
この時、彼は連合軍の第1波が突撃をかける中で、1人だけがそれを横切るように走っています。
これが人間の動線で考えるならば、「十字架」の形になっていて、スコフィールドなりの「受難」が描かれているとも言えるのが興味深いポイントです。
(C)2019 Universal Pictures and Storyteller Distribution Co., LLC. All Rights Reserved.
数々の誘惑や危機を乗り切り、スコフィールドは伝令としての任務を果たし、そして「預言」をブレイクの兄に託します。
スコフィールドが「善人だった」と死んだトム・ブレイクの様子を語る様は、まるでイエスと使徒が彼の言行を語り継ぐ「聖書」の関係です。
そうしてラストシーンで、スコフィールドは樹木の傍らに座り込むわけですが、このシーンは旧約聖書に登場する「生命の樹」を思わせます。
エデンの園と人間の堕落(ルーベンス、ヤン・ブリューゲル画)
創世記のエデンの園を立ち返る光景をラストシーンに持ってくるというのもまた、憎い演出です。
第1次世界大戦という大きな動乱が終盤に差し掛かっており、そうした崩壊を経て、また新しき世界が紡がれていくことを予見させる様でもありますね。
もっと言えば、戦場における「禁断の果実」とは先ほどもお話したように「家族への愛」なのかもしれません。
その愛の深さが時に冷静さを奪い、不安や恐怖を増長させるのだとすると、確かにタブーと言えるかもしれません。
しかし、彼は今回の任務を経て、その「果実」を食らい明日の戦場を行く抜く覚悟をしたようでもありました。
それに気づかせてくれたのが、イエスを想起させる存在であったブレイクだったという点を踏まえると、聖書的な「愛」の伝道の物語であったと締めくくることもできるでしょうか。
おわりに
いかがでしょうか。
今回は映画『1917 命をかけた伝令』についてお話してきました。
こういった個人的な考察記事を読むにあたって、気をつけておいて欲しいのですが、当ブログ管理人の書いている考察はあくまでも一説であって、作品の正当な解釈というわけではありません。



















ということで、作品鑑賞前は「全編ワンカット風」の映像であることくらいしか頭になかったのですが、想像以上に映像の美しさに心を惹かれ、物語にも非常に深みがありました。
ただ、プロットがシンプル過ぎるということも相まって、アカデミー賞作品賞というタイプではないかもしれないなとは思いました。
しかし、この映像と音響を映画館で体験する価値は間違いなくありますので、ぜひ1人でも多くの方に劇場に足を運んでいただきたいと思います。
今回も読んでくださった方、ありがとうございました。