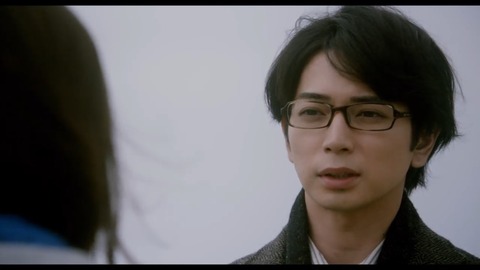みなさんこんにちは。ナガと申します。
今回はですね『Red レッド』についてお話していこうと思います。

直木賞作家である島本理生さんの作品で、発売当時にも大きな話題を呼んだ作品です。
当ブログ管理人は『生まれる森』『ナラタージュ』『ファーストラヴ』を読んだことがありますが、やはり女性の物語を描くのが非常に巧いと思います。
彼女の描く作品に登場する女性たちは、読み手からすると理解に苦しむような側面も確かにありますが、それでいてすごく生々しくて、真に迫るものがあります。
アイコン的な女性像ではなくて、生身の血の通った女性を作品の中に息づかせることができる筆体や表現が、やはり素晴らしいのだと思いますし、多くの読者を惹きつける秘密なのだと思います。
そして、今作『Red レッド』は彼女の作品の中でも特に鮮烈で、議論を巻き起こした作品です。
とりわけ本作が描いているのは、女性性と母性の間で揺れる主人公の葛藤でした。
題材そのものは、これまでに多くの作家やシナリオライターが手垢をつけてきたものだとは思いますが、島本理生さんの手にかかると、これが妙に生々しく、真に迫る物語に変貌します。
女性の家族における身の置き所の無さであったり、社会との繋がりへの渇望、女性として求められることへの欲望、そして子どもの成長を見持っていたいという母性。
これらが入り混じったカオスな心情を、見事な筆体で読み手に実感させたとんでもない作品です。
物語そのものには賛否あるとは思いますが、ぜひ多くの人に見て欲しい、読んで欲しいそんな1作になっています。
今回はそんな『Red レッド』という作品について自分なりに考えたことや感じたことをお話しさせていただければと思います。
本記事は作品のネタバレになるような内容を含む感想・解説記事です。
作品を未鑑賞の方はお気をつけください。
良かったら最後までお付き合いください。
目次
『Red レッド』
あらすじ
イケメンで一流企業に勤める夫とかわいい1人娘に囲まれ、世田谷の高級住宅街で誰もが羨むような生活をしている塔子。
ある日、彼女が友人の結婚式の会場へと足を運ぶと、そこにいたのは大学時代に愛人関係にあった鞍田秋彦と再会する。
かつての記憶が蘇り、彼のことを避ける塔子だったが、ひょんなきっかけで2人で語らう機会を得る。
出産後、控えていたアルコールを摂取し、フラフラとしていた彼女はトイレに足を運んだ際に、鞍田に犯されてしまう。
彼の身体を拒みながらも、自身の中に抗えない女性性の存在を感じてしまった塔子は、彼を拒み、遠ざけようとする。
しかし、鞍田はたびたびアプローチをかけて来る上に、彼女の望みを敏感に察知し、仕事への復帰を手助けすると提案する。
塔子は結婚した際に、夫の真に共働きでという約束をしていたにも関わらず、それを半ば反故にされたことに苛立ちを感じており、夫への反抗もあり鞍田がコンサルティングをしている会社で契約社員として働き始める。
抗えない欲求と、平凡に生きたいという思い、そして1人娘への愛情。
様々な思いに揺れながら、少しずつ彼女は自分の道を模索していくのだった・・・。
スタッフ・キャスト
- 監督:三島有紀子
- 原作:島本理生
- 脚本:池田千尋 三島有紀子
- 撮影:木村信也
- 照明:尾下栄治
- 編集:加藤ひとみ
- 音楽:田中拓人











『少女』といった女性が中心に据えられた作品を手掛け、現代的な家族像を描いた『幼な子われらに生まれ』で高い評価を獲得した三島有紀子監督が今作のメガホンをとりました。
どちらも小説原作ですが、非常に見事な映像化でしたし、特に『幼な子われらに生まれ』は傑出した出来でした。
『Red レッド』は原作もかなりの長編ですし、1本の映画にまとめるのは、非常に難しい題材だと思います。
ただ、三島監督であれば、出来ると思わせてくれますし、どうやら原作とは違った展開が用意されているようなので、尚更楽しみです。
脚本には、『クリーピー 偽りの隣人』や『スタートアップガールズ』の池田千尋さんがクレジットされていますね。
撮影を担当したのは、『OVER DRIVE』や『ニセコイ』で知られる木村信也さん、照明を担当したのは『ニセコイ』『よこがお』の尾下栄治さんでした。
編集には白石和彌監督作品でもお馴染みの加藤ひとみさんが起用されていますね。
劇伴音楽を担当したのは、『幼な子われらに生まれ』でも印象的だった田中拓人さんでした。
- 村主塔子:夏帆
- 鞍田秋彦:妻夫木聡
- 小鷹淳:柄本佑
- 村主真:間宮祥太朗
- 村主宏:浅野和之
- 緒方陽子:余貴美子











主人公の塔子役に夏帆さんを起用したのは、本当にナイスだと思いますね。
第一印象では、少しおっとりしているような印象を与える女優ではありますが、共演した方は軒並みクールで、かっこいい女性であるという印象を述べているのです。
つい先日見た『ブルーアワーにぶっ飛ばす』の役どころもさばさばしていてぶっ飛んだ女性でして、すごくハマり役でした。
そういうある種の第1印象と踏み込んだ時の印象にギャップがある女優だからこそ、塔子にぴったりだと思うんですね。
そして、鞍田役の妻夫木聡さんも個人的には、すごく原作のイメージに近いです。
40代に近づいている俳優でありながら、若者の役もできますし、それでいて年相応の役もこなせるという実力派であり、イケメンであるという彼の特性が鞍田の特長にがっちりとハマるんですよね。
その他にも柄本佑さんや間宮祥太朗さんなど注目のキャスト陣が目白押しです。











『Red レッド』感想・解説(ネタバレあり)
女性が「性」を抱えて「母」として生きるということ
(C)2020「Red」製作委員会
アカデミー賞でも話題になった映画『マリッジストーリー』を見ていると、主人公の離婚調停の担当弁護士になった人物が、女性について次のように言及していました。
酒を飲んで子供にバカという親は許されない。私もやるけどね。
父親は不完全でもいい。”よき父親”なんで言われ始めてせいぜい30年よ。
(中略)
ところが、それが母親には当てはまらない。社会的にも宗教的にも許されない。ユダヤ教やキリスト教の根底には、聖母マリアがいる。
(中略)
女は常に高いレベルを求められる。最悪だけどそういうものなのよ。
(映画『マリッジストーリー』より引用)
この言葉はアメリカの思想の根底には、キリスト教やユダヤ教の考え方があるからという前提に基づくものではありますが、これって日本でも変わらないと思うんですよ。
男性は仕事さえきちんとしていて、家庭に十分なお金さえ入れていれば、多少放蕩しても許され、そして家庭のことを免除されるというような前近代的な傾向は今も見受けられます。
そのしわ寄せをもろに受けているのが、女性の側で、やはり日本でも女性はある種の「完璧」を求められているように思います。
女性の社会進出という風潮もかなり高まってきてはいますが、やはりまだまだ厳しい部分はたくさんありますし、本作『Red レッド』で描かれたような、出産を経た女性の社会復帰も大きな課題ですよね。
女性は子どもが生まれると、「母」としての役割における完璧さが求められますし、社会復帰するとなっても、その完璧さを損なうことが許されないような風潮も見え隠れしています。
しかし、物質の世界でも硬ければ硬いほどに脆く壊れやすいと言いますが、女性も完璧性を求められすぎるが故に、ひょんなことでそれが壊れてしまうかもしれないわけで、本作『Red レッド』を通じて描かれた物語では、主人公の塔子のそんな脆さと崩壊が表出していました。
彼女の家庭は、傍から見れば幸せの象徴そのものだったと思いますし、彼女はそれを主観的ではなくとも、客観的に自覚していたように思います。
ただ、客観的に自覚していたというのが、彼女を苦しめた大きなポイントでもあり、一流企業に勤めるイケメンの夫に尽くす良妻賢母という枠組みに自分を当てはめておかなければというプレッシャーにもなっていたのでしょう。
そんな毎日を過ごしながらも、夫からはもはや女性として見られていないような感覚があり、そして褒められることもなく、社会との繋がりも断たれたままの自分に焦りを感じていたのでしょう。
彼女が抱えていたのは、まさしく女性が「性」を抱えて「母」として生きるということへのジレンマです。
女性として認められたい、1人の人間として社会に出て活躍したいけれども、「母」としての役割を求められ、それが実現できないというのが、まさしく塔子が置かれていた状況です。
そんな絶妙なタイミングで、鞍田という男が現れてしまったんですよ。
彼は、塔子の女性としての価値を全面的に肯定しており、そして職業人としての彼女も高く評価しており、さらにはさりげなく彼女の「母」としての働きを褒めるわけです。











2人の性描写を繋げることで、徐々に塔子が「開いて」いく様を生々しく描写したのは、島本理生さんらしいと思いました。
そうして鞍田との逢瀬の中で、自分の女性性を取り戻した彼女は、1人の人間として、女性として生きたいという欲望がまずます強まっていき、ついには家から出ることを決心するに至ります。
しかし、最終的に彼女は1人の女性として生きる道を選びながらも、「母」としての自分だけは捨てなかったんですよね。
これこそが、本作『Red レッド』が物語の果てに導き出した1つの答えとも言えるでしょうか。
『Red』というタイトルに込められた意味とは?
(C)2020「Red」製作委員会
本作『Red レッド』のタイトルについて島本理生さんは次のように語っています。
「赤は官能的かつ危険を帯びるというイメージがある。以前の自分の小説は“繊細”とか“瑞々しい”というイメージが持たれていて、装丁も青や白といった爽やかな感じの色だった。でも今回は結婚していて、更には子供もいるという中で包み込むような感じではなく、30代女性のリアルさを直に描いてみたかった」
(産経ニュースより)
白と赤が印象的な作品なので、配色的にはコーエン兄弟の『FARGO』なんかを想起させますよね。
白の上に赤というのは、非常に赤が映えるコントラストでして、『FARGO』でも白い雪原と血の赤色が見事な存在感を放っていました。
本作『Red レッド』において「白」を象徴していたのは、物語序盤の塔子だったように思います。
というのも、彼女は自分を幸福な家族の、素晴らしい旦那を支える良妻賢母という枠組みに当てはめ、自分というものを殺して生きていたからです。
しかし、そんな彼女を突き動かしていく2つの「赤」が作中で描かれていました。
- ディオールの赤い口紅
- 娘の翠がキッチンで流した血
この2つの「赤」いモチーフに、本作のテーマが込められているように感じました。
まず、前者のディオールの赤い口紅は、まさしく塔子の女性性の象徴的なアイテムですよね。
彼女が、結婚前に購入しながらも、結婚後ほとんど使うこともなく収納されていたという背景を鑑みてもそうです。
結婚や出産を経て、彼女が閉じ込めるようになった女性性の象徴であり、それを鞍田との逢瀬を重ねる中で再び使うようになるという変化が何より物語っています。
そして、後者の娘の翠がキッチンで流した血というのは、まさしく彼女を「母」という役割に留めおこうとするトリガーとして機能していますよね。
きっと、この事件がなければ、塔子はあっさりと家庭を出てしまっていたと思うんですが、あの血の「赤」色が彼女をそうさせなかったのは紛れもない事実です。
そう考えると、この2つのモチーフは、まさしく本作のテーマを象徴しているんですよ。
前者は、家庭で生きる女性の「性」の部分を表し、後者は女性がそれでも捨てることのできない「母」の部分を表しています。
この2つの「Red」こそが、本作の示そうとした、ある種のアンサーになっているのだと思います。
同書の終盤に、塔子の姑がこんな言葉を残しています。
「塔子ちゃんも、最初はいい子だと思ったけど、結局、自分の思い通りにしたかったのよね。」
(『Red レッド』より引用)
確かに、劇中で描かれた塔子の行動は明らかな不倫であり、身勝手と捉えられてもおかしくはないのですが、それでも彼女の1人の女性としても生きたいし、母親としても生きたいという欲望を簡単に否定してしまうのはどうかと思うのです。
男性も女性も誰だって思い通りに生きたいわけですが、子供がいると当然そうは言えない事情が出てきます。
しかし、子どもが生まれた際に、女性の側ばかりが「思い通り」に生きることを制限され、そして「母」としての完璧を求められるのは、何だか違和感を感じます。
だからこそ『Red レッド』という作品は、女性性を享受し、1人の人間として社会でも認められ、それでいて母親として子供にも寄り添っていきたいという「不完全な母親」像を思いっきり描いてみせました。
ただ、彼女に「不完全だ」というレッテルを貼ることが果たしてできるのでしょうか。
この「不完全さ」というものは、前近代的な価値観に照らし合わせた時に生じる考え方なのだと思います。
先ほどの『マリッジストーリー』からの引用にもあったように、夫の「不完全さ」は許され、なかったことにされるのに、女性には簡単に「不完全」というレッテルが貼られてしまいます。
そういう意味でも、私たちは、社会の在り様も含めて、夫婦双方の「身勝手さ」がある程度許される環境を作っていく必要があると再実感させられます。
硬いほど脆く壊れやすいという性質は「家族」にとっても同じだと思いました。
もっと母親にも、そして家族の形や在り方にも「不完全さ」があって良いと思いますし、そういった良い意味での柔らかさがこれからは一層求められるようになってくるのだと思います。
『Red レッド』はまさに1人の女性の鮮烈な「身勝手さ」と「不完全さ」を通じて、これまでの社会や家族の在り方へのカウンターを示し、そしてその向こう側を見据えたメッセージを提示して見せたと言えるでしょう。
外からは見えない家族のカタチ
近年、週刊誌が不倫騒動をスクープする機会が増え、ワイドショーなどをにぎわせることも珍しくありません。
しかし、人様の家族の問題に全く関係のない一般大衆があれこれと文句を言い、「人間失格」だと言わんばかりに攻撃する風潮には違和感を覚えます。
家族というものには、「一般性」などというものは存在せず、全ての家族がたった1つの特殊な空間でありコミュニティです。
つまり、私たちが自分の家族や在りもしない「一般性」の尺度に照らし合わせて、それを逸脱している家族や夫婦、妻や夫を攻撃するのは、少しズレていると言わざるを得ません。
結局のところ、家族の事情なんてものは、外からは見えないわけで、そのコミュニティに属している人がどんな思いで生きているのかなんてことは、推し量りようもないわけです。
本作『Red レッド』における塔子もまた、高級住宅街で暮らし、イケメンで高収入の夫を持ち、いまどき珍しい専業主婦という周囲から羨ましがられる要素をたくさん持ち合わせています。
しかし、それで塔子自身が幸せを感じているのかと言うと、そうでもないというのが本音なのです。
傍から見ると、絵に描いたような幸せな家族なのに、内部にいる彼女としては、抑圧されているように感じられ、そこから逃げ出したいという願望を抱いているのです。
その責任の一端は、夫にもあり、また彼の母が常に一緒に暮らしているという息苦しい状況にもあったと言えるでしょうか。
本作を読んで、塔子があまりにも身勝手すぎるという意見を持つ方はたくさんいると思うのですが、私はそうは思いませんでした。
というよりは、それを判断する権利は私にはないなと純粋に感じました。
きっと、それを「身勝手だ」と罵ることができるのは、あの家族の中にいる人間だけなんだと思います。
塔子が起こした行動によってあの家族の世間的な体裁にどんなダメージを追ったのかは分かりません。
しかし、1人の女性として生きる道を選んだものの、それでも「母」としての彼女を受け入れて、再び生きていくというのが、夫である真の決断でしたし、それを外野がどうこうということはできません。
彼らが「家族」として迷いながら、葛藤しながら選んだ道なのです。
結局のところ、家族を外から見たイメージや、一般性という在りもしない尺度に照会して値踏みをするなんてことには何の意味もありません。
外から見れば「身勝手」であっても、家族がそれを受け入れて、前に進めるのであれば、その家族にとっては決してネガティブではないですよね。
だからこそ『Red レッド』という作品において、世間的な理想の家族を追求していた彼らが、それを捨ててでも「家族」という形を選び、繋がろうとしたところに、私は希望を見たような気がしました。
「家族」の不幸は外からは見えません。
しかし、同時に「家族」の幸せだって外からは見えないのです。
全くの別物だった映画版について
早速、映画版も鑑賞してきたのですが、これかなりの問題作だと思いますよ。
正直、原作を読んでからこの映画版を見に行った人は、良くも悪くも衝撃を受けることでしょう。
あまりにも内容が異なるので、タイトルが変わっていたとしても、原作が『Red』だとは気がつかないレベルですよ(笑)
今回はいくつかの点に分けて、原作との違いとこの映画版の是非について考えてみようと思います。
鞍田のキャラクター性について
(C)2020「Red」製作委員会
まず、個人的に一番気になったのは、鞍田の人物設定です。
原作を読んでいた時の彼の印象は、ただ強引に塔子に対して身体の関係を迫るだけの人物ではありませんでした。
とりわけ彼女が「一番求めているもの」をさりげなく提供できてしまうのが、鞍田というキャラクターだったように思います。
彼女が体形のことに悩んでいる時には、彼女を言葉で褒めたたえ、復職したいと願っていた時には、仕事を斡旋し、彼女が家庭で辛いと感じた時には、決まって電話がかかってきて会いに来てくれるのです。
単なる身体の関係だけではなく、塔子が女性として、人間として真に欲しているものを提供できるのが彼なのであり、だからこそ彼女が不倫関係になることを分かっていながら、彼に引き寄せられていったことに説得力がありました。
しかし、映画版の鞍田は一方的に彼女に対してキスや身体の関係を迫るだけのクズ男と化しており、もはや何の魅力も残っていません。
妻夫木聡さんが演じていることで、ギリギリ役としての説得力を保っていた気はしますが、あまりにも原作にはあった彼の魅力を削いでしまったように思います。
塔子のキャラクターについて
そして、主人公の塔子についても随分キャラクター設定が変更されていましたね。











原作の塔子の感情がぶっ飛んでいながらも、リアルだと感じることができたのは、彼女が1人の女性である自分と翠の母親である自分との間で強く葛藤していたからなんですよ。
映画版だと割と序盤に鞍田からの強引なキスを自ら受け入れてしまいますし、割と早い段階で性行為を行っています。
こういう描写をしてしまうと、本作が本当にただの不倫文学作品のようになってしまうんですよね。
彼女は家庭を守りたい、そして母親として生きたいと思いながらも、少しずつ抗えない欲求に飲み込まれていくというプロセスにリアリティがあったのであり、そこがごっそり抜けてしまった映画版の塔子の感情には、リアリティも生々しさも感じられません。
先進的なジェンダー観とフェミニズムを取り入れた原作が、映画版になるとなぜか一昔前の不倫小説になるという悪夢を見せつけられました。
真と姑の描き方について
個人的に一番イライラしたのは、真と姑の描写の仕方でした。











原作では、真って確かに塔子の感情に鈍くて、マザコンで、育児にはあまり関わろうとしない人物ではあるんですが、積極的に彼女を縛り付けるような発言はしないんですよ。
映画版の真は、彼女に対してぞんざいな扱いをしますし、さらには「仕事を辞めた方が良いんじゃない。」ですとか「お前の一番の仕事は母親だろ。」といった一昔前のステレオタイプ的な自制蔑視発言を繰り返していました。
ただ、こういう見え透いた女性蔑視的思考を持っているキャラクターとして描くのは、あまりにも不誠実ですよ。
なぜなら、原作における真というキャラクターが際立っていたのは、彼は塔子を縛り付けたり、下に見るつもりはまるでないにも関わらず、無意識的にそれを感じさせる言動を繰り返していたからなんです。
塔子の感情にイマイチ気がつかない、そして女性蔑視的な発言や行動を取っていることに気がつかない鈍感さこそが真の特徴と言っても過言ではありません。
そして同時に姑の描写についても、いかにも息子の嫁に圧力をかけていそうな少し高圧的なキャラクターに仕上がっていました。
しかし、これも原作とは真逆のキャラクター性でして、原作では比較的塔子と良好な関係を築いています。
姑との関係性もかなり良好であったからこそ、それでもあの家から飛び出したいという思いを背負っていた塔子の心情が非常に真に迫るものがあります。
単なる不倫小説・男性へのカウンターでしかない映画版
『Red』という作品を再構築するにあたって、注意すべきはやはり単なる不倫小説として終わらせないことでしょう。
原作の時点で「不倫小説」と揶揄されてしまいそうなところを薄氷を履むが如く、切り抜け、新しい家族のカタチや女性の生き方を問うエポックメイキングな作品となりました。
そして、そんな作品を作り上げる上で重要だったのが、もちろん先ほど挙げたキャラクター像の作り方であり、更に言うなれば、あの痺れるようなエピローグです。











原作では、塔子は鞍田に思いを惹かれ、離婚も一時は決意しながらも、踏みとどまり、最終的には翠の母親を続ける道を選んでいます。
鞍田が命を落とす場面は描かれませんが、彼は塔子との別れという辛い瞬間をある種の「報い」として経験することとなりました。
一方の映画版では、クライマックスが雪国からの車での帰り道に置かれており、さらにここで鞍田が命を落とすんですよね。
しかも、塔子は結婚指輪を公衆電話BOXに置き去りにし、亡き彼と共に自分が自分らしくいられる人生を選ぼうとします。
つまり、母親を続けるという道を選ぶことはないのです。











ここがかなりこの映画版の賛否を分けることは間違いないと思います。
ただ、個人的には原作が悩みながら、絶妙なラインで突いたあの痺れるような結末が失われてしまったことに落胆を覚えました。
正直、映画版の『Red レッド』の物語って、一昔前の不倫小説とそう変わりない内容になってしまっているんですよね。
しかも、ただ単に女性が生きたいように生きるというある種の「身勝手さ」を押しつけるだけの作品となっていて、カウンター以上の何かにもなり得ていません。
原作が不倫を擁護しているという意見には、個人的には反論できますが、この映画版は不倫を擁護していると取られてもおかしくないのも事実です。
原作者公認の『Red レッド』アナザーバージョンなのだとしても、個人的にこのタイトルでこんな内容の物語は見たくなかったと思ってしまいました。
映像作品としての出来と建築デザイナー
(C)2020「Red」製作委員会
原作からの改変の多くについては、正直個人的には納得がいきません。
ただ、それはさておき、本作は1本の映像作品としては非常に優れていると思いました。
まず、かなり独特で見る側からすると、明らかに「見づらい」と感じさせられるカメラワークは印象的でしたね。
アングルに落ち着きがなく、俯瞰というよりはクローズアップショットを多く取り入れ、更にはそこに手持ちカメラ撮影のような味わいも付加されています。
まさに塔子の身の置き所の無さや鞍田の残り僅かな人生でありながら激しく彼女を求める思いが、カメラに宿っている様でもあります。
そうした2人の身の置き所の無さを強調したカメラワークですが、最後のあの2人で朝焼けの道を走っていくシーンで静かに落ち着き、そしてクローズアップショットからロングショットへとズームアウトしていくようなアプローチが取られ、「居場所」を見つけたことが強調されていました。
また撮影以外にも、演出面で「赤」の使い方は非常に良かったですね。
とりわけ原作とは異なる形で「赤」を取り入れており、母親としての「赤」は翠が出張の日の朝に来ていた赤いカーディガンに、女性としての「赤」は鞍田の吐いた血にコンバートされていました。
そして、映画版では後者の「赤」を選び、そして朝焼けの中を、鞍田と共に走り抜けていきます。
青と赤が溶けあうような光の中で2人は「赤」を追い求めて生きていくのだということが強く感じられました。
物語的な部分で言うと、原作ではエンジニア(SE)という設定だった鞍田や塔子を建築デザイナーに改変したのは、個人的には良かったと思います。
というのも建築デザイナーというのは、まさしく「ライフスタイル」をお客様に届ける仕事なんですよね。
だからこそ、2人が自分たちの理想の家の模型を作るシーンも彼らなりの「ライフスタイル」の模索と言えますし、そして何よりこの作品そのものが観客に「ライフスタイル」を提示するようなそんな内容になっています。
ただ、映画版は建築デザイナーに改変し、そうした部分を強調しながらも、新しい「ライフスタイル」を提示するには至らず、なぜか前近代的な不倫小説のカテゴリに収まってしまうという矛盾も孕んではいました。
原作と比較すると、どうしても違和感が大きい映画版ですが、1本の映像作品としては優れている部分も散見されました。
おわりに
いかがだったでしょうか。
今回は『Red レッド』についてお話してきました。











公開前の番宣で、監督が原作とは違った物語にしたということでお話をされていたようで、より一層映画版が楽しみでした。
賛否両論で、問題作とも言われた島本理生さんの作品ですが、非常に鋭くそしてリアルに女性の葛藤を描いていたと思いますし、非常に考えさせられる内容でした。
単なる女性側からのカウンターに終始するのではなく、その先を見据えたメッセージまで内包出来ている点には、流石と思わされましたね。
ただ、この原作と映画版の結末が違いは、原作に愛着があればあるほど受け入れがたいものだとは感じます。
当ブログ管理人もどう受け止めたら良いのか迷っております。
ぜひ、映画だけでなく映画を見た方には、原作も読んでいただきたいと思いますね。
今回も読んでくださった方、ありがとうございました。