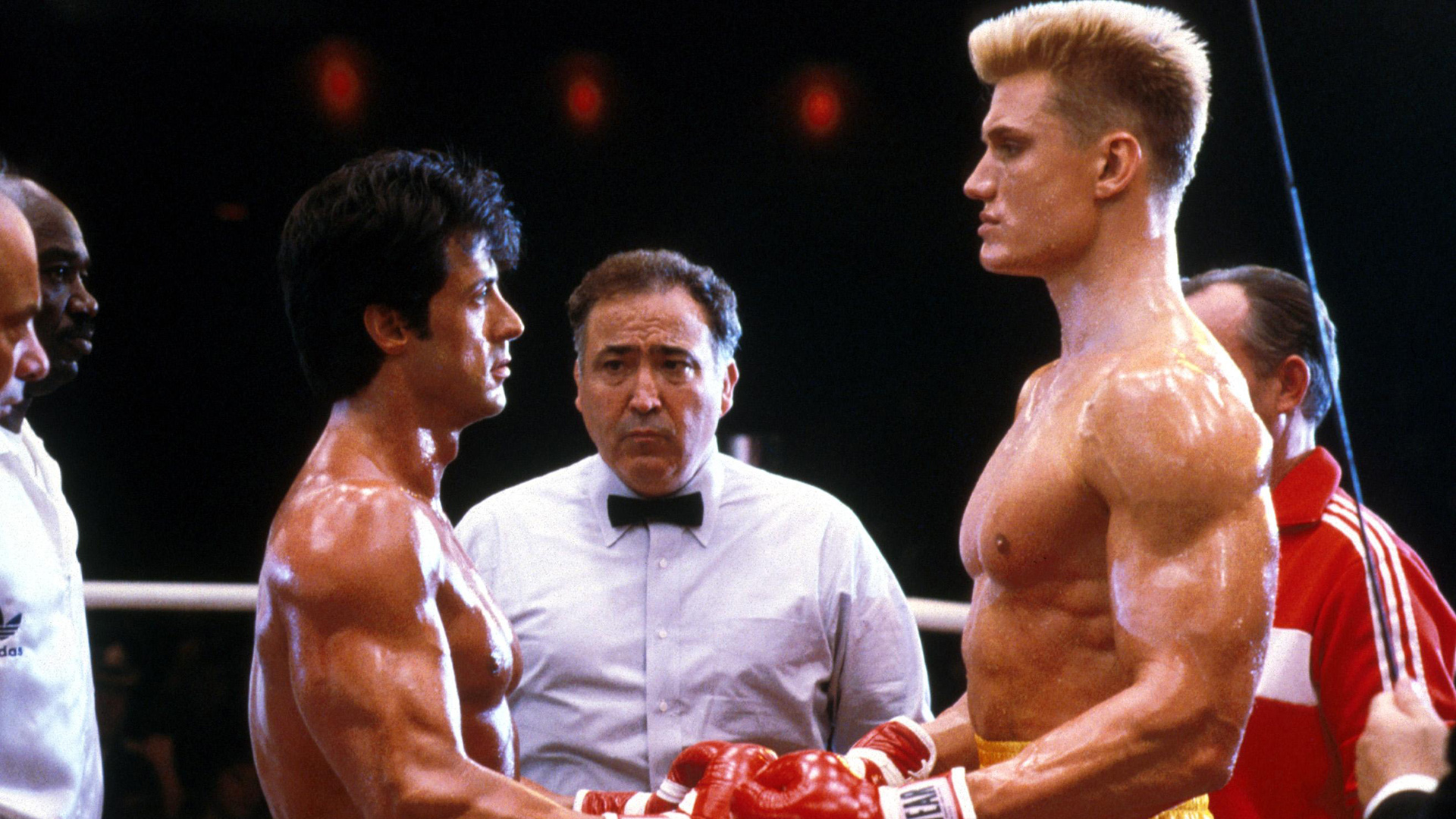みなさんこんにちは。ナガと申します。
今回はですね映画『37セカンズ』についてお話していこうと思います。

公開している時から、Twitter経由でたくさんの人におすすめしていただいたのですが、なかなか時間も場所も合わずで、ずるずると上映終了を迎えてしまい、見逃してしまいました。
そんな2020年2月初旬公開の作品が、何と異例の速さでNetflixにて公開されたということで、ありがたく拝見させていただきました。
こうして、何とか鑑賞の機会を得たので、ブログを書き始めたのですが、あまりの傑作っぷりに書きたいことがありすぎて、まとまらない状態に陥っております。
誇張抜きに申し上げても、近年の日本映画で「映像作品」として『37セカンズ』に比肩する映画はないのではないかと感じたほどに頭3つほど抜き出た傑作です。
主人公に寄り添い過ぎない客観的な映像が、むしろ私たちが主体的に物語を追体験する上で効果的に機能していますし、照明やカメラワーク、ちょっとしたカットインの演出まで全てが完璧であり、ここまで洗練された日本映画は近年なかなか見かけないでしょう。
今回は、そんな映画『37セカンズ』について語っていきます。
記事がかなり長くなりそうというのもありますし、いつもの記事以上に見た人向けの側面が強まる内容ではあるので、作品のあらすじやスタッフ情報はカットして、いきなり本論に入ります。
本記事は作品のネタバレになるような内容を含む解説・考察記事となっておりますので、未鑑賞の方はお気をつけください。
良かったら最後までお付き合いください。
目次
『37セカンズ』解説・考察(ネタバレあり)
今回の記事は、いつもの構成とは少し趣向を変えて、映画のシーンやカットを適宜取り上げながら、順番に語っていこうと思います。

















ということで、もう個人ブログですから、語りたいシーンやカットは全部語りつくすという勢いで書いていこうと思っております。
ファーストカットの謎
まず、『37セカンズ』においてファーストカットは少し謎めいていますよね。
主人公のユマが赤い口紅とマニキュアを使っている描写なのですが、クレジットが流れての直後のシーンで、彼女は赤い口紅を塗っていない状態で登場します。
つまり、このカットは、時系列的に考えると、少し違う時間軸のものであることが推測されますよね。
そう考えた時に、本作において「赤」という色が非常に印象的に登場することがキーになって来るかと思います。
成人誌の編集長が来ている服であったり、彼女が正行為に及ぼうとするシーンの照明であったり、彼女がアシスタントを担当している漫画家やその編集者の着ている服も赤が基調であることが多いですよね。
(C)37Seconds filmpartners

















こういったシーンを紐解いていくと、本作では「赤」という色には、ユマの強烈な願望やなりたい自分が投影されているように感じます。
そこから推測すると、赤い口紅とマニキュアを使っているという行為は、彼女がなりたい自分を自分なりに実現し、じしんをもてるようになったことの表出なのではないかと思うのです。
では、時系列的にはどこに来るのかと改めて考えてみますと、ラストシーンよりもまだ少し後の話なのだと思いました。
ラストで、成人誌の編集長が、知り合いにユマのマンガを紹介するシーンがありましたが、ここから繋がる彼女の明るい未来が実はファーストシーンで示されたのではないかと感じた次第です。
ユマと恭子の関わりを状況で映す
この映画全体に言えることなのですが、本作は出来事をユマの主観で描くというよりは、むしろ客観で描くことに徹しています。
客観的な視点が、非常に効果的に機能していると思うのは、とりわけ日常生活行動に何の支障もなく暮らせているマジョリティが日常生活の中では感じることができない「感覚」を状況から感じ取れるようになっているからです。
例えば、今作のカメラの位置は大半のシーンで、ユマの目線の高さになっています。
それでいて、彼女の主観に寄り添って、映像を撮っていくのではなく、少し離れた位置からの定点観測のような距離感で淡々とカットを積み重ねていきます。
私たちが物語を読むときに、しばしば「自分がこの状況に置かれたらどうするか」を考えると思うのですが、読解というのは、そういうことではなくむしろ「登場人物がこの状況で何を感じているのか」を読み取ることです。
そのため、この映画がユマの主観に寄り添って映像を展開していたとすると、彼女が日常生活や母との関係性の中で感じていた微妙な「ニュアンス」を描き切れなかったと思いますし、それを補完するナレーションなどが必要になったはずでしょう。
風呂場の脱衣所のシーンで感動したのは、彼女の身体が映像の中に収められており、同時にトイレの便器や洗濯機がフレームに収められていた点です。
このカットを見ると、彼女の身体の大きさと便器や洗濯機の大きさが明確に対比されると共に、彼女の視点から見える世界を追体験することができます。
カメラを主人公の主観に据えて、その視点で日常の何気ない事物を大きく、高いものに見せるという手法はよく見ますが、実はこのシーンで重要だったのは、ユマの身体性です。
人間は身体があるからこそ物事を認知したり、思考したりすることができると言われており、人工知能などの研究では、そこで大きな障害が生じることがあります。
つまり人工知能が身体性を持たない知であるが故に、人間が身体を通じて当たり前のように体得している知を感じ取ることが難しいのです。
例えばですが、背もたれがない椅子と机って構造や形状は非常に似ていますよね。しかし、人間はそれが椅子なのか机なのかを自分の身体を使って判断することができます。
しかし、身体がない人工知能の場合だと、そういった身体性に基づく判断というものが難しくなってしまいます。
私たちもいきなりユマの視点で、世界を見せられたとしても、映画の中に「身体性」を持ちませんから、自分見ている景色とはあまりにも違う日常の風景をすぐに飲み込むことは難しいのです。
そのため、脱衣所のシーンでは、ユマがフレームに収まった上で、カメラの目線が彼女の視線の高さになっているという演出が効果的に機能しています。
彼女の身体を基準にして、彼女の置かれている状況を私たちは正確に把握することができているんですね。

















あのシーンも、彼女の視点で撮影せずに、あえて階段の下から撮影することで、彼女の身体では階段を降りることはできないという「状況」を強調しています。
もう1つ印象的なのは、彼女がシェイクスピアの作品を母親から読み聞かせをしてもらっているシーンだと思います。
このシーンは、母の恭子がユマを見下ろし、ユマが恭子を見上げるという視線のベクトルを通じて、2人の関係性を明確にしているのです。
しかもカメラはあくまでもユマの視線の高さにありますから、恭子の表情は完全にフレームアウトしています。
読み聞かせをしている恭子がさりげなく、ユマのプレートに乗ったハンバーグをフォークで切り分けるのですが、この描写は恭子からの一方的な保護のベクトルが垣間見えるカットです。
それに対して、ユマは少し反抗めいた視線のベクトルを母に向けるのですが、恭子はそれを気に留めることなく本を音読し続けます。
何気ないやり取りですが、会話すらほとんどない一連のシークエンスによって、2人の関係性やお互いに対して抱いている感情、そしてお互いの立場が可視化されていました。

















カメラが一気に対象から距離を取り、ユマが食事をしているダイニングを廊下からのショットで収めていますよね。
(C)37Seconds filmpartners
この時、廊下とダイニングを隔てる枠によって食事をしているユマが切り取られ、閉じ込められているような映像になっているんですよ。
しかも、静かに読み聞かせをしている恭子がその枠の右側へと移動していき、フレームアウトしているのです。
これにより、夕陽に照らされたユマと彼女の影がじんわりと浮かび上がり、孤独感を強調しています。
この映像表現の豊かさには、脱帽です。
緩やかな搾取と差別
さて、先ほどのシーンから、一転してポップな劇伴に切り替わった次のシーンでは、ユマの仕事場の様子が描かれます。
まず、目を引くのが、彼女の雇用主でもある漫画家が、彼女の給料を中抜きしている(少し減額している)描写ですね。
ユマは、障がいを抱えているが故に、業務に支障をきたすというようなことはなく、むしろ雇用主のゴーストライターとしてメインで活躍している実力者です。
それでも彼女の給料が中抜きされてしまうという残酷な描写には、障がい者に対する「見下し」のような感覚が垣間見えます。
加えて、印象的なのが、編集者の男性のセリフですよね。
彼は、ゴーストライターの事情を知りませんから、ほとんど悪気もなく「障がい者のアシスタントがいることで、好感度が上がる」などという発言をするのです。
その発言の意図には、その公表によって「障がい者アシスタント」としてユマにも注目が集まって、彼女のためになるだろうという善意もあるはずとは思います。
しかし、ユマの立場からすると、自分の障がい者という立場を「搾取」されているような気分になることでしょう。
もっと言うなれば、彼女の雇用主でもある漫画家も、彼女が障がいを抱えているという点を利用して、自分の地位と名声のために「搾取」しています。
これらの一連のシークエンスの中では、明確な差別は描かれていません。しかし、障がい者という立場を利用し、搾取しようとする善意めいた「差別」がそこには描かれていました。
サイン会のシーンで、サヤカがユマがやって来たことに驚く描写がありましたが、きっと彼女の中にはユマは車椅子に乗っているし、1人でイベント会場までやって来るなんて無理だろうという「見下し」と「軽視」があったが故の驚きでしょう。
サヤカにとっては、車椅子に乗っていて、自分1人での行動圏が狭く、声が小さいユマだからこそ都合が良いのです。
その後のシーンで、ユマが自分の描いたマンガを成人誌の編集社に持ち込むシーンがありますが、ぜひ注目してください。

















彼女が最初に声をかけた編集者の女性は、振り向くと、彼女の顔と乗っている車椅子の間で視線を2往復させています。
加えて、後程登場した編集長の女性も、やはり顔を見た後に車椅子を一瞥していますよね。
人と会うと、初対面で自分は他の人とは違う異質な存在なのだということを相手に感じさせてしまう、そしてそれを表情や視線で否応なく感じさせられるという残酷さが生々しく映像の中に閉じ込められていました。
ユマが出会い系サイトを通じて、優しそうな男性と出会い、映画デートの約束を取りつける展開がありましたよね。
その男性は、ユマに対してとりたてて偏見を持っているような様子はありませんでしたが、彼の本心が映画デートをすっぽかすという行為に滲み出ているようにも思えました。
本作『37セカンズ』は直接的な差別描写やセリフを盛り込むということは、ほとんどしていません。
しかし、それでいて些細な描写にちょっとした差別意識や搾取の構造を忍ばせることで、ユマが置かれている状況や立場を感じ取ることができるわけです。
ホテルのシーンで印象的な赤と青
本作『37セカンズ』はカメラワークも見事ですが、照明や色づかいも非常に優れています。
さて、ユマが映画デートの約束をすっぽかされて、夜の街へと繰り出すシーンがありましたが、ここで彼女は金銭を渡して、性的なサービスを受けるということになります。

















彼女がいるラブホテルの一室は、ピンク色の照明で照らされていますが、これはおそらく赤色とは明確に区別して使われているんだと思います。
本作において「赤」がユマの願望やなりたい自分の投影なのだと解釈すると、それに似て非なる「ピンク」は、彼女が自分の願望だと思いこもうとしているものとも解釈できるのではないでしょうか。
ちなみに「ピンク」は、ラブホテルの一件の後のユマがサヤカのYoutube用の動画を撮影しているシーンで、サヤカが着ているワンピースや部屋のカーテンなどの色としても使われています。
つまり、徐々にユマの目標や憧れが、サヤカからは乖離して言っていることが色づかいの変化から読み取れるわけですね。
その後、部屋から男が去っていくと、彼女は1人取り残されるわけですが、彼女がシャワーを浴びている浴室は「青」い照明なんですよね。
青とは憂鬱を象徴する色であり、ゲーテの『色彩論』によると、その内に闇を内包する色でもあります。

















そして、その次のシーンの色づかいが素晴らしいので、ぜひ注目してみてください。
ラブホテルのエレベーターで下の階に降りようとするユマが映し出されますが、この時のエレベーターの扉の色が何と「赤」色なんです。
そして、「赤」色のエレベーターの扉が開かないという状況を作り出しているわけですね。
つまり、このシーンでは、どんなに望んでも、願望やなりたい自分に近づくことができない、そこに至るための扉を開けることができない彼女の無力感を色づかいだけで強調しているのです。
恭子が抱える劣等感
『37セカンズ』の中心にあるのは、あくまでもユマと恭子の親子関係ではありますが、恭子の感情がふと垣間見えるシーンがあります。
それが、彼女がユマに付き添って仕事場を訪れた際に、サヤカと彼女の母親に鉢合わせた場面ですね。
この場面で表出するのは、ある種の娘の序列が母親同士の序列にも繋がっていることを仄めかすような代理戦争です。
エレベーターに乗り込む際に、恭子はサヤカの母親と一緒になることを極めて意図的に避けましたよね。
これって、恭子自身が、サヤカよりもユマが劣った存在であるという引け目や劣等感を抱えていて、それ故に自分自身がサヤカの母親に対して劣等感を抱いているようにも見えました。
つまり、このシーンが表出させたのは、ユマを一番大切に思っているはずの恭子が、実は彼女の可能性やポテンシャルを信じていないという点です。
その後のシーンで、恭子はユマに対して「私がいなければ何もできないでしょ!」と発言していますが、この言葉からも、彼女が娘を信じてあげられていないことは明白でした。
恭子が勝手に娘の現状や未来を悲観して、劣等感を抱き、そして自分がいつまでも守り続けてあげなければという責任感を背負っているのであり、ユマにとってはそれが息苦しいのだということがひしひしと伝わってきますね。
「見上げる」という行為をポジティブに転じる
(C)37Seconds filmpartners
当ブログ管理人が『37セカンズ』の中で1番感動したのが、酔っぱらった彼女がヘルパーの俊哉に車で送ってもらうシーンです。
このシーンの何がそんなにすごいのかと言いますと、「見上げる」という行為の意味づけをネガティブからポジティブに転じた点だと思います。
基本的に、これまでのシーンにおいて「見下ろす」という行為は、周囲の人が彼女に対して抱く無意識の差別意識の表出であり、「見上げる」という行為はユマの劣等感の表出でもありました。
しかし、酔っぱらった彼女は車の中から、遥か上の景色を「見上げて」、宇宙人が私たちのことを観察しているのではないかというワクワクするような空想をしています。
日常生活行動に何の支障もなく暮らせているマジョリティは、普段取り立てて上を見上げてみるということはしませんよね。
ただ、そういった人たちよりも常に低い目線で生きているユマは、いつだって世界を「見上げて」います。
だからこそ、見上げた先にある美しい世界に気づくのだと思いますし、それは「見上げる」という行為のポジティブな側面に他なりません。

















彼のそのぎこちない視線の動きは、普段私たちがあまり「見上げる」という行為をしないことからくる不慣れさと、ユマの存在が気がつかせてくれたワクワクするような世界の引力を見事に表現しているのです。
この車の中の短いシークエンスは、『37セカンズ』という作品のクオリティを3段階くらい引き上げているように感じました。
マンガを描くという行為に込められた真意
『37セカンズ』では、所々でアニメーションやマンガのような演出がインサートされます。

















序盤に、彼女は成人誌向けの原稿を書くシーンで、マンガのカットインが為されましたが、ここでは現実では不自由でもマンガの中では自由だという対比を強調させているのだと解釈していました。
ただ、物語が後半になるにつれて、ユマが絵を描くという行為には、重要な意味が内包されていることに気づきます。
というのも、両親はまだ彼女が幼い頃に離婚していて、その後母親と2人暮らしになったわけです。
そして、ユマが父親との接点として唯一所持しているのが、父から送られてきたイラスト付きのポストカードでした。
セリフの節々からも伝わって来るように、ユマにはどこか自分の障がいのせいで両親が離婚してしまったのではないかという負い目があります。
だからこそ、彼女はそのポストカードに対する返信を自分の描いた絵ですることで、両親の関係を繋ぎ止めることができると考えたのかもしれません。
しかし、父からの返信はありませんでした。正確に言うと、恭子がそれをユマに渡さなかったわけですが。
ユマがスマートフォンを取り上げられた後のシーンで、例のポストカードがアニメーションとなって動き出す一幕があります。
その中では、父親と幼少期の自分が楽しそうに遊んでいる姿と、車いすに乗った自分の姿が対照的に描かれていました。
この一連のシーンを見ながら感じさせられたのは、ユマにとっての絵を描くという行為、マンガを描くという行為は、ある種の「償い」なのかもしれないということです。
自分が生まれてきたことを悲観し、そして自分のせいで関係を壊してしまったのではないかと負い目を感じているからこそ、彼女は父が送ってきたたった1通のポストカードに対する返信を描き続けているのだと私は解釈しました。
そうした思いを振り切るために、自分のためにマンガを描くために、彼女が父親に会いに行かなければならなかったのは、物語の流れとしては至極当然かと思います。
最後に、彼女の描いた「姉のイラスト」が再び家族を結ぶというエモーショナルな瞬間が訪れますが、本作は、非常にマンガや絵というモチーフを上手く物語のキーにしていたと言えるでしょう。
ラーメンにレモン、俊哉と赤
家出をしたユマは、俊哉の家に居候することとなりました。
その流れで、2人がラーメンを食べるシーンがありますが、これが妙に効いてますよね。
ラーメンにレモンを絞るだけで、そんな少しのことで、全く新しい味が生まれるという内容なのですが、これは『37セカンズ』の後半部分における大きな主題だと思います。
たった1人との偶然の出会いが自分の人生を大きく変えていくかもしれない。レモンというモチーフはまさしくユマにとっての俊哉の存在に重なります。

















(C)37Seconds filmpartners
青い光に包まれた室内で2人が会話をしているのですが、この時の俊哉付近の照明の色づかいを見て欲しいのです。
よく見ると、実は背景で赤い光がじわっと浮かび上がっているんですよ。

















ここまでも書いてきたように、「赤」という色はユマの願望やなりたい自分を象徴する色であります。
俊哉がレモンのような存在なのだとすると、彼はユマに希望をもたらしてくれる存在であり、なりたい自分になるための助けになってくれる存在であることが、この色づかいで見事に表現されているのです。
青と赤の色づかいが印象的な作品でしたが、ここまでそれぞれの色に意味を積み重ねてきたことで、このワンシーンが持つ意味が際立っていたことに、思わず声が漏れましたね。
ユマの成長を他者を鏡として描く
物語の終盤に、ユマは俊哉と共に双子の姉に会うために、タイへと向かいます。
そこで、姉と再会するわけですが、この一連のシーンの中で見事だと感じたのは、ユマの変化や成長を周囲の変化を通じて描いた点です。
実は『37セカンズ』という作品は、ユマの成長を明確には描きません。

















ただ、彼女の周囲の人々が変化していくという描写を通じて、彼女の成長や変化を切り取っていくのです。
例えば、公衆電話でユマが母の恭子に電話をしたシーンはどうだったでしょうか。
この時、恭子はいつもであれば「いまどこにいるの!迎えに行くから教えなさい!」と怒鳴りつけているところだと思いますが、そうはなりませんよね。
(C)37Seconds filmpartners
彼女は、静かに「大丈夫なの?ちゃんとご飯食べてるの?」と言葉をかけ、彼女の居場所や行動について深追いすることはありませんでした。
この一連の描写では、ユマが自立した存在になりつつあることが、恭子の変化を通じて我々に伝えられます。
そして、タイでの展開では、ユマの姉に大きな変化をもたらすことで、ユマ自身の変化や成長を描くことに成功していました。
別れ際に、姉はユマを呼び止めましたよね。ここで、彼女は自分がユマのことを避け続けていたこと、恐れ続けていたことを謝罪しました。
しかし、彼女はそんな姉の手を静かに握り「もう怖くないですか?」と尋ねました。
それを受けて姉は静かにユマを抱きしめましたね。
(C)37Seconds filmpartners
長年存在を知りながらも、距離を取り続けてきた彼女が、ユマを受け入れ、抱きしめようとしたのは、大きな変化であり、そうさせたのは間違いなくユマです。
つまり、姉の心境や行動の変化に、ユマ自身の成長と変化が投影されているわけですね。
ラストシーンでは、彼女が再び成人誌の編集長である吉本に会いに行くシーンが登場します。
この時、彼女は描いていた成人誌向けではないマンガを見せるわけですが、吉本の反応は大きく変わりましたよね。

















つまり、このシーンにおいては、吉本の反応の変化から、その内容を読み取りなさいということなのです。
なぜ、最初に原稿を持ち込んだ際に彼女の作品が受け入れられなかったのかを考えてみますと、それは自分に経験がないことを描こうとしたからですよね。しかし、2回目には受け入れられました。
その理由は、彼女が自分自身を受け入れ、肯定し、自分の経験したことを載せて作品を作ったという変化があったからということでしょう。
本作におけるユマの最大の変化は、自分自身を肯定できるようになったということです。
しかし、『37セカンズ』はあえてそれを明確化せずに、吉本の反応の変化に投影する形で、忍ばせてあるのです。
このように、ユマの変化や成長を、彼女自身の行動や言動の変化というよりはむしろ、それを受ける側の他者の変化を通じて描こうとしたのが、非常に斬新であり、作品に厚みをもたらしていたと思いました。
おわりに
いかがだったでしょうか。
今回は映画『37セカンズ』についてお話してきました。
鑑賞後の勢いで書きましたが、あらすじやスタッフ・キャストの説明なしで10,000字を超えるボリュームになっており、それほど語るところが多い作品であったことを実感します。

















今回は、あえていつもとは書き方を変えて、物語やシーンを点で追いながら、徐々に全体像を解釈していくという手法にしました。
その分、いつもよりも本編にがっつりと触れることとなってしまいましたが、自分の思うところはかなり吐き出せたように感じます。
最初にも書きましたが、近年の邦画の中でもずば抜けた出来栄えであることに疑いの余地はありません。

















今回も読んでくださった方、ありがとうございました。