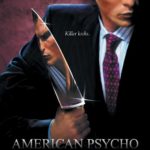みなさんこんにちは。ナガと申します。
今回はですね映画『きみの鳥はうたえる』についてお話していこうと思います。

ただ、公開規模も小さく、時間が合わずで結局鑑賞できなかったのですが、Netflixで配信が始まったということで鑑賞することができました。
原作が、佐藤泰志さんということですが、彼の作品はこれまで3つ映画化されています。
いわゆる「函館3部作」と呼ばれる『海炭市叙景』『そこのみにて光輝く』『オーバーフェンス』ですね。
この3作品はどれも出来が素晴らしく、個人的にも気に入っております。特に『海炭市叙景』の描く函館の閉塞感と、それでもそこから抜け出そうともがく人たちの姿には、心を鷲掴みにされました。
今作『きみの鳥はうたえる』は元々、東京が舞台になっていましたが、映画化するにあたり舞台を「函館」に変更したようです。
そこには、函館出身で、そこを舞台にした名作を世に送り出してきた原作者の佐藤泰志さんへのリスペクトも伺えます。
ちなみに作品のタイトルは、ビートルズのレコードから引用されているそうです。










ただ、映画版では、そこをカットし、劇伴音楽も全体的に今風にアレンジされていますね。
今回は、そんな映画版の『きみの鳥はうたえる』について感じたことや考えたことを綴っていこうと思います。
本記事は作品のネタバレになるような内容を含む感想・解説記事となっております。
作品を未鑑賞の方はお気をつけください。
良かったら最後までお付き合いください。
目次
『きみの鳥はうたえる』
あらすじ
函館郊外の書店でダラダラと働く「僕」とその同僚の佐知子。
「僕」は仕事にも不誠実で、その日の気分で仕事をすっぽかしては、夜通し酒を飲んでいた。
失業中の静雄という男と「僕」は一緒に暮らしており、ある日2人の暮らす家に佐知子がやって来て3人は知り合う。
3人はその日から仲良くなり、夜になると酒を飲み、ビリヤードをして、クラブに繰り出すようになった。
「僕」は佐知子と性的な関係を持つ中であったが、彼女に対して強い執着を持つことはなく、静雄が彼女を映画デートに誘ってもそれを後押しするような素振りを見せていたのだ。
一方の佐知子は、働いている書店の店長と関係を持っており、それを断ち切ろうとしていた。
関係性を終わりにしようと、店長と話し合いの場を持った次の日、彼女は本屋の仕事から退くこととなる。
彼女を案じる「僕」を他所に、静雄は彼女と映画デートに行くこととなるのだが…。
スタッフ・キャスト
- 監督:三宅唱
- 原作:佐藤泰志
- 脚本:三宅唱
- 撮影:四宮秀俊
- 照明:秋山恵二郎
- 音楽:Hi’Spec










本作『きみの鳥はうたえる』の監督を務めたのは、三宅唱さんです。
これまではテレビ映画や60分程度の中編映画を手掛けていたのですが、今回は商業映画で長編として公開されました。
ちなみに2019年には『ワイルドツアー』というワークショップ映画も公開されていますが、今後もっと商業映画を手掛けていってほしいですね。
そして、最初にもご紹介しましたが、原作を著したのは、佐藤泰志さんです。
41歳の時に亡くなられた作家さんですが、死後その作品の評価は高まり、函館を舞台にした作品が次々に映画化されました。
撮影には『宮本から君へ』や『さよならくちびる』など、若者のエモーショナルを鮮烈に切り取ってきた四宮秀俊さんが起用されています。
照明には、『さよならくちびる』『小さな恋のうた』などの青春映画も多く手掛ける秋山恵二郎さんが参加しました。
劇伴音楽には、DJとしても活躍するHi’Specが加わり、本作のクラブ音楽を手掛けています。
- 僕:柄本佑
- 佐知子:石橋静河
- 静雄:染谷将太
- 森口:足立智充
- みずき:山本亜依
- 直子:渡辺真起子
- 島田:萩原聖人










本作『きみの鳥はうたえる』は何か劇的な展開があるタイプの作品ではないので、それだけにキャスト陣が作り出す空気感や雰囲気に強く依拠しています。
そういう意味でも、演技力に乏しいキャストを配置すると、どう考えても間が持たないという事態になり、映画として完成度が落ちてしまうでしょう。
だからこそ柄本佑さん、石橋静河さん、染谷将太さんといった超実力派を据えられたことが大きくて、この3人が作り出す「空気」がどうしようもなく愛おしく、いつまでも続いて欲しいと感じさせられました。
この時点で、もうこの映画は「勝ち確」だったと言っても過言でではないでしょう。
他にも渡辺真起子さんや萩原聖人さんといった実力派が脇を固めています。










『きみの鳥はうたえる』感想・解説(ネタバレあり)
青い照明が強調する「未熟さ」
(C)HAKODATE CINEMA IRIS
本作『きみの鳥はうたえる』で印象的なのは、やはり「青い」照明でしょう。
「青い果実」という言葉は、「未成熟な」果実を意味しますし、「青二才」という言葉は経験が少なく未熟な人間のことを指して用いられます。
このように「青」という色には、「若さ」や「未熟さ」のイメージが内包されているのです。
映画のファーストシーンも青色が印象的ですが、序盤の「僕」と静雄の自室のシーンや、クラブのシーンなど多くのシーンで青い照明が目立ちました。
そこには、彼らのモラトリアムや若さ、未熟さが内包されていたように思います。
しかし、終盤に「僕」と静雄、そして佐知子が卓球をするシーンで再び、青い照明が用いられているのですが、ここでは青い照明に加えて仄かにオレンジ色の照明が加えられています。
その後のシーンで、本屋のアルバイトの若い男女が夜明けの通りを歩いていく一幕がカットインしますが、この時の空の色を見てみると、青い空なのですが、山際から少しずつ朝日が顔を覗かせており、ほんのりとオレンジ色になっていることが伺えますよね。
つまり、3人が卓球しているシーンでの青と仄かなオレンジの同居は、彼らの関係性が変化しようとしていることと、それでも「僕」がそれまでの関係性を持続させようとしているこのコンフリクトが投影されているのです。
そうして、3人の関係性はもはや不可逆のものとなってしまうわけですが、ここで静雄の印象的なモノローグが登場します。
「3人で過ごした部屋の匂いや街の匂いを思い出そうとしたが、どうしても思い出すことができないままだった。」
もはや3人が過ごしたあの「青い時間」というものが、どんなに手を伸ばしても手に入らないことを突きつける鋭い言葉でもありました。
この言葉から伺えるのは、3人にとっての「青色」の意味合いが、物語の後半にかけて転調していることです。
単なる「若さ」や「未熟さ」の表出としての「青」だった前半部分から転調し、後半部分ではノヴァーリスの『青い花』に代表されるような決して届かない「永遠の憧憬」としての「青」になっていたと感じます。
あの時は当たり前だった3人の「青い時間」は、もはやどんなに望んでも手に入らないものになってしまったということが強調されています。
照明の色1つですが、物語の転調によって、その意味合いが変化するという多層的な作りになっていたのは、見事でした。
オフビートが生む作品のリズム
『きみの鳥はうたえる』は基本的に、大きな展開があるタイプの作品ではなく、メインキャラクター3人が夜な夜な飲み歩き、クラブを訪れたりといった日常が持続します。
ただ、作品のリズムの作り方が、絶妙なので、私たちは退屈することもなく物語を見進めることができるのです。










例えば、序盤に「僕」と佐知子は身体の関係を持つシーンがありましたが、普通の映画の流れで言うと、2人が服を脱いで、キスをして…と順序良くことが進んでいきますよね。
(C)HAKODATE CINEMA IRIS
しかし、今作では二段ベットにぶつかってみたり、前戯の途中で虫が現れたり、コンドームを取ろうとした佐知子がベッドから落ちたりと、妙にテンポを崩すような演出が目立ちます。
濡れ場のシーンは、もっとウェットでエモーショナルな印象を与えるものだと思うのですが、それを敢えて崩そうとしているこの演出は、「僕」が佐知子に対して抱いている本心から逃げようとしている様にもリンクします。










他にも森口と「僕」の会話のシーンで、彼が真剣に謝罪の意を表明しているにもかかわらず、「僕」は用を足しているというような妙な「外し」が印象的です。
ではこれらのシーンにどんな意図があったのかと推察してみますと、それは何かに真剣に向き合うことから避け、茶化すことで無為に過ごしてきた「僕」の姿勢そのものを表現していたのだと思います。
何事もシリアスにしたり、エモーショナルにしようとせず、オフビートを貫くことで、どこか冷静で空気のような自分でいることに安心感を覚えていたのかもしれません。
こういった良い意味での「外し」が、演出的にも物語的にも効いていたと感じました。
モラトリアムの「空気」を閉じ込める
(C)HAKODATE CINEMA IRIS
「モラトリアム」という言葉は、元々、心理学者エリク・H・エリクソンによって心理学に導入された概念でした。
一般的には、社会に出て大人として働き始めるまでの猶予期間のことを表しているとも言われますが、広義で言うなれば「何か大きな変化を自分にもたらすことを先延ばしにして、今の日常を続けようとする心理」なのかもしれません。
『きみの鳥はうたえる』では、「僕」と静雄と佐知子の3人の間に通底する空気感や関係性に「モラトリアム」を感じます。
「僕」と佐知子は身体の関係を持っているわけで、さらに言うと店長との関係性も知っているわけですが、強く執着するような素振りはなく、静雄が彼女をデートに誘うことに対しても否定はしません。
つまり、お互いがお互いの人間関係や感情、行動に干渉しない、何も求めないという「ドライさ」が3人の関係性を成立させているわけです。
3人は夜な夜な酒を飲み、ビリヤードをして、クラブに行き、無為な日々を過ごすだけなのですが、そこには関係性を壊すことへの不安や恐怖も感じられますね。
相手に何かを求める、相手に干渉するということは、「空気」を大きく変化させるトリガーになります。
それを拒み続けることで、この3人は不可視の脆弱性を孕んだ関係性を持続させることができるわけですが、いつまでも「同じ」というわけにはいかないんですよ。
静雄は、佐知子をデートに誘うことに関して、「僕」と彼女の関係性を壊しているのではないかという懸念を持っています。
一方で、店長との関係に終止符を打った佐知子は、「僕」にもっと自分に対する執着を持って欲しいと願い始めるようになりました。
そんな変化を拒み続ける彼は、職場で森口というバイトの同僚に、彼女のことを冷やかされ苛立ち、暴力行為を働きました。
自分自身の本心に気づかせ、そしてその関係性の進展急かすような、その言葉に苛立ちを感じたのも無理はありません。
彼が苛立ちを感じていたのは、他でもない自分自身に対してなのですから。
そういう変化を拒み続けてきたことに対するしっぺ返しが「森口に木刀で殴られる」という一件を通じてもたらされるのが、興味深いですね。
彼は自分自身の苛立ちを森口にぶつけ、そして偶然か必然か他人にぶつけたその暴力が自分に降りかかるという形で、間接的に自分を傷つけたわけです。
物語は終盤へと向かい、キャンプから戻ってきた静雄と佐知子は、明らかにその関係性に変化が見えました。
しかし、「僕」は必死にこれまで通りの関係性を持続させようともがくのです。
冒頭と終盤に似たようなビリヤードの描写がありますが、この2つのシーンは実に対照的です。
訪れてしまった変化を必死に拒むような…もはや脱皮の時期を迎えたのに、さなぎの中に閉じこもり続けようとするような欺瞞が、終盤のシーンには満ちています。
「僕」は終わりが見えてもなお、終わらせまいと、3人の間に流れていた脆い空気や温度を持続させようとしていました。
そんな延命治療も、佐知子の言葉によって決定的に終わりを迎えます。
静雄と佐知子は、明確に変化することを選択し、「モラトリアム」にNOを突きつけたのです。
だからこそ、「僕」はもう「変化」から逃れることができません。もう干渉しない、何も求めないを貫くことは彼にはできません。
「僕」は振り返って、去り行く佐知子を見つめて、そして以前のように数字を数えても現れない彼女を思って、確かに「変化」することを選択します。










ただ、彼女が2人のどちらを選ぶのかは、個人的には本作においてはさして重要ではないことがだと思っています。
というのも、『きみの鳥はうたえる』という作品において重要なのは、「選択」し「変化」を受け入れることなのです。
つまり、3人がそれぞれの形で、「変化」を望むことができたのであれば、きっとそれが本作のゴールなんですよ。
「僕」は空気のような男になることで、静雄と佐知子の関係と共存し、今までのような関係性を持続させようと、一時は考えていました。
しかし、そうやって「変化」を遠ざけることを、ようやく拒み、空気を、そして関係を壊す選択したのです。
佐知子は2人のどちらかを選ばなければなりません。そしてお互いが自分に対して好意を抱いている状態です。
病院での静雄のモノローグにも「3人で過ごした部屋の匂いや街の匂いを思い出そうとしたが、どうしても思い出すことができないままだった。」とありました。
その点で、「どう変化したか?」という結果ではなく、あくまでも「変化する瞬間」にスポットを当て、モラトリアムの終焉を切り取ったことにこそ『きみの鳥はうたえる』という作品の素晴らしさがあるのではないかと感じました。
おわりに
いかがだったでしょうか。
今回は映画『きみの鳥はうたえる』についてお話してきました。










物語としては淡白ですが、演出や撮影、照明といった諸要素が非常に丁寧でかつ機知に富んでいるので、見ていて飽きることはありません。
また、三宅唱監督は、今後、もっと高く評価されるようになるだろうと、本作を見て確信しました。
これだけ淡白な物語を、しっかりと映像的に「味つけ」できる方は、日本にはまだまだ少ないと思っているので、短編や中編ではなく、しっかりと長編でもっと見たいと思っております。
みなさんもぜひ『きみの鳥はうたえる』をチェックしてみてくださいね。
今回も読んでくださった方、ありがとうございました。