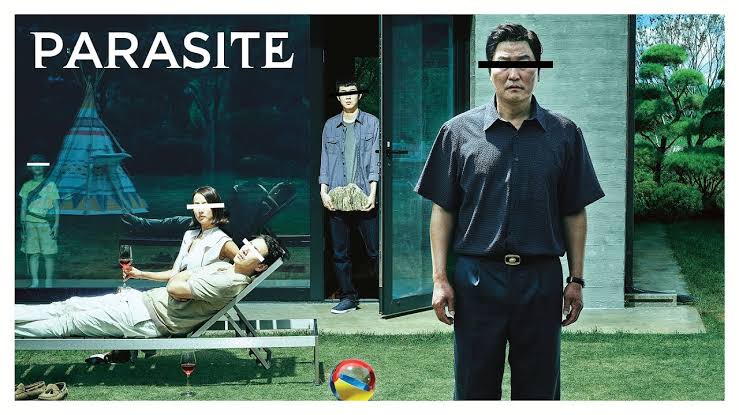みなさんこんにちは。ナガと申します。
今回はですね映画『アメリカンサイコ』についてお話していこうと思います。

クリスチャン・ベイルの出演作としては、『マシニスト』が1番インパクトが大きかったのですが、今作はそれを塗り替えるレベルの怪演ですね。
表の顔は成功を収めた証券会社のエリートですが、その裏では恐ろしいほどの欲望を抱えており、人を殺害することで自分の欲望を満たしています。
何と言いますか、金銭的にも社会的な地位としても認められて、それでも他人よりも優れたいと願い続け、他人と同じ尺度で競い続けることの空虚さと言いますか、底知れぬ劣等感を見事に描いた作品です。
そしてその両面性をクリスチャン・ベイルは完璧に表現しています。
彼の狂気の演技が、あまりにもぶっ飛びすぎていて、恐怖よりは面白さが先んじるような、そんな印象すら受けました。
今回はそんな映画『アメリカンサイコ』について個人的に考えたことをお話していきます。
本記事は作品のネタバレになるような内容を含む解説・考察記事です。
作品を未鑑賞の方はお気をつけください。
良かったら最後までお付き合いください。
目次
『アメリカンサイコ』
あらすじ
パトリック・ベイトマンは、証券会社のエリートで誰からも一目置かれる存在だった。
彼は白を基調とした空虚ながらも家賃の高い住宅に住み、エステや日焼けサロンなどに通い、美貌を保ち優雅な生活を送っていた。
そんな彼は、同僚たちとどちらが格の高いレストランで食事をするか、誰が優れた名刺を持つか、誰がより高い家賃の家に住むかで競い合っていた。
その会社を所有しているのは他でもないベイトマンの実父ということもあり、特に仕事に懸命に取り組んでいる様子もない彼だったが、同僚に何かで敗れるたびに劣等感を隠せなくなっていく。
ある時、自分よりも格の高いレストランで食事をし、自分よりも良い暮らしをしている同僚のポール・アレンに強いジェラシーを感じるようになり、彼を自宅に誘った時に斧で殺害してしまう。
その一件を機に、タガが外れたように狂気を抑えられなくなった彼は、娼婦や女子大生を自宅に招き入れては次々に殺害するようになる。
計画的な犯行でかつ、自宅の中に死体を隠していたことから警察は犯人になかなか辿り着くことができずにいた。
しかし、私立探偵のドナルド・キンボールはベイトマンにアリバイがないことや事件の概要から徐々に捜査の網を狭めていき…。
スタッフ・キャスト
- 監督:メアリー・ハロン
- 原作:ブレット・イーストン・エリス
- 脚本:メアリー・ハロン&グィネビア・ターナー
- 撮影:アンジェイ・セクラ
- 編集:アンドリュー・マーカス
- 美術:ギデオン・ポンテ
- 音楽:ジョン・ケイル

















当初はクリスチャン・ベイル主演&メアリー・ハロン監督のコンビでの企画があったようです。
ただ、その後スタジオがレオナルド・ディカプリオの主演を発表し、メアリー・ハロンとゴタゴタが起き、その結果、監督を降板しました。
監督にはオリバー・ストーンが就任する運びになったが、結果的に作品の制作に至らず、最終的にクリスチャン・ベイル主演&メアリー・ハロン監督のコンビが復帰し、制作が進められたそうです。
メアリー・ハロン監督は『ペティ・ペイジ』や『モスダイアリー』と言った作品の監督も務めていますが代表作としてはやはり本作になりますよね。
脚本には、本作以外でもメアリー・ハロン監督作品の脚本として携わっているグィネビア・ターナーが共同脚本として参加しています。
- パトリック・ベイトマン:クリスチャン・ベイル
- ドナルド・キンボール:ウィレム・デフォー
- ジーン:クロエ・セヴィニー
- イヴリン・ウィリアムズ:リース・ウィザースプーン
- コートニー・ローリンソン:サマンサ・マシス
- エリザベス:グィネヴィア・ターナー
- ポール・アレン:ジャレッド・レト
- クレイグ・マクダーモット:ジョシュ・ルーカス
- ルイス・カルザース:マット・ロス

















主演を務めたのは、『ダークナイト』や『マシニスト』などで知られるクリスチャン・ベイルです。
彼は役作りを徹底的にやり込むタイプの俳優としても知られていて、映画の撮影のために驚くべき減量を実施したりしています。
主人公を追う私立探偵のドナルド・キンボール役には、『プラトーン』や『フロリダプロジェクト』のウィレム・デフォーが起用されています。
その他にも『わたしに会うまでの1600キロ』で知られるリース・ウィザースプーンや、『スーサイド・スクワッド』でジョーカーを演じたことでも知られるジャレッド・レトが出演しています。

















『アメリカンサイコ』解説・考察(ネタバレあり)
本作の現実と幻想の境界はどこなのか?
本作『アメリカンサイコ』を見ていて、多くの人が疑問に感じるであろうポイントは、やはりどこまでが現実だったのかという線引きだと思います。
というのも、この作品は基本的に主人公であるパトリック・ベイトマンの語りによって進行されるのですが、彼がいわゆる「信頼できない語り手」となっているのです。
ミステリではよくある設定ですし、映画でも『シャッターアイランド』のような作品がそうですが、語り手が精神的な疾患を抱えているために、物語に現実と幻想が混在しているという状態になっています。
そのため、今作は公開されて以来、映画ファンの論争の種となっているわけですが、これについて監督・脚本を担当したメアリー・ハロンは次のように述べています。
“One thing I think is a failure on my part is people keep coming out of the film thinking that it’s all a dream, and I never intended that. All I wanted was to be ambiguous in the way that the book was. I think it’s a failure of mine in the final scene because I just got the emphasis wrong. I should have left it more open ended. It makes it look like it was all in his head, and as far as I’m concerned, it’s not.”
この最初の1文を和訳すると、「私が自分の過ちは、映画を見た人が全部夢だったという結論に至っていることであるが、そもそも私はそのようには意図していないのだ。」となる。
監督は、ある程度見た人に解釈が委ねられるいわゆる「オープンエンド」にしたかったそうですが、作中の出来事の全てがベイトマンの夢の中の出来事であったという風に解釈されることを良しとしないとコメントしているわけです。
そうなると、当然この映画には現実に起きていたことと、そうではないことが混在しているということになり、それを整理しなければ混乱してしまいます。
ということで、今回は映画をシーンを細かく追いながら、本作の虚実の境界を探ってみようと思います。
そもそも本作は顔のない男の物語である
『アメリカンサイコ』にて不気味なのは、主人公のパトリック・ベイトマンの暮らしぶりでしょう。
冒頭に彼のモーニングルーティンが紹介されますが、そこで注目したいのは、彼がミントの顔パックをしている描写です。
(映画『アメリカンサイコ』より引用)
ペラペラと顔に貼りついたパックを剥がしていくシーンは強烈な印象を与えますが、この時のナレーションが「だが本当の俺はそんざいしない。実在するが幻影のようなものだ。」と語っています。
このナレーションと映像の調和は、主人公の男が何者でもなく、ただベイトマンの仮面を貼りつけているに過ぎないのだということを言わんとしているように感じられました。
加えて、この時にカメラが捉えているのは、ベイトマンの実体ではなく、鏡に映った彼であり、そこにも脱身体性が伺えます。

















白を基調にした、殺風景な部屋は、個性というものを全く感じさせることがありません。まるで生活感がないのです。
そんな生活感のなさ、没個性感が、そこには元々誰も住んでいないかのような雰囲気を漂わせているわけですが、もっと言うなれば、この家が特定の誰かの家とは思わせないようにさせています。
この一連の冒頭のシーンが感じさせるのは、本作が描こうとしているのはベイトマンの物語ではなく、80年代にウォール街を支配していた白人の物語であり、ひいてはアメリカという国そのものの映画であることです。
名前についてのギミックを探る
この映画の最初のシーンはベイトマンたちがレストランで食事をしている描写でした。
ただ、ここでいきなり本作を取り巻く状況を説明するうえで非常に重要な情報が示されていたことに気がつきましたか。

















「あれロビンソン?」
「ラリってんのか?違うよ。」
「じゃあ誰だ?」
「ポール・アレンさ。」
「違うよ」
「ポール・アレンはあっちだ。」
(映画『アメリカンサイコ』より引用)
彼らは同僚のロビンソンやポール・アレンについて話しているはずなのですが、完全な人違いを繰り返しており、ただベイトマンによるとポール・アレンという人物は向こうの席で女性と一緒に食事をしている男であるということが分かります。
しかし、考えてみると、この会話って実に不自然だと思いませんか。
最初に喋った男は見ず知らずの他人を「ロビンソン」と間違え、さらにもう1人の男が「ポール・アレン」と人違いをしているわけです。
つまり、本作『アメリカンサイコ』においては、名前という概念が実に希薄なのです。
ウォール街に生きている白人は、髪をジェルで持ち上げ、スーツで着飾り、似たようなクレジットカードでレストランの支払いをし、似たような名刺を持ち、食事をするレストランの格や住む住宅の家賃で競い合っています。
彼らは社会的に成功しており、誰からも羨ましがられる存在であるはずなのですが、全員が外見的にも行動的にも似たようなことをしており、完全に没個性化しているのです。

















主人公は、パトリック・ベイトマンという名前ですが、彼はその時々によって自分の名前を変えていることに気がつきましたか。
彼はポール・アレンに最初に出会った時に、「マーカスハルバーストラム」という別人と間違えられていました。
他にも例えば、ポール・アレンに斧を振り下ろして殺害し、死体を持って表通りに出た彼は通りでカップルから「パトリックか?」と声をかけられますよね。この時、彼はそれを否定しました。
その後、彼はアレンの家に向かうと、留守電に彼のふりをしてメッセージを残しました。後のシーンで彼は自宅に2人の女性を招いているシーンでで「ポール・アレン」を名乗っていました。
さらには、彼は自宅に来ている女性にそれぞれ「クリスティ」と「サブリナ」という名前をつけていましたよね。
このように『アメリカンサイコ』という作品においては、登場人物の名前というものが曖昧になっています。
その極めつけが終盤にベイトマンが自分の担当弁護士と会話をするシーンなのですが、彼は「君だったんだな!ベイトマンが殺人なんて最高だね。」と告げ、ベイトマンのことを「デイヴィス」と呼称しました。
(映画『アメリカンサイコ』より引用)

















しかもあの弁護士は、殺害されたはずのポール・アレンと10日前にロンドンで食事をしていたという話をしており、それ故にベイトマンによってポール・アレン殺害されたはずがないと語っています。
ジブリアニメの『千と千尋の神隠し』でも主人公が名前を奪われるという描写がありますが、「名前」とはその人のアイデンティティの象徴として扱われます。
つまり、『アメリカンサイコ』において登場人物の名前が極めて不正確で、不安定なのは登場人物たちにアイデンティティがないということを暗に仄めかすためのように感じられます。
この物語を語っていたのは、確かにベイトマンではあるのですが、ベイトマンとは一体誰のことだったのかは謎に包まれています。
私たちがベイトマンだと思って追いかけてきたクリスチャン・ベイルが演じている主人公は、単なる「デイヴィス」なのかもしれません。

















そういう意味では、本作が描いたのは、顔も名前もない「80年代にウォール街の白人」というある種の抽象概念が孕む残虐性だったのかもしれません。
ラストの独白について
本作のラストを飾るベイトマンのモノローグは実に重要で作品の命題にも直結するものだと思います。
もはや境界線は存在しない
俺たちが共有する 抑制できない衝動、狂気、悪意、不正
俺が引き起こした暴力と
それに対する無関心さを俺は超えてしまったのだ
激しい痛みがおさまらない
他人のためにこの世が良くなることなど願わない
他人にも俺の苦痛を味わわせたい
誰も逃がしたくない
でもこれを認めた後でさえカタルシスは起こらない
俺は処罰を受けず、自分を深く理解することもできない
告白から何か新しい知識を得るわけでもない
この告白には何の意味もないのだ
(映画『アメリカンサイコ』より引用)

















このモノローグは、自分という存在が何者でもない、空虚な存在であることを強調しているように思います。
まず「もはや境界線は存在しない 俺たちが共有する 抑制できない衝動、狂気、悪意、不正」という部分には、本作が描いていたのが「80年代にウォール街の白人」による集合的狂気であるということを仄めかしているのではないでしょうか。
「俺が引き起こした暴力とそれに対する無関心さを俺は超えてしまったのだ」とその次にありますが、これは自分が犯した殺人とそれに対する他者の無関心さは、もはや自分という存在を置き去りにしてしまったかのようだということです。
しかし、確かに自分の中には他人を傷つけたいという衝動が隠れていて、殺人を犯したはずだと思うのですが、彼は処罰されることもなく、自分が何者なのかもわかりません。
結局、自分がいくら殺人の罪を告白したところで、そこには何の価値もなく、誰も気に留めないのだと締めくくっていますね。
モノローグを紐解くと、どうやらラストシーンでもって、本作はこれまでベイトマンという1人の人間が引き起こしてきた狂気をもっと上のレイヤーへと昇華し、個人から解き放ったように感じられます。
本作において、「ベイトマン」は確かに罪を犯したと言えるのでしょうが、それが本当にクリスチャン・ベイルが演じている主人公の男によって引き起こされたものなのか、はたまた他の誰かが起こしたものなのかはアンビギャスなままなんですね。
ラストシーンのレストランのテレビには、時の大統領であるドナルドレーガンが映し出されています。

















レーガン大統領は、とにかく「強いアメリカ」というイメージを前面に押し出し、指導力がある大統領であることを誇示していました。
元々映画やミュージカルの俳優も務めていた経験を持つ彼は、政治シーンを自信を主人公に見立てたショーのように仕立て上げる傾向があり、演説や記者会見で映画のセリフを引用することも多かったと言われています。
ただ、そういった虚構を作り上げることの巧さによってレーガン大統領は、当時高い人気を誇っていました。
それを決定的に覆してしまったのが、イラン・コントラ事件であり、これに関するレーガン自身の事件への指示・関与の疑惑が湧いて出てきたわけです。
結果的に、彼は側近をトカゲの尻尾きりのように有罪に仕立て上げることで、自分自身の責任追及から逃れようとし、結果的に「強いアメリカ」という幻想を崩壊させることへと繋がりました。
『アメリカンサイコ』がラストシーンで、わざわざレーガン大統領の映像を流すのは、本作がアメリカという国ないし白人特権階級に対するアイロニーを内包しているからに他なりません。
レーガンという人間は、確かにテレビの向こうで大統領として立っているわけですが、彼は政治というショーの舞台で「レーガン」という仮面を演じているに過ぎないのかもしれません。
彼が何者なのか、つまり「中身」には誰も興味など抱いておらず、彼の身に着けている「レーガン」という仮面にしか興味を持っていないというのがその実とでも言うのでしょうか。
カート・アンダーセン氏が自身の著書の中で、幻想と現実の境界を曖昧にしてしまうアメリカ人の国民性について論考していました。
アメリカ人は現実がどうなのかには興味を持たず、幻想や虚構に傾倒する傾向があることを、建国以来の宗教や文化、経済、政治といった様々な側面から読み解いています。
そこに書かれていたのは、まさしくアメリカ人が「中身」には興味を持たないという事実でしょう。
つまり、クリスチャン・ベイルが演じている主人公が仮に「ベイトマン」の仮面をかぶって、多くの人を殺害する蛮行を犯していたとしても、人々が関心を持つのは「ベイトマン」という仮面であり、彼自身ではないのです。
彼の周囲にいた人間たちは、彼がどこのレストランで食事をしているのか、どんな名刺を持っているのか、どんな女と付き合っているのかといった表面的な部分にしか興味がなく、彼の「中身」には何の興味も示しません。
レーガンという人間は、イラン・コントラ事件に関わるという罪を犯していたかもしれません。というよりも犯していたでしょう。
しかし、政治というショーの舞台に「レーガン大統領」という仮面をつけて現れる彼は、自分自身には責任がなかったと言い張るのです。
本作『アメリカンサイコ』は、アメリカという社会において虚構や幻想が強大な力を持つことに対する痛烈な皮肉が込められています。
虚構や幻想を身に纏い、虚構や幻想を信じることで、その「中身」がどうなっているかについて誰も関心を持たなくなってしまったわけです。
だからこそ、クリスチャン・ベイル演じる主人公が自分が罪を犯したのだと語ったところで、そんな言葉に誰も興味を示しはしません。それ故に彼の告白は無意味です。
ラストシーンでベイトマンの背後のドアの表示を見てみると、そこには「This is not an exit.」という1文が書かれています。
レーガン大統領はイラン・コントラ事件がひと段落し、気持ちを切り替えて前に進んでいくのだという内容をテレビで語り、そしてベイトマンは自分の引き起こした一連の事件が罰せられることもないままに終わっていくことをモノローグに乗せて語っています。
ただ、「This is not an exit.」という1文はそうしたアメリカの幻想偏重の社会に終わりがないことを暗に示していると言えるでしょう。
幻想と現実の境界線が溶け、もはや物事の「中身」に誰も興味を示さなくなり、レストランを料理の内容ではなく格式の高さと評判だけで選ぶようなそんな時代が続いていくのだという絶望が今作のラストには強く投影されています。
結局のところ主人公は罪を犯したのか?
さて、ここまで本作が何を描こうとしていたのかについてお話してきたわけですが、最後に結局のところ主人公は殺人を犯したのかどうかについてお話してみましょう。
これはあくまでも私の考えではありますが、主人公は殺人を犯したと言えるでしょう。
先ほど、本作の主題はアメリカという国の幻想と現実の境界線の曖昧さにあるというお話をしました。

















まず、本作における彼の最初の殺人は、ホームレスの男性とその飼い犬でした。これについては紛れもなく彼が実際に犯した犯行ではないでしょうか。
その後も同僚のポール・アレンや売春婦の女性などを次々に殺害し、過去には自分の元ガールフレンドを殺害していたことなどが明らかになっていきます。
私は、個人的にここで彼が犯していた一連の殺人やアレンの家に保管していた死体は紛れもなく事実であったと解釈しています。
それは、終盤には彼が死体を隠していたアレンの家を訪れたシーンが大きな根拠になるでしょうか。
彼は、死体を隠しており、血まみれになっていた部屋の壁が綺麗にペンキで白く塗られていることに気がつきます。

















これってアメリカの歴史そのものを投影した描写にも思えました。
アメリカという国は、元々はイギリスからのプロテスタント系の移民が勢力を拡大し、先住民を弾圧し虐殺して、その上に成り立っている国とも言えます。
しかし、そういった負の歴史を覆い隠し、幻想を上塗りすることで、自分たちの国の「正義」を主張しているのです。
『アメリカンサイコ』におけるアレンが住んでいたはずの賃貸も、そこには生々しい殺人の痕跡が残されていたわけですが、そんなことが表に出てしまえば住み手がいなくなってしまいます。
だからこそ、その真実を闇に葬り去り、「白いペンキ=幻想・虚構」を上塗りすることで、そこが優良な高級住宅であるというファンタジーを作り上げるのです。
ただ、その背後には主人公が、殺人を犯していたという事実が紛れもなく存在しています。
しかし、その真実を求めておらず、そして誰も関心を示さないために、彼は罪に問われないのです…。

















おそらくですが、彼がATMのところで猫を殺害しようとした描写から始まる一連のシーンは、現実ではないと思っています。
まず、ATMに「FEED ME A STRAY CAT」という表示が出るシーンは、現実ではありえませんので、そこには主人公の幻想が入り混じっているでしょう。
(映画『アメリカンサイコ』より引用)
その後、警察に追跡されて、銃撃戦が起きますが、彼はパトカーの爆発のあまりの大きさに驚いた表情をしていましたよね。
これって、彼が「本当にこれが現実の出来事なのか?」とそのあまりにもフィクショナルな爆発を怪しんでいる表情でもあると思うんです。
その後、彼は間違って別の似たようなオフィスビルに入ってしまうのですが、そこで受け付けの人間に「Mr. Smith」と呼ばれているんですよね。

















最終的には、自分のオフィスに辿り着き、そこで弁護士に自分が何人の人間を殺害したのかを告白しますが、もう自分が何人の人間を殺害したのかが曖昧になっていました。
つまり、彼は自分が現実で殺害した人間と、虚構の中で殺害した人間の区別がつかなくなっているのです。
このシーンで、彼を追跡していると思われるヘリコプターの音は聞こえるのですが、ヘリコプターの姿が映し出されることはありません。
しかも翌日彼は何事もなかったかのように自室でシャワーを浴びて、いつものモーニングルーティンをこなしています。
こういった一連の描写から推測するに、主人公が犯した罪の中で「FEED ME A STRAY CAT」の表示以降のものは、個人的には幻想の範疇に含まれると解釈しています。
一方で、それ以外のものについては、終盤の賃貸の管理人の様子からしても事実だったの考えるのが、妥当ではないでしょうか。
また、彼がオフィスのデスクの引き出しに入れていたノートには、確かに彼の猟奇的な殺人のビジョンが描かれていました。これも彼が殺人を犯したことを裏付ける証拠の1つと言えるのではないでしょうか。
(映画『アメリカンサイコ』より引用)
ただ、本作『アメリカンサイコ』の肝は、現実の殺人と虚構の殺人をシームレスに描いている点だと思っています。
そこに区別がなく、そして、その現実に起きた罪すらも虚構の中へと溶け出していき、裁かれることはないのです。
おわりに
いかがだったでしょうか。
今回は映画『アメリカンサイコ』についてお話してきました。

















ただ、全ての出来事が「幻想」でしかなったと解釈するのは、監督の発言から考えても少し無理があるように思います。
むしろ幻想と現実が共存しており、そしてそれを同じトーンで描き切ってしまったことが本作の真の恐ろしさだと思っております。
現実が幻想へと溶け出していき、逆に幻想が現実に溶け出してくることで、主人公は、もはや自分が何者なのかすらも分からなくなってしまいます。
そこには、一個人の物語というよりも、アメリカという国そのものの現実と虚構のコンテクストが反映されていると思います。
「中身」には誰も興味を持たず、上塗りされた白いペンキのような「幻想」にしか誰も興味を持たないのです。
そんな「幻想」が多い隠してきたたくさんの血が、アメリカという国を「サイコ」たらしめるのだという痛烈なアイロニーを本作は打ち出してみせたのです。
謎の多い映画ではありますが、ぜひ多くの方にご覧いただきたい1本です。
今回も読んでくださった方、ありがとうございました。