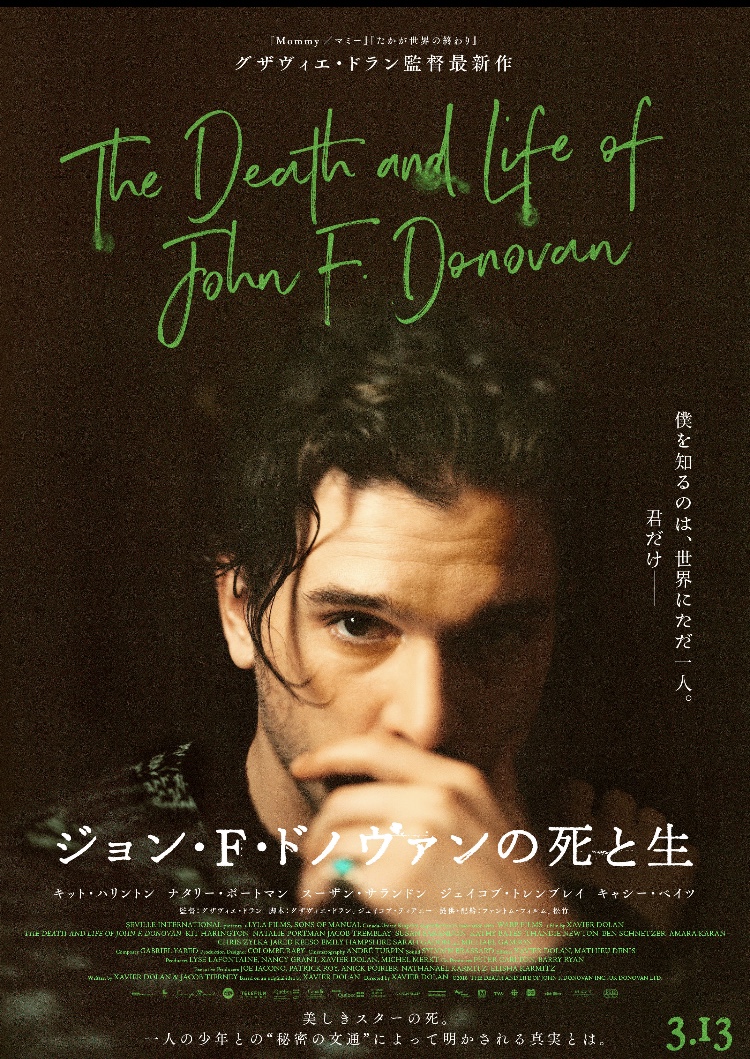みなさんこんにちは。ナガと申します。
今回はですね映画『ザ ブックオブヘンリー』についてお話していこうと思います。

問題作と話題になっていましたし、『ジュラシックワールド』で高めたコリン・トレボロウ監督の名声を地の底に叩き落すほどの勢いだったので、どんな映画なんだろうかと気になっておりました。
結論から申し上げますと、この映画は道徳的にも、倫理的にも危うく、それでいてプロットがカオスでおおよそ物語として成立していると認めがたい内容でした。
いろいろとち狂った描写や展開が盛り込まれているのですが、1番衝撃を受けたのは、サラ・シルバーマン演じるヘンリーの母親の友人が、彼のお見舞いに来て、彼にキスをするシーンです。

















いえ、思いっきり唇にですよ。
しかも、特にそれに至るまでの助走もありませんでしたし、そのキスについて後の物語で触れられることもなかったので、一体何だったのかとモヤモヤしました。
というより重病で死にかけている自分の友人の12歳の息子の唇を奪うってヤバくないですかね…。
これは本当に氷山の一角でして、他にも今作にはかなりぶっ飛んだシーンや展開が連発されています。
今回はそんな奇妙な映画『ザ ブックオブヘンリー』が何を伝えようとしていたのか、そしてどこがおかしいのかを自分なりに考えたので、書いていこうと思います。
本記事は作品のネタバレになるような内容を含んでおります。
作品を未鑑賞の方はお気をつけください。
良かったら最後までお付き合いください。
目次
『ザ ブックオブヘンリー』
あらすじ
ヘンリーは先天的に飛び抜けた知能を持っているいわゆる「ギフテッド」であり、同級生と比較しても飛び抜けた能力を持っていました。
そんな彼はクラスの美少女で隣に住んでいるクリスティーナに好意を寄せているのですが、彼女が日に日に精神的に病んでいく様を見て、心を痛めていました。
ある夜、自宅の窓から隣の家を見ていると、クリスティーナが継父から虐待されている様子を目撃してしまいます。
何とか、彼女の力になりたいと地元の警察や児童保護局に通報をするのですが、その継父は地元の警察に親戚がおり、虐待の事実を握りつぶしていたのでした。
それを知ったヘンリーは、激高し、彼女の継父を殺害する計画を自分のノート「ザ ブックオブヘンリー」に書き留め始める。
しかし、そんな折に彼は脳の腫瘍によって、突然、余命僅かであるという状況に追い込まれてしまう。
自分の死期を悟った彼は、母親であるスーザンと弟のピーターにノートを託し、計画を実行に移してくれるよう懇願します。
スーザンは当初、その計画に否定的でしたが、ある夜に隣の家でクリスティーナが虐待される場面を目撃してしまい、継父を殺害することを決意して…。
スタッフ・キャスト
- 監督:コリン・トレボロウ
- 脚本:グレッグ・ハーウィッツ
- 撮影:ジョン・シュワルツマン
- 美術:カリーナ・イワノフ
- 編集:ケビン・スティット
- 音楽:マイケル・ジアッキノ

















『スターウォーズ9』の監督を退いたのは、決して『ザ ブックオブヘンリー』の評価が低すぎたからというわけではないと思います。
ただ、『ジュラシックワールド』で一気に名声を得たにもかかわらず、それをボロボロにするくらいのインパクトはあったと言えるでしょうか。
それでも、本作最大の問題点は脚本だと思いますね。担当したのは小説家として知られるグレッグ・ハーウィッツです。
グレッグ・ハーウィッツは基本的にスリラー系の小説を書いている作家だと思いますが、そこに無理やり家族ドラマと社会問題を持ち込んだ結果、カオスな内容に仕上がったということでしょうか。
撮影を担当したのは、ジョン・シュワルツマンで彼は『ジュラシックワールド』などでも撮影に関わっています。
音楽には、ディズニー作品やMCUなどにも携わっているマイケル・ジアッキノが起用されました。
- スーザン:ナオミ・ワッツ
- ヘンリー:ジェイデン・リーベラー
- ピーター:ジェイコブ・トレンブレイ
- シェリア:サラ・シルバーマン
- デイヴィッド:リー・ペイス
- クリスティーナ:マディ・ジーグラー
- グレン:ディーン・ノリス

















母親のスーザンを演じたのは、ナオミ・ワッツで正直プロット段階では感情表現しにくいことこの上ないと思っていたのですが、ある程度形にしていました。
またジェイデン・リーベラーとジェイコブ・トレンブレイの子役2人も本当に素晴らしい演技で、特に後者の演技が良かっただけに、もう少しピーターの物語は掘り下げて欲しかったですね。
他にもサラ・シルバーマンやリー・ペイスといった脇を固めるキャストも豪華で、それだけにプロットがもっと良ければと思わずにいられませんでした。

















『ザ ブックオブヘンリー』感想・解説(ネタバレあり)
この映画が言いたいのは「ダンスすげえ!」ってこと
(映画『ブックオブヘンリー』より引用)
まず、このとち狂った映画『ザ ブックオブヘンリー』が何を伝えようとしていたのかを自分なりに考えてみようと思います。
全体的に考えると、おそらくは「暴力に訴えないことの大切さ」「自分の意志を持って生きることの重要性」といった主題になるのでしょう。
しかし、それらのものを伝えることが本作のプロットなのだとすると、かなり無理が生じてくるのです。
本作が見る者に混乱を与えることになる最大の要因は、多くのジャンルをミックスしすぎたことだと思っています。
物語冒頭に関しては、少し不思議な家族モノというテイストで、ヘンリーが家族の資産運用をしているという突飛な設定はありつつも、割と面白く見れます。
しかし、開始30分ほどに到達すると、いきなりヘンリーが隣人のグレンの暗殺を計画し始めるため、物語が一気にシリアスな方向へと転じるのです。
ただ、その計画が進行してクライムスリラー的な展開に進むのかと思いきや、突然彼が重病を患っていることが発覚し、物語は「余命もの」に突入します。

















そこで安定するのかと思いきや、ヘンリーが命を落とし、今度はスーザンの隣人暗殺スパイ映画のようなテイストに変わっていきます。
ただ、オチのつけ方は結局「家族映画」的なところに回帰していくので、これまたよく分かりません。

















こういうジャンルミックスが1時間40分程度の作品の中で起きているために、観客は振り回されまくり、あまり感情移入もできないままにエンドロールに到達してしまうのです。
加えて、物語の最大の力点に当たるシーンが、物語の進行と登場人物の感情の変化が一致していないということが、大きな問題でしょう。
本作『ザ ブックオブヘンリー』で、主題について考える上で、最も大切なシーンは、スーザンがグレンを殺害しないという決断を下すシーンです。
このシーンは、グレンを殺害しないという決断に関して言うなれば、「彼女を救うとしても暴力以外の手段を択ばなければならない」という道徳的かつ倫理的なものだと思います。
しかし、この映画が彼女の心情の変化のために用意していたギミックは、2人の息子の写真を見るというものであって、そのモチーフが彼女に気がつかせるのは、せいぜい「自分が母親である」ということくらいですよね。
確かに今作のメインプロットの中には、家のことや自分のことをヘンリーにまかせっきりにしていて、家族のことや子どものことを自分で決定できないスーザンの成長譚が忍ばされています。
しかし、そんな彼女の「自分で決断できるようになる」ことへの選択と、グレンを殺害しないという選択を同時に処理したのは、明らかに道徳的・倫理的な解決とは言えません。
警察や児童保護局にもどうしようもない虐待を私的な暴力によって裁いても良いのかというすごく深いテーマを内包しながら、その解決に至る動機が「私は母親だから、自分で決めなきゃ!」では明らかにダメなんですよ。
そして、ここまでは1000歩譲って許したとしても、ラストのグレンが自殺して、書類を偽造していたことによりスーザンに親権が移るという展開は、あまりにもご都合主義すぎて「失笑もの」と言わざるを得ません。

















このラストは道徳的にも、倫理的にもネジが外れすぎていて、衝撃を受けました。
そもそも今作はグレン側の事情をあまり掘り下げていませんし、彼が虐待を働いていることは仄めかすように描いていますが、それについての明確な描写もありません。(G指定作品ですので、やむを得ませんが)
つまり、グレン側にどんな事情があるとか、どんな家庭の状況なのかですとか、亡くなった彼女の妻の話だとかがほとんど挙がらずに、ヘンリーやスーザンの視点から提供される情報のみで、彼を追い詰めていきます。

















「死」というものは作品の中で重く扱われる必要があると思いますし、最終的にグレンに「死」という罰を課すのであれば、それなりに彼について作中で掘り下げておく必要があると思います。
また、ご都合主義に感じられるような展開で、安易に「死」に手を出すのは悪手です。
『ザ ブックオブヘンリー』は安易でかつ圧倒的なご都合主義で彼に「死」をもたらした上に、グレンについて特に掘り下げもないままという惨状でしたので、余計に「プロットに殺された感」が強く出てしまったと言えるでしょう。
こういう作品性ですので、主題が「暴力に訴えないことの大切さ」だと言うのであれば、成立しないと思いますし、「自分の意志を持って生きることの重要性」が主題だというにはトーンが弱すぎます。

















その上、今作においてクリスティーナを救ったのは、ヘンリーやスーザンではないんですよ(笑)
おそらくスーザンだけがあの後に通報したとしていても、揉み消されて終わっていたでしょう。
しかし、クリスティーナが発表会の場で素晴らしいコンテンポラリーダンスを披露し、それが学校の先生らの心を大きく動かしたがために、彼女は父親の呪縛から解放されたのです。
つまり、今作の最大のテーマは「ダンスってやっぱすげえよな!人の心をこんなにも動かすんだぜ!」ってことなのだと思っています。
というか、それ以外にメッセ―ジ性を感じ取ることは難しい作品であり、それくらいしか伝わってこない作品なのです。
子どもが苦境から脱するには己の力で…?
(映画『ザ ブックオブヘンリー』より引用)
さて、先ほど、今作において結局のところクリスティーナを救ったのは、彼女のダンスだったという話をしましたよね。

















近年、経済格差や虐待といった親由来の課題や問題によって、子供の将来の可能性が狭められてしまうという状況は日本のみならず世界中で解決に向けた取り組みがなされています。
アメリカではヒルビリーと呼ばれる白人労働者階級の子どもたちが、トピックに挙がるなどしていて、親以上の人生を歩むことはないという悲観的なコメントも出ていました。
もちろん子どもが自分の力で、そういう状況から脱するには、周囲の大人の助けが必要になるはずです。
本作『ザ ブックオブヘンリー』も作中で、しきりにヘンリーが「僕は子どもなんだよ。」ということを言ってしましたが、まさしくその通りで、子どもだからこそきちんと大人がサポートしてあげないとダメなのです。

















だからこそ、余計にラストのクリスティーナを救ったのが、彼女自身のダンスだったという展開はあり得ないと思うのです。
なぜなら、これでは子どもが自分の置かれている苦境を脱するためには、自分の力で周囲の人を動かしたり、環境を変えたりしないといけないのだというプレッシャーに繋がるからですよ。
これは正直に申し上げて、絶対にやってはいけない「児童虐待」との向き合い方だと思っていて、もちろん本人の力で解決するのは理想かもしれませんが、大半のケースではそれが難しいでしょう。

















そういう入りをしておきながら、結局は彼女が自分の力で助かってしまうというオチはどう考えてもあり得ません。
この程度の展開や描写の仕方しかできないのに、「児童虐待」と「ビジランテ」という高度なテーマに踏み込んでしまうと、どうしてもボロが出てしまうものです。
先ほどの章で書いたことにも繋がりますが、『ザ ブックオブヘンリー』という作品の最大の問題点は、この作品のジャンルが曖昧であり、そして扱った社会問題に対する作品としての姿勢が曖昧な点です。
ここをぼやかしてしまうと、非常に不誠実な作品になるので、注意が必要であるというある種の反面教師になったのではないでしょうか。
やはり聖書的なお話が好きですね
(映画『ブックオブヘンリー』より引用)
ハリウッド映画を見ていると、やはり「聖書」的な要素を持ち込んだ作品は数多く作られているように感じます。
『ザ ブックオブヘンリー』という作品も、実はそうではないかと個人的には感じました。
まず「The Book」という言葉は、英語圏でしばしば「聖書」のことを指して用いられます。
そのため、「ザ ブックオブヘンリー」という劇中に登場するノートは、ヘンリーが命を落としたことが「イエスの死」に重なり、ある種「聖書」的に機能しているのです。
とりわけスーザンは、「ザ ブックオブヘンリー」に忠実に行動するようになり、自分自身が主体となっての選択を放棄するようになります。
正常な判断ができなくなり、彼の言葉のままに、グレンの殺害計画を実行に移していくわけです。
しかし、信仰は、依存したり寄りかかったりするためにあるのではなく、「自分が生きる上で支えの1つになるもの」だと思います。
つまり、教えのままに忠実にかつ盲目的に行動するようになってしまっては、本末転倒なのですよ。
近年、話題になったいたイスラムの過激派は聖典コーランの中にある「ジハード」の解釈によって、テロ活動をするようになったと言われています。
つまり、聖典に書かれている言葉がすべて正しいのであり、自分はそこに何の疑いを投げかけることもなく、忠実に生きるだけなのだという考え方になってしまっているわけですよ。

















聖典や聖書に書かれていることに忠実であれば、人を殺害したり、暴力を振るっても良いという思考に盲目的に人間を至らしめてしまう恐ろしさが、歴史的に考えてもやはり存在しています。
だからこそ、自分の意志で選択し、人生を選んでいかなければならないのです。
『ザ ブックオブヘンリー』は、おそらくスーザンの物語を通じて、こういうことが言いたかったのだと思います。
物語の力点が、明らかに彼女がグレンを殺害するかどうか→思いとどまる一幕に置かれていましたから、「選択」がキーワードだったことは間違いありません。
ただ、そこを明らかに「児童虐待問題」「ビジランテ問題」「人を救うための暴力」といった複数の主題とごちゃ混ぜにしてしまっているために、有効に示せていないというのがその実でした。
おわりに
いかがだったでしょうか。
今回は映画『ザ ブックオブヘンリー』についてお話してきました。

















序盤のギフテッドの息子であるヘンリーが家族のことを何から何まで決めていて、スーザンが母親として機能していないという描写の仕方は結構興味深いものでした。
また、ヘンリーの存在がある故に劣等感を感じたり、母親が自分を子ども扱いすることに反発するピーターの描き方も膨らませれば、良い物語になったと思います。
こういった家族映画、ヒューマンドラマとしての物語の種はたくさん散りばめられていましたので、そこを丁寧に拾って、スーザンが自ら決断できるようになり、そしてピーターと向き合っていく内容にすれば、シンプルな良作になったはずなんです。
しかし、この作品はそこにスリラー要素、スパイ映画要素を持ち込み、さらにはかなり重ための社会問題や哲学的・道徳的な主題を持ち込んだことで、完全に要素過多でぶっ壊れてしまいました。
作品のジャンル、姿勢、物語の力点や方向性。これらのものが全くと言って良いほどに確立されておらず、空中分解していたわけです。

















これをやったらダメと言う脚本の悪手がこれでもかと言うほどに詰まった作品でした。
最後に、サラ・シルバーマン演じる女性がヘンリーの唇を奪うシーンは、もう作った側がどうかしてると思います(笑)
これは本当にヤバい…。
今回も読んでくださった方、ありがとうございました。