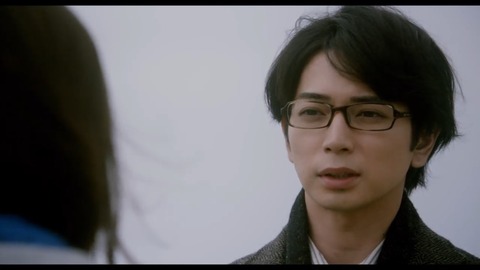みなさんこんにちは。ナガと申します。
今回はですね又吉直樹さんの『劇場』についてお話していこうと思います。

小説の方を既に読破しましたが、内容的にはそれほど革新性があるものではないですね。ただ、構成の面で趣向が凝らされていて、メタ的に楽しめる1冊となっています。
そのため、映画というメディアに落とし込んだときに、この構造的な魅力をどれくらい引き継ぐことができるかが行定監督の腕の見せ所になってくるでしょう。
物語的には大きな展開があるわけでもなく、とりわけ役者の魅力で見せるタイプのプロットという側面も強いので、主演の2人、特に沙希役の松岡茉優さんの演技には要注目でしょうか。
そして、映画版に関して言うなれば、全国の映画館での大規模ロードショーからAmazon Primeとミニシアター公開の2つの柱で公開される運びとなりました。
「『劇場』というタイトルなので、映画館で見たい!」という声もありましたが、この作品は別に劇場という場が重要な作品ではないんですよ。
むしろ人生が演劇に浸食され、同化していくことによって、自分という存在が1つの「劇場」の中で生きているかのように錯覚させるという意味合いでつけられたタイトルなのです。
ですので、あえてAmazon Primeというたくさんの方が見られるメディアで配信するという選択も個人的には肯定的に捉えておりますし、ミニシアターのみの劇場公開に絞ることで、苦しい劇場への支援を試みている姿勢も好感が持てます。
アフターコロナの映画業界を考えた時に、もはや新作を公開すれば儲かるというビジネスモデルは成立し得なくなっていくのではないかと思っております。
つまるところ、劇場での鑑賞は作品そのものの価値だけではもうダメで、そこでしかできない体験にもっと付加価値を見出せる場にしていかないと先は暗いのではないかと感じております。
先日も『泣きたい私は猫をかぶる』というアニメ映画が劇場公開からNetflix独占配信に切り替えたことで話題になりました。
アメリカでも劇場公開から配信に切り替えた作品がコロナ禍の最中で大ヒットしたことで、劇場で映画を見るという行為に対しての風向きが大きく変わりつつあります。
私はこういうブログをやっている人間ですので、もちろん映画館という空間にはそこでしか味わえない感覚や経験があると実感しています。
しかし、こういった変化は時代や技術の変容につきものですし、それに対応できないものは淘汰されて然るべきだとも思っています。
これまでただ新作が上映されているからという理由で足を運んでいた層が、配信に吸収されるようになっていった時に、映画館はどんな「価値」を訴求できるのかについては考えていく必要があるでしょう。
そういう意味でも『劇場』が邦画実写映画の中で初となるAmazon Primeでの配信を主軸とした上映モデルに切り替えたという事実はいろいろと思うところがありますね。
さて、少し話が逸れましたが、今回はそんな『劇場』という作品について個人的に感じたことや考えたことを綴っていきます。
本記事は作品のネタバレになるような内容を含む感想・解説記事です。
作品を未鑑賞の方はお気をつけください。
良かったら最後までお付き合いください。
目次
『劇場』
あらすじ
永田という男は『おろか』という小さな劇団を学生時代の同級生と立ち上げ、脚本家として創作活動に励んでいた。
しかし、彼の劇団の作品は「前衛的」の意味をはき違えているとしばしば批判されており、公演の動員も伸び悩み、金銭的にも苦しい状況が続いていた。
浮浪者のような出で立ちをして居る彼は、ある日街で見かけた1人の女性に強烈な引力を感じ、思わず声をかけてしまう。
永田の風貌に当初は恐れおののいている様子だったが、沙希という名前のその女性と喫茶店に入り、そして夜ご飯を一緒に食べて解散した。
しばらく会うことがなかった2人だったが、永田の頭の片隅にはいつも彼女の存在があり、メールや電話で何度か連絡を取ろうとしたものの思いとどまっていた。
ある日、彼の劇団に所属している演者3人が、劇団から脱退したいと申し出てきた。タイミングが悪く、駅前での少し大きめの規模での公演が決まっていたこともあり、永田は自分の脚本に起用する役者選びに苦心する。
そんな時、女優を目指していると語っていた沙希の存在が頭をよぎり、彼は彼女に出演をオファーした。
かくして、彼女は永田の手掛けた作品に出演することとなり、その作品は彼女の演技の凄みも相まって高い評価を受けることとなる。
その一件を経て、2人は恋人同然の関係となり、同居生活を始めるのだが…。
スタッフ・キャスト
- 監督:行定勲
- 原作:又吉直樹
- 脚本:蓬莱竜太
- 撮影:槇憲治
- 照明:中村裕樹
- 編集:今井剛
- 音楽:曽我部恵一

















行定監督と言えば『世界の中心で、愛をさけぶ』が最も有名な気がしますが、最近も『ナラタージュ』といった男女の物語を数多く手掛けています。
ただ、かなりウェットな演出を特長にしている印象が強く、その点で好みを分けるのではないかなとは思いますね。
とりわけ直近の『ナラタージュ』や『リバーズエッジ』に関して言うなれば、原作からの改悪も目立ちましたので、その点も心配ではあります。
一方で今回の脚本には蓬莱竜太さんが起用されていますが、彼は『ピンクとグレー』などの素晴らしい作品を手掛けていますので、非常に映画化が難しい題材だとは思いますが、期待しています。
撮影・照明には『リバーズエッジ』にも参加していた槇憲治さんと中村裕樹さんが、編集には『パラレルワールドラブストーリー』や『AI崩壊』の今井剛さんがクレジットされています。
今井剛さんの編集は、良くも悪くもダイジェスト感があり、個人的にはあまり好きではないので、今作のような少し特殊な構成で成立している作品をどうまとめるのか、不安もありますね。
- 永田:山崎賢人
- 沙希:松岡茉優
- 野原:寛一郎
- 青山:伊藤沙莉
- 小峰:井口理

















主人公の永田役の山崎賢人さんはちょっと原作のイメージからすると美形すぎるかなという印象は受けますが、彼は演技力も優れていますので、問題ないと思います。
そして誰よりもはまり役なのが、沙希を演じる松岡茉優さんでしょうね。
彼女の演じる役って、言わば男性が望む理想の女性的な部分があるのですが、そんな理想の裏で1人現実に生き、精神をすり減らしていくという辛い役回りでもあります。

















そういう全てを包み込んで、受け入れてくれるような、それでいて儚い不思議なオーラをまとったキャラクターに松岡茉優さんがピッタリすぎて、映画で彼女の演技を見たら正気を失ってしまう可能性があります…。
また、作品のキーパーソンの1人である青山の役には、こちらも唯一無二の存在感を出せる伊藤沙莉さんが起用されており、こちらも原作のイメージドンピシャです。
King Gnuの井口理さんが、永田の嫉妬している天才脚本家の役を演じていますが、こちらも想像がつかないので、どんな演技になるのか気になるところです。

















『劇場』感想・解説(ネタバレあり)
理想と現実、演劇と人生の間でもがき、見出す答え
(C)2020「劇場」製作委員会
まず、『劇場』という作品は、一見するとかなりありふれた物語でして、劇的な展開があるわけでもありません。
そのため、表面的な部分だけを追ってしまうと、保守的な内容だと感じるのも無理はないでしょう。
しかし、この作品の肝は、その特殊な構造にあるわけでして、劇中で主人公の永田が脚本を書いているわけですが、そもそもこの『劇場』という小説そのものが彼の語りで構築された1つの脚本の様であるために、メタ的になっているんですね。
それを象徴するのが、この作品の書き出しでもあります。
まぶたは薄い皮膚でしかないはずなのに、風景が透けて見えたことはまだない。もう少しで見えそうだと思ったりもするけど、眼を閉じた状態で見えているのは、まぶたの裏側の皮膚にすぎない。あきらめて、まぶたをあけると、あたりまえのことだけれど風景が見える。
(又吉直樹『劇場』より)
この書き出しは、主人公の永田の語りになっているわけですが、まずまぶたを上げるという行為そのものが、「目覚め」を意味しており、彼の人生の一幕が始まったことを表現しています。
それと同時に、この「まぶた」というモチーフは演劇における「幕」を想起させるようになっており、劇場で幕が上がって演劇がスタートするという光景を重ねているのです。
この書き出しが、本作が永田の人生と現実に向き合ったものであると同時に、作品全体が1つの演劇のようになっているという構造を明示しているんですね。
さて、この作品が大きく展開していくのは、永田と沙希の出会いがきっかけです。
沙希という女性の本作における意義については後程詳細にお話する予定ですが、彼らが恋人関係になる契機となったのは、他でもない「演劇」でしたよね。
女優を目指して上京してきた沙希に、永田は自分の書いた脚本に登場するヒロインを演じて欲しいと依頼し、彼女はそれを引き受けました。役者が不足していたという都合もあり、彼自身もこの作品に出演しました。
つまり、彼らの恋愛関係は確かに現実ないし2人の人生というレイヤーで始まったのですが、同時に理想と演劇というレイヤーでも彼らの関係は始まっていたのです。
その後、2人は良好な関係を築いていきますが、永田は常に心のどこかで彼女に対して「理想」を押しつけている節があります。
基本的に2人の生活費の大半は、彼女の方が負担しているわけですが、お金が苦しいので助けて欲しいといった現実的な話を持ち出すと、永田はすぐに話を逸らそうとします。
この行動というのは、彼が思い描いている理想ないしプロットを維持しようとするものであり、それを崩壊させ、現実をまざまざと突きつけるような言葉や展開を避けようとしているとも取れますよね。
作品の中で、印象的だったセリフの1つに「ここが一番安全な場所だよ。」というものがあります。
これは、沙希が部屋で2人きりでいる時に、永田に対して告げた言葉なのですが、これがすごく気持ちが悪いんです(笑)
この言葉は、現実のレイヤーで沙希が発した言葉に思えて、同時に理想や演劇のレイヤーで永田が彼女に言わせた言葉という風にも解釈できると思います。
現実や人生を直視せずに、理想やプロットの中に閉じこもっていれば、いつまでも辛い思いをせずに生きていけるという甘い言葉なのであり、永田の心がそんな言葉を彼女に言わせているのだとすると、不気味なシーンですよね。
ただ、そこで考えたいのが、本作の『劇場』というタイトルです。
劇場というのは、演劇を上演する「場」であるわけですよね。プロットは自分の頭の中から出さない限りは理想や空想上の産物でしかなく、現実に市民権を持ち得ません。
しかし、そのプロットを演劇として劇場で上演するということは、作り手と演者と、そして観客が1つの場を共有することによって演劇を現実のレイヤーに落とし込むという工程でもあります。
永田は、いろいろと頭の中にプロットや脚本、理想をたくさん持っているのですが、なかなかそれを巧く表現することができていません。
(C)2020「劇場」製作委員会
同世代の天才として作中に登場する小峰という劇作家は、自分の理想を確かに持ちつつも、それを現実ないし劇場という場に落とし込む術に長けているという点で、永田よりも優れています。

















そういった彼の演劇に対する姿勢が、沙希への向き合い方にもリンクしているわけで、彼は頑なに自分の頭の中に思い描いている理想の中に彼女を閉じ込めようとしています。
永田のプロットの中では、いつもニコニコとしていて温かく迎え入れてくれる沙希ですが、彼女は彼の作り上げる理想とそして現実の境界で苦しんでいる人物です。
彼の望む自分で痛いと思いつつも、金銭的にも、肉体的にも、精神的にも現実に生きようとする中で消耗していき、心を病んでいきます。
そうして生まれたギャップは塞がることを知らずに広がり続け、結果的に破局へと向かって行きました。

















先ほど2人が恋人関係になるきっかけが演劇作品だったと書きましたが、その時の脚本が彼女の部屋にまだ残っており、終盤に2人で読み合わせをするシーンがあります。
この演出があることで、『劇場』という作品そのものが、永田の書いた失恋を題材にした劇中劇と強くリンクする構造になっていました。
しかし、彼らはその本に書かれている通りにセリフを読み進めるのではなく、どんどんとアドリブでその内容を変換していきます。
これは、永田が自分の書いたプロット=理想を壊す選択をしたことの表出でもありますよね。
理想に囚われてしまうのではなく、現実に目を向けなければならなかったと悟った彼の決心が感じられる行動でもあるのですが、『劇場』はここにもう一ひねり加えています。
というのも、この作品は、理想や演劇、フィクションを否定するというよりは、むしろその力をそれでも信じようとするような思いが強く感じられる幕切れになっているのです。

















本作を象徴するとも言える著者の思いが綴られた一節があるので、引用します。
演劇は実験であると同時に発見でもある。演劇で実現できたことは現実でも再現できる可能性がある。
(又吉直樹『劇場』より)
つまり、演劇というものが理想や空想であることを認めたうえで、それが現実と切り離されて存在しているものではなく、地続きのものとして存在していると言っているのです。
だからこそ、クライマックスのシーンで、永田は現実に直面しながらも、それでも彼女との未来の理想の話をひたすらにし続けます。
それは単なる現実逃避や青写真などではなく、彼が現実にするんだと強い決意を持って語っているものです。
演劇で実現できたことは現実でも再現できるからこそ、彼は自分の頭の中にある理想を自分の力で実現してみせるのだと、沙希に語っているんですね。
しかし、沙希はそんな理想にも疲弊しきっており、ただただ「ごめんね」と繰り返すばかりです。
そんな彼女に対して永田は「沙希ちゃん、セリフ間違えてるよ。」と告げるわけですが、この言葉には彼がそれでもなお2人の未来を望む、自分の思い描く理想を現実にした時に、彼女に一緒にいて欲しいという強い願いを感じます。
『劇場』という作品の最後は、こんな一節で締めくくられています。
沙希は観念したように、ようやく泣きながら笑った。
(又吉直樹『劇場』より)
理想と現実の境界で打ちひしがれながらも、それでも理想や演劇というものが持つ力を信じるのだと、そしてその力が人を動かすのだという著者の強い信念を感じる作品であるわけですが、この一節はその微かな力を具現化しています。
別れの物語でありながら、いつか2人が再会し、幸せな未来を実現させるのではないかという仄かな期待を漂わせつつ、余韻と共に物語はフェードアウトしました。
このようにメタ的な構造を作り、現実と理想、演劇と人生というレイヤーを見事に表現したことで、本作はフィナーレを傑出したものとしています。
沙希という女性の存在について
(C)2020「劇場」製作委員会
さて、本作の中で特に印象的なのは、何と言っても沙希という女性だと思います。
何と言うか、不思議な引力がある女性ですし、語弊を恐れずに言うのであれば、「男性の理想の投影」だと思うんですよね。
自分のやることなすことをすべて肯定してくれて、金銭的にも支えてくれて、こんな女性いるわけないじゃんと思うわけですが、その現実感のなさこそが、重要な意味を持っていると思います。
先ほどの章でもある程度言及はしてしまったのですが、沙希は永田の作り出す理想ないし演劇のプロットの中に生きるキャラクターであり、同時に現実を生きる生身の人間です。
物語の中盤付近までは、その2つのレイヤーに存在する彼女にそれほど距離がなかったために、問題が顕在化することはありませんでした。
しかし、大学を卒業し親からの仕送りが止まり、働かざるを得なくなった彼女は経済的にも苦しくなり、肉体的にも疲弊していく中で、永田の理想の中で生きることに疲弊していきます。
生活が苦しくなり、光熱費を払って欲しいとお願いをしても、彼は言い訳を作って逃れてしまうわけですが、そんな彼に対して沙希は笑顔で納得するかのように振舞うのです。
そうして理想に生きようとすればするほど、現実で疲弊し、現実で生き抜こうと苦心するほどに、理想から遠ざかっていくというジレンマを彼女は1人で抱えていました。
沙希が血の通った人間でありながら、演劇のプロット上の1キャラクターにしか思えなくなるのは、きっと永田の理想に合わせようと言動に気を使っているからなのだと思いました。
先ほども少し触れた「ここが一番安全な場所だよ。」というセリフは、現実的に考えると不気味であり、彼女が生身の人間であるという事実を一瞬忘れさせるような冷たさを感じます。
原作者の又吉直樹さんがあとがきの中で、恋愛と演劇は共通しているということを語っています。
演劇には構想があり、脚本があり、それを実現させるための演出がある。恋愛にもやはり構想があり、筋道があり、それを達成するための演出がある。
(『劇場』あとがきより)
だからこそ、演劇が破綻するが如く、恋愛においても自分が思っていた構想通りにいかず、筋道が逸れていき、思っていたところとは全く違うところに着地してしまうという現象が起きるわけです。
おそらく成熟した2人であれば、どちらか一方の理想や構想に基づいて進行していくのではなく、2人が共通認識としてお互いに納得したプロットの上で関係性を進展させていくことができるでしょう。
しかし、今作に登場する永田と沙希のような未熟な2人だと、どうしても上手くいかないことがあります。
とりわけ2人の関係が静かに終わりへと向かって行ってしまうのは、永田が脚本家であり、沙希が役者であるという関係性が最初に出来上がってしまっていたからです。

















そのため永田は必死に、そのプロットに固執したわけで、一方で沙希は与えられた役を演じることに徹することとなってしまいました。
ただ、彼らは恋愛という名の演劇を演じていく一方で、もちろん現実ないし人生を歩んでいかなければならないわけで、理想に逃げ込み続けることはできません。
いつかは理想と現実の折り合いをつけて、彼らなりの道を選択しなければならなかったわけですが、2人とりわけ永田がそれを何年もの間避け続けてしまいました。
結果的に、沙希が与えられた役を演じ切れなくなり、壊れてしまうわけです。
2人の関係性ないし、彼にとっての沙希という存在を言い表した一節があるので引用します。
世界のすべてに否定されるなら、すべてを憎むことができる。それは僕の特技でもあった。沙希の存在のせいで僕はセカイを呪う方法を失った。沙希が破れ目になったのだ。
(又吉直樹『劇場』より)
これは、永田視点の彼女の存在に関する解釈となっているわけですが、つまりは彼が自分を赦して、受け入れてくれる場としての存在を彼女に押しつけたんですよね。
劇中で沙希が彼からの頼みや提案を一切断らないのが、実に気持ち悪いのですが、思えばこの作品そのものが1つのプロットのようであり、彼女がそのキャラクターなのだとすると、それらが永田の理想の産物でしかないことも浮き彫りになります。
ただ、彼女の問題が表面化するにつれて、彼も彼女が生身の人間であるということを改めて感じ取るようになり、少しずつ関係性を変化させていきます。
それと同時に、彼にとっての演劇というものの価値観が大きく変化していくのも印象的でした。
永田は周囲から前衛的の意味をはき違えているなどと厳しい批判にさらされてきたわけですが、観客を引き込むというよりは、とにかく自分のやりたいことを、理想を追求するのだという姿勢が強かったんですよね。

















彼に足りなくて、劇中に登場した劇作家の小峰にはあったものは、劇場という場において、自分だけでなく演者、スタッフ、そして観客に自分のプロットを共有し、現実のレイヤーに落とし込む技量です。
永田は沙希との関係性の変化を通じて、初めて演劇というものが現実や人生と地続きのレイヤーに存在しているものだと悟ったのだと思います。
そういう意味でも、本作は恋愛関係の変化を通じて、主人公の演劇人としての在り方や価値観を変容させていくような物語であり、そう考えると、そのきっかけとなる沙希という女性はますます特異な存在に思えます。
現実に苦しんでいながらも、どこか現実からは切り離された存在に思えるそんな不思議なヒロインの存在が『劇場』という作品において大きな役割を果たしているのです。
原作と映画、その違いに見る魅力
さて、いよいよ7月16日よりAmazonPrimeで今作の映画版が配信開始となりました。

















当ブログ管理人も劇場に足を運ぼうと考えていたのですが、新型コロナの感染者が急増中ということもあり、極力映画館に行くのは回避と決めました。
無念ではありますが、AmazonPrimeにて本作を早速鑑賞したので、原作と比較しながら、その魅力について考えてみようと思います。
とりわけ物語そのものは、原作と映画でほとんど変わりないのですが、やはり映像と活字というメディアの特性の違いによって微妙に物語のトーンが変化していると感じました。
ですので、今回はそういった「違い」にフォーカスしてみようと思います。
光と影が表す2人の関係
(C)2020「劇場」製作委員会
原作を読みながら、行定監督がどんなアプローチで映画を作り上げるのか、あの物語を映像に落とし込むのかが気になっておりました。
まず、映像の特徴ですが、非常に陰影が際立つように照明の当て方、自然光の取り入れ方に趣向が凝らされていたのが印象に残りました。
永田が映し出されている時の映像内空間は、朝や昼にもかかわらず、影が非常に濃く、彼はその影の中にいます。一方で、残酷なほどに光の部分は明るいのです。
この陰影の強烈な対比が、主人公の燻っている思いや置かれている状況を表現していたと言えるでしょう。
そんな影の中にいる彼が出会うのが沙希という女性であり、彼女はどこまでも光の中にいる人物です。出会った時には光を象徴する黄色、そして最初のデートの時には白色の衣装を身に纏っていました。
彼女といると、自分も光の中にいるように思えてくる。
沙希と一緒にいる時の永田は影から解放され、自分も光の中にいるかのように錯覚でき、幸せな気持ちになるわけです。
本編の開始から39分ごろの2人が通りを歩いていくシーンを見て欲しいのですが、この時永田は陰の中を歩いており、一方で沙希は日の当たる部分を歩いています。
しかし、少しだけ扇動するかのようにして歩く彼女につられて、永田は日の当たる場所へと出て行くのです。
また、部屋で2人で過ごしている時のシーンの照明は、暖色系の温かみのあるものが使われています。
そこには、それまでずっと日陰で生きてきた彼がようやく見出した「いちばん安全な場所」が視覚的に表現されていたと言えるでしょう。
ただ、永田が彼女の部屋に住み着くようになって、ある程度時間が経過すると、少しずつ彼女を取り巻く照明のトーンが変化していきます。
底抜けに明るかった彼女の表情には翳が見え始め、部屋の中には昼間でも濃い影が立ち込めるようになっていきました。
暖色系の温かみのある照明に包まれていた彼らの部屋は、徐々に闇に飲み込まれていくのです。
まるで彼の孕む暗い影に沙希が引きずり込まれていくかのような、そんな印象すら受けましたね。
そして、永田はそのうちに彼女の家から引っ越していくわけですが、それを契機として彼女の部屋は真っ暗になっていることが増えていきますよね。
まるで、彼が自分が内包していた闇と影だけを、彼女の家に残していったかのようなそんな残酷さすら感じさせられました。
このように映画『劇場』は2人の関係性の変化をも、影や闇の使い方、照明のトーンの変化によって表現していたわけです。
そして、2人が夜道を自転車で走っていく本作のクライマックス。
夜の闇の中を小さな自転車のダイナモライトが照らす。
2人の目の前に広がる未来はもう真っ暗闇なのかもしれない。
それでもいつかその闇を2人で照らすことができたら…そんな願いにも似た感情を抱かせてくれます。
ラストのリアルと演劇の交錯
(C)2020「劇場」製作委員会
本作のクライマックスは永田の劇中劇と、2人の現実がリンクする非常に視覚的にもインパクトがあるシーンです。
原作でもこの場面で一気に作品を包んでいたメタ的な構造を昇華していくようになっており感動しましたが、ここについてはやはり映画で映像ありきで見ると、また違った印象を受けますね。
セリフや展開が大きく変わったというわけではないのですが、とにかく沙希を演じた松岡茉優さんの演技が言葉にならないほどに素晴らしいのと、そして演出がよりストレートになっていたのが原作との大きな違いとなっていました。
まず、永田が自分の夢をいつか現実にするんだと熱く語り始めるシーンで、沙希が窓の方を見つめるのです。
その時の表情には、確かに光とそして希望が宿っていました。絶望の中にいた彼女の瞳に確かに「未来」を見たような気がして、思わず涙がこぼれました。

















また、映画版は原作では少し曖昧に描かれていたラストの演劇と現実の交錯をより視覚的にストレートに描いてるのが印象的でした。
というのも、2人が部屋の中で会話をしているシーンから突如として、舞台の上へとシーンを移していくのです。

















そして、舞台が始まると、先ほどまでは「演じる」側にいた沙希が永田の舞台を見つめる「観客」の側にいるのです。
私は、原作を読み終わったときに、永田がいつかあの時語った演劇を現実のものにして沙希との未来を実現するのではないかという希望を仄かに感じました。
しかし、映画版はむしろ2人の運命がもはや交わり得ないことを強烈に印象づけているように思えます。
なぜなら、沙希はもう彼の「舞台」からは降りてしまっているからですよ。
彼の演劇を見ながら、そのセリフに呼応するかのように「ごめんね」と繰り返す沙希。
そしてエンドロールが終わると、彼女は劇場に1人取り残され、そして舞台の上に作られた、かつての自分の家を模したセットを一瞥すると、静かにその場から去っていきます。
ただ、これでは今回の映画版は原作のラストの否定になってしまいますから、もちろんそれだけで終わってしまったというわけではありません。
映画の中盤過ぎに、永田が疲れて眠っている沙希を見て、お面をかぶってリアクションをもらおうとする一幕があったのを覚えていますか。
あの時、彼女は眠ったままで目覚めることはありませんでしたよね。つまり、彼は彼女を笑顔にしたいと考えたにもかかわらず、それを実現することができなかったわけです。
しかし、ラストシーンで彼は再びお面をかぶって、ピエロのように道化を演じるわけですが、そこでようやく沙希は泣きながら笑いました。
これって、自分の頭の中でやりたいと思っていたことを、「演劇」の中でやっていたことを現実に還元するという構造なんですよね。
演劇の中で永田が沙希を笑顔にしようとしていて、そして現実の彼女がまさしく笑顔になったわけです。
そこにこそ演劇の力があるわけで、現実と虚構という本来なら交わり得ないものをつないでくれる可能性がある、交わらせてくれる可能性がある。
そしてそれを実現する場がまさしく「劇場」なんですよね。
映画版のラストは原作以上に、2人の未来をシビアな目線で描いていると思います。
それでも、「劇場」という現実と虚構が共存する場を共有した2人は、いつかあの時思い描いた「演劇」を彼らの「人生」に変えてくれるのではないかという淡い期待は捨てさせないでくれていると感じました。
活字と視覚情報(映像)では、やはり受け手に与える情報のインパクトや強度に大きな差があるので、同じことを描こうとしてもひと縄筋ではいかないことがあります。
ただ、今回の映画『劇場』は、原作以上に残酷な結末を印象づけながらも、希望を描くことは諦めませんでした。
夜道を小さな自転車のダイナモライトで照らしながら走ったあの日のように…。
松岡茉優さんの演技の凄まじさ
あくまでも個人的にはですが、本作『劇場』については、映画版より原作をおすすめします。
しかし、それでも映画を鑑賞する価値があるとすれば、やはりその中心にあるのは、松岡茉優さんの演技でしょう。

















永田が出会った頃の彼女は、天性の明るさを兼ね備えた女性です。
しかし、彼と関わっていくうちちその表情が少しずつ変化していきますよね。
笑顔なのに、どこか闇を内包したような表情。
(C)2020「劇場」製作委員会
笑顔なのに、心から笑っているようには見えない、この繊細な表情に思わずハッとしましたね。
この笑顔はの裏にあるものを感じ取っているのに、感じ取っていないふりをして目を背ける永田という構図も皮肉にも強烈で、笑顔の裏で、彼女が精神をすり減らしていくプロセスを見事に演じ切りました。
そして、完全に笑顔のメッキが剥がれてしまったような、疲弊しきった表情も終盤になると見せてくれます。
(C)2020「劇場」製作委員会

















笑顔でしようと努力して見るものの、もはや笑う気力すらないほどに、心が疲弊してしまった沙希の表情は、出会った頃の底抜けの明るさからは想像もつかないところまで来ています。
沙希という1人の女性を演じながら、松岡茉優さんは「笑顔」という表情に微細な変化をつけることで、キャラクターが置かれている状況や心情を完璧に表現しているわけです。
もはや彼女にしか成し得ない究極の表情芸だと思いましたし、映画を見ていると彼女の瞳に吸い込まれてしまいそうになるほどのパワーがありました。
おわりに
いかがだったでしょうか。
今回は『劇場』についてお話してきました。
この作品は、構造的な部分に目を向けないと、すごく地味でありきたりに思えてしまうので、映画化はかなり難しいチャレンジになると思います。

















そこをどう行定監督がクリアしてくるのかも含めて、映画版も非常に楽しみです。
また、何と言っても松岡茉優さんが沙希を演じているというのが、個人的には完璧なキャスティングだと思っていて、予告編の時点であの特異な役どころを完全に捉えているんですよ。
ぜひ、映画とそして原作を合わせて鑑賞してみてくださいね。
今回も読んでくださった方、ありがとうございました。