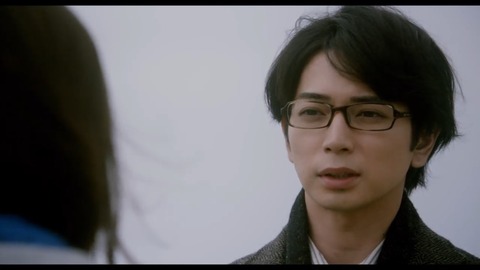みなさんこんにちは。ナガと申します。
今回はですね映画『#ハンド全力』についてお話していこうと思います。

その中でも『ワンダフルワールドエンド』と『私たちのハァハァ』あたりがお気に入りなのですが、何と言うか「普通の映画」は撮らない監督ですよね(笑)
青春映画も多く手掛けていますが、ただキラキラしているだけではなくて、『スイートプールサイド』のような屈折間であったり、『私たちのハァハァ』で大人たちによって突きつけられるシビアな現実であったりと、すごくエッジの効いた作品を世に送り出しています。
今回の『#ハンド全力』は予告編の時点では、「スポ根×復興×SNS」というかなり王道の要素を組み合わせた作品と言う雰囲気もありました。










これ鑑賞した人がTwitterでタイトルを入力すると、自動でタグ化されるタイトルになっているんですよ。
このあたりも作品の内容とリンクするうえに、話題作りとしても非常に面白いですね。
個人的には「スポ根×復興×SNS」をストレートに描くだけなんてことは、松居監督に限ってはやらないだろうなという、期待を裏切ってくれることに対しての「ワクワク感」のようなものを持って、鑑賞に臨みました。
本記事は作品のネタバレになるような内容を含む感想・解説記事です。
作品を未鑑賞の方はお気をつけください。
良かったら最後までお付き合いください。
『#ハンド全力』
あらすじ
熊本は震災から3年が経過し、少しずつ復興を遂げていたが、まだ多くの人が仮設住宅に暮らしており、その爪痕はまざまざと残っていた。
そんな熊本で仮設住宅に暮らしている高校生・清田マサオ。彼は夢中になれるものもなく、無気力な毎日を送っていた。
中学生の頃はハンドボールに取り組んでいたが、震災の時に試合にも出場できない状況に絶望し、止めてしまっている。
一方で彼の同級生だったタイチは、県外の高校に進学し、着実に実力を伸ばし、日本を代表する選手へと成長を遂げた。
ある日、彼は自身のInstagramに、中学生時代のタイチの写真を投稿する。
すると、その写真が小さなバズを記録し、マサオは自分の承認欲求が満たされたように気がして、SNSにのめり込むようになるのだった。
親友の岡本の提案で、「#ハンド全力」というハッシュタグをつけて、「ハンドボール×復興」のメッセージを発信するようになると、その取り組みが大きな注目を集める。
フォロワーは一気に増加し、テレビの取材や、学校にハンドボール部への支援が届く事態にまで発展する。
しかし、マサオは「頑張る」という行為に懐疑的であり、Instagramに映える写真を撮ることだけに熱を注ぎ、肝心のハンドボールの練習には、ほとんど取り組まない。
そんな時、マサオの不注意でとんでもない事態が起こるのだが…。
スタッフ・キャスト
- 監督:松居大悟
- 脚本:松居大悟 佐藤大
- 撮影:谷口和寛
- 照明:根本伸一
- 編集:瀧田隆一
- 音楽:森優太
- 主題歌:小山田壮平










松居大悟監督の作品は、『アフロ田中』以来ほとんど欠かすことなく鑑賞してきましたが、やっぱり大好きですね。
特に今回の『#ハンド全力』は『私たちのハァハァ』に凄く似ている作品だと感じました。
王道青春譚のようなパッケージングをしていたり、高校生の無茶で、でも青春な取り組みにスポットを当て、閉じた世界を描きつつも、そこに突如として「世間」や「大人」の視点を突きつけるんですよね。
普通の「青春映画」は撮らねえぞ!という気概を感じますし、その視点の鋭さも素晴らしくて、今回も「震災」や「SNS」というものを独自の視点で描いています。
そして脚本には『交響詩篇エウレカセブン』シリーズなどでも知られる佐藤大さんが共同で入っていますね。
彼もアニメ界を激震させた『ANEMONE』の脚本を書いたわけで、本当に尖ったプロットをかける人だと思います。
この2人の化学反応により、物語としても唯一無二で、そして直視したくないけれども、これがリアルなんだと深く考えさせられるような内容に仕上がっていました。
撮影には『ダンスウィズミー』の谷口和寛さん、照明には『聖の青春』の根本伸一さん、編集には『羊と鋼の森』や『見えない目撃者』の瀧田隆一さんが起用されていますね。
- 清田マサオ:加藤清史郎
- 岡本:醍醐虎汰朗
- 黒澤:蒔田彩珠
- 七尾:芋生悠
- 島田:佐藤緋美
- 蔵久:坂東龍汰
- 七尾次郎:鈴木福
- 吉牟田:篠原篤
- タイチ:甲斐翔真
- アニウエ:仲野太賀
- テルテル:志田未来
- 市川:安達祐実










何だか懐かしい子役が集結みたいなことになっているキャスト陣ですが、加藤清史郎さんも舞台の方でかなり経験を積まれていたのだとか。
それほど演技が巧いという印象も特に持っていなかったので、今回演技を拝見して驚きましたね。今後俳優としても活躍していくのではないかと予見させられます。
そして鈴木福さんの方も映画にたまに出演されていたようですが、出演作を見逃していたこともあり、本当に『マルモのおきて』以来見たんじゃないかくらいです(笑)
一方で、当ブログ管理人が非常に注目しているのが、蒔田彩珠さんです。
(C)2020「#ハンド全力」製作委員会
『志乃ちゃんは自分の名前が言えない』での演技が凄まじかったこともあり、その時以来、出演している作品はチェックするようにしております。
目の雰囲気が清原果耶さんを思わせるのですが、少し「影」のある良い演技をするんです。
今作でも主人公たちの行動に懐疑的な視線を向ける女子ハンドボール部員の役でしたが、あの「ドライさ」が作品に欠かせないものであったことは言うまでもありません。
「ドライさ」が彼女なりの情熱の表出であるという、かなりバランスを要する演技でしたが、蒔田彩珠さんは見事に表現してくださいました。
また、大人のキャスト陣は篠原篤さん、仲野太賀さん、安達祐実さんら実力派が揃い、作品を引き締めています。










『#ハンド全力』感想・解説(ネタバレあり)
震災が「生活」の人と震災を「物語」として享受する人
(C)2020「#ハンド全力」製作委員会
2011年以降、東日本大震災をテーマにした作品は増えたと思いますし、テレビを見ていても「復興」を扱ったドキュメンタリーや 番組は当然増えたように思います。
ただ、綺麗ごとや美談として、同情や涙を誘うための道具として「震災」を扱ったものも多く、真にそういった災害と向き合った骨太な作品ってどれくらいあったんだろうな?とふと感じました。
お金儲けをする、同情を買って支援を取りつける。こういった行為の表面に「震災」や「復興」という言葉を貼りつけることで、人々はそれが心からの「善意」や「熱意」によって為されているのだと勝手に解釈してくれます。
こういったいわゆる「復興ビジネス」というものは、東日本大震災の時も、そして熊本自身の時も少なからずあったでしょうし、それは悪だとは思いません。
本作の序盤でInstagramに復元作業中の熊本城とハンドボールを持っている岡本の画像をアップするシーンがありましたよね。
この時に、彼はテキストを入力せずにただ「#ハンド全力」とハッシュタグだけを入力して、投稿しました。
岡本の言い分としては、こうすれば余白が生まれてフォロワーが勝手に想像や解釈を膨らませて盛り上がってくれるだろうと。










確かに、マサオたちが「震災」ないし「復興」というものを利用し、それに便乗してSNS上で話題になったことは事実です。
しかし、彼らには彼らなりの考えがあったわけで、「ハンドボール」というものに注目を集めることで、インターハイを目指している女子部員たちの練習環境の改善にも貢献したという実利も生み出しているんですよ。
それでも、彼らのアカウントのからくりが世間に流出してしまった際には、マサオたちは容赦ない非難を浴びることとなります。
彼らの初の公式戦の時に、勝利した相手側の高校のInstagramに誹謗中傷のコメントが寄せられていましたよね。
結局のところ、SNS上で彼らを応援している人たちの本質って、マサオたちの投稿する写真に勝手に自分の物語を投影して、勝手に期待して、勝手に同情しているだけなんですよ。
彼らがどんなことをしていて、どんな生活をしていて、どんな思いを持っていてなんてことには興味はなくて、自分の想像している物語の中にある「#ハンド全力」に勝手に物語を作って、感動しているに過ぎません。
彼らに勝利した相手高校のアカウントに誹謗中傷のメッセージを送る人間は、つまるところ自分の思い描く、自分が快感を得られる「物語」を妨害されたことが苛立たしいのであって、そこにマサオたちの高校を応援したいという思いはほとんどないんだと思いますよ。
でも、これって私たちが目を背けてきた「震災」の本質だと思いました。
終盤にデニスの植野行雄が演じているコンビニ店員が発狂しているシーンがありましたよね。彼の怒りの矛先にあったのは、「#ハンド全力」に手のひらを返した人間たちでしょうか。
なぜ、彼はあんなにも激怒していたのか。
それは熊本に暮らす人たちにとって震災は「現実」であり「生活」なのに対し、部外者にとって震災は「物語」でしかなくなってしまっていたからです。
『火口のふたり』という昨年公開された日本映画で「被災者になったふりは出来ても、被災者にはなれない。」という言葉がありました。
まさしくこの言葉ともリンクするところなのだと思いますが、私たちがいくら想像力を働かせて、思いを推し量ったところで「ふり」は出来たとしても、本当になることは叶わないわけですよ。
タイチは震災後、熊本を離れて富山県の高校に通い始めたわけですが、そこで被災した故郷を捨ててきた心無い人間だと揶揄されることがあると話していました。
これって部外者が勝手に作り上げた「被災者の物語」「被災者の美談」に彼がそぐわないがために、非難しているようなものですよね。
「被災者たる者こうあるべきだ!」という物語を部外者が勝手に押しつけているに過ぎないわけで、それを求める外部からの圧力が被災し、心に深い傷を負った人間を追い詰めているなんてことは微塵も考慮していません。
『#ハンド全力』という作品がそういった二面性を正面から描き切ったことなのだと思います。
「復興ビジネス」はお金になるし、被災地にも実利をもたらします。震災のリアルを切り取り、部外者の想像力を掻き立てることで、支援を得るということは何ら「悪」ではないでしょうし、むしろ当たり前に為されていることです。
しかし、忘れてはならないのは、「被災者になったふりは出来ても、被災者にはなれない。」ということなのでしょうね。
結局、被災地に居なかった人間にできるのは「震災」をある種の「物語」として享受することでしかなくて、それが「生活」になっている被災者たちとの間には、決して埋まらない距離があると思います。
それを自覚しなければ、勝手に自分の物語のレールに乗せて、そこから外れたら容赦なく攻撃するという不毛な行動をしてしまうわけです。
先日、東京オリンピックの1年前イベントで、白血病の闘病生活を送っていた池江璃花子さんが聖火を手にして、メッセージを発信した件で、賛否両論がありました。
その時に、彼女を政治利用するなという政府批判が巻き起こったり、なぜこんな仕事を受けたのか?という彼女に対する懐疑的な声もありました。「病人なんだから…」なんて声もありました。
ただ、こういった批判のどこに池江璃花子さん本人の思いや選択があるというのでしょうか…。
もちろんオリンピックを開催したい政府が、闘病という逆境を跳ね返した彼女自身の物語に、開催が危ぶまれているオリンピックの状況を重ねたいという思惑があったのは事実でしょう。
しかし、あの場所に立つ選択をしたのは、他でもない彼女自身なのですから、それを外野がいくら批判したところで何だか空虚ではありませんかね。ましてや彼女に対して批判の声を上げている人は一体何を考えているのでしょうか。
結局、私たちが思い描いている「物語」において、彼女があの場に立っていることが許しがたいので批判をするというメカニズムが生まれてしまっていませんか。
メディアやSNSを通じて、そういったある種の「歪み」が生じていることに私たちは目を向けなければなりませんし、自分の考える「こうあるべき」に他人を当てはめようとする行為がいかに危険なことなのかを改めて考える必要があります。
ただ、本作はそういったネガティブさだけにフォーカスしているわけではなくて、「#ハンド全力」が発信したメッセージによって、七尾やタイチのように「救われた」と感じた人間をも描いています。
彼らもまた、そのメッセージを自分の「物語」に当てはめるということをして、勝手に「救われて」いる人間ではあるのですが、ここに「震災」を「物語」として享受することの意義も描かれていたような気がしました。










「物語」を作り出して、そのコンテクストにいろいろな思いを抱いたのは、他でもない自分自身なのですから、それと現実の間に生じた齟齬の責任を誰かに求めるのは違うような気がします。
七尾やタイチのように「信じた自分を信じる」という行為で包み込んでしまえば良いのかもしれませんし、自分が作り出した「物語」が「現実」からズレていたと考えても良いでしょう。
(C)2020「#ハンド全力」製作委員会
『#ハンド全力』という作品はそういう震災やSNSのリアルに真っ向勝負を挑み、そのネガティブな側面だけでなく、ポジティブな側面をもバランスよく描いた傑作なのだと感じました。
おわりに
いかがだったでしょうか。
今回は映画『#ハンド全力』についてお話してきました。










松居監督が、ただの「青春映画」を撮るはずもなくて、ここまで今の世間に対する鋭い視点を盛り込んで描いてくれたことに、やはり良い意味で「裏切り」を期待・信頼できる監督だと感じました。
もちろん「スポ根」としてもすごく面白い作品ですし、熱くなれる作品です。










こんなに上手くSNSの描写を演出に組み込んだ作品って他にないんじゃないかと思うんですよね。
これまでハッシュタグをつけることで、誰かに認められ、応援されて、頑張りを認められてきたマサオたち。
しかし、劇中のセリフにもあったように、「本当に全力な人間は「全力」なんて書かない」んですよね。
だからこそ、ラストシーンで七尾が彼らの写真をInstagramにアップする際に、ハッシュタグを入力しながらも、消去しました。
もう「全力」なんて書かなくても、彼らは全力なのであり、それを誰かに認めてもらう必要はないのです。
ここまで痺れる「青春映画」を世に送り出してくれた松居監督には、あらためて感謝感謝ですね。
今回も読んでくださった方、ありがとうございました。