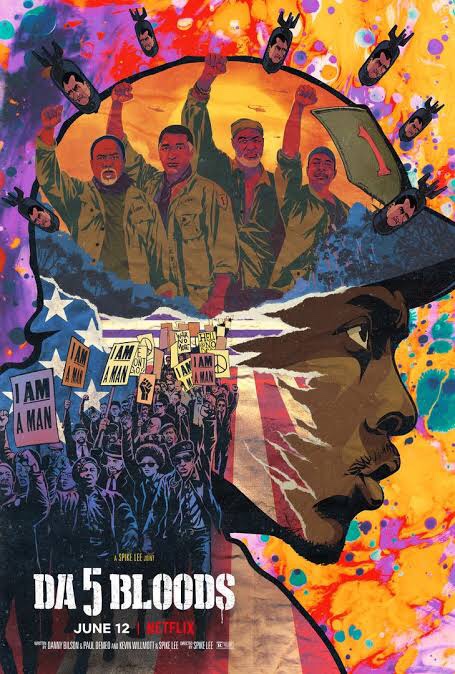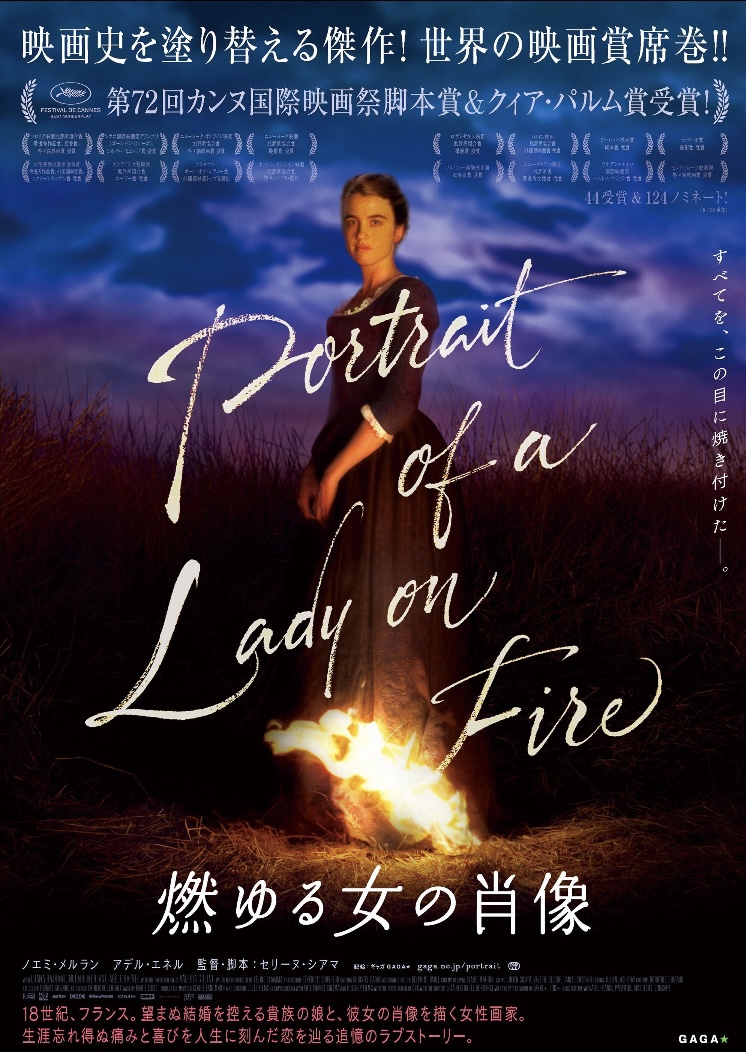みなさんこんにちは。ナガと申します。
今回はですね映画『悪魔はいつもそこに』についてお話していこうと思います。

メインキャストにMCU版『スパイダーマン』シリーズのトム・ホランドが起用されているということもあり公開前から注目されておりました。
ただ、内容はそれほどキャッチーではなく、とりわけ聖書やキリスト教色が強いため、当ブログ管理人も含めて日本で暮らしている多くの人にとっては少し理解が難しい物語になっていると言えるでしょうか。
あとは、全体的にナレーションが主体の映画となっており、そのビジュアルノベルのようなテイストは好みを分けるかもしれません。
ちなみにこのナレーションは原作著者のドナルド・レイ・ポロックが担当しているようです。
In the director’s statement that accompanied screeners of the film, Campos explained, “I wanted to use a narrator to tell the story and build a world in which we gave a voice to the ‘Creator.'”
(looperより引用)
これについては監督のアントニオ・カンポスがインタビューの中で明かしています。
引用した箇所からも分かるように、作品の「創造主」であり、この物語の全てを見通している神の視点を持つ者である彼がナレーションを担当することに意味があったと監督は考えていたようです。
そんな本作の主題となっているのは、やはり「暴力の連鎖と円環」なのだと思います。
人間の歴史を振り返ってみると、ここ100年だけでも目を覆いたくなるような悲惨な戦争や非人道的な行為が繰り返されてきました。
ヒトラーが行ったユダヤ人の大量虐殺からまだ100年も経過していないというのに、今中国でウイグル人たちの弾圧と強制収容が大きな問題となっています。
人間の歴史というものは、終わらない暴力のサイクルなのです。
そんな円環構造を本作は、大きな物語とそして小さな物語をリンクさせる形で演出しています。














本記事は作品のネタバレになるような内容を含む考察記事となっております。
作品を未鑑賞の方はお気をつけください。
良かったら最後までお付き合いください。
目次
『悪魔はいつもそこに』
あらすじ
ウィラード・ラッセルは第2次世界大戦から帰還し、家族のいるオハイオ州ノッケンスティフへと戻る。
ウィラードは、戦争中にある男が日本兵によって生きたまま十字架に架けられていた様子を見たことが大きなトラウマとなっており、結婚してからは家の裏手に十字架を立て、神に祈るようになった。
彼は1人息子のアーヴィンを授かり、妻と3人で幸せに暮らしていた。アーヴィンが成長し、9歳になると学校でいじめを受けるようになる。
ただ、その暴力を黙って耐えている彼を見たアーヴィンは暴力には暴力で返さなければと伝え、自らがそれを体現する。
そんな矢先に妻のシャーロットがガンに侵され、医者から余命がわずかであり、治療は不可能であると宣告された。
そのことにショックを受けたウィラードはアーヴィンと共に今までにも増して熱心に祈るようになり、しまいには愛犬を生贄に捧げるに至る。
結果的に妻は息を引き取り、後を追うようにウィラードは自殺、ウィラードは祖父母の家へと引き取られていった。
そこで、義理の妹のレノーラと出会い、そして4人で平穏な暮らしを続けていくのだが、彼にも脈々と続く暴力の連鎖が降りかかっていくことに…。
スタッフ・キャスト
- 監督:アントニオ・カンポス
- 製作:マックス・ボーン / ジェイク・ギレンホール / リバ・マーカー / ランドール・ポスター
- 原作:ドナルド・レイ・ポロック
- 脚本:アントニオ・カンポス / パウロ・カンポス
- 撮影:ロル・クローリー
- 美術:クレイグ・レイスロップ
- 衣装:エマ・ポッター
- 音楽:ダニー・ベンジー / ソーンダー・ジュリアーンズ














これまで『ピアッシング』などの映画の製作に名前を連ねてきたアントニオ・カンポスが今回監督・脚本を務めました。
そんな彼が今回映画化に挑んだのがドナルド・レイ・ポロックの『The Devil All the Time』という小説ですね。
撮影には、『ポップスター』や『さざなみ』で印象的な仕事をしてきたロル・クローリーが起用され、劇伴音楽には『ジェーン・ドウの解剖』や『複製された男』のダニー・ベンジー &ソーンダー・ジュリアーンズの2人がクレジットされています。
ちなみにですが、製作には今回ジェイク・ギレンホールも携わっているようです。
- アーヴィン・ラッセル:トム・ホランド
- ウィラード・ラッセル:ビル・スカルスガルド
- サンディ・ヘンダーソン:ライリー・キーオ
- カール・ヘンダーソン:ジェイソン・クラーク
- リー・ボーデッカー保安官:セバスチャン・スタン
- シャーロット・ラッセル:ヘイリー・ベネット
- レノラ・ラファーティ:エリザ・スカンレン
- ヘレン・ハットン:ミア・ワシコウスカ
- プレストン・ティーガーディン牧師:ロバート・パティンソン














まず主人公のアーヴィンを演じたのが、冒頭にもご紹介したようにMCU版のスパイダーマンを演じるトム・ホランドです。
そしてアメコミつながりで行くと、リー・ボーデッカー保安官役にウィンターソルジャー(バッキー)を演じているセバスチャン・スタンも起用されています。
さらに言うなれば、DC映画最新作にてバットマンを演じることが発表されているロバート・パティンソンが変態牧師のプレストンを演じました。
ちなみにこの牧師の吹き替え版の声優が何と…。
Netflixで配信スタートした『悪魔はいつもそこに』に登場する変態牧師のビジュアルがロバートパティンソンな時点で既に最強なのに、吹き替えだとこの出で立ちから櫻井孝宏さんの声が出るの本当どうなってるんですか? pic.twitter.com/8ttK3SJR3b
— ナガ@映画垢🐇 (@club_typhoon) September 16, 2020














他にもジェイソン・クラークを初めとする名優が集結した非常に豪華な作品となっております。
このキャスト陣の演技を見ているだけでも満たされる2時間18分ではないでしょうか。














『悪魔はいつもそこに』解説・考察(ネタバレあり)
大きな物語として見る「暴力の連鎖」とその暗い結末
『悪魔はいつもそこに』予告編より引用
さて、本作はまず大きな物語として見ていくと、2つの戦争が象徴的に作品の冒頭と結末に配置されています。
まず、冒頭に配置されていたのが第2次世界大戦ですね。
ウィラード・ラッセルはこの戦争に参戦し、その時に同胞が日本兵によって惨殺されている姿を目撃し、それが後に帰国してからの信仰へのきっかけとなりました。
そもそも戦争というものは、暴力と暴力のぶつかり合いであり、アメリカ軍はこうして殺された同胞たちの何倍もの人間を殺害して第2次世界大戦に勝利したわけです。
一方で、物語のラストに配置されていたのがベトナム戦争でした。
こちらについては直接的な描写があるわけではなく、カーラジオからジョンソン大統領の会見に関するニュースが流れてくるだけです。
以下にその内容を引用しておきましょう。
南ベトナムに配備する兵を大幅に増やします。大統領はこう述べました。
我々は共産主義には屈しないと示す必要がある。
武力においても他の力においても示すのは難しい。(映画『悪魔はいつもそこに』より引用)














まず「南ベトナムに配備する兵を大幅に増やします。」という言葉から読み取れるのは、これからアメリカがますますカオスを極めるベトナム戦争の泥沼に足を突っ込もうとしている「転機」にあるということですね。
つまり、ここで手を引けば、まだ傷は浅くて済んだものを、そこで止まることができずに突き進んでしまう最後のタイミングだったということが仄めかされています。
そして「我々は共産主義には屈しないと示す必要がある。」という言葉は、本作が描いてきたある種の宗教的な対立を象徴しているように感じました。
本作『悪魔はいつもそこに』では、キリスト教や聖書の価値観が色濃く反映されていましたが、その中でそれぞれの人間が抱える「信仰」がぶつかり合う様も見受けられました。
資本主義と共産主義も言わば思想的なレイヤーの事物であり、どちらを信奉するのかによって国と国が対立しているわけですよ。
結果的に、それらの思想・信仰のどちらが優れているのかを証明するのが「暴力」でしかないわけで、それが戦争という形となって私たちの社会には存在しています。
ベトナム戦争とは、まさしく東西陣営の、資本主義と共産主義のぶつかり合いであり、言わば思想と思想の対立の具現化なのです。
『悪魔はいつもそこに』という作品は、そうしたアメリカにとっての2つの大きな戦争を始まりと終わりに据え、そのちょうど狭間の時期に起きた人間のドラマに焦点を当てています。
そして2つの大きな戦争が登場する理由は言うまでもなく、「暴力の円環」を示すためです。
人間の歴史の中で脈々と受け継がれ、繰り返されてきた暴力の「円」が1つの作品の中に内包されているわけですよ。
さらには、カーラジオの放送の内容にあったように、ラストではアメリカという国がベトナム戦争の泥沼へと突き進んで行く暗い未来が暗示されています。
アメリカという国は、ここで暴力の連鎖を断ち切ることに失敗してしまっているわけですよ。
しかし、本作の主人公であるアーヴィン・ラッセルを中心とした人間たちの小さな物語として見た時に、結末時点で実は「分岐」のようなものが示されているのです。
次の章では、本作を人間に焦点を当てた小さな物語として読み解いていきたいと思います。
小さな物語として見る「暴力の連鎖」とその希望のオルタナティブ
さて、ではここからは『悪魔はいつもそこに』における人間たちの物語に焦点を当てていきます。
この作品の登場人物たちの関係を見ていて興味深いのは、世代を超えた円環が明確に描かれている点でしょう。
例えば、レノーラと彼女の母親であるヘレンの運命は実に強くリンクしています。
ヘレンは教会で自分が神の啓示を受けたと語っていた、いかれた男ロイに惹かれ、彼と結婚するのですが、寵愛を受けたと確信したロイの奇行に巻き込まれ命を落とします。
一方で、レノーラもまた教会で変態牧師のプレストンに惹かれ、彼に身体を許すようになり、結果的には妊娠してしまうのです。そして彼に子どもは自分の責任ではないと突き放されたことで自死を選びます。
『悪魔はいつもそこに』予告編より引用
しかし、後程言及しますが、ここで重要なのは、レノーラは自死を選びましたが、彼女の死因は「自殺」ではないということです。














サンディは夫のカールの人間が死にゆくまさにその瞬間を撮影したいという欲求に付き合い、殺人と撮影の旅を続けていました。
しかし、彼女はそんな生活から抜け出そうと作中では少なくとも2度試みているんですよね。
『悪魔はいつもそこに』予告編より引用
最初に暴力の円環から抜け出そうとしたのは、彼女が車で逃げ出そうか思いとどまろうか迷っていた時です。結果的に逃げ出すことはできませんでした。
そして2度目は、アーヴィンを後部座席に乗せた時であり、彼女は彼と一緒に夫のカールを殺害してこの生活から脱却するビジョンを思い描きました。
しかし、どちらのタイミングでも彼女はその決断をすることができず、結果的に暴力の円環に巻き込まれたまま、最後はアーヴィンに射殺されてしまうのです。
レノーラとサンディの物語が示唆しているのは、まさしく「暴力の円環」から抜け出すことの難しさなんだと思います。
彼女たちはその連鎖から抜け出すチャンスがあったわけで、2人とも抜け出すことを望んだわけですが、運命のいたずらに巻き込まれるかのようにして命を落としました。
「暴力の円環」というものが、人間1人の力ではどうしようもないほどに大きな力を持っているものであり、そこから抜け出そうとする小さな力を簡単にねじ伏せてしまうことがこの2人のエピソードから読み取れてしまうのです。














彼は父であるウィラードを嫌悪しており、遠ざけようとしているのですが、次第に自分が父の姿に重なっていくのを感じています。
例えば、アーヴィンは幼少の頃に父親が罵倒してきた相手に仕返しをしに行く場面を目撃しているわけですが、彼自身もまた妹をいじめた相手に徹底的な仕返しをするのです。
さらには、父親の形見である銃を使って、妹を自殺に追いやった変態牧師のプレストンを周到な計画を巡らせて殺害したわけですが、この目的のためならば手段を選ばない姿勢は父を思わせるものですよね。
父のウィラード何としてでも妻と一緒に生きたいと願い、愛犬を殺害して、神への生贄に捧げるという通常であれば考えられないような行動を取りました。
アーヴィンは、父を嫌悪し、ノッケンスティフから離れ、そしてキリスト教信仰からも距離を取り、何とかして父親の陰を払拭しようとしています。
しかし、どうしてもその影を振り払うことができず、次第に父親と自分の姿が重なっていき、物語の動線が最終的にノッケンスティフへと向かって行くのは何とも面白いですよね。
ノッケンスティフでウィラードによって描かれ始めた線が、アーヴィンによって閉じられ、まるで1つの「円」を描こうとしているかのような動線なのです。
結果的に、アーヴィンはノッケンスティフへと向かう過程で多くの人を殺害します。
父の死に場所でもある森でリー・ボーデッカー保安官と銃撃戦を繰り広げることとなったわけですが、この2人もどこか似た者同士の2人です。














そして先ほどまでは「復讐する側」にいたアーヴィンがこの戦いにおいては、翻って「復讐される側」の人間になっています。
まさしく自分が誰かに振るった暴力が形を変えて我が身へと降りかかって来るという円環の構図を端的に示した人間ドラマになっていたと言えるでしょう。
このように本作は徹底的に登場人物たちの縦と横の運命的なリンクを演出しているわけです。














先ほどの章で、今作のラストはアメリカが暴力の円環を断ち切ることができず、次のサイクルへと入っていくことを暗示した暗い結末であることを指摘しました。
しかし、このカーラジオを聴いているアーヴィンは様々な可能性を検討しています。
- 罪を許されて、祖父母の下へと戻れる可能性
- 父のように結婚して家庭を持つ可能性
- 軍に入隊してベトナム戦争で戦う可能性
そして物語は、アーヴィンが眠りにつき、そしてカーラジオが「次なる一手は…」とアナウンスしているところで突然幕切れます。
『悪魔はいつもそこに』という作品は、アーヴィンのこれからについて明確な結論を出すということはしていません。
『悪魔はいつもそこに』予告編より引用
しかし、アメリカという国が選択した道とは違う道を、彼が選択する可能性を確かに感じさせる結末になっているのです。彼には父が辿った道とは異なる道を選ぶチャンスがあります。
彼はヒッチハイクをして助手席に乗り込むわけですが、知らない人間の隣では眠りたくないと語っていました。














これが何を意味しているのかを考えるに当たって重要なのが、彼が誰かの隣で眠りたくない理由です。
その理由というのは、言うまでもなく直前に起きたカールとサンディの一件でしょう。アーヴィンは暴力を振るわれることを恐れるからこそ、助手席で眠ることを躊躇うのです。
では、眠ることを選択したラストシーンが何を意味しているのかと言うと、彼が「暴力」に対する不安や疑心から解放されたということなのかもしれません。
そう思うと、彼はきっとバックで流れるカーラジオが象徴するアメリカとは異なる物語を辿るはずです。
ノッケンスティフを離れるという動線を演出することで、アーヴィンは父が辿ったのではない、そして暴力に怯えるのでもない、自分だけの道へと再び繰り出していくことが仄めかされながら終わりを迎える、本作は暗い中にも微かな希望を確かに示してくれています。
いつしかアーヴィンは「暴力の円環」から抜け出し、幸福と平穏に包まれた生活を手に入れるはずだと、不確かながらも信じようと思わせてくれるそんな帰結なのです。
おわりに
いかがだったでしょうか。
今回は映画アーヴィンはについてお話してきました。














個人的にナレーションで心情や状況の説明をしてしまうと、解釈が固定化してしまうのでそれほど好きではありません。
役者の演技のレイヤーではすごく重層的に形作られている感情がナレーションのフィルターを通ることによって分かりやすくはなるのですが、同時に豊かさが失われてしまうという状況に直面してしまいます。
今作は聖書の要素を多分に取り入れた作品だったということもありますので、その点で説教師が聖書の記述を語っているかのような口ぶりで物語を展開したかったというのが本音でしょう。
Netflixにて無料で見られる分には、損をしたという感覚はない作品なのですが、それほど優れているというわけでもなく、何とも言えない映画ではありました。
あまり積極的にはおすすめしませんが、キャスト陣のファンの方などは見ておいても損はないでしょう。
特に変態牧師がロバート・パティンソンでしかもCVが櫻井孝宏さんなのは、ヤバすぎました。要チェックです。
今回も読んでくださった方、ありがとうございました。