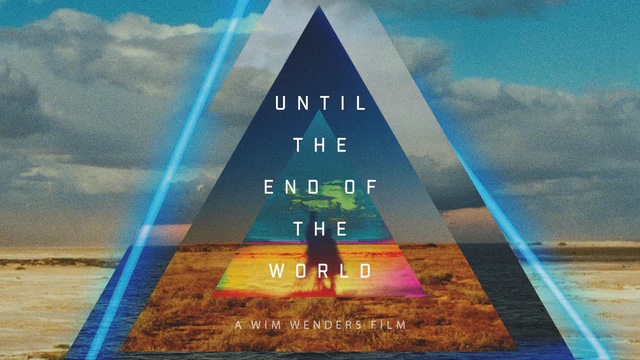みなさんこんにちは。ナガと申します。
今回はですね映画『望み』についてお話していこうと思います。

(C)2020「望み」製作委員会
ポスターのビジュアルが発表された時は、映画ファンからヒットしたからって『パラサイト』意識しすぎだろと呆れられていました。
では、実際に作品を鑑賞すれば、その妥当性が理解できるのかという疑問が生じるわけですが、正直あまり必然性はありません。
『パラサイト』は貧困をテーマにした作品であるわけですが、『望み』は全く違っていて、息子が犯罪に巻き込まれた時の家族に焦点を当てた作品です。
では、なぜビジュアルを『パラサイト』に寄せるような真似をしてしまったのでしょうか。
もちろん話題性という理由が大きいのでしょうが、実は微妙な共通点を見出すことはできるんですよ。
それが「家」というモチーフが作品の中で重要な役割を果たすという点です。
『パラサイト』では、「家」が経済格差を象徴しており、さらには家の内部の構造を活かし、登場人物の経済状況や置かれている状況を暗喩するという示唆的な演出が印象的でした。
一方で、『望み』においては「家」というモチーフが、そこで暮らす人たちのライフスタイルの象徴、「望み」の投影として描かれます。
また、主人公が建築家であり、自宅も凝った作りにしているということもありますから、その点で無理矢理『パラサイト』に共通点があると言ってしまえばそうなのでしょう(笑)













というのも、原作を著したのは、『犯人に告ぐ』や『検察側の罪人』などで知られる雫井 脩介さんなのです。
とりわけ2018年に劇場公開された『検察側の罪人』は映画版を木村拓哉さん主演で製作したこともあり、大きな注目を集めました。
雫井さんの作品は、2つの思いに揺れ動くキャラクターたちのその葛藤や信念にスポットを当てるのが非常に巧いんですよ。
『検察側の罪人』は、罪人を「正しく」裁くための不法行為が認められるのか?という問いを2人の検察官に突きつける内容となっていました。
そして、今作はもし自分の子どもが犯罪に関わっていたと分かり、家族の元へと戻って来るとしたら、「生きた加害者」としてか、それとも「死んだ被害者」としてか、どちらを「望む」かという究極の問いを突きつけられます。
大きな展開を用意するのではなく、淡々と息子が戻って来るのを待つ家族の日常に機微を切り取る本作は、異常なほどに「リアル」です。













さて、ここからは作品に関して自分なりに感じたことや考えたことを綴っていきます。
本記事は作品のネタバレになるような内容を含む感想・解説記事です。
作品を未鑑賞の方はお気をつけください。
良かったら最後までお付き合いください。
目次
『望み』
あらすじ
高校生の息子の規士と高校受験を控えた娘の雅を育てながら平穏に暮らしていた石川一登と喜代美夫婦。
一登はフリーの建築家として順調にキャリアを積んでおり、妻の喜代美はフリーの校正者として収入を得ており、その暮らしも安定していた。
規士は中学時代にサッカーで強豪ユースチームに所属していたが、高校では部活に所属。しかし、その部活中に先輩から悪質なタックルを受け、怪我を負い、サッカーを辞めることを決断した。
一方の、雅は、成績優秀で、有名な私立高校への進学を目指している。
ある日、規士がホームセンターで切り出しナイフを購入したことにより、家族に緊張が走る。
父の一登は、規士を諭し、そのナイフを取り上げて、自分の工具箱の中に収納した。
その明くる日、規士は夜更けに「ちょっと出かけてくる」と家を飛び出し、そのまま翌日になっても帰って来なかった。
さすがに息子のことが心配になった両親は、何とか連絡を取ろうとするのだが、電話もメールも繋がらない。
そんな矢先、家族に飛び込んできたのは、彼らの住む町で起きた凄惨なリンチ殺人事件だった。
そしてその被害者は、あろうことか規士の同級生で友人の男の子である。
事件の関係者の親だとして警察やマスコミからアプローチを受けるようになる一登と喜代美。
現場に残された1つの遺体。2人の逃走者。そして証言の中で明らかになったもう1人の犠牲者。合計3人の行方不明者。
果たして、規士は加害者なのか、それとも被害者なのか…。
スタッフ・キャスト
- 監督:堤幸彦
- 原作:雫井脩介
- 脚本:奥寺佐渡子
- 撮影:相馬大輔
- 照明:佐藤浩太
- 編集:洲崎千恵子
- 音楽:山内達哉
- 主題歌:森山直太朗













『トリック』シリーズや『SPEC』シリーズでおなじみの堤幸彦さんが今作の監督を務めています。
とりわけ彼の前作に当たる『十二人の死にたい子どもたち』は見るに耐えない酷い出来で、そのさらに前の『人魚の眠る家』は傑作だったということで、個人的には評価がイマイチ定まらない監督ではあります。
ただ、今作に関しては原作が非常に映像向きだと思いますし、演出がハマれば素晴らしい作品になるはずの題材です。
脚本に細田守監督作品を支えてきた奥寺佐渡子さんもクレジットされていることですし、個人的には今作に期待しております。
撮影・照明には『人魚の眠る家』の相馬大輔さんと佐藤浩太さんが起用されています。
個人的に『人魚の眠る家』の撮影ないし照明の使い方は優れていたと思っておりますので、非常に期待値が高いです。
編集には、堤監督作品ではお馴染みの洲崎千恵子さんが起用されていますが、ここはどうかな~?という半信半疑ではあります。
というのも前作の『十二人の死にたい子どもたち』は編集が完全に事故っていて、それが作品の出来の悪さに直結していた印象すらあるからです。
その他、劇伴音楽には山内達哉さん、主題歌には森山直太朗さん起用されています。
- 石川一登:堤真一
- 石川貴代美:石田ゆり子
- 石川規士:岡田健史
- 石川雅:清原果耶













まず、主人公である父親の一登を演じるのは堤真一さんですね。やっぱり父親役と言われると、当ブログ管理人は『三丁目の夕日』のイメージもあって彼がしっくりきます。
妻の貴代美役には石田ゆり子さんですね。今作で彼女が演じる役は、ぼんやりとしているように見えて、すごく芯が強く、事件で起き込まれる家の中で1人気を吐いて奮闘する役どころですので、適役だと思いますね。
また、2人の子どもの役には今若手俳優の中でも演技が高く評価されている岡田健史さんと清原果耶さんが起用されています。
前者は『中学聖日記』で注目され、後者は朝ドラの主演に抜擢されるなど既にその実力は同世代の俳優の中でもずば抜けているでしょう。
こんな4人が中心となって形作られて行く映画ということで、もう楽しみと言う他ないですね。













『望み』感想・解説(ネタバレあり)
家というモチーフと家族の「望み」
さて、記事の冒頭でも少しだけ触れましたが、本作『望み』においては「家」というモチーフが重要なものとして扱われます。
まず、主人公の一登が建築家であり、依頼者のライフスタイルや「望み」を鑑みて、理想の家を提供するという仕事をしているのが非常に示唆的です。
家というものは、まさしく家族の身の置き所であり、その生活の中心となる空間ですよね。
賃貸であっても、一軒家であっても、まずはそこに暮らす主体である人が、自分のライフスタイルや「望み」に基づいて決断を下していくことになります。
まずは立地や予算と言ったところもそうですが、もう少し踏み込むと外観、間取り、デザイン、そしてキッチンや風呂場と言った細部へのこだわりも生じてくるでしょう。
また、家族の場合であれば、家を購入または借りた当初とは違った生活様式になっていくこともあり、そうした変化への柔軟性や耐久性も求められることとなりますよね。
例えば、ペットを飼う、子どもができた、両親も同居することになった。どんなことが起こり得るかは分からないわけで、一軒家を建てたとなると、基本的にはその範疇で上手くライフスタイルをアレンジしていく必要があります。
つまり、「家」とは最初は住む主体の「望み」に基づいて建築・選択され、徐々に住む人間のライフスタイルに合わせて内部が独自の色に塗り替えられていくという特性を持っていると言えるのではないでしょうか。
この点については、本作『望み』の序盤に、主人公の一登がお客さんに案内をしている時に言っていた内容とも重なります。
そして、作品の中盤で1つの大きな事件が、主人公の家族に大きな変革をもたらすこととなります。
それが、息子の規士の同級生の殺害事件であり、さらに言うなれば、その事件に何らかの形で息子が関わっていることが判明するわけです。
ただ、事件が起きて、何とか息子と連絡を取ろうとするも、両親は自分の息子の交友関係なんかをほとんど把握していないことをまざまざと突きつけられます。
1つ屋根の下に暮らしていた「家族」のことを全くもって知らないのだと。
ここで、思い出したいのが、規士が一登の連れてきたお客さんに対して邪険な態度をとっていたことですよね。
「いきなり見ず知らずの他人が部屋に入ってきて、愛想よくしろって言うほうが無理あるし。」
(雫井 脩介『望み』より引用)













一登にとって自宅は生活の拠点であると同時に、生活費を稼ぐための建築家としての仕事における商売道具の1つでもあるわけです。
それが一登の「望み」であり、自宅はそれが反映された形となっているわけで、妻や娘の雅はそれに対して理解を示しています。
しかし、規士はそれを拒むような姿勢を見せており、ここに家族内の「望み」の対立が起きていますよね。
こうした現象が起きることにより、家族のライフスタイルにも当然変化が生じます。他の家族は規士の部屋にはあまり近づかないようになりますし、その結果として彼の部屋で何が起きているのかが不可視になっていきます。
そうなると、当然両親は、規士のことを少しずつ理解できなくなっていきますよね。
彼の自室というのは、言わば家の中にある彼にとってのもう1つの「家」であり、そこには彼の「望み」が投影されているはずです。
そんな「家」とのリンクが切れかかってしまうと、彼が今何を考えていて、何を望んでいるのかが分からなくなります。
このように「家」というものは、そこに住む人の暮らしぶりを体現するものであり、「家」そのものに家族の関係性までもが投影されていくのです。
作中で個人的に面白かったのは、事件が起き、息子が行方不明になったから、日を追うごとに家の中における妻の貴代美の存在感や凄みが増していくことです。
(C)2020「望み」製作委員会
というのも、基本的にこの家族に置いては父の一登の決定権が強かったのだろうということは何となく伺えます。
しかし、事件が起きて狼狽している彼を他所に、妻の貴代美の方が腹をくくり、息子が加害者として帰って来た時のことを想定した行動を開始したのです。
一方で一登はいたずらによって汚された家の外観の掃除や修復に並々ならぬこだわりを見せるなど、今の「家=ライフスタイル」へのこだわりを強く見せています。
彼が、息子が加害者だった際の心配事として、真っ先に自分の仕事やキャリアが失われることを頭に浮かべているのも印象的です。













今の家へのこだわりを強く表出させている一登とは対照的に、自分の校正業務の稼ぎでひっそりとした家で息をひそめて暮らすのも悪くないと、新しい暮らしの形までも考慮に入れているのが貴代美でした。
彼女は、「息子が加害者として事件に関わる」という変革を前にして、それに応じた自分たちの新しい「家=ライフスタイル」を既に模索し始めているわけです。
今作の面白さは、「家」というモチーフを主軸に据え、「家」と人間の向き合い方や関係性の変化によって、登場人物の思考・感情とその変化を表出させている点にあると言えます。
その点では確かに「家」が演出面で機能する作品であり、『パラサイト 半地下の家族』と共通していると言えなくもないのかもしれません。
本作が描く葛藤や苦悩のリアルさ
私が『望み』という作品を鑑賞していて、すごく重要だと感じたのは、物語を語っていく「視点」なんですよ。
というのも、この手の事件の加害者・被害者に焦点を当てる作品では、視点をその双方に分散させたり、客観的な視点を取り入れてマスコミや日本の「容疑者」の在り方を批判したりといった様々なアプローチが為されてきました。
つまり、観客には客観的かつニュートラルな視点を与えることによって、自分を主体としてその主題性やメッセージ性について考えさせるという手法です。
では、本作『望み』における視点がどうなっていたかを考えますと、それはひたすらにあの「家」の中に置かれていました。
要は、加害者側の視点であったり、中立的な語り手的(神的)ポジションの視点であったりといった他の視点というものの混じり気がなく、視点が「家」にほとんど固定されています。
(C)2020「望み」製作委員会
例えば、娘の雅が塾で同じ志望校を志しているライバルに嫌味を言われたなんて話も、実際にその現場を描くのではなく、家に戻ってきた彼女による「話」として「家」の中に持ち込まれました。
また、今作の主人公の家族は積極的に息子を捜索するという姿勢は取らず、基本的には「家」でじっと待っているという状況になります。













しかし、自分の子どもがいざ事件に巻き込まれたとなっても、何もできないのがその実だと思いますし、個人的にはその方がリアルに近いような気がしました。
そのため、息子の捜査に関する情報が基本的には「受動的」にしか流入してこないというのが面白いんですよね。
例えば、家にやって来た記者からの断片的な情報であったり、テレビから流れてくる情報であったり、親族や友人からの電話であったりと、基本的に「家」に入って来る情報しか彼らはキャッチすることができません。
加えて、多くの作品では批判的な視線を向けられるのが、事件の被害者や加害者に群がるマスコミなのですが、今作ではかなりニュートラルに描かれています。
過剰に彼らを批判的に描くようなことはしておらず、ただシンプルに主人公の家族のライフスタイルを脅かす存在として描くことに徹したのです。













それは、本作が事件の真相そのものにスポットを当てた作品ではないからです。
この手のミステリー性のある作品では、どうしても鑑賞する側が「結果=真実」を求めがちですよね。













確かにそうなんです。ただそういう視点で見るならば、この『望み』という作品は何とももどかしい作品になるはずです。
なぜなら、主体的に「真相」に近づこうとしていく人間が主人公の家族にはいないからですよ。
ミステリーにおいては基本的に謎を解く側の人間がいて、その人物が主体的に真相に迫ろうとアプローチが楽しいのであり、その行為に読み手の「真相が知りたい」という心理が重なることで物語の推進力を生み出します。
しかし、今作『望み』は主人公の家族はひたすらに警察の捜査の進展を待っている状態であり、主体的に動くことはほとんどありません。
それ故に、早く真相に辿り着きたい読者は、ひたすら待たされることになり、じれったい思いを抱え込むことになります。
ただ、これこそが観客とキャラクターの心理をリンクさせるための作者の1つの狙いなんでしょうね。
つまり、真実を早く知りたいというミステリー作品の読者の心理を逆手に取り、それを利用して主人公の家族があの「家」の中で経験している時間の長さや「待つ」という行為による疲弊を追体験させてくれるのです。
そして何より、本作が「家」の中に視点の大半を置いたのは、事件の情報が漏れ伝わってくる過程で、主人公たちの「ライフスタイル」がどう変化していくのかを描くことに主眼を置いたためでしょう。
(C)2020「望み」製作委員会
例えば、先ほど話題に挙げた妻の変化はその最たるものであるわけですが、他にも彼女の構成の仕事の進捗であったり、娘が部屋に籠りがちになったり、一登が悪夢にうなされてねむれなくなったりと、彼らの生活のディテールの変化に本作は焦点を当てています。
マスコミの描き方だってそうで、彼らの存在そのものの在り方を問うというよりはむしろ、彼らの存在が主人公の家族のライフスタイルをどう変化させるのかに本作の主眼が置かれています。
例えば、犬の散歩に生きづらくなる、買い物に行きづらくなる、窓のカーテンは常に閉めておかなければならなくなると言った具合にマスコミの存在は彼らの生活に少なくない変化をもたらしました。
『望み』という作品の面白さは、「生活感」に目を向けたことだと個人的には思います。
1つの家族を揺るがす事件を契機とし、そこから漏れ伝わってくる情報や周囲の人から向けられる視線が、彼らの生活をどう変えていくのか?
それを追ったある種の実験的な試みなのです。
だからこそ、劇的な展開や変化は少なく、小さな変化の積み重ねが繊細に描かれていきます。
しかし、そうした姿勢こそが本作の妙なリアリティを支えるものであり、私たちが思わずあの家族と同じ空間で、同じ問いかけに悩んでいるかのように錯覚させられてしまう理由なのでしょう。
ぜひ、あの「家」の中で流れていく、ひりつくような「空気」を肌で感じて欲しいです。
クライマックスで示される「望み」の双方向性
さて、本作の終盤の展開は胸が締め付けられるような苦しい展開が待っているわけですが、そこで描かれるのは、「望み」の双方向性であり、それにより形作られる「家族」であります。
今作においては、主人公の家族3人の規士に対する「望み」がひたすらに描かれました。
父の一登は、とにかく規士には「加害者」であって欲しくないという思いを強く持っています。一方で妻の貴代美は息子には「加害者」としてでもいいから生きていて欲しいという思いを強く持っています。
そんな中で妹に当たる雅は、兄が「加害者」になることにより、自分の人生に少なくない影響が出ることを憂慮していました。
彼らはそれぞれ規士に対して違った「望み」を抱き、この齟齬によって家族のカタチは揺れ、少しずつ壊れていくのです。
そうして真相が明らかになり、息子の規士は被害者であり、既に死亡していたという事実が家族に突きつけられます。
- 自分の「望み」が望んでいなかった形で実現してしまった父。
- 自分の「望み」とは正反対のことが起きてしまった母。
- 自分の「望み」そのものが罪になってしまった妹。
彼らは、それぞれに規士に「望み」を抱き、それに対する懺悔をすることとなるのです。
しかし、本作が構成として非常に素晴らしいと感じたのは、クライマックスの局面でこれまで「望みの器」としてのみ描かれてきた、規士自身の「望み」を明らかにする点なんですよ。
(C)2020「望み」製作委員会
そして彼の「望み」を象徴するのは、彼の「家=自室」に置かれたリハビリのインストラクターとして働くための教則本と持ち出されたかに思われた切り出しナイフの2つです。
前者は、これまで父が規士に対して抱き続けてきた「望み」へのアンサーになっています。
そして後者は、規士が自分のことだけでなく家族のことまでも考えて、自分の身の振り方を選択したことの証明です。
これも言わば父が規士に対して抱いていた「望み」に対するアンサーです。
「父さんが何か注文をつけるとするなら、他人様に迷惑をかけるような真似はするなということだ。それさえ守ってくれれば、何をやって生きていくかはお前の自由だ。」
(雫井 脩介『望み』より引用)
そして、母親が規士に対して抱いていた願いや「望み」に応じる行動を示すものでもありました。
「望み」というものは、非常に難しいもので、親は子に「望み」をかけるわけですが、子どもがそれに応えてくれないケースというのは非常に多いわけですよ。
つまり、「望み」というものは一方向的に存在することはできません。
それは冒頭に一登の建築スタジオを訪れたお客さんが自分たちの希望ばかりを言ってなかなか家のカタチが定まらなかったのと同様です。
「望み=理想の暮らし」と「望まれる=ライフスタイルから導き出される暮らし」の双方向性が実現することで形になるのが「家」なんですよ。
だからこそ、本作のラストでは、家族から向けられていた「望み」に対して、規士本人の「望み」が明かされることで、その双方向性が実現します。
結果的に彼の「望み」が壊れかけていた家族を救いました。
残された家族は自分たちの「望み」とそして規士に「望まれたこと」の狭間で生きていくこととなります。
それこそが本作の中で彼らに示される新しいライフスタイルです。
規士が家族から欠けてしまったことで、未来の石川家のリビングは、照明が落ち、ぼっかりとした隙間が目立ち、温度の上がらないものになってしまった。
(雫井 脩介『望み』より引用)
人は「望むこと」と「望まれたこと」も狭間でもがきながら生きていくしかありません。
その葛藤をこれほどまでに克明に描き出し、鑑賞した私たちに深く考えさせる本作は素晴らしいと言う他ないでしょう。
おわりに
いかがだったでしょうか。
今回は『望み』という作品についてお話してきました。
ここまでお話してきたように本作において重要なのは、視点の置き方と「家」というモチーフです。
そしてこれらは、映画という可視のメディアに落とし込んだときに、必然的に演出や撮影といったセクションで重要になってきます。













一方で、これらの原作を支える要素が上手くハマれば、本来であればこの作品は映画向きであると思っておりますので、とてつもないパワーを持つ作品になることでしょう。
やってはいけないのは、キャラクターのエモーションの部分にだけ寄り添うような作品にしてしまうことでしょうね。それでは平凡な作品になってしまいます。
大切なのは、事件がもたらす彼らの「家」の変化であり、そのディテールの部分です。
ここをどこまで描けるかが映画版の焦点になるでしょう。
今回も読んでくださった方、ありがとうございました。