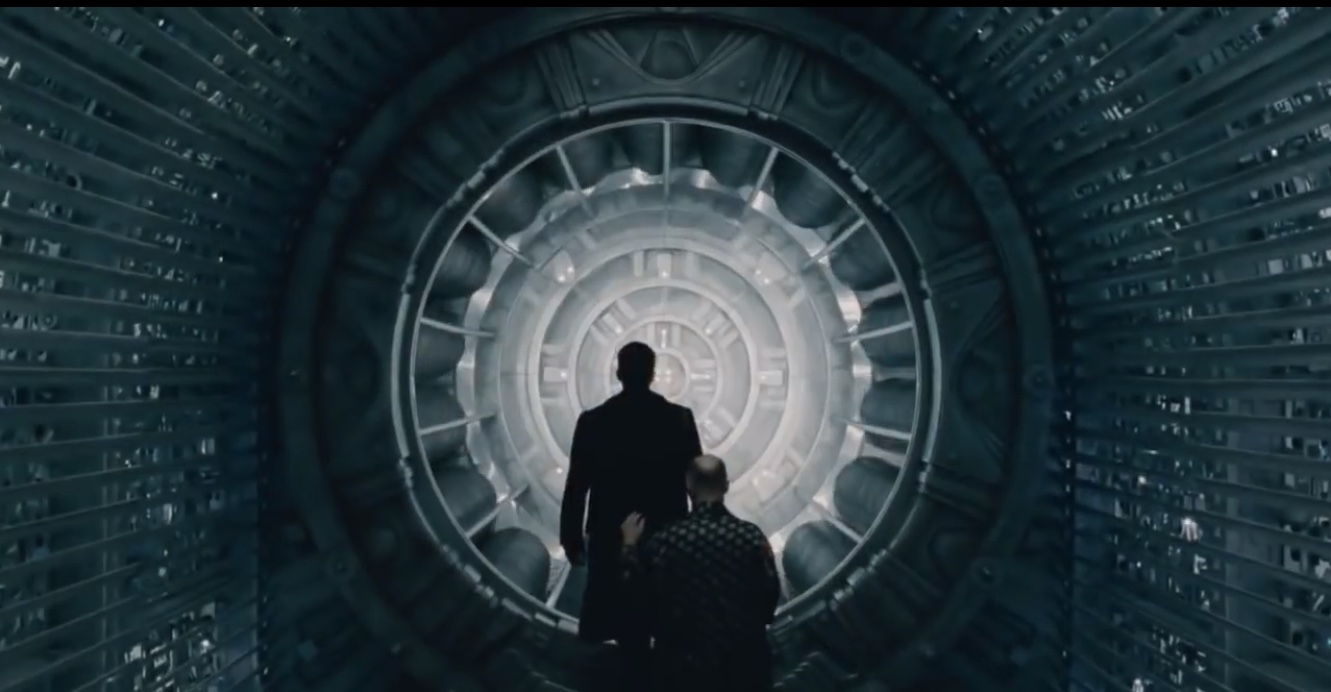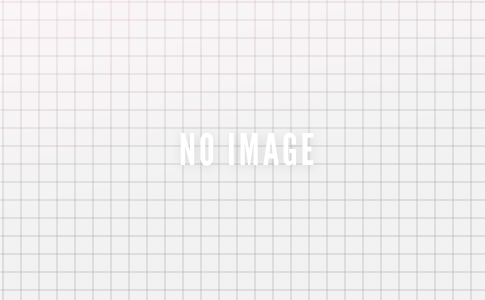みなさんこんにちは。ナガと申します。
今回はですね映画『Mank マンク』についてお話ししていこうと思います。

Netflixでは12月上旬に配信スタートということですが、一部の劇場では11月20日より先行上映ということで、もちろん鑑賞してまいりました。
デヴィッド・フィンチャーと言えば、みなさんはどんな作品を思い浮かべますか?
やっぱり『セブン』?いや、そこは『ファイトクラブ』?いやいや『ドラゴンタトゥーの女』だろ?
と、みなさん自分の印象に残った作品を思い浮かべることと思いますが、不思議なことにほとんどの作品が高い評価を受けていて、いわゆる「ハズレ」のない監督なんですよ。
しかし、無難な映画を作っているというわけではなくて、どれも映像的にもプロット的にも攻めた内容であり、それ故に世界中の映画ファンから高く評価されています。













ええ…もちろん。それは彼のデビュー作でもある『エイリアン3』です。
フィンチャーは自分のフィルモグラフィーから同作を排除するほどに、この作品に強い後悔を抱いているようです。
商業映画デビュー作で、いきなりリドリー・スコットの1作目、そしてジェームズ・キャメロンの2作目に続く『エイリアン』シリーズの3作目を任されるのは、とても名誉なことだったでしょう。
しかし、彼は意気込んでこの作品の撮影に臨むのですが、これが上手くいかず、どんどんと空回りした挙句に、満足のいかない状態で公開される運びとなります。
小規模映画と大規模映画って作品作りのプロセスが全くもって異なるので、小規模からいきなり大規模作品を任されると、彼のように失敗してしまうケースは少なくありません。
当ブログ管理人が大好きなヴィム・ヴェンダースもドイツで人気を博し、フランシス・フォード・コッポラ監督に招かれ、アメリカで『ハメット』という大作を任されるのですが、これが全く上手くいかず、一時はハリウッドから撤退するに至りました。
フィンチャーはインタビュー等でもNetflixの映画作りに対する姿勢に好感を示しており、今回は通ると思っていなかった脚本を通してもらい、さらには6か月以上の潤沢な撮影期間を与えられ、のびのびと映画作りに取り組めたのだとが。
映画作りというものは、やはり監督だけの力ではどうしようもないわけで、いかに環境や周囲のサポート体制が重要なのかということを考えさせられますね。
さて、ここからは本作『Mank マンク』に話題を移していきます。
サラっと触れておくと、本作はオーソン・ウェルズの『市民ケーン』の脚本家であるハーマン・J・マンキーウィッツに関する物語となっているようです。
同作への映像的なオマージュ要素も多いため、ぜひ鑑賞前に『市民ケーン』を予習・復習しておくと良いでしょう。
本記事は作品のネタバレになるような内容を含む解説・考察記事となります。
作品を未鑑賞の方はお気をつけください。
良かったら最後までお付き合いください。
目次
『Mank マンク』
あらすじ
ハーマン・J・マンキーウィッツ(マンク)はハリウッドの嫌われ者であり、30年代前半に数多くの作品の脚本・脚色を手掛けたが、徐々に仕事が減ってしまっていた。
経済的にも苦しくなってきたある日、新鋭の映画監督であるオーソン・ウェルズから自身の監督作の脚本を執筆してくれないかという依頼が舞い込んでくる。
その依頼は、新聞王ウィリアム・ランドルフ・ハーストをモデルにした脚本を書いて欲しいというものであり、同時にウェルズは脚本にマンクをクレジットしないことを条件に盛り込んでいた。
脚本に取り掛かる直前に事故で足を負傷したマンクは世話係が必要という事情もあり、砂漠の牧場で缶詰め状態の中、僅か60日間で脚本を仕上げることを要求される。
彼は、映画業界に身を置く中で経験してきたことに思いを馳せながら、徐々に作品を仕上げていく。
ウィリアム・ランドルフ・ハーストとその愛人マリオン・デイヴィス。カリフォルニア州知事選挙を巡るハーストの陰謀と映画業界の加担や罪。
それらに対する痛烈なアンチテーゼとして形作られていった、後に『市民ケーン』と題されることとなるその脚本は圧倒的な完成度であり、ウェルズも満足する。
しかし、いよいよ映画の公開に向けて動き出した時に問題が起きる。
モデルになったウィリアム・ランドルフ・ハーストが製作・配給会社に圧力をかけてきたのである…。
スタッフ・キャスト
- 監督:デヴィッド・フィンチャー
- 脚本:ジャック・フィンチャー
- 撮影:エリック・メッサーシュミット
- 美術:ドナルド・グレアム・バート
- 衣装:トリッシュ・サマービル
- 編集:カーク・バクスター
- 音楽:トレント・レズナー アティカス・ロス













近年のNetflixオリジナル映画の気合の入り方は尋常ではないですよね。昨年の賞レース直前にはマーティン・スコセッシの新作『アイリッシュマン』も公開され、話題になりました。
どんどんと有名監督が参戦してくるNetflix戦線における、新たな刺客として選ばれたのは、デヴィッド・フィンチャーですね。
『セブン』『ファイトクラブ』『ソーシャルネットワーク』など映画ファンであれば、誰でも知っている名作たちを作り上げてきた人物です。
フィンチャーは『ソーシャルネットワーク』という作品に、『市民ケーン』への強い憧れを込め、その構成や演出等に関してオマージュ要素をたくさん散りばめてあります。













そして、今作の脚本を著したのは、2003年に他界した実父ジャック・フィンチャーなんだそうです。彼が生前に執筆した脚本をベースにこの『Mank マンク』が作られたというわけです。
撮影には、エリック・メッサーシュミットが起用され、『市民ケーン』のグレッグ・トーランドや写真家のアンセル・アダムスに影響を受けたと語っているようですね。













編集には『ベンジャミンバトン』以降のフィンチャー作品を語る上では欠かせないカーク・バクスターがクレジットされ、劇伴音楽では『ソーシャルネットワーク』でアカデミー賞作曲賞を受賞したトレント・レズナーとアティカス・ロスが再びタッグを組みます。
- ハーマン・J・マンキーウィッツ:ゲイリー・オールドマン
- マリオン・デイヴィス:アマンダ・サイフレッド
- ウィリアム・ランドルフ・ハースト:チャールズ・ダンス
- リタ・アレクサンダー:リリー・コリンズ
- ルイス・B・メイヤー:アーリス・ハワード













そのキャリアにおいて、何度も圧倒的なまでの怪演を披露し、観客の度肝を抜いてきたゲイリー・オールドマンが今作の主人公を演じます。
アルコール依存症に苦しみながら『市民ケーン』の脚本執筆に追われるという独特の役どころであるわけですが、今回もどう演じてくれるのか楽しみで仕方がありません。
どことなく『ウィンストンチャーチル』での出で立ちを思い出したりもしますので、併せてチェックして見て欲しいです。
女性のキャスト陣を見てみますと、『しあわせの隠れ場所』でデビューし、『あと1センチの恋』などで知られるリリー・コリンズや『マンマ・ミーア! ヒア・ウィー・ゴー』のアマンダ・サイフレッドらが起用されています。
デヴィッド・フィンチャー最新作ということで、非常に豪華な顔ぶれとなっており、彼らがモノクロの映像の中でどんな世界観を作り上げてくれるのか要注目です。













『Mank マンク』解説・考察(ネタバレあり)
現実のような映画VS映画のような現実
Netflix映画「Mank マンク」より
本作『Mank マンク』は、ウィリアム・ランドルフ・ハーストによる圧力ないしそれに屈した映画業界に対する痛烈なアンチテーゼであり、その象徴として『市民ケーン』という作品を位置づけました。
物語はマンクことハーマン・J・マンキーウィッツがオーソン・ウェルズからの依頼で脚本に着手するところから始まります。
アルコール依存症で酒が手放せない彼は砂漠の牧場に居ながらも、何とか酒を飲み、酔いと眠りの中で自らが映画業界で経験した様々な出来事をナラタージュしていくわけです。
この現在軸の進行に回想をインサートしていくというフラッシュバックの手法は、オーソン・ウェルズが『市民ケーン』で用いたものであり、デヴィッド・フィンチャーは極めて意図的にこの構成を採用したと言えるでしょう。
ただ、この構成が『市民ケーン』と同じ意味合いで用いられているかと言われると、少し違っていて、今作に『Mank マンク』おいてはマンクの頭の中の思考プロセスを垣間見ているかのような味わいがあります。
その回想の中で描かれるのは、彼がなぜハリウッドから「嫌われている」のかやカリフォルニア州知事選挙を巡る映画業界の功罪についてです。
彼は、脚本家としては非常に高く評価されており、信頼も厚かったのですが、ハリウッドの大きな流れからは少し外れた言動やアルコール依存症が原因で、人間的に嫌われていました。
そして、ハリウッドとマンクの確執が思わぬ形で表出してしまうのが、1934年のカリフォルニア州知事選挙です。
候補者の1人であったアプトン・シンクレアは社会主義者であり、アメリカ精肉産業での実態を告発した『ジャングル』などの著作で知られる活動家でした。
そんな彼が民主党の候補として当時のカリフォルニア州知事選挙に出馬します。
カリフォルニアに大規模な土地や財産を有し、さらに当時の世界恐慌で自身の富が減少の一途にあったハーストは当然、この動きに目をつけ、徹底的に圧力をかけて行きます。













ただ、そんなハーストの圧力に加担してしまったのが、当時の映画業界だったんですよね。
MGMを初めとする映画業界は、ハーストの圧力を受けて、世論を扇動するような「現実のような映画」を作ることとなり、そのニュース風の映画はたちまち拡散され、知事選挙を巡る世論を扇動しました。
劇中でシェリー・メトカーフという男が、ちょうど映画の仕事に困っていることから目を付けられ、MGMのプロパガンダ映画に加担させられます。
これって、もはややっていることは劇中でも言及されていましたが、ヒトラー政権と同じなんですよね。
ヒトラー政権でも体制批判的な映画は検閲にかけられて徹底的に排除され、逆に政府主導で政権を賛美するような作品が多く作られました。
そうした映画が政治のための道具に使われるという歴史がハリウッドにもあったのだという点を、本作はマンクの視点から暴き出しているわけです。
シェリーはすごく純粋な男であり、映画人であったため、このようなプロパガンダ映画を作り、結果的に世論を誘導して、シンクレアの敗北に寄与してしまったことを恥じて自殺を選択してしまいます。
マンクがこの一件に只ならぬ怒りを覚えており、この一件に関わった映画配給会社の人間やさらにその上に君臨するハーストに復讐の念を抱いていたのは、映画からも分かる通りです。
アメリカという国は、その建国の経緯から考えても、「幻想の国」という側面が強いとされます。
しばしば、政治はショーと化し、フィクションと化し、現実との境界を曖昧にしていくわけですが、アメリカ国民はそうした現実と虚構を同列に扱う傾向があるんですよ。
カート・アンダーセンは自身の著書である『ファンタジーランド 狂気と幻想のアメリカ500年史』において次のように語っています。
権威ある専門家が何と言おうと、自分たち一人にこそ、何が真実であり何が真実でないかを決める権利があると考えるようになった。それどころか、情熱的で空想的な信念が何につけても重要なのだと思い込むようになった。
カート・アンダーセン『ファンタジーランド 狂気と幻想のアメリカ500年史』
アメリカ国民には、建国来のマインドとしてこうした傾向があり、例え虚構や幻想であっても、自分自身が信じたのであれば、それを「現実」と認識してしまうようなところがあると同書では綴られています。
『Mank マンク』の劇中で、マンクが映画『キングコング』を例に挙げながら、人々は映画の中で描かれた幻想を信じ込んでいると語っていました。
この言葉には、映画というものが果たすべき責任のようなものが内包されており、とりわけ本作は「現実のような映画」が政治に関わってしまうことへのアイロニーだと解釈できます。
「現実のような映画」によって人々を扇動し、政治を捻じ曲げてしまうことに、純粋に映画というものの力を信じているマンクは強い怒りを覚えたのでしょう。
だからこそ、彼は『市民ケーン』という作品の脚本を書くことに必然性があったのだと、本作は結論づけていきます。
『市民ケーン』はウィリアム・ランドルフ・ハーストをモデルにした新聞王ケーンを描いたフィクションなのですが、これが紛れもない「現実」だったりするわけです。
そこには、マンクが映画業界で過ごし見聞きしてきた様々な出来事が込められており、フィクションのようであり、しかしどこまでも現実であるという体裁をとっています。
当然、ハーストはこんな映画が作られてしまってはたまらないですから、圧力をかけますよね。
しかし、その頃既に全盛期ほどの財力も権力も持ち合わせていなかったハーストは、映画の公開を止めることができず、結果的に『市民ケーン』は1941年に封切られます。
ただ、公開され、識者から高く評価され、アカデミー賞に9部門ノミネートしながらも、批評家への圧力が徹底的にかけられていたため、本作は脚本賞以外の受賞を逃します。
しかも、当時の大衆の評価はマンクではなく、オーソン・ウェルズに注がれ、マンク自身は共同執筆者として脚本賞を受賞しながらも日の目を浴びることがありませんでした。
だからこそデヴィッド・フィンチャーは、今一度映画界の過去の罪とそして失われてしまった名誉を取り戻すべく、今作を撮ったのでしょう。
かつてのハリウッドでは確かに「映画のような現実」が力を持っており、それが知事選挙を不当に扇動したり、アカデミー賞の結果を歪めてしまったりと言った黒歴史に繋がったわけです。
そんな映画業界やハーストに対して、「映画のような現実」を携えて戦いを挑んだのは、オーソン・ウェルズもそうですが、その脚本を手掛けたマンクだったのです。
もちろんこの『Mank マンク』という作品にも多くの脚色が含まれますし、全てが真実としては描かれていません。













それでも、本作はハリウッドが過去に犯した罪を現前させ、その中で埋もれ、消されていった本当に映画を愛した者たちの「声」を取り戻そうとしています。
だからこそ、本作はデヴィッド・フィンチャーなりの映画讃歌なのでしょう。
マンクにとっての「バラのつぼみ」とは何だったか?
Netflix映画「Mank マンク」より
さて、先ほども書きましたが、本作はオーソン・ウェルズの『市民ケーン』の舞台裏についても言及されています。
基本的な世間の認知としては、『市民ケーン』の主人公である新聞王ケーンのモデルになったのは、ウィリアム・ランドルフ・ハーストです。
その一方で、世間で本作の脚本を担当したのがオーソン・ウェルズであるという認識が強いことから、この主人公には、オーソンらしさもあるだなんてこともしばしば批評されます。
ただ、デヴィッド・フィンチャーが今作『Mank マンク』で描いたのは、極めて真剣な「市民ケーンのモデルはマンク説」なんですよね。
基本的に、この映画は事実と映画としての脚色が混在しており、事前情報なしで鑑賞すると、ここに描かれていることが全て真実なのではないかと錯覚してしまうほどです。
まず、本作の脚本ができあがっていった経緯ですが、これも微妙に脚色されているのです。
実際には、マンクが足を負傷し、そこからしばらくはオーソンらと共に物語に関する会議の場を持ち、足の怪我が治った頃にハーストを題材にした映画を作ろうという方向性が固まり、砂漠の牧場での執筆が始まるという流れだったそうですが映画版は少し異なります。
今作『Mank マンク』では、マンクが負傷したまま牧場へと送られ、ウェルズは『闇の奥』の撮影で忙しいからと、脚本をマンクにほとんど一任しているのです。
そのため、何度かウェルズから「何について書いているんだ?」という類の質問が電話越しに聞こえてくるわけですが、マンクは完成するまでそれを明かすことはしませんでした。
映画の冒頭に「Tell Your Own Story.」というセリフがありましたが、そういった言葉の意味通り、マンクは自分の人生を回想しながら、物語を綴っていきます。
これが本作『Mank マンク』の全体的な作品構造にもなっているわけですが、そういったきっかけの描き方から推察しても、やはり本作は『市民ケーン』のモデルはハーストであり、同時にマンク自身なのだという説を全力で描こうとしているように思えるわけです。
『市民ケーン』のザナドゥ城とマンク自身が脚本を執筆したとされる砂漠の牧場に不思議なリンクを見出すことができるのもそのためです。
ハリウッドの黄金期にいながら、その立ち回りのせいで「道化」として軽んじられ、徐々に片隅へと追いやられていったマンク。そして砂漠の牧場では、ほとんど来客もなく、妻と数人の世話係に囲まれた寂しい生活を送っている。
そんな境遇が、ザナドゥ城で孤独な生活を強いられていたケーンの姿に重なるのは、きっと偶然ではないはずです。
「道化」として駆り出され、良いように使われ、決して後世には名前が残らない。彼はそんな日陰を歩き続ける宿命を背負っていました。
『市民ケーン』の脚本の件だってまさしくそうであり、彼が脚本を書いたにもかかわらず、クレジットが出なければ、全てオーソンの手柄にされてしまいます。
しかし、金銭的に苦しく、アルコール依存症に苦しんでおり、業界からも見放されていたマンクは、クレジットされないという条件をも飲んで、執筆を始めました。
ただ、作品が出来上がり、自分でも驚くようなその出来栄えについて思いを馳せていくうちに、そして「道化」だと軽んじられてきた自分の人生を思ううちに、これではダメなのだと改心します。
そこで、彼が取った行動が、『市民ケーン』の脚本クレジットに名前を掲載して欲しいと懇願することだったわけです。
彼がハーストの城で1934年のカリフォルニア州知事選挙でのハーストの行動とドン・キホーテを組み合わせた『市民ケーン』のプロトタイプを語るシーンがありましたよね。













一方で、このシーンで彼が語っていたのは、悪者が悪者のままでいられるのは、現実世界だけであり、映画の中では何らかの反省や罰が与えられなければならないと語っています。
それを反転させて考えると、マンクのような人物が、道化のままで扱われてしまうのは、あまりにも悲惨であり、だからこそ彼にはふさわしい名誉と地位が与えられるべきなのではないかという考えにも至ります。
『市民ケーン』という作品において注目すべきなのは、「バラのつぼみ」というキーワードです。
同作の中では、「バラのつぼみ」はケーンが幼少期に両親の元を離れる際に残してきた子ども用のそりの裏側に書かれた言葉として描かれました。
つまり、「バラのつぼみ」というのは、ビジネスで成功し、全てを手に入れたかに見えるケーンという男が唯一どうしても手に入れられなかった両親からの愛を象徴する言葉なんですよね。
そういう意味では、マンクにとっての「バラのつぼみ」は、やはり道化としての立ち回りや役割を強いられてきたがために、得ることができなかった脚本家としての名声や評価なのでしょう。
結果的に『市民ケーン』の脚本家として彼は名を連ねることになりましたが、現実世界においてその名声も評価もオーソン・ウェルズの方へ降り注ぐ結果となり、彼は日陰から出ることは叶いませんでした。
それでも、この『Mank マンク』では、彼が得ることのできなかった「バラのつぼみ」を自らの手で取り戻すような結末が描かれています。
「道化」として軽んじられてきた彼が、オスカーを手にし、インタビューに答える姿。
『市民ケーン』の劇中ないし、それを巡る現実では「バラのつぼみ」をついぞ手に入れることが叶わなかったマンクはこの映画のラストで、それを手に入れるのです。
誰かの言いなりではない、自分自身の作り上げた物語に対する正当な評価を得る。
これこそがマンクの望みであったのだと、彼にとっての「バラのつぼみ」だったのだと。
『市民ケーン』という映画は、そもそも新聞王ケーンが遺した「バラのつぼみ」という言葉の意味を探る物語となっていました。
そう考えると、このの『Mank マンク』という映画は、デヴィッド・フィンチャーなりのマンクの「バラのつぼみ」に関する1つの解釈であり、謎解きなのでしょうね。
おわりに
いかがだったでしょうか。
今回は映画『Mank マンク』についてお話してきました。













とりあえず『市民ケーン』と『ザ・ディレクター [市民ケーン]の真実』は見ておくと、かなり話がスッと入って来るんじゃないかと思いますね。
とりわけ前者は、映像や演出の部分でもオマージュ要素が散見されますので、見ておくと相乗効果でより作品を楽しめると思います。
また、ウィリアム・ランドルフ・ハーストに関する書籍なんかも発売されていますので、こちらをチェックしておくのも良いでしょう。
とにかく登場人物が多く、当時の映画界とそして政治の繋がりなんかにも言及しながら話がサクサクと進んでいくので、こういった予習をしておくことで随分と理解度が違ってくるはずです。













今回も読んでくださった方、ありがとうございました。