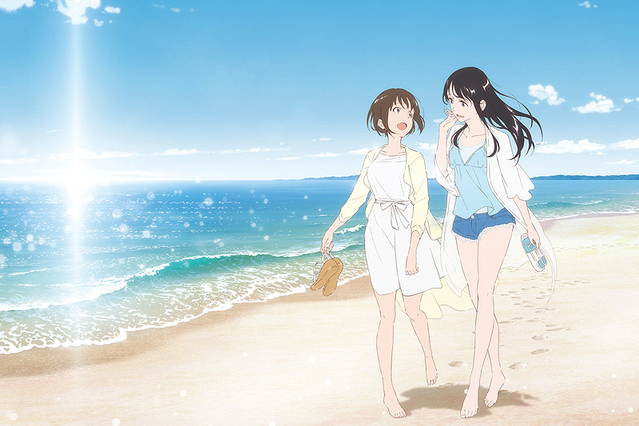みなさんこんにちは。ナガと申します。
今回はですね映画『燃ゆる女の肖像』についてお話ししていこうと思います。

さて、クィアパルム賞と聞くと、「なんだそれ?」と思う方も多いかもしれませんが、これはカンヌ国際映画祭においてLGBTやクィアをテーマにした映画に与えられる賞です。
クィアという言葉は、セクシュアルマイノリティの総称としても用いられますが、近年の社会の流れを受けて、カンヌ国際映画祭では、そうした題材を扱った作品を評価するべく、2010年より同賞を選出しています。
過去にはグザヴィエ・ドラン監督の『わたしはロランス』やトッド・ヘインズ監督の『キャロル』などが受賞したことでも話題になりました。
また同賞に加えて、脚本賞も受賞しているということで、今作が如何に高く評価されているかということが分かりますよね。
さて、この『燃ゆる女の肖像』という作品は、1枚の絵画を巡る回想劇を主体にしています。主人公のマリアンヌが描いた1枚の「燃ゆる女」の肖像画にはどんなバックグラウンドがあったのかを探るラブストーリーなのです。
そして、本作を見る上で欠かせないのが、「オルフェウス」の物語ですね。
彼の妻エウリュディケーが毒蛇にかまれて死んだことが契機となり、死んだ妻を取り戻すべくオルフェウスが冥府に下ったというのは、有名なエピソードです。
もちろん作品の中でも、この「オルフェウス」の物語についてはある程度説明はしてくれるのですが、それでも事前に知っておくと作品を深く味わうことができると思います。








また、本記事では作品を鑑賞した方向けに、ネタバレありの解説や考察を書いていきます。ぜひ作品鑑賞後に読んでいただけると嬉しいです。
良かったら最後までお付き合いください。
目次
『燃ゆる女の肖像』
あらすじ
画家のマリアンヌは、絵画の格子として、門下生たちに肖像画の指導をしていた。
そんな時、生徒の1人が教室に飾られた1枚の「燃ゆる女」の肖像画を見つけ、その絵について尋ね始める。
マリアンヌは、その絵に秘められた過去を静かに回想し始める。
ブルターニュの貴婦人から娘エロイーズの見合いのための肖像画を依頼され、孤島に建つ屋敷を訪れたマリアンヌ。
しかし、エロイーズは見合いを頑なに拒んでおり、以前にやってきた男性の画家は結局肖像画を描くことを断念して、島を後にしてしまったのだという。
夫人は、見合いのための肖像画だと明言してしまうと、また娘が警戒心を持つだろうと推察し、マリアンヌにまずは一緒に行動して信頼関係を築き、その中で見た彼女の姿を肖像画に落とし込んで欲しいという無茶な依頼をする。
難しい依頼だと分かりながらも、引き受けた彼女は、孤島の海岸でエロイーズと行動を共にするようになり、次第に彼女に惹かれていく。一方で、エロイーズもまたマリアンヌに心を奪われていく。
そんな中、マリアンヌは画家としてのプライドと、絵を完成させてしまうとエロイーズが結婚してしまうということの間で気持ちが揺らぐようになって…。
スタッフ・キャスト
- 監督:セリーヌ・シアマ
- 脚本:セリーヌ・シアマ
- 撮影:クレール・マトン
- 衣装:ドロテ・ギロー
- 編集:ジュリアン・ラシュレー
- 音楽:ジャン=バティスト・デ・ラウビエ








さて、セリーヌ・シアマは『水の中のつぼみ』や『ぼくの名前はズッキーニ』などで知られる気鋭の映画監督です。
『水の中のつぼみ』もまた、女性同士の恋愛模様を描いた作品であり、意中の相手に近づくべく同じスイミングスクールに入会する少女の物語にスポットを当てています。
一方で、『ぼくの名前はズッキーニ』では、子どもの虐待問題や悲惨な生育環境にスポットを当て、ストップモーションだからこそできる「ぎこちない」味わいも相まって。非常に高くされました。
そして、今回の『燃ゆる女の肖像』へと続き、カンヌ国際映画祭にて高い評価を得るに至ったわけです。
撮影には、マイウェン監督の作品なども手掛けたクレール・マトンが起用され、編集には映画『プラネタリウム』などで知られるジュリアン・ラシュレーがクレジットされています。
また、劇伴音楽をジャン=バティスト・デ・ラウビエが手掛け、シンプルながらもストリングスを基調とした重厚なサウンドで、物語の中に内包された激しい感情の動きを表現していました。
- マリアンヌ:ノエミ・メルラン
- エロイーズ:アデル・エネル
- ソフィル:アナ・バイラミ
- 伯爵夫人:バレリア・ゴリノ








主人公のマリアンヌを演じたのは、『ヘヴン・ウィル・ウェイト』で注目され、その後もフランス映画の話題作に多く出演してきたノエミ・メルランです。
一方のアデル・エネル先ほど紹介したセリーヌ・シアマの『水の中のつぼみ』にも出演しています。
その他にもダルデンヌ兄弟の作品や同じくクィアパルム賞を受賞した『BPM ビート・パー・ミニット』などにも出演するなどフランス映画界を代表する女優の1人です。
夫人役には、アカデミー賞受賞作『レインマン』にも出演し、自信も監督として映画を手掛けているバレリア・ゴリノが起用されました。








『燃ゆる女の肖像』解説・考察(ネタバレあり)
静かに燃ゆる愛と恋慕
(C)Lilies Films.
まず多くの方が、この『燃ゆる女の肖像』という作品がラブストーリーでありながら、実に淡々と物語が展開されていくことに驚くのではないでしょうか。
ウェットな印象はほとんど感じませんし、後半になると、2人が交わるシーンも当然あるのですが、そういった濡れ場をもってしても、この映画が持つドライさは全く損なわれないと言っても過言ではありません。
何と言うか、マリアンヌとエロイーズがお互いに「ポーカーフェイスで」恋愛をしているような印象すら受け、お互いが自分の中から溢れそうになる感情を抑えながら、関係を結んでいく様が何とも印象的なのです。
平兼盛が読んだ和歌に
しのぶれど 色に出にけり我が恋は 物や思ふと人の問ふまで
というものがありますよね。
これは自分の恋心を押しとどめようとしていたのに、思わず表情や空気感でそれを表に出してしまい、気がつかれてしまったという意味の恋の歌です。
そしてこの歌と対になるのが、
恋すてふ わが名はまだき立ちにけり 人知れずこそ思ひそめしか
という壬生忠見の和歌ですね。
こちらも同じく秘めた恋心について歌っているのですが、自分の秘めた恋を見抜かれてしまった驚きにスポットが当てられていると言われています。
さて、日本の和歌の世界にもこうした「秘めた恋」に伴う美徳のようなものは、古来より存在していたわけですが、そうした感覚や空気感がまさしくこの『燃ゆる女の肖像』という作品には反映されているのです。
そして、本作のタイトルにも含まれている「燃ゆる」というのが、本作のキーワードでもありますね。
基本的にドライで淡々と物語を進行させていき、感情をウェットに演出することが少ない作品なのですが、状況や表情、登場人物を取り巻く空気感、そして何より彼らの視線が、複雑な感情の渦を見事に可視化しているのです。
状況的に説明すれば、マリアンヌとエロイーズはお互いに心を通わせているわけですが、エロイーズは絵が完成してしまえば、見合いに行ってしまいますよね。
ただ、マリアンヌとしては絵の完成を放棄して、エロイーズと駆け落ちなんてことになれば、画家としての名誉は地の底に落ち、もう日の目を見ることはなくなるでしょう。
そういうジレンマの中で、彼女は肖像画を描きながら2つの視線をエロイーズに向けるのです。
1つは肖像画を描くための画家としての視線。そしてもう1つが肖像画の完成を拒む1人の人間としての、女性としての恋慕の視線です。
『燃ゆる女の肖像』という作品は、画家とモデルという関係を表層的に配置しながら、その背後に人間同士で向き合うというコンテクストを介在させ、そのマリアージュによって「秘められた愛情」を表現しています。
その心の内に秘められた愛情や恋慕の念は、静かに熱を増していき、そしてある瞬間に「燃え上がる」のです。
それも音を立てて燃え上がるわけではありません。静かに。静かに。誰にも悟られないように燃え上がります。
オルフェウスの物語と振り返らないことの永遠性
(C)Lilies Films.
この映画は、記事の冒頭にも書きましたが、ギリシャ神話に登場するオルフェウスの物語に着想を得ている部分があります。
簡単に解説しておきますと、オルフェウスは毒蛇に噛まれて命を落とした妻のエウリュディケーの命を呼び戻すべく、冥府へと下ります。
冥界の王ハーデースとその妃ペルセポネーの王座の前に立ち、オルフェウスは竪琴を奏でて妻の命の返還を求め、その音色で、彼らの感情を揺さぶったことで、エウリュディケーの命を取り戻すチャンスを得ました。
しかし、冥府から出るまでの間、「絶対に振り返って妻の姿を確認してはいけない」という条件を課されるのです。
そして、オルフェウスは、冥府を出る寸前のところで、不安に駆られて妻の方を振り返ってしまい、そのチャンスを不意にしてしまうという悲劇的な結末を迎えます。
つまり、このエピソードは「振り返る」という行為が「永遠の別れ」に直結してしまうというコンテクストを生み出しているわけです。
さて、この『燃ゆる女の肖像』という作品においては、メインキャラクターの3人がまさしく「オルフェウスの物語」について議論をする描写がありました。
その中で、芸術家であるマリアンヌは、オルフェウスの振り返るという選択を「詩人としてのもの」だと語ります。一方で夫人に仕えている侍女のソフィルは「愛ゆえの行動なのではないか」と考えるのですが、エロイーズはオルフェウスの選択を「身勝手だ」と断言します。
振り返ってはいけないとあれだけ言われていたにもかかわらず、振り返ってしまい、永遠の別れをもたらしてしまったその選択は、自分勝手で身勝手であると主張しているわけです。
そうして、マリアンヌとエロイーズは決して結ばれ得ない恋路を辿ることになるわけですが、やはり残酷にも別れの時は訪れます。
本心では一緒にいたい、結ばれたいと思っているはずですが、彼らはお互いのためにその思いを胸の奥にしまい込み、別れを選ぶのです。
エロイーズは、自分がもし身勝手な選択をしてしまえば、画家としてのマリアンヌのキャリアを台無しにしてしまうことを知っています。
本作の中で、「女性は描ける絵に限りがある」と言われていたり、終盤の展覧会で女性の絵は見向きもされず、出品すらされないことを暗に仄めかしていることからも、一度ついた汚名を払拭することは難しいでしょう。
(C)Lilies Films.
一方で、マリアンヌもエロイーズの姉の死であったり、彼女の母親の思いであったりを知っています。そして、女性が男性と結婚するという社会通例を踏襲しなければ、辛く苦しい運命が待っていることも承知です。
だからこそ、彼女の幸せのために自分の身勝手でそれを台無しにするようなことがあってはならないとして、身を引くわけですよ。
そうした2人の間には、まさしくエロイーズの姉が遺した「赦して…」という言葉が介在しているような気がしました。
お互いが愛情を確かめ合っている状況なのに、それを選ぶことはできない、あなたのために選べない。そんな身勝手を選ぶことができない自分の身勝手を「赦して」ほしいという思いを2人から強く感じるのです。
マリアンヌの回想は、エロイーズが「振り返ってよ!」と叫び、彼女が振り返ろうとしたところで突然断章します。
「振り返る」という行為が永遠の別れであるとするならば、この回想の終わりはまさしく2人の永遠の別れを象徴するかのようです。
しかし、その後2つの2人の再会シーンが描かれるのですが、その内の2つ目がこの映画を傑作足らしめています。
オペラの劇場で、再会を果たした2人ですが、お互いがお互いの存在に気がついている状況で、2人は決して目を合わせることがありません。
とりわけエロイーズは、絶対にマリアンヌの方を振り返るまいとステージを見つめ、目から大粒の涙を流しながら、それでもじっとステージを見つめているのです。








そうであるとすれば、エロイーズのオペラハウスでの行動というのは、まさしく2人の関係を終わらせないための、社会の柵へのささやかな抵抗なのです。
2人はおそらく結ばれることはありません。当時の社会において女性の同性愛に市民権はないと考えるのが当然です。それを望めば、きっと2人は全てを失ってしまうでしょう。
だからこそ、2人は結ばれない選択をしながらも、「振り返らない」という選択によって、あの島での思い出を、2人が交わした愛情を「永遠に」しようと試みているのです。
この映画のラストシーンでステージを見つめるエロイーズは、直接的にそう視覚表現が為されているわけでもないのに、なぜか燃え上がる炎に包まれているように感じられました。
その「愛」の炎は目には見えませんが、静かに、力強く、燃え上がっています。
「振り返らない」という行為は一見すると、もうエロイーズはマリアンヌのことを忘れてしまった、何とも思っていないのではないかと想起させる行為です。
しかし、そこにオルフェウスのコンテクストが内包されることで、その意味は見事なまでに反転します。
この表層的な部分とその背後にあるものの二重性ないしマリアージュが、『燃ゆる女の肖像』という作品の重層的な味わいを生み出していました。
おわりに
いかがだったでしょうか。
今回は映画『燃ゆる女の肖像』についてお話してきました。








とにかく言語化されていないバックグラウンドや感情の描写が非常に多く、映像に多くを託した映画であり、それ故に見る人によって味わいが大きく変わる作品になっています。
また、女性が主人公の映画としても、傑出した内容となっており、社会に迎合せざるを得ないという建前と、その背後に燃え上がる恋慕や抵抗の念を「炎」という力強いモチーフで表現したことは素晴らしいと思いました。
しかも、その炎は音を立てて豪快にと燃え上がるようなものではありません。
心の内で、静かにされど熱く、どんなものよりも力強く燃える、秘めたる炎なのです。
だからこそ、視覚的に炎が描かれているわけでもないのに、確かに「燃えているではないか!」と感じずにはいられない本作のラストシーンは、傑出した出来栄えでした。
振り返らないことで、あの島で過ごした2人の時間が永遠になるのだと思うと、私はその選択に涙が止まりませんでした。
何を差し置いても見ていただきたい2020年における恋愛映画の最高峰だと思います。
今回も読んでくださった方、ありがとうございました。