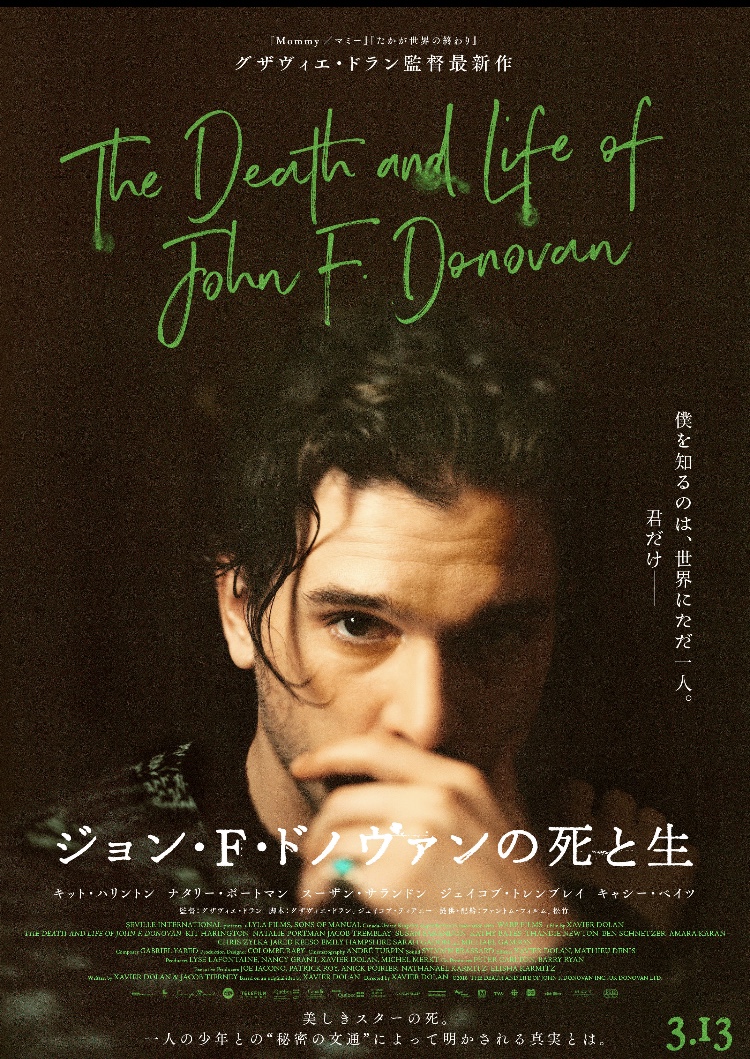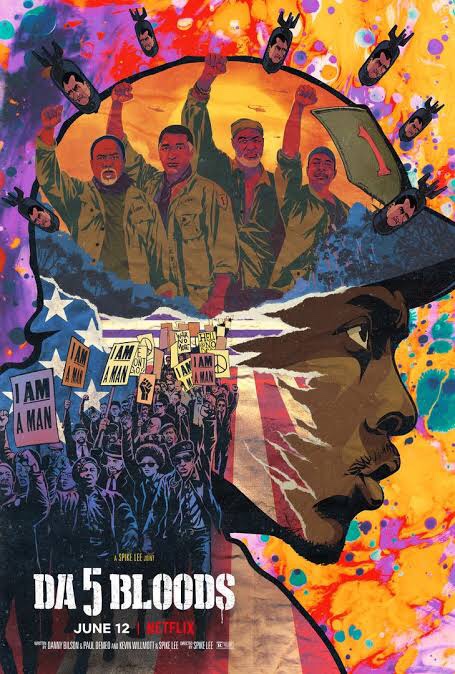みなさんこんにちは。ナガと申します。
今回はですね映画『あの頃。』についてお話していこうと思います。

「あなたにとってあの頃の名曲と言えば?」
当ブログ管理人がこの質問をされたら、おそらくテレビアニメ『けいおん!』の楽曲を挙げると思います。










とは言え、このブログを読んでいるあなたが「あの頃の名曲」と言われて思い浮かべたのは、おそらく全く別の楽曲ですよね。
それはピンクレディーかもしれませんし、Mr. childrenかもしれませんし、モーニング娘。かもしれませんし、SMAPなのかもしれません。
10年後に同じ質問をしたら、米津玄師やYOASOBIも「あの頃の名曲」と言われているのかもしれません。
つまり、「あの頃」を自分以外の他人と共有することって実はとても難しいことで、そして同時にとても尊いことなんですよ。
この点を踏まえて、本作のキャラクターたちの関係性を思い出してみると、心から羨ましいなと思えるものになっています。
なぜなら、彼らにとっての「あの頃」はお互いで示し合わすまでもなく、同じ時間や同じ瞬間だからです。
「あの頃」という時間軸は、どこにでもあって、同時にどこにも存在しない時間と言えます。
なぜなら、「あの頃」は人の数だけ存在していて、特定の1点になど普通は定まることがないからですね。
しかし、人間は他者との関わりの中で「あの頃」を自分の外の世界に存在させることができてしまうのです。
「あの頃良かったよなぁ…。」という言葉を聞いて、そのイメージを共有できる。これってすごいことなんですよ。
だからこそ、他人と「あの頃」という特異点をお互いの思いのベクトルの交点として共有するという関係性を描いた本作がとても尊く、どこまでも眩しいのだと思いました。
本作は一見すると「アイドルとそのオタク」の映画なのですが、個人的にはむしろ今泉監督らしい「片想い」の映画なんだなと感じましたね。
もちろんオタクがアイドルに対して抱いている思いは「片想い」という上澄み的な部分も指摘できますが、今作の根幹にあるのは「時間の片想い」なのです。
今回の記事では、なぜ「片想い映画の旗手」と言われる今泉監督が『あの頃。』をこういった独特なスタイルで映像化したのかを考えていきたいと思います。
本記事は作品のネタバレになるような内容を含む解説・考察記事です。
作品を未鑑賞の方はお気をつけください。
良かったら最後までお付き合いください。
目次
『あの頃。』
動画レビュー
当ブログの公式YouTubeチャンネルの方で、同作の動画レビューを公開してます。
この記事は作品を鑑賞した人向けにがっつりと考察したものですが、動画の方はネタバレなしのレビュー記事です。










あらすじ
大学院受験に失敗し、ベースで生計を立てることを夢見ながら、バイトで何とか生計を立てる青年・劔。
ある日、友人から借りた松浦亜弥のミュージックビデオDVDを見た彼は涙が止まらなくなり、その足でCDショップに向かう。
偶然立ち寄ったショップで、彼はナカウチという男性に出会い、そこでハロプロのファンイベントを紹介される。
そのイベントを主催しているコズミンら個性的な仲間に迎えられた劔は、失われた青春を取り戻すかのように日々を謳歌する。
ハロプロを応援して、仲間と集まってバカをやって、イベントを主催して、そんな日々が永遠に続くと思っていた。
それでも、時は流れ、彼らはアイドルよりも大切なものを見つけて次第に離れ離れになっていく。
そんなある日、かつての仲間たちの中心にいたコズミンが肺がんに侵されていることを知り…。
スタッフ・キャスト
- 監督:今泉力哉
- 原作:劔樹人
- 脚本:冨永昌敬
- 撮影:岩永洋
- 照明:加藤大輝
- 編集:佐藤崇
- 音楽:長谷川白紙










監督を務めた今泉力哉さんは、今最も注目されている日本の映画監督の1人と言っても過言ではないと思います。
『愛がなんだ』や『mellow』、『his』などの作品を手掛け、「片想い映画の旗手」なんて異名もついていますが、どれも素晴らしい作品ばかりです。
個人的に彼の作品が好きなのは、「定点観測」のような人物の撮り方をする点ですね。
今回の『あの頃。』では、主人公の劔とコズミンが松浦亜弥の握手会が当選したことを喜びながら、部屋でシチューを食べるシーンでまさしくこの今泉監督らしいショットが使われています。
(C)2020「あの頃。」製作委員会
この独特の定点観測的なアングルと長回しによって、このシーンが強烈に観客の脳裏に焼きつけられ、そして終盤の展開の中で思考の上に蘇って来るという実に巧妙に計算された映画の撮り方をしているのです。
他にも好きなポイントはたくさんありますが、語りすぎるとキリがないので、一旦このあたりで。
そして、脚本を担当したのは『素敵なダイナマイトスキャンダル』や『南瓜とマヨネーズ』などでも知られる冨永昌敬さんです。
彼の脚本って、一見すると「散漫じゃない?」と感じさせるような趣もあります。
ところがどっこい、見終わってから思い返してみると、本当にマグロくらい捨てるところがない良質な脚本だったと思い知らされます(笑)
そういうオフビート感を漂わせつつも、全体で見た時には無駄がなく、タイトに作られていると言うのが冨永さんの脚本の強みなんじゃないかなと思うのです。
撮影には『愛がなんだ』や『知らない、ふたり』などでも知られる岩永洋さん、編集には沖田修一監督作品でおなじみの佐藤崇さんが起用されていますね。
- 劔樹人:松坂桃李
- コズミン:仲野太賀
- ロビ:山中崇
- 西野:若葉竜也
- ナカウチ:芹澤興人
- イトウ:コカドケンタロウ
- アール:大下ヒロト
- 佐伯:木口健太
- 靖子:中田青渚










菅田将暉さんのラジオに呼ばれては、遊戯王デュエルリンクスの話ばかりするということで、ジョークで「出禁」扱いにされていたとも言われる生粋のオタク気質の松坂桃李さん。
彼だからこそ、今作での役が噓っぽくないんですよね。違和感を抱かせるまでもなく「オタク」であると観客に思わせてしまうガチさがありました。
そして、今作のもう1人のキーパーソンであるコズミン役には、仲野太賀さんが起用されています。
飄々としていて、底抜けに明るいオーラを出しながら、なんで一気に突き抜けた切なさや哀愁を漂わせられるのだろうか…とそのギャップに驚かされるばかりでした。
また、昨年『君が世界のはじまり』にも出演し、『中学聖日記』来注目を集めている中田青渚さんも出演していました。
本編では比較的序盤に映画からフェードアウトしてしまうので、もう少し見たかったなという思いはありましたね。










『あの頃。』解説・考察(ネタバレあり)
向こう側とこちら側。それを繋ぐ「扉」
さて、まず『あの頃。』という作品を見ていて、感動したのは、タイトルロールが出るまでの一連のシークエンスですね。
スタジオの外から徐々にカメラで迫っていくのですが、防音室の中で奏でられている音はあまり漏れ聞こえてきません。
しかし、次の瞬間にはスタジオの中にシーンが映り、今度は奏でられている音やそこで飛び交う怒号が生の音として耳に突き刺さります。
このファーストカットが何を指し示していたのかと言うと、本作『あの頃。』における2つの視線の存在です。
もっと言うなれば、自分と他人の視線の存在を端的に表出していたと言えます。
スタジオの外から見ている他人の視線と、スタジオの中で自分が今まさに向けている視線。
防音室やすりガラスによって隔てられた2つの場所から発せられた視線が当然交わることはなく、それらは断線しています。
また、スタジオの中で音を奏でているメンバーたちの視線の方向も、明らかに交わっておらず、そうした視線の掛け違いを強く印象づけるのが、このファーストカットというわけです。
そして、もう1つタイトルロールに至るまでのシークエンスで注目しておきたいのが、「扉」というモチーフです。
「扉」とは元来、壁と壁で隔てられた2つの別の空間を繋ぎ、行き来させるためのハブのような役割を果たしますよね。
本作の中でも、この「扉」が幾度となく映像の中に登場しますが、まず、最初に描かれたのが主人公の部屋に佐伯がやって来るシーンですね。
部屋でうなだれており、永遠にそこから抜け出せないのではないかという『四畳半神話大系』の主人公の青年のような雰囲気を漂わせる劔は、「扉」の向こうからやって来た佐伯を気に留める様子もありません。
コンビニから帰ってきた彼は、自宅の「扉」のドアノブに佐伯からの差し入れで松浦亜弥のライブDVDがつられているのを発見し、部屋に入り、再生します。
すると、ブラウン管のテレビの液晶の「向こう側」に松浦亜弥の姿が映し出され、劔はその姿に魅了され、思わず涙するのです。
その瞬間、彼は「扉」を開けて、部屋を飛び出します。
なるほど、この映画は松浦亜弥ないしハロプロとの出会いが、彼を今いる自分の世界の「向こう側」へと導いていく映画なのだということが端的に映像で表現されているわけです。
そして、自転車で道路を爆走しているところでタイトルロール。完璧ですね。
その後、彼がCDショップに辿り着くと、彼は店の入り口の「扉」を開けることになります。
このようにして、『あの頃。』という作品は、向こう側とこちら側を意識させるような画を反芻していきますし、同時に「扉」というモチーフを要所で登場させてきました。
「向こう側」は「こちら側」になっていく
(C)2020「あの頃。」製作委員会
さて、ここまで『あの頃。』においては「向こう側」と「こちら側」の対比がファーストカットから明確にされているということをお話してきました。
ここからはそうした2つの空間の関係性が実は流動的に物語の中で変化して言っている点を指摘していきます。
まず、主人公はあの暗い自宅が「こちら側」であり、松浦亜弥、ハロプロそして後に「恋愛研究会。」と名乗ることとなるメンバーたちのいる場所が「向こう側」だったんですよね。
そのため、劔は幾度となく「扉」を開き、まだ見ぬ「向こう側」へと足を踏み入れていき、退屈な日常から脱しようとしていきます。
そうして仲間を手に入れた彼は、くだらなくも愛おしく、刺激的な毎日を送るようになっていくわけです。
また、松浦亜弥という軸で見ても、当初はモニターの「向こう側」にいるのを見つめているだけだったのに、握手会に参加し同じ空間で時間を共にするに至りました。
つまり、過去の自分にとって「向こう側」だった場所は、今の自分にとっては「こちら側」に転じていくというロジックが『あの頃。』という作品の中で幾度となく示されているのです。
面白いのは、過去の自分にとって「こちら側」だった場所が、いつしか「向こう側」に転じていくという構造ではないでしょうか。
当初、主人公の劔にとっての「こちら側」はバンドマンとしての夢や生活であり、一方で「向こう側」にあったのがハロプロオタクの世界でした。
しかし、彼がハロプロオタクの世界に足を踏み入れると、今度はバンドマンとしての夢や生活が「向こう側」になってしまうのです。
そのため、彼は当初は新鮮で刺激に満ちていると感じていたハロプロオタクのコミュニティに徐々に停滞感のようなものを感じるようになり、いつしかそこから飛び出して、東京のライブハウスでは働き始めます。
人間はいつも「向こう側」を求め続ける人間ということなのでしょう。
本作の終盤に、まさしく映画のファーストシーンとシンクロするスタジオでの演奏シーンがインサートされていますが、ここは特に印象的です。
ファーストカットでは、退屈そうに演奏をしていた劔。あの時の彼は、バンドマンとしての夢や生活が「こちら側」になり、閉塞感を感じていたようにも思えます。
しかし、そこから一度距離をとり、もう一度バンドマンとしての夢や生活を憧憬と共に「向こう側」として再認識することで、彼はあの場所に立つことに喜びや幸福感を抱くのです。
この「向こう側」と「こちら側」の関係性が映画の中で、何度も入れ替わっていく構造は非常に特殊です。
そして、もう1つ指摘しておかなければならないのは、こうした構造やそれを繋ぐ「扉」というモチーフが、「時間」に強く関連している点でしょう。
過去と現在、未来、そして「扉」
「扉」というモチーフは面白いですよね。
自分が今いる空間のことは分かるけれど、扉を隔ててその向こう側にどんな光景が広がっているのかは、開けて飛び込んでみるまで分かりません。
そう思うと、「扉」を開けるという現在進行形の行為が隔てているのは、過去と未来という見方もできます。










『あの頃。』という作品が「時間に纏わる映画」であることは、タイトルもそうなのですが、映画のとあるワンシーンで明確に示されました。
それは、主人公がハロプロのライブに行く約束をしていた靖子にドタキャンされたあの日の会場での一幕です。
劔は空席のはずの自分の隣の席に、1人の老人が座るのを目撃し、声をかけるのですが、その老人は「私は未来の自分自身(劔自身)である」と口にします。
つまりこの2人は同一人物であり、異なる「現在」軸から、それぞれ自分の過去を見つめ、未来を見つめるという形で、双方向から視線を発しているのです。
未来の劔は、ガルパンおじさんよろしく「ハロプロはいいぞ(彼女はいないけどなw)」と幸せ全開アピールなのに対し、過去側の劔はそんな自分の未来を悲観し視線を逸らします。
ここで、まさしく過去から未来に向けられる視線と、未来から過去に向けられる視線のすれ違いが起きていますよね。
未来にいる自分は過去の自分の存在を愛おしく思っている。しかし、過去にいる自分は未来の自分の存在を好ましく思っていないという構造が成立しています。
ここがまさに『あの頃。』という映画における「片想い」なんです。
つまるところ、今作は人間ではなく、時間を巡る「片想い」を描いた作品だということです。
では、ここからいよいよ本作の核心に迫っていきます。
一方通行の時間が織りなす「片想い」の物語
(C)2020「あの頃。」製作委員会
私たちの体感上で、時間というものは常に時間は過去から未来へと一方向に流れていきますよね。
それを物語の中で残酷にも突きつけるのが、言うまでもなくコズミンというキャラクターが直面する「死」です。
「死」は不可逆であり、一度「死」した人間が生き返ることは基本的にあり得ません。
そうした元来「片想い」的な一方通行の志向性を持った時間という概念を扱うことで、本作は今泉監督らしい「片想い」の映画になっているわけです。
しかし、この作品が面白いのは、その時間が抱える「片想い」性をいかに突き崩していくかというところでしょう。
作品の後半で、何度かTwitterが登場する場面がありましたが、こうした場面では必ず劔がこう確認するんですよ。
「そのツイートっていつ?」
それに対して、ナカウチはこう返します。
「今。今だよ。」
このやり取りも、ただ無意味に作品の中に何度も取り入れられているわけではありません。
何気ないやり取りが意味するのは、「今」という瞬間に、離れた場所にいる人間の思いと思いが交わるという構造です。
それに対して劔がRTボタンを押す一幕がありましたが、これは2つの視線と思いのベクトルが双方向から発せられ、1つのツイート上で交わった瞬間を描いているとも言えます。
また、今作『あの頃。』においてもっとも印象的に使われている楽曲は、言うまでもなく「恋ING」ですよね。
この楽曲は歌詞の中にも「恋愛進行形」という言葉が登場し、過去や未来の恋愛ではなく、今まさに自分が身を置いている恋愛のことを歌っています。
好きな人も出来なくて
グルメ気取ってた時期もあった
今 実際 恋愛中
恋する人に夢中いつまでも二人でいたい
パンが1つなら わけわけね
まだ 実際 駆け出しね
すべての 始まりね恋愛進行形
(モーニング娘。『恋ING』より引用)
つまり、『あの頃。』という作品は、後半にかけて「今」という時間軸の重要性を繰り返し訴えかけてくるようになるのです。
個人的に面白かったのが、劔がモーニング娘。メンバーの卒業コンサートを訪れた時の、チケットを譲ってくれた馬場という女性とのやり取りです。
彼女は高校の先生をやっていて、それ故に「卒業式」という場を「送り出す側」として見ているんです。つまり、どちらかと言うと、卒業するまでのあれこれを思い出すような親目線の心情が込められた視線とも言えるでしょうか。
一方で、モーニング娘。から卒業するメンバーは当然、グループから飛び出した後、自分がどうしていくのかという未来を見つめています。
ここにも、実は未来から過去方向、過去から未来方向のベクトルが内包されていて、それがモーニング娘。というライブという場で交錯するようになっているのです。
そのライブのシーンの直後に、同ライブの映像がDVD化されて、それが劔たちが集まっている部屋のモニターで再生されているという一幕がインサートされます。
では、そこに映し出されている卒業ライブの映像は「過去」なのでしょうか。
確かに時間の概念から言えば、紛れもなく「過去」ではあるのですが、あの映像の中に流れている時間は固定されており、そしてその映像は時を越えて見た人の心に影響を与えていきます。
そう思うと、単純に「過去」だと言いきってしまうのは、何だか乱暴な気もしてくるのです。
では、どんな言葉を使えば良いのか。それがまさしく「あの頃」なのではないでしょうか。
「あの頃」という時間軸は、どこににでも存在していて、同時にどこにも存在していないとも言えます。
しかし、会場に足を運んだ人たちが、メンバーの卒業を思う人たちが、DVDを見た人たちが視線を向けることで、その交点として「あの頃」は生まれます。
つまり、「あの頃」という概念は、時間の「片想い」性に対するささやかな抵抗なのです。
この点を踏まえて考えていくと、本作のあのラストシークエンスの見え方が変わってくるはずです。
本作のラストシーンが示した「あの頃」という交点
(C)2020「あの頃。」製作委員会
さて、『あの頃。』におけるもっとも大きな物語上の展開はやはり、コズミンがガンにかかり、亡くなってしまうというものでしょう。
ガンに苦しむコズミンは、次第にアニメに傾倒するようになっていき、とりわけ『一騎当千』というアニメにハマり、病室には同作のフィギュアが溢れています。
こうした病室の様子は、コズミンにとってもハロプロの存在が「過去のもの」になってしまったのではないかという一抹の寂しさを感じさせますね。
そして、いよいよ彼が亡くなる直前のシーンがクライマックスの少し前に映し出されていて、そこで看護師の女性がアニメのフィギュアを彼に持たせると落ち着くという一幕がありました。
しかし、このシーンは意図的に途中でカットされていて、終盤も終盤に彼が求めていたのは、実はフィギュアではなく、「恋ING」が流れているイヤホンを耳に戻して欲しいというものでした。
つまり、コズミンにとってハロプロは決して過去のものになどはなっておらず、現在進行形で今も心に残り続けているものだということが分かりますね。
さて、本作が時間の「片想い」性を描いていたという話をしてきましたが、終盤にかけてはそうした「片想い」たちが「両想い」へと転じていきます。
象徴的だったのは、恋愛研究会。の仲間たちが棺の「扉」を開けて中にあるコズミンの亡骸を見つめるシーンではないでしょうか。
ここでは極めて明確に棺の中からのコズミンアングルと、棺の外からの仲間たちのアングルが使い分けられています。
「扉」は「こちら側」と「向こう側」を隔てるものとして機能していますが、ここでは生と死を隔てています。
コズミンにとっては「死」が現在であり、「生」は過去です。つまり彼が棺の中から外を見つめる視線は「過去」を見つめる視線ですよね。
一方で、棺の外にいる仲間たちにとっては「死」は自分たちの未来であり、それ故に彼らの視線は「未来」を見つめる視線です。
そして、その2つの視線があの場所、あの時間に交わっています。
その後のコズミンの追悼イベントの場面では、しきりのコズミンのブロンズ像の「視線」が目が光るという機能を通じて強調されていました。
彼は死しても、未だ前を見つめ続けているのであり、そしてハロプロを見つめ続けていたのです。
いよいよラストシーンです。
実はラストの劔とコズミンの再会の場面が「いつ」なのかは明言されません。
BEYOOOOONDSというグループが話題に挙がっていることから少なくとも2018年以降ではないかと推測できますが、明確に断定することはできません。
しかし、コズミンにとっての時間は亡くなったあの時で止まってしまっていますから、ラストシーンの時間軸はそこにいるはずだった「未来」を見つめる視線と言えるでしょうか。
一方で、劔があの場面でコズミンの姿を見ているのは、そこにいたはずだった彼への視線であり、それは「過去」への視線とも言えます。
そんな双方向の異なる時間軸からの視線が見事に交わり、「あの頃」という交点を生み出すのが、本作のラストシーンなのです。
映画の冒頭では明確にすれ違っていた未来志向の視線と、過去志向の視線が交わる。
だからこそ、ラストシークエンスで、主人公の劔はこのシーンとは逆の方向へと歩いていきます。
(C)2020「あの頃。」製作委員会
まさしく2つの異なるベクトルが交わる様が、動線として可視化されたわけです。
時間の不可逆性によって、断絶された仲間たちが、「あの頃」という特異点を作り出し、そこでこれからも共に存在し続けるのだというある種の抵抗が示されたとも言えます。
そして、それを可能にしたのが、ハロプロであり、モーニング娘。であり、彼女たちが歌った楽曲でした。
「あの頃。」は映画を見る前だと、過去への憧憬やノスタルジーが込められたタイトルなのかなと思っていました。
しかし、映画を見終えた今思うのは、「あの頃」というのは「ING」つまり現在進行形で共にあり続けるものなのだということです。
過去を振り返るだけでは「あの頃」は完成せず、過去から未来へと視線を向け返してくれることで初めて「あの頃」は「あの頃」足り得るのかと。
自分の中でそれを完結させるのではなく、それを誰かと共有して成し遂げるということがいかに尊いことなのかと。
本作『あの頃。』の根底にあるのは、やはり「片想い」とその交錯なのではないでしょうか。
そしてラストシーンにおける視線の「交錯」は「別れ」をも意味します。
要するに、サルトルによれば、眼差しの交差は、相手を対象と化す相互メドゥーサ的な営為にほかならない。目合いは、サルトルにあっては、永遠に実現不可能な愛の合体のメタファーとなる。
(谷川渥『鏡と皮膚――芸術のミュトロギア』)
まさしくタイトルの句点「。」を象徴するように、本作はラストシーンで「あの頃」に別れを告げました。
しかし「あの頃」を捨てたり、切り離したりするということではなく、思い出のアルバムの1ページに刻み込み、これからも心にしまい続けるのだと思います。
私たちは過去の自分を「大丈夫だ」と肯定し、過去の自分に「大丈夫だ」と励まされながら、「あの頃」と共に今日も一歩ずつ前へと進んでいくのです。
おわりに
いかがだったでしょうか。
今回は映画『あの頃。』についてお話してきました。










予告編を見る限りでは、アイドルオタクのドタバタコメディかなと思っていたのですが、蓋を開けてみると、これは時間を巡る「片想い」の映画なんじゃないか?という趣でした。
それにしても、終盤の映像の時系列の組み換えなんかは本当に上手いですし、ラストカットに「あれ」を持ってきてしまうのが、また泣かせます。
後半、ハロプロ映画としての趣が弱まっていくからこそ、ラストシーンの唐突な「あれ」がバシッと決まるのです。
こういうところまでしっかりと計算されて作りこまれて映画であることに驚かされますし、まんまと感情を手玉に取られてしまいました。










ぜひぜひ多くの方にご覧になっていただきたいです。
今回も読んでくださった方、ありがとうございました。