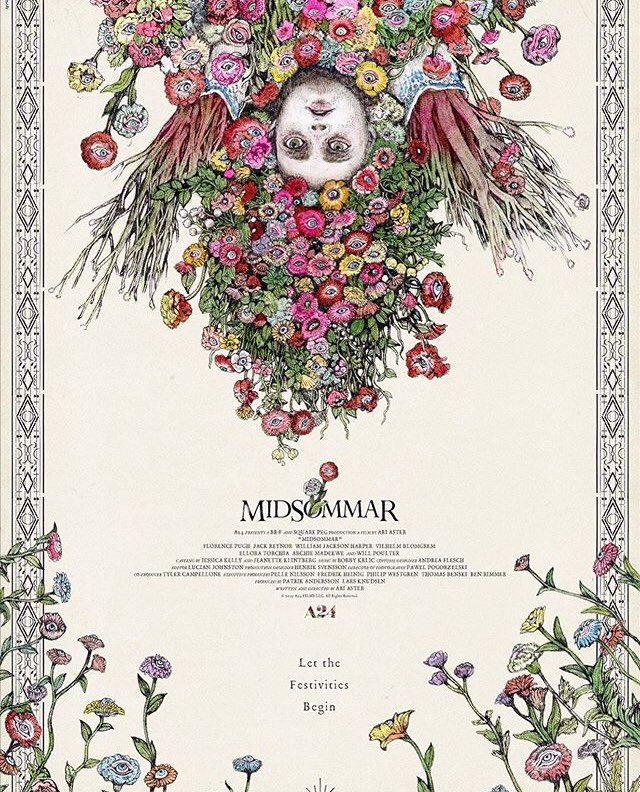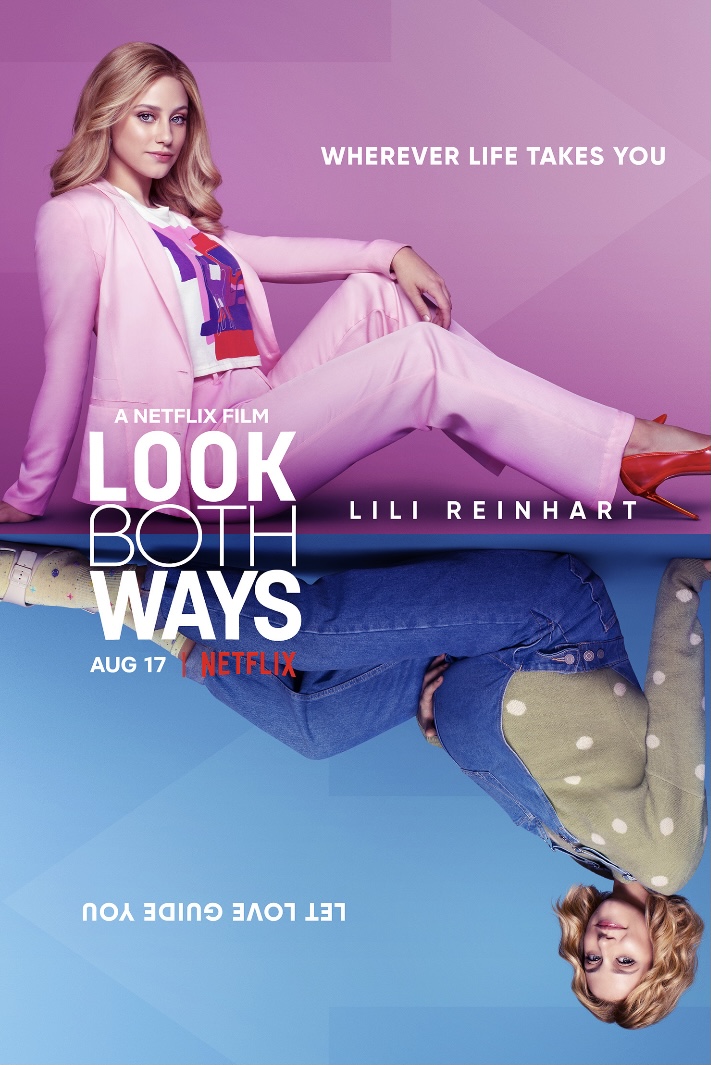みなさんこんにちは。ナガと申します。
今回はですね映画『ビバリウム』についてお話していこうと思います。

何を言っているのか分かりませんよね(笑)
普段、誰かに映画を勧めるときって、その作品が「面白いから」というのが根底にあると思うんですが、この『ビバリウム』は違います。
圧倒的に「退屈だから」こそ見て欲しいと勧めたくなる作品なのです。
本作の物語は、トムとジェマという1組のカップルが、とある不動産屋を訪れるところから始まります。
その不動産屋では「Yonder」と呼ばれる郊外の住宅地の案内をしており、その店員の怪しさも相まって2人は購入するつもりはなかったが、「見るだけでも」という声に絆され、その住宅地へと向かうことになるのです。
そうして、彼らが辿り着いたのは、ライムグリーンないしティールと形容すべき青緑一色で構築されたおもちゃのような住宅地でした。
部屋は素晴らしいものの、どこか不気味な住宅地に2人は住む気は無かったのですが、突然その家を案内してくれた「マーティン」という男性が消えてしまいます。
トムは「もうこの隙に帰ろうぜ!」と言い出し、2人は車に乗り、「Yonder」から出ようとするのですが、彼らは一向に出口を見つけ出すことができません。
何度車を走らせても、彼らは「マーティン」に案内された「9番」の家へと戻ってきてしまうのです。
やむを得ず、一晩をその家で過ごした2人。翌朝彼らに不思議な荷物が届けられmasu。
それは、人間のカタチをした不思議な生き物の赤ちゃんでした。またそこには「育てたら解放される」という文言が書かれています。
こうしてトムとジェマはやむを得ず、その子どもを育てることとなるというのが、『ビバリウム』の物語の大枠です。
ビバリウムは、とにかく「子育て」を巡る厭な部分を徹底的にループさせてくる実に醜悪な作品となっていて、正直97分という上映時間がとても長いものに感じられました。









本作の主人公を演じたのは、『グランドイリュージョン』シリーズでおなじみのジェシーアイゼンバーグと『バーバラと心の巨人』『グリーンルーム』などで知られるイモージェン・プーツです。
またこの2人の演技が、良い味を出しているので、ぜひ2人と共にこの97分の「地獄」を体感して欲しいと思います。
それでは、ここからは謎めいた本作が一体何を意味していたのかについて、自分なりの解説・考察を書いていきます。
本記事は作品のネタバレになるような内容を含みますので、作品を未鑑賞の方はお気をつけください。
良かったら最後までお付き合いください。
目次
『ビバリウム』解説・考察(ネタバレあり)
本作の構造は冒頭の「カッコウ」の映像でネタバレされている!
(C)Fantastic Films Ltd/Frakas Productions SPRL/Pingpong Film
まず、多くの人が「ちょっと何言ってるのかわからない。」と言いたくなるであろう『ビバリウム』ですが、実は親切に映画の最初に説明をしてくれているんですよね。


というのも、本作の元になっているのは、「カッコウ」です。
カッコウは「托卵」という少し特殊な子孫の育て方をする生き物で、親は自分の雛を自分で育てるのではなく、他の鳥の巣に自分の卵を産み付け、他の種の親に自分の雛を育てさせるんですよね。
『ビバリウム』の冒頭で、雛が巣から落とされている描写がありましたが、これはカッコウの雛が自分だけを育てさせるために、親の本来の子どもにあたる雛を巣から蹴落とす習性があることを表しています。









つまり、カッコウを「托卵」されてしまった鳥は、自分がお腹を痛めて産んだ子供を殺され、代わりに全く違う種類のカッコウの雛をを育てさせられるわけです。









映画の冒頭の映像で、餌付けをしている親よりも、雛のカッコウの方が大きくなっているという不気味な映像が映し出されていましたが、あれも現実に起こりうることです。
比較的小さい種類の鳥の巣に「托卵」された場合、親鳥は自分よりも既に体の大きいカッコウの雛に餌付けをする羽目になります。
そうして、ある程度の大きさまで成長すると、カッコウは親鳥を顧みることもなく飛び立っていくのだそうです。
こういったカッコウの「畜生」としか言いようのない修正を把握しておくと、この『ビバリウム』という作品の構造そのものを理解することはそれほど難しくはないでしょう。
トムとジェマは、謎の生命体から赤ん坊を託され、それを育てることを強要され、自分たちの肉体と精神を摩耗させていきます。
しかし、そうして何とか育てた息子はわずかな期間で自分たちよりも大きな身体になり、最終的にはあっさりと親を見捨てるのです。
まさしく「カッコウ」の「托卵」をモチーフに作られたのが、この『ビバリウム』という作品だと分かりますね。
第一に「子育て」の苦痛を描き出した作品である
(C)Fantastic Films Ltd/Frakas Productions SPRL/Pingpong Film
では、ここから『ビバリウム』が一体何を描こうとした作品なのかについてお話していこうと思います。
第一に、この作品が描き出したのは、「子育て」というものの苦しみとそれに伴う女性の負担なのでしょう。
『ビバリウム』という作品において、見ている多くの人は気づいたかもしれませんが、基本的に家事全般をこなしているのは、ジェマですよね。









その時、トムは何をしているかと言えば、外で「仕事」をしています。
つまり、本作はあの狭い空間の中で「男は外、女は内」の旧来的なジェンダーの価値観を見事に描いているのです。
トムは疲れて帰って来て、寝るだけの生活をしており、次第に家にも帰らずに「外で」練るような生活を送るようになります。
対照的に、ジェマは子どもの相手をすることに精神をすり減らし、次第に非協力的な夫に対しても苛立ちを覚えるようになりました。









本作の子どもは、徹底的に
親につきまとい、じっと見つめ、
親の真似事をし、
そして、お腹が減り機嫌が悪くなると、金切り声を上げます。
夜の夫婦の営みの時間すら与えてくれず、トムとジェマは「自分たちの時間を与えてくれ」と懇願しますが、子どもはそんな事情を知る由もありません。
子どもが親に似てくること、そして親にずっとついて回ること、さらに機嫌が悪くなると駄々をこね、泣くというのは普通に子育てをしていると直面することではあります。
しかし、『ビバリウム』という作品は、こうした子育てにつきまとうネガティブな側面だけを極めて明確な悪意を持って、増幅させ、観客とそして2人の主人公に突きつけているわけです。
そのため、子育てに苦心し、精神的に壊れていくジェマと、仕事で疲れ、肉体的に壊れていくトムという関係は見事にステレオタイプ的な核家族を描き出していると言えますね。
また、この『ビバリウム』が醜悪なのは、そうした子育てのルーティンを何度も何度も映画の中で繰り返し、観客が退屈だと感じるようになっても尚、ひたすらに繰り返してくることです。
これにより、観客は主人公たちの置かれている状況を強制的に追体験させられ、映画館にいながら地獄を味わうことになります。
だからこそ、この『ビバリウム』という作品は、退屈こそが美徳足り得る稀有な映画なのだと思いますし、今作を見て、子育てを女性に任せっきりにしている男性たちは肝を冷やすことになるでしょう。
第二に資本主義の残酷さを描いた作品である
(C)Fantastic Films Ltd/Frakas Productions SPRL/Pingpong Film
さて、では『ビバリウム』が描いたものとして、映画の中では明言されていないもう1つのものについて自分なりの考えを述べさせていただきます。
結論から申し上げますと、今作が描いたのは、私たちが生きている「資本主義社会」そのものだと言えるでしょう。
まず、本作における不動産屋やあの子どもは何を暗喩しているのかと言うと、それは「資本家」です。
一方で、トムやジェマは、いわゆる「一般人」ないし「労働者」を体現しています。
「資本家」の最大の望みは、自分たちが利益を得ること、いや「利益を得られる社会構造を維持すること」です。
だからこそ、自分が利益を得られている場所をそのまま自分の子孫へと受け渡し、それを脈々と受け継いでいくことが重要なんですね。
一方で「労働者」の階級にあたるトムとジェマは、そうした「資本家」から搾取される側にあり、彼らは社会構造を変えることはできません。
彼らが毎日精神と肉体をすり減らしながら、必死に働いたとしても、彼らは「資本主義社会の歯車」でしかないわけで、その養分を「資本家」に吸われるだけです。
だからこそ、彼らの労働や家事の恩恵は全て、あの子どもへと吸収されていきます。
また、彼らは「死にはしないが、幸福な生活を送れているとも言えない」微妙なラインの食べ物と最低限の生活必需品を与えられて、いわゆる「普通の生活」を維持することを要求されていますよね。
住宅も含めてですが、こうしたパッケージ化された「生活」は、1950年代のアメリカで起きた郊外生活というバックグラウンドを反映しています。
郊外に住宅地が作られるようになり、それに伴って企業は「消費者文化」を形成することに重点を置き始めます。
要は核家族化を促したというわけですが、それはそれぞれの家に独自の洗濯機と乾燥機、テレビといった家電を設置し、さらに生活を送るための必需品を完備させるというコマーシャルをテレビ等のメディアを通じて消費者に植えつけることで、確立されていきました。
そうして、人為的に作られたカルチャーの中で、消費者たちは生活をしていくことになり、この事実が『ビバリウム』の世界観そのものというわけです。
また、物語の後半で、トムが体調を崩すのですが、薬をもらったり、医療的な処置を受けたりすることができないというのが、何ともアメリカらしいなと思います。
アメリカは、日本と違って国民皆保険の制度が存在しないため、貧しい人たちは病気になっても、なかなか病院に行けないなんてケースも少なくありません。









トムが死に向かって衰弱していっているのに、病院にも行けず、薬ももらえず、資本家を象徴する「息子」からは無視されるというアメリカならではの残酷さが本作の終盤では明確に描かれていると言えるでしょう。
こうして「労働者」階級であるトムとジェマは、「資本家」に搾取されるだけ搾取されて、その生涯を終えることとなります。
彼らが育てた「資本家」は、不動産屋でその生涯を終えたこれまでの「資本家」に成り代わるだけで、社会の構造は何も変わることはありません。
それは、あの不動産屋に冒頭のトムとジェマと同じようなカップルがやって来て、家を検討している描写からも明らかです。
社会の構造を変えることができず、一部の「資本家」が「労働者」を搾取し、その地位を世代を超えて維持し続けているというこの社会の歪さを『ビバリウム』は強烈に描き出しています。
終わりのないループが表現した救いようのない結末には、歪んだ社会を生きる私たちの悲哀が強く込められていました。
おわりに
いかがだったでしょうか。
今回は映画『ビバリウム』について自分なりの解説や考察を書かせていただきました。









この手の作品は、物語の後半で支配される側が何とかして構造を転覆させたりするものなんですが、『ビバリウム』はそれすら認めてくれないんですよ。
「資本家」が「資本家」の跡を継いで終わるという、固定された階級社会の醜悪さを体現するような映画になっていました。
そうした映画の本質を伝えるために、アプローチとしては「ただただ何も起きない。気が狂いそうな毎日を延々と繰り返す」という一見するとかなり「退屈な」内容となっています。
しかし、それこそが『ビバリウム』の凄みだということをぜひ知っておいてください。
「退屈だ!」という言葉が誉め言葉になるのが、本作の素晴らしさなのです。
そして、私が書かせていただいたような作品の背景を少し掘り下げて考えてみるのも、1つの本作の楽しみ方なのかなと思います。
今回も読んでくださった方、ありがとうございました。