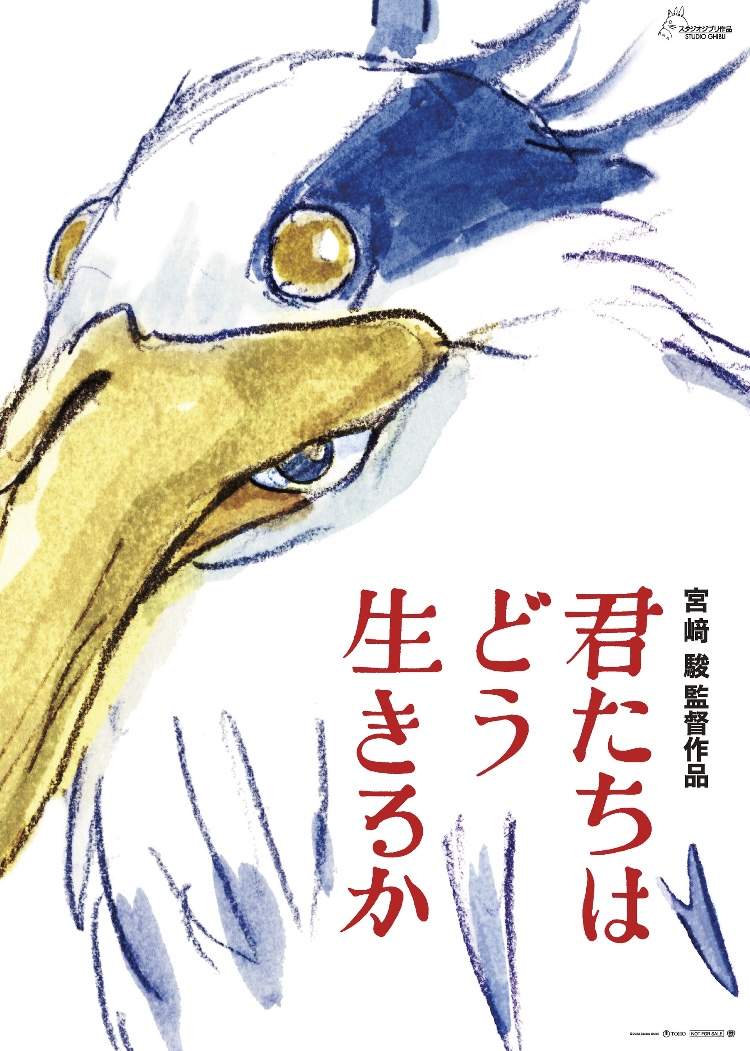みなさんこんにちは。ナガと申します。
今回はですね映画『ノマドランド』についてお話していこうと思います。

コロナ禍で映画の公開本数が少ないことも相まってか、今年の主要な賞レースを総なめにした本作。
第77回ベネチア国際映画祭で最高賞にあたる金獅子賞、第45回トロント国際映画祭でも最高賞の観客賞を受賞するなど高い評価を獲得しました。
そして、アカデミー賞の前哨戦とも言われる第78回ゴールデングローブ賞でも作品賞や監督賞を受賞し、アカデミー賞本命に名乗りを上げました。
もう公開前から期待値が上りに上がった本作ですが、鑑賞してみて、その評価や名声に値する作品だと思いました。
ただ、最初に書いておきますが、万人受けするタイプの作品ではないというのが、率直な印象です。
作劇はドキュメンタリーテイストで、ノマドという生き方を選んだ人物との出会い、対話、そしてアメリカの雄大な自然の映像を織り交ぜながら、少しずつ主人公のファーンの心の変化に迫っていく不思議な映画なんですよね。
そのため、ドラマ性という点では淡く、演出もかなり簡素で、その雄大な自然の映像を織り交ぜながら展開していくスタイルはテレンス・マリック監督作品なんかを彷彿させます。
また、物語そのものも日常の連続と円環にフォーカスしており、何か大きな出来事が起きるというわけではないので、そうしたタイプの作品が得意ではないという方には向かないでしょう。
それでも、この耽美的な映画は、静かに、そして美しい詩を聞いているかのような感覚で、心の奥底に沁みる特異な映画だと言えます。
刺さる人にはとことん刺さる映画だと思いますので、ぜひこの作品が必要な人に届いて欲しいなと思うばかりです。
監督は、『ザ・ライダー』で高く評価された新鋭クロエ・ジャオ、そして主人公のファーンを『スリービルボード』のフランシス・マクドーマンドが演じました。
とりわけフランシス・マクドーマンドの演技は、傑出していて、この淡々としたドラマを1人で繋いでいく圧倒的な存在感に痺れました。
さて、ここからは映画『ノマドランド』について自分なりに感じたことや考えたことをお話させていただきます。
本記事は作品のネタバレになるような内容を含む感想・解説記事です。
作品を未鑑賞の方はお気をつけください。
良かったら最後までお付き合いください。
目次
『ノマドランド』
あらすじ
ネバダ州の企業城下町で暮らす60代の女性ファーン。夫亡き後も、その町で暮らし続けていたが、リーマンショックによる企業倒産の影響もあり、長年住み慣れた家から追い出されることとなる。
キャンピングカーに全てを詰め込んだ彼女は、季節労働の現場を渡り歩きながら車上生活を送ることになった。
帰属する場所を持たない孤独な生活の中で、彼女は自分と同じように「ノマド」として生活する高齢者たちと出会う。
旅の中で新たな出会い、そして別れを経験し、彼らとの関わりの中で徐々に夫亡き後の喪失感に向き合っていくのだが…。
スタッフ
- 監督:クロエ・ジャオ
- 原作:ジェシカ・ブルーダー
- 脚本:クロエ・ジャオ
- 撮影:ジョシュア・ジェームズ・リチャーズ
- 編集:クロエ・ジャオ
- 音楽:ルドビコ・エイナウディ






監督・脚本を担当したのは、記事の冒頭にもお話したように『ザ・ライダー』などで知られるクロエ・ジャオです。
後程詳しくお話しますが、このドキュメンタリーとフィクションの「あわい」に生まれたような奇跡的な映画を作り上げた手腕は高く評価されるべきだと思います。
というのも、今作は、主演のフランシス・マクドーマンドを除く出演者の多くが本当に現実に「ノマド」としてアメリカで暮らしている人たちだったりするんです。
つまり、フィクションとも言えるし、一方でドキュメンタリーとも言える不思議な映画なんですね。
今作『ノマドランド』の原作は、ジェシカ・ブルーダーのノンフィクション『ノマド 漂流する高齢労働者たち』です。
また、本作の美しい映像を手掛けたのは、『ザ・ライダー』や『ゴッドオウンカントリー』などで、雄大な自然の映像を切り取ってきたジョシュア・ジェームズ・リチャーズです。
美しい映像とドキュメンタリーともフィクションとも位置づけられれない不思議な立ち位置が奇跡的な融合を果たし、映画史に残る稀有な作品を作り上げています。
なぜアカデミー賞作品賞最有力なのか?






この動画の中では、本作がアカデミー賞に強い理由を
- 過去の編集賞と監督賞の受賞・ノミネート作品から見る傾向
- 近年の人種の多様性を重んじる傾向
- 前哨戦での圧倒的な結果
の3つの観点から解説しております。
また、本作が作品として優れている部分を特に「脚色」と「撮影」にスポットを当てて解説しましたので、こちらもぜひご覧いただきたいです。
『ノマドランド』感想・解説(ネタバレあり)
対話と風景で演出するサブタルな心の変化
(C)2021 20th Century Studios. All rights reserved.
まず、本作『ノマドランド』について賞賛しておくべきは、その作劇の仕方でしょう。
この映画の中で、基本的に主人公のファーンの心情が直接的に語られることはありません。
彼女は主人公でありながら、ドキュメンタリー作品のインタビュアーのように、人と出会い、彼らの話に耳を傾けます。
ちなみに、キャストを調べていただけると分かりますが、リンダやスワンキー、ボブといったキャラクターは、実名での出演であり、現実にアメリカでノマドとして暮らしている人たちです。
こうした実際の人物が映画に登場するというクリントイーストウッド監督の『15時17分、パリ行き』のような側面があることも、本作のドキュメンタリー性を高めていると言えます。
さらには旅をする中で、アメリカの広大な自然と直面し、その風景の中で「地球」という大きな家に生きる自己を知覚していきました。
『ノマドランド』が素晴らしいのは、そうして出会った他者や、直面した自然が、あまり語られない主人公の心情の「映し鏡」のように機能している点です。
移り行く季節、時間によって変化する景色、森や荒野の風景。変わらない様で移ろいゆく風景はファーンの心模様とも言えます。
(C)2021 20th Century Studios. All rights reserved.
また、彼女と対話をする他者は、彼女の心情を代弁するかのように心の内を明かしていくのです。
ノマドとして生きることの尊さ、喜び、苦労、そして孤独。出会いと別れ。生と死。誰かと語らう中で、徐々に主人公のぼんやりとした「像」が浮かび上がってくるという構成を全編に渡って貫くアプローチは称賛に値するでしょう。
また、今作の構成が憎いのは、そうした映像や風景が1周して「円環」を為すという点です。
1年が経って、主人公のファーンは最初の年に経験したことと同じことを繰り返します。
Amazonで働き、荒野でのノマドたちの集まりに参加して…という具合に円を描くように出来事が最初に回帰し、また始まります。
しかし、そこには当然のように変化がありますよね。
彼女が友人だと言っていたリンダは、もうAmazonの配送センターでは働いていません。
2人が1年前パズルを楽しんだあの部屋には、ファーンが1人佇んでいるだけです。
また、ノマドたちの集まりには、故スワンキーはいなくなっており、自分の居場所を見出したデイブももういません。
同じことの繰り返しの様で、少しずつ変化していく。
そうした小さな変化が同じことの繰り返しでありながら、その中で確かに変化した主人公ファーンのサブタルな心情の変化にも重なります。
映像で魅せるというアプローチを選択することには勇気が必要です。
それでも、大胆にドキュメンタリーを思わせるような構成や演出を取り入れ、それを最後まで貫き通した作り手の勇気に僕は拍手を贈りたいですね。
ノマドとして生きることの悲哀と皮肉
(C)2021 20th Century Studios. All rights reserved.
この作品を見て、「ノマド」という生き方を賛美する映画だと捉える方がいるかもしれないが、決してそうではないことは明白です。
むしろ、本作『ノマドランド』は、「ノマド」という生き方につきまとう負の側面やアイロニックな部分にも焦点を当てています。
例えば、ファーンたちは、資本主義から放り出された存在で、そこから独立した世界で助け合って生きようと高らかに宣言しているわけですが、彼らが季節労働しているのは、そうしたアメリカの資本主義の象徴とも言えるAmazonだったりしますよね。
というより、Amazonのような社会のシステムを変革させた巨大企業は、ファーンのような高齢者がかつて生活の基盤としていた社会のシステムや企業をリタイアに追い込んだ「張本人」でもあるわけですよ。
そうした企業で、季節労働者として働かなければ、生計を立てられないと言うところが、すごく「皮肉」として効いているのがお分かりいただけると思います。
荒野で、ノマドたちの集会があり、そこで車上生活のコツや排せつ物の処理に関する講座が開かれていたりしますが、定住していれば何の心配もないことであって、ポジティブに語られていますが、本当は苦悩の連続です。
ボブは、「ノマド」というのは、お金への執着から解放された生き方だと語っていましたが、ファーンは金銭的に苦しく、自分の生活の基盤であるバンが故障すると、親戚に借金をするしかない状況に追い込まれました。
そんな彼女が借金をしたのは、これまた資本主義の権化とも言える不動産業で財産を築いた親族からでしたよね。
というように、本作『ノマドランド』では、資本主義から解放されて自由な暮らしを選んでいるはず「ノマド」たちが、結局はそうした資本主義から逃れることができていないという「皮肉」的な部分にも焦点を当てています。
生活そのものも苦しく、資本への執着から解放されたと口では言っていても、現実問題として逃れることはできないという運命。
そんな状況の中で、「ノマド」として生きることしかできないのが彼らなのです。
本作『ノマドランド』において1つ特徴的なのが、映画の中で登場する道路の大半が「1本道」であるという描写の仕方です。






この「1本道」という視覚的な風景は、ポジティブに捉えるならば、執着から解放され、自然となりゆきに身を任せて生きる「ノマド」の生き方の象徴でもあります。
しかし、翻っては「ノマド」たちが今の生き方から逃れることができない、というより他の生き方を選択するチャンスに恵まれないという悲哀を表現しているとも取れますよね。
このように、『ノマドランド』という作品は、単に「ノマド」の生き方を賛美するような映画にはなっておらず、むしろその負の側面をも積極的に描こうとしています。
そうした悲哀と皮肉の向こうに、それでも燦然と輝く精神的な「解放」や「自由」とは何なのか?
これを作品を通じて私たちに問いかけ続けたわけです。
もちろん明確な答えはありません。みなさんが感じたままが正解です。
ホームレスではなくハウスレス
(C)2021 20th Century Studios. All rights reserved.
本作『ノマドランド』を見ていて、個人的にすごく印象に残ったのは、冒頭のこのセリフでした。
「ホームレスではなく、ハウスレスなの。」
この言葉は、まさしく『ノマドランド』という作品の本質を表現していると思います。
ホームとハウスの違いは何か。それは「概念」か「物質」かです。
ホームというのは、形があるものではなくその人の認知や知覚によっても変化する「概念」のようなものですよね。
一方で、ハウスはいわゆる住宅のことであり、居住空間のことであり、これには明確な形があるため「物質」です。
ただ、これまでこのホームとハウスが同一の場所を示しているという考え方が当たり前だったんですよね。
日本語でも「家に帰る」と言う表現を使ったら、その「家」という言葉には当然ホームとハウスの両方の意味が内包されています。
「家」というのは、自分の心の帰属する場所であり、同時に家族や大切な人がいる居住空間であり、確かにそれが一致しているのが普通という見方があっても不思議ではありません。
しかし、現代の世界を見た時に、実はこのホームとハウスが一致しているという例がいかに幸せなものかを考える必要があります。
例えば、難民の問題です。彼らは紛争などによって自分の国を離れなければならなくなり、家族や友人とも離れ離れになってしまう運命にありますよね。
そうなると、何とかアメリカのような国に住むことになって、そこに居住するハウスを得られたとしても、自分のホームを祖国に取り残したままになってしまいます。
こうしたケースでは、ハウスとホームは当然別の場所を指すこととなりますね。
『ノマドランド』において、アメリカでノマドとして暮らしている主人公のファーンもまたそうしたハウスとホームの「ズレ」に葛藤している人間の1人と言えます。
物語の冒頭、主人公は亡き夫の遺品を2人で暮らした街の倉庫に大切そうに保管している描写がありました。
特に彼女が大切にしていたのは、結婚当初に手に入れたアンティーク調の食器で、それが自分と亡き夫を繋いでくれる「物質」のように感じられたのかもしれません。
映画の始まりの時点では、ファーンはハウスレスであるにも関わらず、ハウスへの執着が捨てきれていない人物として描かれています。
夫の遺品を自分の現在の居住場所であるバンに持ち込むことで、彼女はその空間をハウスであり、ホームでもあるのだと信じ込もうとしています。
いや、むしろ彼女は2人で暮らした街の倉庫に夫と共に暮らした頃の物品を保管しておくことで、あの場所をホームだと思っているのかもしれません。
つまり、彼女は物質としては存在しないホームという概念に確証が持てず、夫の遺品を残すことで、物質的に「ホーム」を作り出そうとしているのです。
本来概念でしかないホームの存在を確かめるために、物質に固執するという「ズレ」がファーンという女性の中に渦巻いている葛藤の正体なのだと思いました。
それが、まさしく表出したのが、デイブがファーンの大切にしていたアンティーク調の食器を割ってしまう一幕ではないでしょうか。
この時の彼女の激昂は、単なる食器を割られたという事実以上のものであり、自分のホームを壊されたと感じたが故のものなのです。
しかし、徐々にファーンはそうした物質への執着から解放されていきます。
1つの転機になったのが、デイブの家を訪れたシーンでしょう。
かつてはノマドだったデイブが自分自身のハウスとホームが一致する場所を見つけたという事例を基に、そうした場所を一緒に見つけようという彼の提案がファーンを苦悩させます。
しかし、彼女はその提案を受け入れることはありませんでした。
物語の果てに彼女は気づいたのです。ホームとは「物質」ではなく、目に見えず、絶えず自分の心の中にある「概念」なのだと。
だからこそデイブの暮らすあの家が、彼女にとってのホームになることはないのだと確信し、1人故郷の街を目指します。
彼女が取る行動はもう決まっています。それはもちろん、亡き夫の遺品をすべて処分することです。
「思い出は生き続ける。」
自分の心の中に常にホームが存在し続けるのだと、確認することができたファーンにはもう必要のないものですね。
そこに、かつて夫の生きた証を残すことに固執してエンパイアに留まっていた彼女の姿はもうありません。
どこにも、誰にも物質的に帰属しない「ノマド」という生き方。
大切な人との出会いは、どんどんと心の中に蓄積されていき、そうして形作られていくホームが失われることはありません。
君は永遠に詩の中を生きる。
詩が君に命を与え続ける。
「物質」という脆く壊れやすいものに固執するのではなく、もっと本質的な目に見えない何かを大切にして生きていくという人間の「営み」を『ノマドランド』は描き切りました。
「家とは心の中にあるもの」
劇中でも述べられたこの言葉が、きっと本作の何よりのアンサーなのでしょう。
愛は円環。変わらないものと変わりゆくもの。
(C)2021 20th Century Studios. All rights reserved.
そして、『ノマドランド』が何よりも素晴らしかったのは、作品そのものが1つの円環構造を為していたことなのでしょう。
私たちの生きている地球も1つの大きな「円」を為す構造をしており、劇中に登場する結婚指輪もまた「円」を形作っています。
一方で、私たちの生きている1年は同じ季節を12か月を1つのサイクルとして繰り返します。もっと小さな単位で言えば、1日は朝、昼、夜を繰り返す「円」の構造になっていますね。
私たちの生きる世界には、空間的にも、時間的にも、そして概念的にも「円」的なものが溢れています。
しかし、そうした「円」の中で取り残されていくものがあるとすれば、それは「物質」なんですよね。
「物質」は時間的、空間的な影響を受け、その形が変化していきます。買ったばかりのバンが新品であっても、年月と共に劣化し、みすぼらしい見た目になっていくのと同様です。
もっと言うなれば、人間の「死」も同じですよね。人間は永遠に生きることはできませんから、その肉体はいつか円環から逸脱することになります。
つまり、「物質」に固執し続ける限り、そうした「円環」の構造から私たち人間は取り残され続けるということなのかもしれません。
だからこそ、「物質」への固執から解脱し、目には見えないものを大切にするという「ノマド」という生き方を選択するということは、そうした「円環」の理に身を任せるということなのだと思います。
劇中で、ある老人が「ノマドという生き方には最後のさよならがない」と語っていました。
それは、彼らが物質的ではなく、精神的・概念的なレイヤーで、出会った人との再会を思いながら「また、どこかで!」と告げ、別々の旅に戻っていくからです。
つまり、物質的に例えその人がこの世界から失われてしまったとしても、精神的・概念的なレイヤーでいつか再会できると信じることができるのです。
物語は円を描き、ファーンは彼女の始まりの場所でもある、エンパイアの自宅へと戻ってきます。
そこに夫婦が暮らした物質的な痕跡はもはや残されていません。
それでも、彼女は確かにそこにあったホームを心の中で感じることができ、きっと夫との再会を果たしたのでしょう。
だからこそ、再び彼女の「円」があの場所から始まります。
映画そのものが1つの「円」を為し、主人公のファーンの行動も1つの「円」を為していました。
そして、また新しい彼女の「円」の物語の始まりを伺わせながら、本作は幕を閉じます。
(C)2021 20th Century Studios. All rights reserved.
町を出て、戻って来て、また街を出て行く。
何も変わらない。でも何かが変わった。
それを観客に感じさせられたことが、『ノマドランド』という作品の成功を何よりも物語っています。
おわりに
いかがだったでしょうか。
今回は映画『ノマドランド』についてお話してきました。






少し違った角度で今のアメリカないし世界を捉えた作品ですし、独特な語り口で主人公のサブタルな変化を描き切ったクロエ・ジャオの手腕は卓越しています。
個人的には、デヴィッド・フィンチャーの『マンク』に作品賞を取って欲しいという思いはありつつも、本作が受賞したとしても文句はありません。
ドラマ性の淡さに困惑した方もいるかもしれませんが、じんわりと心の深くに沁み込んでいくような作品に仕上がっていましたので、刺さる人にはきっと刺さったはずと信じています。
ぜひ、日本でも多くの人にご覧になって欲しい1本です。
今回も読んでくださった方、ありがとうございました。