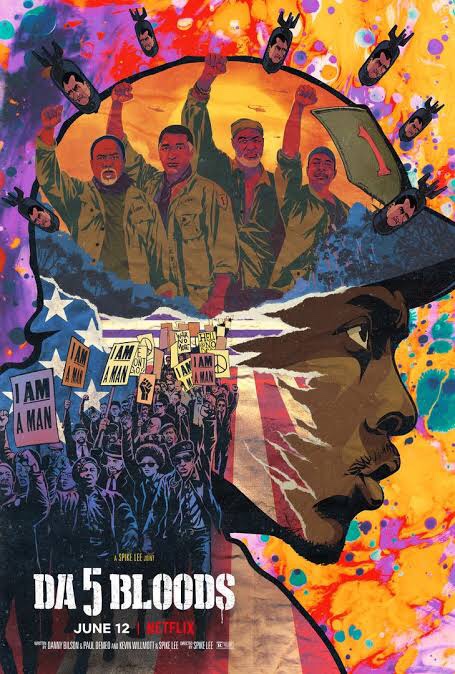みなさんこんにちは。ナガと申します。
今回はですねNetflixにて配信中の短編映画『隔たる世界の2人』についてお話していこうと思います。

先日発表された第93回アカデミー賞にて、短編映画部門で堂々のオスカー獲得となり、話題になっている作品です。
この作品を端的にご説明するならば、「ジョージ・フロイドさんが白人警官に窒息死させられた事件」と同じ1日を繰り返す「ループもの」を組み合わせて作られた映画というのが分かりやすいでしょうか。
シチュエーションとしてはクリストファー・ランドン監督の『ハッピーデスデイ』に非常に似ていて、主人公のカーターは白人警官のマークに殺されるたびに同じ1日がリセットされるというものになっています。
どんな生活を送ったとしても、彼は最終的にマークに殺害され、そして同じ1日を始めからやり直すことになるわけです。
こう聞くと、よくある「ループもの」のジャンルに時事ネタを組み合わせただけじゃないの?と思う方もいるでしょう。
しかし、本作がとんでもないのは、この時事ネタに「ループ」という設定を持ち込んだことについての意味が後半にかけて、きちんと明かされるからであり、そしてそこにアメリカの歴史、映画という枠組みへのメタ的な視座が内包されているからなのです。




今回は短編映画の考察記事ということで、短めにはなると思いますが、本作の後半の展開に込められた意味を紐解いていこうと思います。
本記事は作品のネタバレになるような内容を含む考察記事です。
作品を未鑑賞の方はお気をつけください。
良かったら最後までお付き合いください。
目次
『隔たる世界の2人』考察(ネタバレあり)
終盤にかけて描かれる「ループもの」の域を超えた展開
まず、簡単に『隔たる世界の2人』の後半の展開を解説させていただきます。
本作の主人公カーターは、毎朝一夜を共にした女性の家で目覚め、そして通りで出くわした白人警官のマークに殺害されるというループを繰り返していました。
彼がそもそも疑いをかけられるのは、所持していた札束が原因なのですが、これはジョージ・フロイドが偽札と思われる20ドル札を使おうとした際に逮捕され、抵抗し、窒息死に至った事実からの引用でしょう。
そうして何度試しても死から逃れられないことを悟った彼は、同じく自分がループしていることを悟り始めた白人警官のマークに懇願し、パトカーで家まで送ってもらうことにしました。
2人は、しばしの間歓談し、和やかな時間を過ごし、白人と黒人の垣根を超えて分かり合えたような雰囲気になっていきます。
会話が盛り上がったところで、2人は目的地に到着し、カーターは自分の家へと戻ろうとします。しかし、ここで警官のマークが彼に銃口を向けるのです。
そして彼はこう告げます。
「名演だったよ、カーター。ブラボー。楽しませてもらった。俺の良心に訴えかけるとはよく考えたもんだ。最高だった。勇気だけは認めてやる。今回は秀逸な演技を見せてもらった。」
マークが和やかにカーターと語らっていたのは、演技でしかなく、彼の本心は結局カーターを殺すことでしかなかったという強烈な差別意識が表出した瞬間でした。
ここで重要なのは、マークが善良な白人警官を「演じていた」ということなのだと思います。
この点についてここからは2つの観点から、その意味を考えてみましょう。
アメリカの人種差別の歴史から紐解く
(映画『隔たる世界の2人』より引用)
まず、本作を紐解く上で欠かせないのは、アメリカにおける人種差別の歴史についての背景情報です。
2000年代に入ると、アメリカは国内の多様な人種の共生に向けて舵を切り、2008年にその1つの象徴とも言える出来事が起こります。
それが、バラク・オバマの大統領就任ですよね。
彼の大統領就任が、国民に「黒人差別の終わり」が終わりに向かっていることを期待させたことは想像に難くありません。
しかし、それは極めて表面的でかつ、あくまでもシンボル的な事象に過ぎず、現実の社会においては依然として人種間の分断が根強く残っていました。
とりわけ、この頃から黒人への反感を強めていったのは、ヒルビリーと呼ばれる人たちに代表されるような没落した白人の中間層です。
彼らは政府が人種差別の撤廃や黒人の権利を回復するための対策に注力するがあまり、自分たちの利益を蔑ろにし、その結果として自分たちが困窮しているという幻想を抱いていました。
そうしたくすぶった火種がついに爆発してしまったのが、2012年にフロリダ州起きた黒人の少年トレイボン・マーティンが白人警官に射殺される事件でした。
この事件がきっかけでBLMの運動がスタートしたとも言われていますが、2010年代はオバマの大統領就任に代表される人種分断の融和のビジョンが崩れ去り、依然として色濃く残存するアメリカの人種差別意識が再び顔を覗かせた時期と指摘することもできます。
人種間の分断が解消され、共に生きる時代が来るという理想が音を立てて崩れ始め、その流れは2016年の大統領選挙でドナルド・トランプ氏が当選したことで顕著になりました。




白人警官のマークは、社内でのカーターとの会話の中で自身の誕生日が「11月8日」であることを明かしていました。
この「11月8日」というのは、2016年のアメリカ合衆国大統領選挙が行われた日であり、言い換えるならばドナルド・トランプ氏が当選した日でもあります。
つまり、マークというキャラクターに反映されているのは、
- 2000年代の融和の時代の中で隠されていた白人の黒人に対する根強い差別意識
- ドナルド・トランプ氏の当選に代表される人種間の分断を歓迎する没落した白人中間層の抵抗
という2つの社会的・歴史的なコンテクストなのでしょう。
とりわけ彼がカーターに好意的な警官としての振る舞いを「演じて」いた事実は、2000年代の融和を目指していた時期のアメリカを想起させます。
そして、終盤にマークはその演技の仮面の裏に秘めた強い差別意識を再び表出させ、カーターを殺害しました。これは再び人種間の分断が顕著になった2010年代を投影したような行動です。
こうした2000年以降のアメリカにおける人種差別の歴史を、物語の展開の中に巧く内包させた点が『隔たる世界の2人』という作品の素晴らしいところなのだと思います。
特に後半のマークが善良な白人警官を「演じて」いたという皮肉は、まさしく「幻想の融和」から「分断の表出」へと至った黒人差別の歴史への皮肉にもなっているのです。
映画という枠組みから紐解く
(映画『隔たる世界の2人』より引用)
そして、もう1つマークが善良な警官を「演じて」いたという展開を紐解くための視点をご紹介できたらと思います。
「演じる」という行為が真っ先に想起させるのは、俳優が役を演じるという映画やドラマと言ったフィクションですよね。
近年、ポリティカルコレクトネスの考え方が叫ばれ、映画やドラマにおいては有色人種が積極的に起用され、作品の題材も黒人差別にスポットを当てたものが増えてきました。
「人種間の対立の融和」を描いた作品が数多く作られ、それらがアメリカにおける有色人種とりわけ黒人の権利回復や人種差別の終わりをアピールするキャンペーンとして機能していたのは事実でしょう。
しかし、そうした映画やドラマに代表される「演技」とは裏腹に、現実のアメリカ社会に広がっていたのは、タナハシ・コーツが『世界と僕のあいだに』で指摘していたようなシビアな黒人差別の現状でした。
つまり、フィクションが打ち出していた理想とアメリカに広がっていた現実の間には途方もない距離感があったわけです。
本作『隔たる世界の2人』においてマークが善良な白人警官を「演じた」という構図には、こうした映画と現実の乖離に対する皮肉も込められているような気がしました。
人種差別を糾弾するようなテーマの作品を作り、黒人俳優が活躍する映画を作り、それらを映画を愛する国民の多くが支持するにも関わらず、現実が好転しないのです。
つまり、結局は映画というものは、現実とは隔てられた「箱庭」のような世界の中で、理想を「演じ」、それを繰り返しているだけなのではないかというある種の冷めた視座がこの作品には据えられているのではないでしょうか。
おわりに
いかがだったでしょうか。
今回は『隔たる世界の2人』という作品についてお話してきました。
「隔たる」という言葉が表しているのは、白人と黒人の隔離のことなのかもしれませんし、映画と現実の隔離のことなのかもしれません。
本作は、何度倒れようと、黒人は戦い続けなければならないという決意表面でもって幕切れました。
それは、甘い理想に惑わされるのでもなく、そして白人を恐れて何もしないのではなく、現実に地に足をつけて戦い続けていくという覚悟の表出でもあります。
アメリカが歴史の中で延々と繰り返してきた負のループを、作品のループ設定に投影し、そこから抜け出すための戦いを続けようと強く呼びかけた本作は、もはやよくあるループ映画の枠に収まるものではありません。
『隔たる世界の2人』は問題提起をしたに過ぎず、ループ映画として当然描かれる必要のある、ループからの脱却も描かれていません。
その「答え」は、現実に委ねられています。
30分ほどの短編で、ワンシチュエーションものでありながら、ここまで示唆に富んだ作品はなかなかないと思いますので、ぜひご覧になっていただきたいです。
今回も読んでくださった方、ありがとうございました。