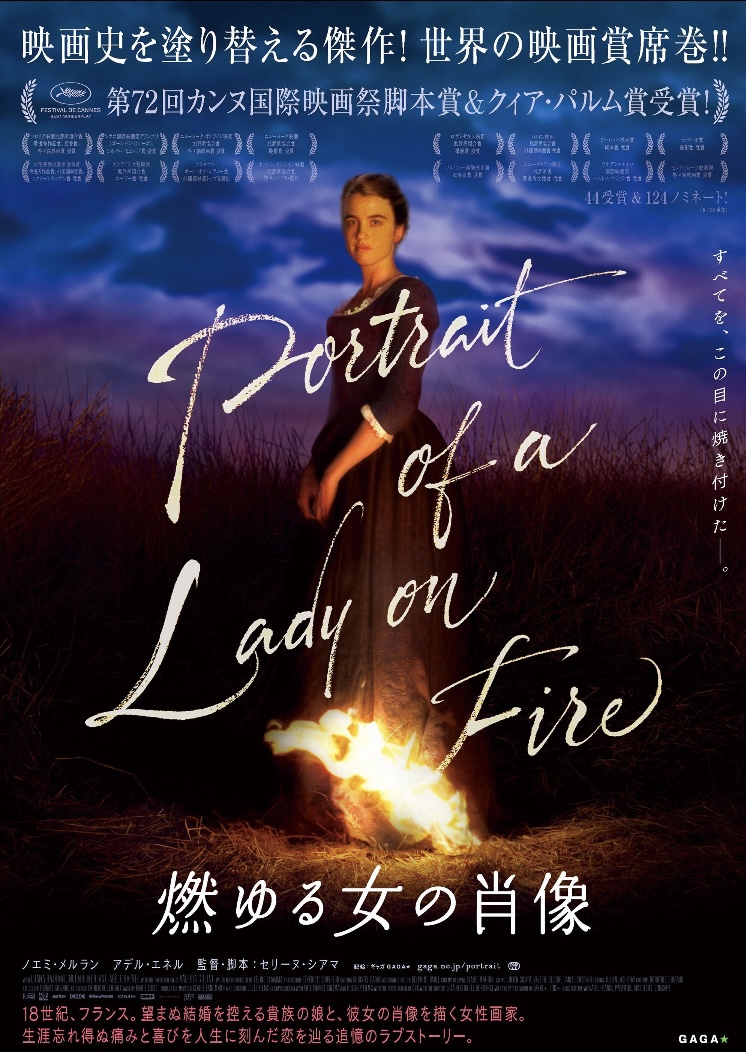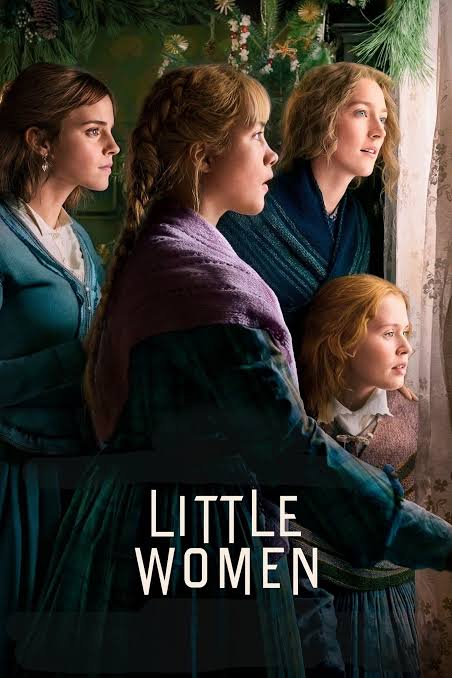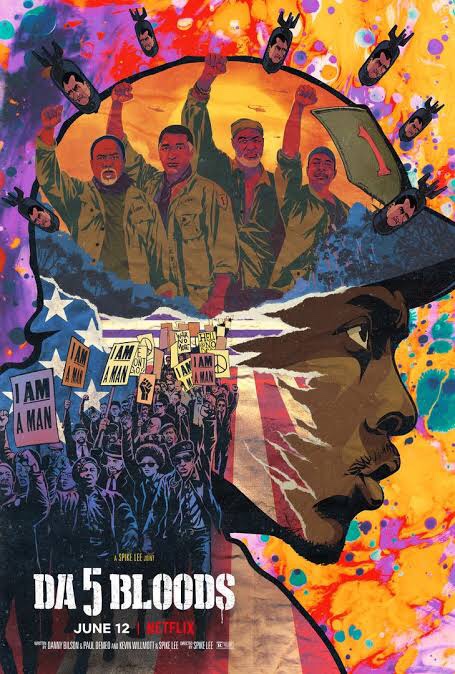みなさんこんにちは。ナガと申します。
今回はですね映画『プロミシングヤングウーマン』についてお話していこうと思います。

俳優・クリエイターとして幅広く活躍しているエメラルド・フェネルが、オリジナル脚本で初の長編映画に挑戦した本作。
デビュー作にして、いきなりアカデミー賞脚本賞を受賞してしまったのが、これまたすごいですよね。
ドラマシリーズ『キリング・イヴ/Killing Eve』で脚本を担当し、高い評価を獲得すると、外の年のエミー賞ドラマシリーズ脚本賞にノミネートするなど脚光を浴びました。
このシリーズでも、とにかく女性クリエイターだからこそできる女性の描写が注目されましたが、その経験や視座が今回の『プロミシングヤングウーマン』にも活かされていると感じました。
作品の方に話を戻していくのですが、この映画はどうしてもテーマ性の部分で、好みが分かれてしまう作品ではあると思います。
「女性」による「男性」への復讐劇というコンテクストで語られてしまうのは仕方ないですし、そのアプローチや方法についても賛否分かれるところでしょう。
しかし、『プロミシングヤングウーマン』は「男性」と「女性」というコンテクストを超えて、もっと普遍的に「加害者」と「被害者」という視点で語られて然るべき作品でないかと思うのです。
おそらく最も賛否が分かれたであろう終盤の「衝撃の展開」については、エメラルド・フェネル自身もかなり迷いながら、あの描き方を選択したといいます。
ですので、賛否が分かれることも分かった上で、なぜこの結末を選んだのかという視点を持つことを忘れてはいけません。
ぜひ、多くの人にご覧いただいて、自分なりに咀嚼する過程で、じっくりと考えてみてほしい、そんな作品に仕上がっていると思いました。
ここからは、本作『プロミシングヤングウーマン』について自分なりに感じたことや考えたことをお話していきます。
本記事は作品ネタバレになるような内容を含む解説・考察記事です。
作品を未鑑賞の方はお気をつけください。
良かったら最後までお付き合いください。
目次
『プロミシングヤングウーマン』解説・考察(ネタバレあり)
「プロミシングヤングウーマン」というタイトルの妙
(C)Universal Pictures
日本で未成年による犯罪が起きたときに、被害者の実名は当たり前のように報道されるのに、加害者の実名は伏せられる傾向があります。
なぜ、加害者の実名が出ないのかというと、それは「少年法の目的が処罰ではなく更生を目的としていること」に起因します。
もちろん事件の特性によっては、実名報道が容認されるケースもありますし、どちらにしてもメリット・デメリットがあるので、一概に実名報道をするべきだ!と肯定するつもりはありません。
しかし、被害者は「未来」を奪われているというのに、加害者の側だけが「未来があるから=プロミシングだから」という理由で、守られることにいささか違和感を抱くのは当然のことだと思います。
『プロミシングヤングウーマン』のタイトルは、そもそも法律用語の「プロミシングヤングマン=前途有望な若者(男性)」から引用してつけられたものです。
男性を裁判の場で擁護する際に、プロミシングヤングマン=前途有望な若者(男性)」だからという理由で、女性に不利な判決が出ることがアメリカで容認されてきたバックグラウンドに対し、皮肉を込めてつけられたわけですね。
今作において、ニーナはアルによる性的暴力の被害を受け、その将来を閉ざされてしまいました。
しかし、アルは本来その罪により未来を閉ざされるべきであったのに、その裁きを受けることなく、何事もなかったかのように輝かしい未来を享受しているのです。
なぜ、被害者だけが未来を奪われ、加害者は「プロミシング」だとして守られ、奪われるべき未来を奪われることもなく、のうのうと人生を謳歌することができるのか。それが許されてしまうのか。
『プロミシングヤングウーマン』は「男性」と「女性」という構図を強調していますが、突き詰めると、もっと普遍的な「加害者」と「被害者」の物語の様相を呈しています。
「人を呪わば穴二つ」という言葉もありますが、誰かを陥れておいて、自分だけが許されて良いはずなどありません。
だからこそ、『プロミシングヤングウーマン』は事件の加害者ないし傍観者の立場にあった人間が受けるべきであった「罰」と向き合う物語だと言えます。
そして、それはアルやジョーといった積極的加害者だけを対象にしたものではありません。傍観者だったライアンやマディソンも対象であり、さらにはニーナのために何もしてあげられなかったキャシー自身にとっても贖罪の物語となっているのです。
1つの死、奪われた未来に対して、周囲の人間がどう向き合い、どう裁かれるべきなのか。
それをじっくりと問いかけ、然るべき罪を背負うことを求められていく様を秀逸な脚本で描き切ったからこそ、本作はアカデミー賞脚本賞を受賞するほどの高評価を得ることができたのです。
「リベンジ」もののプロットは2パターンある
(C)Universal Pictures
本作『プロミシングヤングウーマン』は、大別すると「リベンジもの」と呼ばれるジャンルに含まれる作品です。
さらに、この「リベンジもの」というジャンルの物語の展開の仕方は、大きく分けると2つ存在しているのではないかなと考えています。
1つ目は主人公をいわゆる「ビジランテ」に仕立て上げ、超法規的にリベンジを実現させる物語ですね。
これは、分かりやすいところで言うと『ジョンウィック』のような作品で、法やシステムがどうすることもできない世界・領域で、個人が自分の理念や考えに基づいて独自に正義を追求していくものとなります。
アクション映画だと主人公を「ビジランテ」に位置づけてしまう方が、物語の構図が単純明快になるため、好んでこの展開が用いられている場合が多い印象を受けますね。
一方で、2つ目は主人公がシステムや法の範疇でリベンジを目論見、最終的にはその法やシステムに裁きを委ねるというものです。
例えば、『ショーシャンクの空に』に登場する悪徳刑務所長の男がいましたが、彼は最終的に主人公サイドから暴力でボコボコにされるというような断罪のされ方はしませんでしたよね。
あくまでも淡々と証拠を突き出され、司法の下で「裁き」を受けるという形で、主人公サイドからのリベンジを受けました。
『プロミシングヤングウーマン』は、この2つのアプローチのどちらか一方を選択するのではなく、そのハイブリッドのような形で物語を展開させたのが非常に面白かったと思います。
序盤は、キャシーがアナーキーな雰囲気を漂わせており、自らの手で「男性」ないしニーナの事件の関係者を断罪する姿勢を見せているため、観客は当然前者のプロットを想定して物語を追っていくことになりますよね。
特に、序盤は主人公が金銭を払って、女性を襲わせたり、女子高生を誘拐させたり、弁護士の男性を襲わせようとしていたことを匂わせたりと、暴力的でかつ超法規的なリベンジを意図しているのだと幾度となく観客に印象づけてきます。
しかし、実際には女性は襲わせておらず、誘拐も未遂でしかなく、弁護士の男性に至っては赦しを与えていたりと、そうした印象が少しずつひっくり返っていくのです。
そして、終盤に突入すると、キャシーがあの山小屋で、ニーナを襲った張本人であるアル・モンローにリベンジを果たす算段となります。
ここで、再びエメラルド・フェネルは、キャシーを「ビジランテ」的なリベンジに走らせるような素振りを見せます。
彼女がアル・モンローの身体に「NINA」という文字を堀り、その名前を一生身体に背負って生きるよう求めるわけですが、ここで物語が大きく転回していきました。
エメラルド・フェネルはキャシーを「ビジランテ」にはしなかった
(C)Universal Pictures
今回の『プロミシングヤングウーマン』の脚本を執筆するにあたって、エメラルド・フェネルはかなり終盤の描写について迷っていたそうです。
というのも、当初はキャシーがアル・モンローの身体に傷を入れ、更には性器を切断し、家に火をつけて去っていくという痛烈な復讐劇を完遂を描くつもりだったんですね。
しかし、これ彼女はそうした結末がいささか現実離れしており、その「痛快さ」のために本作が観客にフィクションとして安易に消費されてしまうのではないかと危惧したのだとか。
これを踏まえて、エメラルド・フェネルは今一度脚本を見直し、劇場公開された映画で描かれた形に辿り着きました。
この結末は、キャシーを「ビジランテ」にしてしまうのではなく、むしろ法やシステムにその裁きを委ねるものとなっていました。
ただ、この結末だったからこそ、『プロミシングヤングウーマン』は多くの人に余韻を残し、深く考えさせ、エンタメとして安易に消費されない強度を持った作品に仕上がったのだと感じています。
そもそも「ビジランテ」は自分の中の正義に基づいて行動するため、法やシステムを侵害していることがほとんどで、そうなるとキャシー自身も正義を追求していると言えど、「罪人」というカテゴリから逃れられなくしてしまうのです。
そうなると、復讐を果たしたことに対しては痛快さや爽快感を観客に抱いてもらうことはできるかもしれませんが、じっくり考えてみると、果たしてその行動は正義といえるのか?というモヤモヤを抱えることになるでしょう。
だからこそ、キャシーを「ビジランテ」にするのではなく、あくまでも法とシステムによる「裁き」を突きつける者として描き切ることで、『プロミシングヤングウーマン』は彼女を、その死でもって高潔で、神聖な女性として印象づけることに成功しています。
あくまでも、その行く末については、既存の法とシステムと、そこに携わる人に委ねているわけです。
また、『プロミシングヤングウーマン』の脚本が素晴らしいのは、ニーナの事件に関わった人間1人1人が、キャシーの死に伴って、自分の中の「罪」と向き合うことを余儀なくされるという状況の作り出し方なのだと思いました。
マディソンは、過去に自分を頼って相談してくれたニーナに対して、まともに取り合わず、「あなたにも非があったのでは?」と突き放したわけですが、今度は自分自身が同じ状況に置かれ、ニーナの置かれた状況の悲惨さを自らの身体を持って体感しました。
アル・モンローやジョーは、再び自分たちの犯した罪を闇に葬り、何事もなかったかのように自分の人生に戻ろうとしたわけですが、もはやその罪から逃れることはできません。
かつてアル・モンローに有利になるような裁判の進め方をし、ニーナを精神的に追い詰めた弁護士の男はキャシーの死の証拠とニーナの事件の録画ビデオのデータを入手し、自分が裁判でどのような振る舞いをするのかが問われています。
そして、観客にもっとも重なるのは、ライアンが置かれた状況ではないでしょうか。
ライアンに突きつけられた結末と後味のこの上ない悪さ
(C)Universal Pictures
ライアンは積極的に罪を犯した人間ではなく、あくまでもアル・モンローの蛮行を傍観していた人間の1人に過ぎません。
しかし、それを止めなかったこともまた立派な罪なのであり、何もしなかったことはそれそのものが責められるべきだと断罪されるのです。
エメラルド・フェネルは、キャシーを「ビジランテ」に仕立て上げることによる痛快さよりも、観客に物語の「当事者」の1人になることを強いるような「後味の悪さ」を選択しました。
ライアンはキャシーについて聞かれた際に、彼女の精神的な不安定さを肯定し、アル・モンローないし自分の身を守ろうとする素振りを見せましたよね。
つまり、彼自身も人間として成長したように見えて、実際のところあの時から何にも変わっておらず、罪を犯す人間を「傍観する」立場に立ち続けているのです。
だからこそ『プロミシングヤングウーマン』は、そんな「傍観者」にいるライアンに当事者意識を植え付ける結末を用意したわけですが、引いてはこの「傍観者」というのは観客である私たちに重なります。
観客は、本作を見ながら自分ならアル・モンローやジョーの行いを許さないし、彼らを止めに入り、断罪するだろうと「物分かりの良いこと」を考えるはずです。
しかし、現実で同じようなことが起きれば、きっとそんな人たちもライアンと同じような行動を取るでしょう。
当ブログ管理人も、現実で同じような状況に直面した時に、毅然とした振る舞いができるかと問われたときに、迷わず首を縦に振ることができる絶対的な自信はありません。
少なからず、周りに流されたり、自分の保身を考えてしまう可能性を否定できませんし、積極的に加担していない「傍観者」が断罪されることはないだろうと高をくくってしまう可能性を排除することもできません。
ただ、映画を「傍観者」として見ている分には、自分がそうした正義を行使できる超人になれるだろうと安易に考えてしまいがちです。
そうした考えに至るのは、私たちが映画の中の物語に何ら関与しない「傍観者」でしかないからこそですよね。
しかし、『プロミシングヤングウーマン』は観客に「傍観者」の立ち位置に留まることを許してはくれません。
ライアンというアバターを通じて、私たちは明確にこの物語の、あの事件の「当事者」の1人に位置づけられ、問われるのです。
そうした「後味の悪さ」があることにより、『プロミシングヤングウーマン』という作品はとてつもないパワーを秘めた作品となりました。
私も展開が二転三転する物語をどこか客観的な視点で「楽しんで」いたわけですが、このラストシーンを見たときに、座席に座ったままひんやりとしましたね。
映画は物語を見て、そこで完結するものではないと常々思っています。
それを観客が見て、自分の中である程度咀嚼して、そこで1つの「体験」として完成するものだと私は思うのです。
『プロミシングヤングウーマン』は、まさしくそうした映画の醍醐味を体感できる素晴らしい作品と言えます。
おわりに
いかがだったでしょうか。
今回は映画『プロミシングヤングウーマン』についてお話してきました。



映像の迫力や臨場感の部分で、観客に「体感」させるような映画作品は近年の映像技術の発展もあり、増えてきましたが、脚本の妙で観客を物語に巻き込んで、逃がさない作品はなかなかお目にかかれません。
そういう意味でも『プロミシングヤングウーマン』は、卓越した映画作品だと思いますし、見終わった後に、この映画について考えることから逃れられない作品だと思います。
どうしても、「男性」「女性」という括りで見られてしまいがちな部分はありますが、もっと普遍的な物語として見ていただきたいなと個人的には感じています。
誰かの未来を奪った人間に、然るべき罰も与えられず、その未来が担保されることが許されてしまって良いのか。そして、罪を傍観してきた人間には「罪」がないと言い切れるのか。
この映画は、私たちに伝えようとしているのではなく、問いかけ、考えることを求めているのです。
今回も読んでくださった方、ありがとうございました。