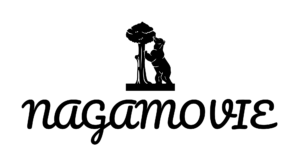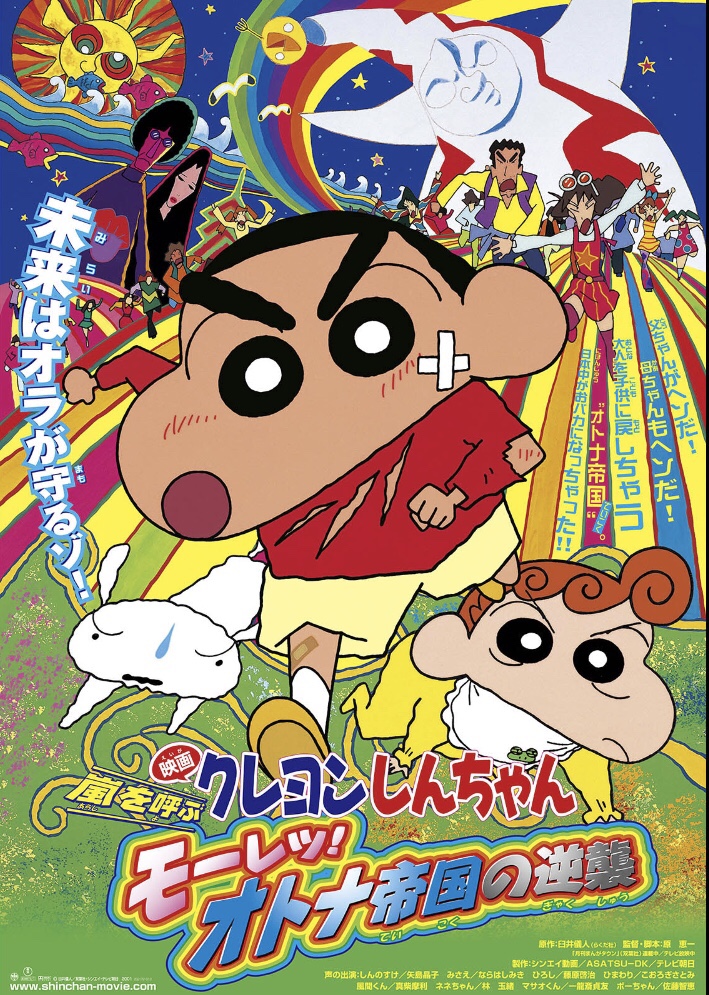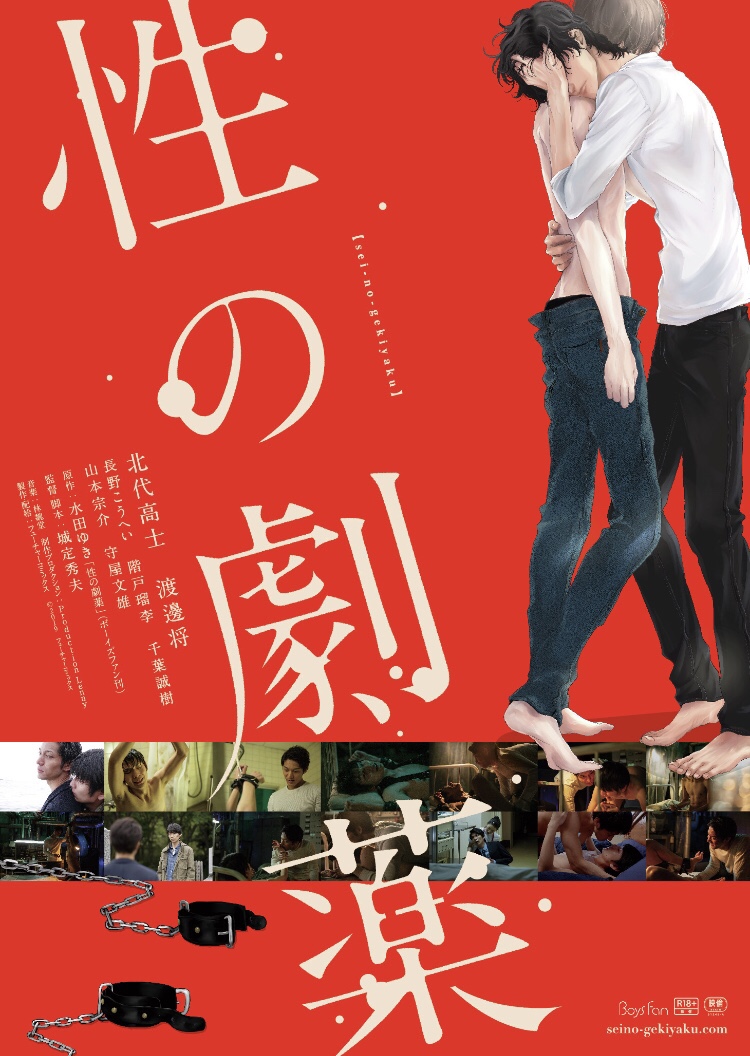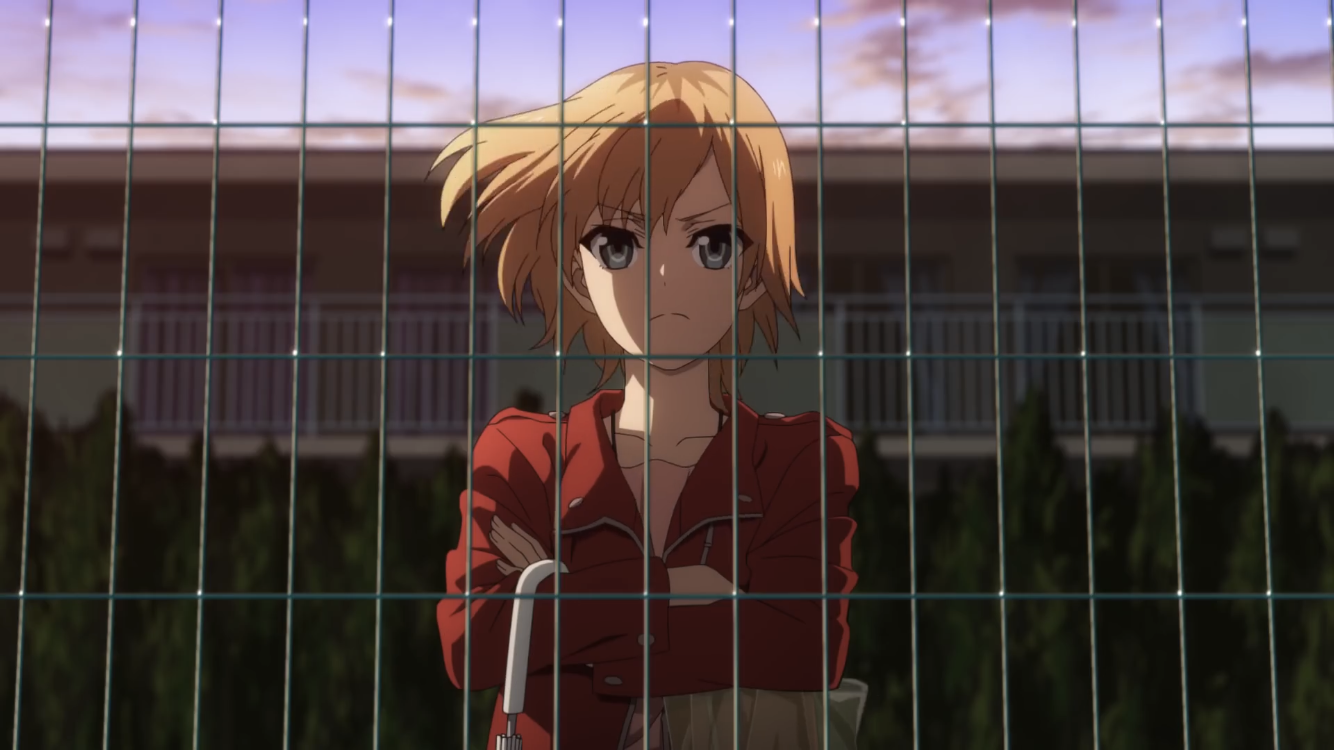みなさんこんにちは。ナガと申します。
今回はですね映画『クレヨンしんちゃん 謎メキ!花の天カス学園』についてお話していこうと思います。

昨年公開された『映画クレヨンしんちゃん 激突!ラクガキングダムとほぼ四人の勇者』はシリーズ屈指の名作で、終盤は号泣でした。
最近の映画『クレヨンしんちゃん』の傾向として、顕著なのが、近年の教育界の動向に敏感なプロット作りだと思います。
昨年の作品では、教育改革のキーワードにもなっている「創造性」の部分に焦点を当て、子どもたちの自由で豊かな、大人に縛られない自由な創造が担保されることの重要性を説きました。
そして、今回の『クレヨンしんちゃん 謎メキ!花の天カス学園』は脚本の担当がうえのきみこさんに戻りましたが、そうした教育アニメ路線は継続されている印象を受けます。
特に面白かったのは学校というシステムにおける「子どもの評価」という難しい領域に言及していた点でしょうか。
それに加えて、AI技術をプロットに盛り込み、人間らしさとは何か?を問うような深い視座が見え隠れしている作品にもなっていたこともあり、大人の自分も引き込まれました。
また、今回の映画『クレヨンしんちゃん』は、ひろしやみさえと言った大人組がほとんど絡んでこない一風変わった物語になっているのですが、それがかえって新鮮でしたね。
学園モノ、ミステリ、青春映画、恋愛映画、スポーツ映画、SF…と様々なジャンルをミックスしたある種の「闇鍋」映画ではありましたが、伝えたいことは一貫しており、強く心に響いた1本だったと思います。
今回はそんな『クレヨンしんちゃん 謎メキ!花の天カス学園』について個人的に感じたことや考えたことをお話していこうと思います。
本記事は作品のネタバレになるような内容を含む感想・考察記事です。
作品を未鑑賞の方は、お気をつけください。
良かったら最後までお付き合いください。
目次
『クレヨンしんちゃん 謎メキ!花の天カス学園』感想・考察(ネタバレあり)
「サザエさん時空」でいかにして「変わる」「終わる」を描いたか?
(C)臼井儀人/双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 2021
『クレヨンしんちゃん』シリーズは、キャラクターが歳を取ることなく、半永久的にその世界の中で同じ時間を繰り返す、いわゆる「サザエさん時空」の作品です。
そのため、漫画の連載が始まったころから今に至るまで、主人公のしんのすけたちはずっと幼稚園児のままですよね。
ただ、この「サザエさん時空」は「青春映画」というジャンルとは実はかみ合わせの悪い設定でもあります。
なぜなら、「青春映画」においては、登場人物に変化や終わりがもたらされることが何よりも重要視されるからです。
「終わり」があるからこそ青春というものは輝くのであり、「変わる」があるからこそ青春は感情を揺さぶるわけですよ。
『うる星やつら2 ビューティフルドリーマー』は名作として名高い作品ですが、この映画では、「サザエさん時空」に巻き込まれた主人公が、そこから脱却していくところに物語の力点が置かれています。
何も変わらない時間が永遠に続く世界から脱却し、主人公が「青春」を取り戻すという構図が1つの作品にまで昇華したわけです。
つまり、「サザエさん時空」と「青春映画」は完全に水と油の要素であり、それを混ぜ合わせるのは、かなり難しいことなんですね。
話を戻しますが、今回の『クレヨンしんちゃん 謎メキ!花の天カス学園』は、まさしく「サザエさん時空」と「青春映画」を融合させようと試みたかなりチャレンジングな作品だと思います。
『クレヨンしんちゃん』で「青春映画」をやるというのは、簡単なようで、すごく難しいんですよ。
例えば、同シリーズには「オトナ帝国の逆襲」という名作がありますが、あれもあくまで単発の作品であり、あの映画の中で起きた出来事はその後の『クレヨンしんちゃん』の物語に影響を及ぼしていません。
といった具合に、映画の中で物語が完結し、リセットされてしまう構造がある以上、変化や終わりを描いたとしても、それが持ち越されることはないのです。
では、そんな制約がある中で、今回の『クレヨンしんちゃん 謎メキ!花の天カス学園』は、「青春映画」のジャンルを持ち込んだのか。
それは、変化や終わりの到来の予感を物語の中に持ち込むことでした。
今作は、しんのすけとひろし&みさえという親子関係の変化、そして春日部防衛隊の面々の友情の変化という2つの「変わる」に焦点を当てています。
まず、前者については開始早々に印象的なシーンがありました。
(C)臼井儀人/双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 2021
天カス学園への体験入学で1週間家を不在にするしんのすけをみさえが「1週間分だからね」と強く抱きしめ、涙ながらに見送る描写なのですが、これグッときましたね。
いつか、しんのすけが成長して、あの家を出る日が来るのではないかという遠い日の別れの予感を漂わせる印象的な描写だったと思います。
そして、春日部防衛隊の面々の友情の変化についてですが、こちらも彼らが卒業した後の小学校進学の話題を挙げる中で徐々に予感を漂わせていきました。
風間君が私立の小学校受験を志している一方で、しんのすけたちとずっと一緒にいたい、ずっと友達でいたいという相反する願いを内に秘めており、その狭間で葛藤している様に胸を締め付けられましたね。
彼らはもしかすると、同じ小学校には通っていないのかもしれませんし、同級生という関係性は終わりを迎えてしまうのかもしれません。
それでも、彼らはずっと友達で居続けるのだろうという未来への温かな希望が確かに感じられる物語の結末になっており、『クレヨンしんちゃん』でよくぞここまで王道の「青春映画」を作り上げたな!という感動がありました。
変化や終わりを明確に描くと、「サザエさん時空」によって、リセットされてしまうかもしれません。
しかし、変化や終わりへの「予感」であれば、それは半永久的に訪れることがないとわかっていても、消えることはありません。
そんな予感を映画の中に通底させることによって、「サザエさん時空」の中で「青春映画」を描き切った本作に拍手を贈りたいですね。
「無駄」こそ必要だ!という大切なメッセージ
(C)臼井儀人/双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 2021
記事の冒頭でも少しだけ触れましたが、近年の映画『クレヨンしんちゃん』シリーズは、すごく新しい教育の在り方に敏感な作品に仕上がっている印象を受けます。
そして、今作と前作の『映画クレヨンしんちゃん 激突!ラクガキングダムとほぼ四人の勇者』はメッセージ性の部分では、非常に似ていると思いました。
伝えようとしているのは、一貫して
「無駄」こそ必要だ!
というメッセージ性なのです。
前作では、「ラクガキ」という役に立たないものが春日部を救うという形で大人の価値観に縛られない子どもの自由で無限の発想や創造を全肯定しました。
そして今作では、AIによる子どもたちの評価という面白いアプローチを盛り込んでいましたね。
「エリート」というのは、誰目線の概念なのかと聞かれると、それは当然大人や社会からの目線によって決定されるものです。
今の大人の価値観や考え方、そして社会の在り方や仕組みから逆算的に考えたときに、あるべき理想の姿の子どものことを指して「エリート」と呼称するわけです。
例えば、学歴至上主義の社会に私たちが生きていたとしたら、そして社会を構成する大人たちが学歴で人を判断するような価値基準のもとに生きていたとしたら、当然勉強ができる子どもが「エリート」だということになります。
仮に私たちが狩猟社会に生きていたとしたら、力の強さや仮のテクニックに優れている子どもが「エリート」ということになるでしょう。
でも、この「エリート」というのは、あくまでも今現時点の社会やそこに生きる大人の視座でしかなくて、未来の社会がどうなっているのかが全く見えない現代において、本当に通用する概念なのか?という疑問は持っていたほうが良いと思います。
今回の『クレヨンしんちゃん 謎メキ!花の天カス学園』に登場する天カス学園は、今の社会に適応する人間を効率よく育てる工場のような仕組みに裏打ちされていました。
大人から見た「無駄」を子どもたちの学びや生活から排除し、きわめて合理的かつ最短ルートで子どもたちを社会に適応する「エリート」に育てようとする方法論は、今の社会を維持していくという意味で悪くない手法かもしれません。
しかし、それでは子どもたちの可能性を広げることはできませんし、未来が開けていかないのです。
私が好きでよく見ているYouTuberさんの中に「藤原麻里菜」さんという方がいらっしゃいます。
彼女の肩書は「無駄づくり発明家」なのですが、一見何の役にも立たなそうな発明品を作り出し、それをSNSや動画サイトで発信することによって、人を楽しませるというエンターテインメントを提供しているんです。
私自身、彼女の考え方がすごく好きなんですが、「無駄」なことであっても、自分が好きだからと信じて続けることで、そこに「価値」が生まれるわけですよ。
これからの社会に求められるのは、彼女のような自ら自発的に考え、何かを創造していく人間だと学習指導要領などでも明記しているわけで、だからこそなおさら大人や社会が子どもたちの「無駄」を決めてしまってはいけないと思っています。
大人たちは自分が子ども時代、青春時代を既に通り過ぎてきたからこそ、失敗や後悔を経験していて、それに基づいて、子どもにはそれを回避してほしいとついつい物を言ってしまうものです。
しかし、そうした失敗や後悔もまた今のあなたを構成している大切な要素であり、それは決して「無駄」ではありません。
大人の立場から「無駄」だと決めつけて、そうした失敗や後悔を子どもに回避させようとする親心が可能性を狭めてしまったり、主体性を奪ってしまうことがあるかもしれません。
だからこそ大切なのが、
「どんな青春でも……いつか笑って思い出してほしいですね。」
という大人の視座なのだと思いました。
私も大人になってから、時々学生時代のことを思い出します。でも、思い出すのは巧く言った経験ではなく、失敗した経験や後悔した出来事ばかりです。
そうした経験や出来事を「無駄」だったと切り捨てることは簡単だと思います。
でも、そんな「無駄」を今は愛おしく思いますし、あの「無駄」が今の自分を支えてくれていると断言することができます。
つまり、無駄ではなかったということですね。
近年のトレンドにもなっている「持続可能な社会」というキーワード。でも、「持続可能な社会」って未だかつて人類が実現していない社会なんですよね。
それを実現するための答えを私たちはまだ持っていないのです。私たちが「無駄」だと切り捨てたものが答えになる可能性だってあります。
だからこそ、これからの教育は、大人に示された道を行き、大人に示された問いに答えを出すだけでなく、自ら問いを作り出し、答えのない問題に果敢に挑んでいくような姿勢を育てていかなくてはなりません。
そのためには、子どもたちが「無駄」に取り組む姿を温かく見守り、応援してあげるほかないのかもしれないですね。
『クレヨンしんちゃん 謎メキ!花の天カス学園』は、子どもが楽しめる映画でありながら、子どもに対して大人がどう向き合うべきなのかを考えさせてくれる素晴らしい作品に仕上がっていたと思います。
「無駄」こそ必要だ!
この言葉を、私自身も大切に心のうちに持っておきたいです。
おわりに
いかがだったでしょうか。
今回は映画『クレヨンしんちゃん 謎メキ!花の天カス学園』についてお話してきました。



学園モノ、ミステリ、青春映画、恋愛映画、スポーツ映画、SF…と様々なジャンルをミックスしたことで、かなりごちゃっとした印象は受ける映画でしたが、テーマの軸がしっかりとしていたので、何とかまとまっていたと思います。
前作に引き続き、大人が子どもに向き合う際に気をつけたい大切なことが詰まった良い作品に仕上がっていましたね。
『ドラえもん』や『名探偵コナン』といった長寿シリーズが、近年大人向けな内容にシフトしていますが、『クレヨンしんちゃん』シリーズは子ども向けを貫きながらも、大人ないし保護者に響く物語性を担保できているのが素晴らしいと思いました。
そういう意味でも、唯一無二のポジションを確立しつつあるといえるのではないでしょうか。
公開延期にはなってしまいましたが、今年の映画『クレヨンしんちゃん』が多くの人に届いてくれるよう影ながら応援しております。
今回も読んでくださった方、本当にありがとうございました。