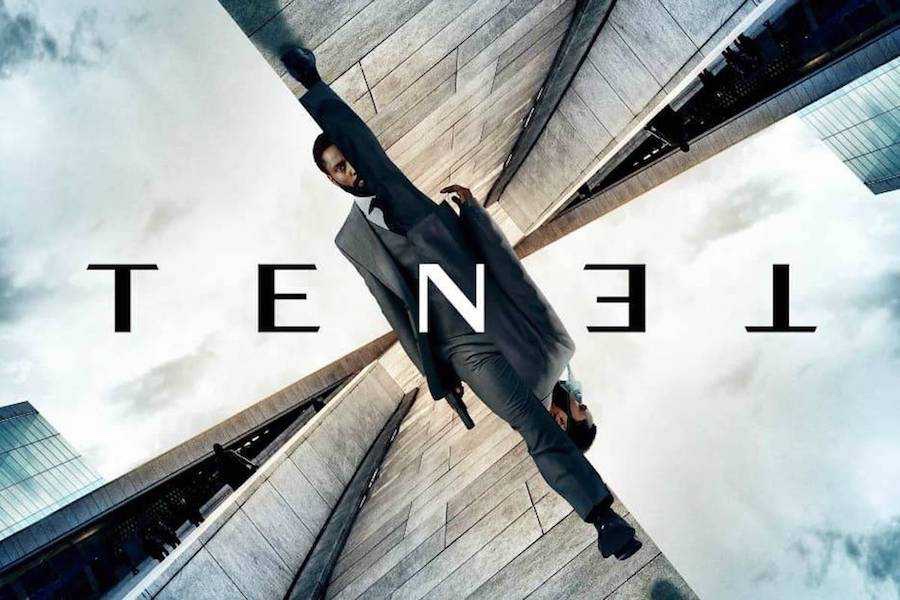みなさんこんにちは。ナガと申します。
最近、映画館に行ったら『グレイテストショーマン』の主演2人が『インセプション』みたいなことやってる映画の予告編が流れてたんですよね。
あ、これですね。映画『レミニセンス』!
(C)2021 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved
う~ん。いや、このポスターのデザインというかタイトル文字の色というか、どこかで見たことあるんだよな~。

(C)2010 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved
構図から配色に至るまで完全にやっちゃってるんですが、確かに予告編の印象は『インセプション』に似ていました。
だからといって、ここまで似せて、二匹目のどじょうを狙いに行くのってどうなの?と思いますし、そもそもこんなに似せちゃって良いの?という疑問もあります。
ただ、調べてみると、この2つの映画とんでもない共通点がありました。
まず、『インセプション』の監督。これは言わずも知れた名匠クリストファー・ノーランですね。
『ダークナイト』や『インターステラー』などでもお馴染みです。
次に『レミニセンス』のプロデューサーと脚本を見てみましょう。
プロデューサーがジョナサン・ノーラン。脚本がリサ・ジョイ。









クリストファー・ノーランとジョナサン・ノーランは、なんと兄弟関係にあります。(クリストファーが兄で、ジョナサンが弟)
さらにさらに、脚本のリサ・ジョイ。彼女はなんとジョナサン・ノーランの彼女というか嫁というか奥さんというか家内というか妻なんですよ。
つまり、リサ・ジョイから見ると、クリストファー・ノーランは「義理の兄」になります。
そう考えると、『インセプション』と『レミニセンス』は血縁関係があるので、ポスターが似ているのも当たり前ですね。
今回の記事では、そんなジョナサン・ノーランについてある程度、解説をさせていただいた上で、『レミニセンス』の印象的なラストシーンにの自分なりの解釈を書かせていただこうと思います。
本記事は作品のネタバレになるような内容を含む解説・考察記事です。
作品を未鑑賞の方はお気をつけください。
良かったら最後までお付き合いください。
目次
『レミニセンス』解説・考察(ネタバレあり)
ジョナサン・ノーランの3つの偉大すぎる功績とは?
①ストーリーテーリングの革命『メメント』誕生秘話
ノーラン兄弟の功績を振り返る上で、その原点ともいえるのがやはり2000年公開の映画『メメント』です。
ネタバレになるので、詳細は伏せますが、映画の時系列表現の常識をひっくり返したと言っても過言ではない作品だと思います。
『メメント』は、一般的にクリストファー・ノーラン監督の出世作として知られ、アカデミー賞でも脚本賞と編集賞にノミネートされました。
しかし、この『メメント』の最大の功労者と言っても過言ではないのが、実は弟のジョナサン・ノーランなのです。
兄クリストファーがデビュー作である『フォロウィング』の撮影を終えた頃、弟ジョナサンは大学の休暇に入りました。
この休暇中に、ジョナサンはふと大学の心理学の授業で学んだ「逆行性健忘症」のことを思い出し、これを題材にした物語を作ってみたいと思い立ちます。
そうして、ジョナサンは『Memento Mori』という短編小説を書き始めました。
ちょうどその頃ジョナサンは、兄と一緒に車でシカゴからロサンゼルスまで旅をしたのですが、その際に『Memento Mori』のアイデアをに話したところ、「それめちゃくちゃ面白いじゃん!」と大盛り上がり。
それを受けて、クリストファー・ノーランは後に『メメント』として公開されることになる映画の脚本の執筆をスタートさせたのです。
時系列を解体する物語の独特な見せ方や演出、クリストファーにしかできない芸当ですが、
映画『メメント』にはジョナサン由来のアイデアもたくさん見受けられます。
「逆行性健忘症」の主人公という基本設定はもちろんとして、妻が殺害されているサスペンス性や主人公が身体にタトゥーでメッセージを彫りこんでいるという視覚的な演出は短編『Memento Mori』にも描かれていた内容です。
この2人の違った視点や作家性が融合したことで、『メメント』は革新的な映画となり大絶賛で迎えられました。
こうして、後に『ダークナイト』や『インターステラー』といった名作を世に送り出すこととなるクリストファー・ノーランとジョナサン・ノーランというゴールデンブラザーズが誕生したわけですね。
②『ダークナイト』シリーズ大成功の陰の立役者?
みなさんはクリストファー・ノーラン監督作品と言えば何を思い浮かべますでしょうか。
この動画を見たみなさんにぜひ覚えておいていただきたいのが、実はこの5つの作品の原案・脚本に弟のジョナサン・ノーランが関わっていること。
- 『メメント』
- 『プレステージ』
- 『ダークナイト』
- 『ダークナイト ライジング』
- 『インターステラー』
その中でも、その最大の功績の1つは、やはりヒーロー映画史に残る傑作と名高い『ダークナイト』を世に送り出したことですよね。









それは『バットマン ビギンズ』から『ダークナイト』への進化、そして『バットマン ビギンズ』にはジョナサンが参加していなかったという事実だけが分かれば皆まで言う必要はないでしょう。
この作品で特に注目を集めたのが、ヒースレジャー演じるジョーカーですよね。
『ダークナイト』のジョーカーの恐ろしさは、そのオリジンやバックグラウンドが全く描かれず、始まりと終わりの秩序に縛られないアナーキーな存在感に由来すると多くの人から指摘されています。
『Batman: The Killing Joke』というコミックスで、バットマンに追い詰められ、逃げるために化学薬品の溶液の中に飛び込んだという有名なオリジンが描かれているのは有名です。
ただ、ジョナサンは「最も恐ろしい悪役はその動機が謎めいている、もしくは動機を持っていなキャラクターだ」と語っており、こうした背景を脚本に持ち込みませんでした。
そのコンセプトがヒーロー映画史に残るヴィラン誕生に一役買ったわけですから、ジョナサンの存在は大きいですよね。
また、続編の『ダークナイトライジング』では制作初期の段階で、400ページに及ぶ脚本を執筆し、物語の基礎を構築しました。
この脚本はチャールズ・ディケンズの名著『二都物語』にインスピレーションを受けて書かれたもので、クリストファーにも感銘を与えたと言われています。









③最高傑作『インターステラー』の基礎を作り上げた!
そして、クリストファーノーランを語る上でもう1つ欠かせない傑作は、やはり『インターステラー』でしょう。
僕自身も2020年に大阪エキスポシティのIMAXシアターでリバイバル上映をされた際に改めて鑑賞したのですが、フル画格の映像に心が震えましたね。
実はこの映画が作られるきっかけを知るには、かなり時を遡らなければなりません。
この映画のプロットのアイデアやコンセプトは、プロデューサーのリンダ・オブストと理論物理学者のキップ・ソーンの2人から生まれました。
そして、このプロットに最初に目をつけたのは、クリストファーノーラン…ではなく名匠スティーブン・スピルバーグでした。
スピルバーグが監督を務めるプランでこの映画の制作プロジェクトが始まり、その脚本を執筆を担当したのが、他でもないジョナサン・ノーランだったのです。
ただ、スピルバーグが諸事情で監督を務められなくなり、後任を誰にするかという話が浮上し、この時に脚本を書いた弟のジョナサンが、兄のクリストファーを推薦したんですね。
こうしてクリストファー・ノーランの代表作の1つでもある『インターステラー』の公開に向けて時計の針が動き始めました。
物語の大枠はジョナサンが作り上げていたのですが、ここにクリストファーが「人間の本質や感情に迫るようなドラマ性」を加えていったことがインタビューなどで明らかになっています。
まず、ポスターを見ても一目瞭然ですが『インターステラー』の中心にあるのは親子の愛の物語で、特にクライマックスは感動しますよね。
親子の設定そのものは、元々の脚本にあったものですが、「親子愛」にここまでフォーカスして物語を展開するというアプローチは、クリストファーが付け加えたものなんだそうです。
これに関連して、ネタバレになるので皆までは言えませんが、ジョナサンの脚本と実際に映画として公開された『インターステラー』では、ラストが全く別物なんだとか。
オリジナルの脚本では、かなりダークで残酷な結末が待っていたようです。こちらもインタビューなどで一部明らかになっているので、ぜひ調べてみてください。
また、クリストファーが付け加えた要素として非常に大きいのが、映画を見た人ならイライラしたこと間違いなしの「マン博士」です。
『ダークナイト』のハービー・デントのような光と闇を内包した人間像は、クリストファー・ノーランらしいと思います。
このように、クリストファー・ノーラン作品と言うのは、弟のジョナサンが物語の大枠や基礎を作り、そこに兄クリストファーが斬新で、目を引くアイデアやドラマ性を追加しながら作り上げられてきたことが分かりますよね。
『レミニセンス』のラストシーンを紐解く
(C)2021 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved
ここからは映画『レミニセンス』のラストシーンについて個人的な解釈を書かせていただこうと思います。
記事の冒頭で『インセプション』風のポスターになっていることを紹介しましたが、SF性やサスペンス性のある作品であることをやたらと匂わせていました。
ただ、本編を見てみると、新海誠監督作品のような青臭さとエゴすら感じさせる、1人の男の「恋愛」と「執着」の物語だったので、そのギャップに驚かされましたね。
そうしたギャップのせいか全米でも興行成績が振るわず、批評家・オーディエンス共にから支持を得られていない状況に追い込まれている本作。









特にあのいろいろな感情が押し寄せてくるラストシーンの余韻は言葉にならないものがあり、思わず涙がこぼれました。
では、なぜ『レミニセンス』のラストシーンが素晴らしいのかを、自分なりの解釈とともに語らせていただきます。
自分の記憶を覗くと「第三者視点」になるという設定
(C)2021 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved
まず、ラストシーンについて語る前に抑えておかなければならない重要な設定があります。
劇中で本作の過去の記憶を見る装置の設定について言及されていた時に、こんな話が挙がっていたのを覚えていますか?
自分の過去を覗くとき、あなたは過去の光景を「第三者」視点で見ることになる。
この設定って私たちの回想の構造を巧く投影しているものだと思いました。
例えばですが、みなさんが「恋人や友人との印象的な思い出を1つ頭に浮かべてください。」と言われたとしましょう。









おそらく、多くの人のイメージの中に「自分」が含まれているんじゃないかなと思います。
自分を排した1人称視点で過去の光景を思い出す人ってまずいないんじゃないでしょうか。
当ブログ管理人も友人と旅行に行った日のことを思い出してみましたが、やっぱり思い出している自分自身の視点が当時の自分と重なって「1人称」で過去を見るなんてことにはならなりませんでした。
つまり、人間は回想をするときに、過ぎ去った過去を「当事者」として振り返るのではなく、過ぎ去った時間に干渉することのできない「傍観者」としてただ眺めるにすぎないわけです。
『レミニセンス』という作品において、この過去を振り返る際に自分は「傍観者」にしかなり得ないという設定は非常に重要な意味を持っています。
主人公のニックは愛するメイを救うために、様々な人物の記憶をさかのぼり、自分が見ることのできなかった彼女の姿を目撃していきました。
しかし、どれだけ過去を深く知り、どれだけ真実に迫ったとしても、起きてしまった出来事を変えることはできないのだという現実を突きつけられていきます。
そして、今作において最もエモーショナルなシーンの1つは、やはり命を絶つ寸前のメイがサイラスを前にして、いつの日かこの記憶を見るであろうニックに向けた告白をするシーンです。
あの言葉は確かにニックに向けられたものであり、明白な愛の告白でした。
しかし、ニックはあの場にはおらず、彼女の目の前にいたのはサイラスであり、これは動かすことのできない事実なのです。
記憶を再現する装置の上で、ニックがサイラスのイメージを搔き消し、メイの前に立ったところで、それは切ない「IF」に過ぎず、彼はどこまでも「当事者」にはなり得ません。
メイはニックに助けを求め、彼の仕事場の扉を叩いていました。ニックがそれに応えて、扉を開けたときにはもう誰もいませんでした。
彼は、サイラスの記憶を辿る中で、その事実を知ります。
事実を知ることで、過去のイメージの見え方は変わりますが、その本質が変わることはありません。
何度その記憶を呼び起こしたところで、ニックが扉を開けてメイを迎え入れる世界線は存在せず、彼はメイがサイラスに連れていかれるのをただ傍観することしかできないのです。
このように人間は自分の、他人の過去を、どこまでも「第三者」視点でしか見ることができず、過去に一切の干渉を許されない「傍観者」であることを強いられるという空虚さと切なさを抱えることになります。
『レミニセンス』には設定により「記憶を見るときは第三者視点」という点を明確にすることで、物語のエモーショナルさをグッと高めていました。
では、「傍観者」として過去を覗くことには何の意味もないのか。自分が「当事者」として生きられる現在とそして未来にしか価値はないのでしょうか。
そうしたジレンマに対し、本作はそのラストシーンでもって1つの答えを出そうとしていました。
「傍観者」として観測する愛する人の幸せ
(C)2021 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved
『レミニセンス』のラストでは、主人公のニックが未来に向かって生きることを断念し、装置の中で、過去に生きるという決断を下します。
現在や未来から目を背けて、既存の時間軸の中に自分を埋没させるという生き方は、私たちの目には「逃げ」という風に映るかもしれません。
しかし、『レミニセンス』という作品は清々しいまでのニックのエゴの物語であり、ラストシーンもまたそんな彼のエゴに裏打ちされていることを忘れてはなりません。
とは言っても、過去に生きるということは「傍観者」として生きるということであり、それは何にも影響を及ぼすことができない無意味な存在になり下がるということではないのかと指摘することもできるでしょう。
そうした指摘を否定することはできません。
では、なぜニックは現在や未来を放棄し、過去に生きる道を選択したのか。
その理由は、「傍観者」として、記憶の中の幸せなメイを生かし続けたかったからではないでしょうか。
もし、ニックが現実をこれからも生き続けるとしましょう。
彼が現実に生きるということは、彼は記憶の中の悲劇的な結末を迎えたメイの存在と向き合い続けることを意味します。
それでは「ハッピーエンドがいい」と言っていたメイの願いを叶えることはできません。
かと言って、彼が過去に干渉して、あの朝仕事場の扉を開けて、メイを守るなんて芸当ができるはずもありません。
では、どうすればメイに「ハッピーエンド」を用意してあげることができるのか。
その1つの方法が、ニックが「傍観者」となり、過去のニックとメイが幸せな時間を過ごし続ける光景を目撃し続けることだったのだと私は思います。
ラストシーンでニックは『オルフェウス』の逸話をメイに語り聞かせていました。
オルフェウスは最愛の妻エウリュディケの死を受け入れることができず、冥界にまで彼女を連れ戻しに行きます。
ハデスは「冥界から抜け出すまでの間、決して後ろを振り返ってはならない」という条件を出したうえで、エウリュディケをオルペウスの後ろに従わせて冥界から送り出します。
しかし、冥界からもう少しで抜け出すというところで、オルフェウスは後ろを振り向いてしまい、それが最後の別れとなってしまうのでした。
つまり、『オルフェウス』は悲劇の物語なのですが、ニックはその物語を途中で改変し、無理やり「ハッピーエンド」の物語へと改変しているのです。
真実はオルフェウスとエウリュディケの永遠の別れであり、彼らが冥界から脱出して幸せな生活を送ったなんていうのは欺瞞でしかありません。
それでも、ニックは悲劇的な真実ではなく、幸福な欺瞞を選んだのです。
ニックが自分の幸せな時間を辿り、それらを観測し続けることで、彼の記憶の水槽の中にいるメイは永遠に幸せな時間を生き続けることができます。
彼が観測する物語には終わりがなく、そして真実の悲劇的結末からも隔離された完全なる「ハッピーエンド」です。
もちろんこれもニックのエゴが生んだ決断であり、そこにメイの意志は絡んでいません。
水槽の中を泳ぐ魚を見て、私たちが「気持ちよさそうに泳いでいる」と感じるのは自由ですが、それが魚の本心に何ら関係がないのと同様です。
しかし、例えそれがエゴだとしても、ニックは自分にできる方法で、メイの望んだ「ハッピーエンド」を叶えようとしました。
「傍観者」は干渉することはできません。しかし観測することはできます。
愛する人の幸せな姿を見届け続けていくことが、メイを幸福な時間の中で生かし続けることなのであるとニックは言いたいのでしょう。
その選択を「逃げ」だなんて非難することは私にはできません。
エゴだと切り捨てることは簡単かもしれませんが、それでも彼の選択は心からメイを思う「愛」だったのだと、そう思います。
おわりに
いかがだったでしょうか。
今回は映画『レミニセンス』についてお話してきました。









SF性やサスペンス性が煽られた宣伝の影響で、かなり違った先入観を作品を見る人に植えつけてしまっていたのが、大きな問題だったと思います。
ミニマルで私的な物語であること、そしてSFサスペンスというよりはラブストーリーであることを念頭に置いて干渉すると、味わい深い作品ではないでしょうか。
記事の中でノーラン兄弟の話をしたので、最後に少しだけ最近のノーラン兄弟事情をお話しておきます。
兄クリストファーはジョナサンにではなく、自身で脚本を一から手がける傾向が強まり、
『ダンケルク』や『TENET』などの作品を世に送り出しています。
一方で、弟ジョナサンは、『スターウォーズ フォースの覚醒』などで知られるJ・J・エイブラムスに憧れているようで、
映画だけでなくテレビドラマシリーズにも進出するようになりました。
自身が監督、脚本、原案を担当し、妻のリサ・ジョイも脚本として参加した『ウエストワールド』は大ヒットし、話題を集めましたね。
そんな中で、今回ジョナサンは、妻のリサ・ジョイを監督、脚本に据えて『レミニセンス』を製作しました。
このように、『インターステラー』を1つの節目として、ノーラン兄弟は別々の道を歩み始めました。









今回も読んでくださった方、ありがとうございました。