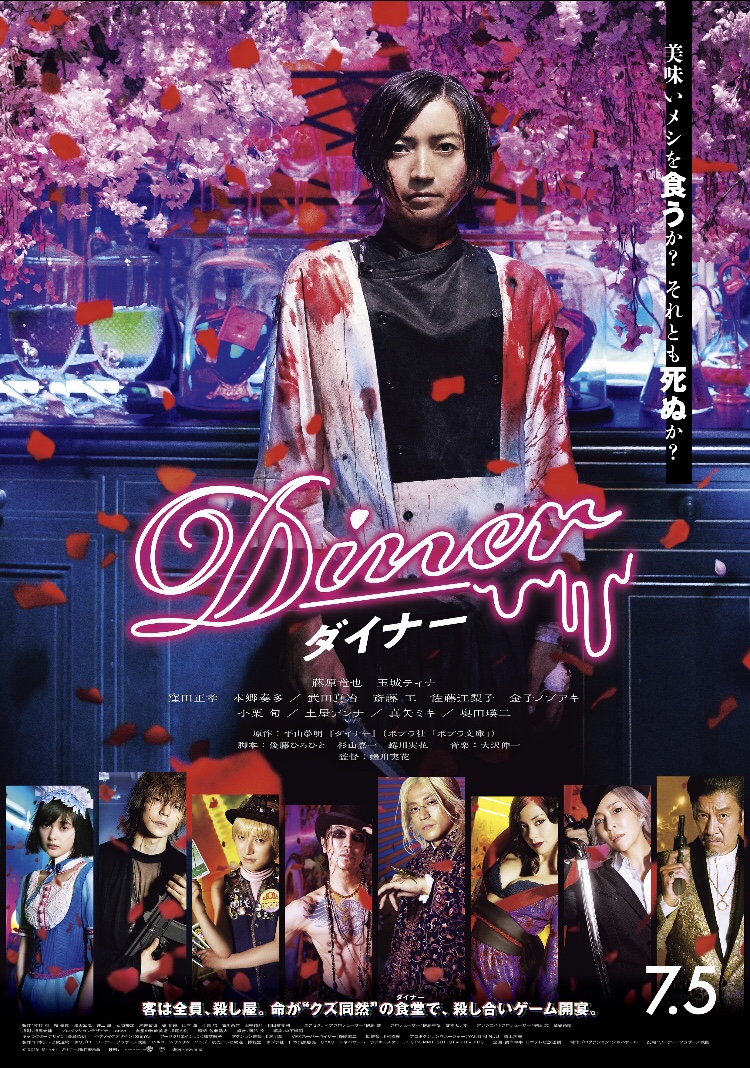みなさんこんにちは。ナガと申します。
今回はですね映画『007 ノータイムトゥダイ』についてお話していこうと思います。

公開前から本作がダニエル・クレイグが演じる最後のジェームズ・ボンドになることが発表されていたので、いろいろと覚悟はしていたんですが、それでもいざそのフィナーレを見届けると言葉になりません。
2006年に『007 カジノロワイヤル』を皮切りにスタートしたダニエル=ボンドの集大成である今作は、物語的にも、そしてシリーズのコンセプトとしても「完結した」と言える素晴らしい作品だったのではないでしょうか。
もちろん『007』というシリーズに何を求めているのか?、どこまでは許容できるのか?といった嗜好は人によって違いますから、この『007 ノータイムトゥダイ』を受け入れられるかどうかについても賛否あるのは当然のことだと思います。
作り手側もこういう内容を提供すれば、観客がどういう反応になるかはある程度想定した上で作っているはずです。
否定的な反応が一定数出てくるのは承知の上で、ダニエル=ボンドの物語やコンセプトを一貫し、完結まで導いたこと。
それこそが今回賞賛され、評価されるべきポイントなのではないかと私は思っています。
今回の記事では、作品の映像やアクション、物語の解説とともに、ダニエル=ボンド作品を振り返っての総括も書いていきます。
本記事は作品のネタバレになるような内容を含む解説・考察記事です。
作品を未鑑賞の方はお気をつけください。
良かったら最後までお付き合いください。
目次
『007 ノータイムトゥダイ』解説・考察(ネタバレあり)
「No Time To Die」というタイトルに思いを馳せて
(C)2019 DANJAQ, LLC AND MGM. ALL RIGHTS RESERVED.
タイトルが発表されたときから、何度も語られてきた今回の007のタイトル「No Time To Die」ですが、作品を見ると、すごくその主題にマッチしたものであると感じました。
そもそもこのタイトルがどこから生まれたのかという話をしますと、その由来は近年のボンドシリーズをプロデュースするバーバラ・ブロッコリの父にあります。
バーバラの父であるアルバート・R・ブロッコリは、シリーズ1作目の『007 ドクター・ノオ』から同シリーズをプロデュースしてきた人物で、『007 消されたライセンス』まで携わっていました。
そんな彼が1958年にプロデューサーを務めた作品に『Tank Force!』という作品があります。
この作品は公開時にこのタイトルに変えられてしまったのですが、元々は「No Time To Die」というタイトルで公開する予定で、日本では『今は死ぬ時でない』と訳されて公開されたのです。
バーバラは、今回そんな父アルバートが携わった作品の1つからタイトルを引用したわけですが、すごく作品にマッチしたものだと思います。
単純に日本語で意味をとると「今は死ぬ時ではない」となりますし、公開前には007の悪役ドクターノオ(Dr. No)とかけていて「ノオよ、死ぬ時間だ!」といった意味があるのではないかという憶測も呼びました。
ただ、今回の『007 ノータイムトゥダイ』は時間をテーマにした作品であり、その点でこのタイトルになったというのがその本質でしょう。
今作の冒頭でボンドはマドレーヌとの幸せな時間を過ごしていました。
「焦ることはない。時間はたっぷりとあるんだから。」
そんな言葉を発しながらも、穏やかな生活を続けていたボンドですが、スペクターに追われ、彼女を信じることが難しくなり、別離を選びます。
そこから数年にわたって彼は、何も信じることができず、誰も愛することのできない空虚な時間を過ごし、いたずらに時間を消費することだけを望むような人生を送ってきました。
つまり、生きているのか、死んでいるのか分からないような時間をマドレーヌを失ったボンドは過ごしてきたわけです。
そんなボンドが007に復帰し、サフィンを打倒し、マドレーヌと娘のマチルデを取り戻すための作戦に挑むわけですが、作戦の末に彼は死を選ばざるを得ない状況へと追い込まれます。
「たっぷりと時間はあるんだから」とマドレーヌに告げたこと。生きているのか、死んでいるのか分からないような空虚な時間をただただ浪費してきたこと。
ボンドはマドレーヌやマチルデと一緒に生きられる時間がもはや得難いものになって初めて、生きられる時間の有限性を悟り、「No Time To Die(死んでいる時間なんてないんだ)」とそう思ったのではないでしょうか。
しかし、このタイトルはそうしたボンドの悲哀を感じさせるためだけのものではありません。
命を落としてもなお、マチルデの青い瞳の中に「ジェームズ・ボンド」は生き続けるのです。
つまり、「ジェームズ・ボンド」が命を落としたとしても、それは彼が本当の意味で「No Time To Die(死ぬ時ではない)」ということをも表しています。
こうしたエモーションと未来への希望を込めたタイトルとして、「No Time To Die」という言葉のチョイスはすごくしっくりくるものだったのではないでしょうか。
シリーズを予習・復習するならどれをチェックするか?
『007』のような長寿シリーズが公開されると、絶対に話題に挙がるのが、シリーズのどれを見ておけば、物語についていけるのか?という問いですよね。
私自身もこういうブログを書いている人間でありながら、『007』シリーズは数本未見があったりしますので、あまり全部見返さなくては!と気負う必要はないと思います。
その中でも今回は優先順位をつけて、『007 ノータイムトゥダイ』鑑賞前にチェックしておきたい作品をいくつかピックアップしてみました。
『007 スペクター』優先度:最高
『007 ノータイムトゥダイ』を鑑賞する前に、絶対に見ておくべき作品があるとすれば、それは間違いなく前作の『007 スペクター』ですね。
本作では、『007 カジノロワイヤル』から始まるダニエル=ボンドシリーズの全ての事件の裏側で暗躍していたスペクターという組織が明るみに出て、そのボスであるブロフェルド(フランツ・オーベルハウザー)が満を持して登場し、ボンドと対峙します。
また、事件を追う過程で、『007 カジノロワイヤル』以来、ボンドが追ってきたミスターホワイトの正体も明かされ、彼の娘であり、後にボンドと連れ添うことになるマドレーヌもこの『007 スペクター』で初登場となりました。
物語的にも、キャラクター的にも『007 ノータイムトゥダイ』に直結する作品ですので、鑑賞はマストに近いと思いますね。
『007 カジノロワイヤル』優先度:高
『007 ノータイムトゥダイ』に向けてもう1本予習の優先度が高い作品があるとすれば、ダニエル=ボンド始まりの作品である『007 カジノロワイヤル』でしょう。
今作を見ておきたい理由は、『007 ノータイムトゥダイ』の冒頭で語られる、ボンドのヴェスパー・リンドという女性への思いを知るためです。
(C)2019 DANJAQ, LLC AND MGM. ALL RIGHTS RESERVED.
ヴェスパーは、任務の中でボンドが愛してしまった女性の1人なのですが、任務成功後に脅迫を受けていたこともあって、ボンドを裏切るんですね。
ただ、心が清かった彼女は彼を裏切ってしまったことに責任を感じ、鍵を閉めて、自死を選んでしまうのです。
愛する人を信じてあげられず、その結果、死を選ばせてしまったというボンドにとっての大きなトラウマは、今回の『007 ノータイムトゥダイ』におけるマドレーヌとの関係にもつながっています。
『007 慰めの報酬』『007 スカイフォール』優先度:中
ダニエル=ボンドシリーズは基本的に5作品全てがつながって緩やかに1つの大きな物語を構築しています。
そのため、シリーズの完結作として『007 ノータイムトゥダイ』を見届けたいと考える場合は、『007 慰めの報酬』『007 スカイフォール』についても鑑賞しておいたほうが良いということになるでしょう。
『007 慰めの報酬』は『007 カジノロワイヤル』の直後から始まる作品で、若きボンドがスパイとしての心得や振る舞いを学び、成長していく過程にスポットを当てています。
とりわけこの作品くらいから、悪役の設定が今の世界情勢を意識したものになっていったような印象を受けました。
そして、『007 スカイフォール』は『007』シリーズ最高傑作と多くの人に評されたエポックメーキングな1本です。
それまでの『007』シリーズが内包していた「最強の男がぶっ飛んだガジェットを使ってゆる~く戦い、女性を抱き、酒を飲む」というイメージを根底からひっくり返した衝撃的な内容なので、1本の映画として見ておく価値があると思います。
サム・メンデス監督が作り出したスマートで洗練された無駄のないアクションシーンは、アクション映画史に残る偉業ですし、硬派でリアリスティックな作風は、多くのスパイ映画ないしブロックバスターに影響を与えました。
『女王陛下の007』『007は二度死ぬ』優先度:低
物語に直接的な関連はありませんが、オマージュ要素を追うという意味で見ておきたいのが、『女王陛下の007』『007は二度死ぬ』の2本となります。
前者の『女王陛下の007』は、ボンドが1人の女性と結婚する様を描いた当時としては衝撃的な内容でした。
そして、『007 ノータイムトゥダイ』におけるボンドとマドレーヌの関係は『女王陛下の007』に多大な影響を受けています。
同作の最後にランチア・フラミニアに乗ってボンドと妻のテレサが新婚旅行に出かけるシーンがあるのですが、『007 ノータイムトゥダイ』の冒頭のマドレーヌとの旅行シーンやラストシーンはそのオマージュでした。
ボンドとマドレーヌが乗っている車がスペクターに襲撃され、やたらと撃ち込まれた銃弾によってできた車のフロントガラスのひびにスポットを当てるのも、『女王陛下の007』を見ていれば、その意図が理解できると思います。
(C)2019 DANJAQ, LLC AND MGM. ALL RIGHTS RESERVED.
一方で『007は二度死ぬ』は、日本を舞台にした『007』作品としても知られていて、同作の中にガントラム・シャターハント博士が作った「毒の庭」なるものが登場します。
有毒植物や蛇やサソリなどの毒を持つ生き物で構成された庭園なのですが、今回の『007 ノータイムトゥダイ』でサフィンが作っていた庭園はそのオマージュでした。
また、原作の『007は二度死ぬ』は、唯一ボンドの血を継いだ子どもができるエピソードでもあり、そういった点でも今回の映画とつながりが深い1本と言えそうです。
先ほども書きましたが、この2本はあくまでもオマージュ要素の元ネタとして知っておくと、より作品を深く味わえる程度のものなので、予習が必須とは思いません。









キャリー・ジョージ・フクナガの天才的な映像とアクションのセンス
次にお話したいのが、本作の監督を務めたキャリー・ジョージ・フクナガの映像センスの素晴らしさについてです。
ボンドを演じたダニエル・クレイグは監督について「力強い視覚センスを持っている」と評しており、その言葉通り、本作は映像作品として非常に優れた1本に仕上がっています。
今回は個人的に印象に残った工夫を2つの観点からお話させていただきます。
過去のダニエル=ボンドとは異なる映像のトーンとアクション
ダニエル・クレイグがジェームズ・ボンドを演じた作品は5作品あります。
どれも独特の映像センスに裏打ちされていて、映像作品としても素晴らしい作品たちばかりなのですが、その中で目につくのは映像のトーンの使い分けです。
まずは『007 カジノロワイヤル』ですが、この作品はボンドの00への昇格試験からスタートするという物語の都合もあり、彼の「若さ」が際立つ内容なんですね。
(C)2019 DANJAQ, LLC AND MGM. ALL RIGHTS RESERVED.
そのため、ボンドの粗野さや未熟さが際立つようなフィルミングが印象的でした。
映像のカット割りが細かく、状況を全体像や俯瞰で映し出すというよりは、表情や手元、武器をピンポイントで抜いていき、それを組み合わせて展開することにより映像は「落ち着き」を失います。
こうした映像の切り替わりや揺れ、焦点の当たる範囲の狭さがボンドの未熟さを顕著に表していたわけです。
一方で、サム・メンデス監督の『007 スカイフォール』や『007 スペクター』では、スパイとして洗練され、完成したボンドが描かれています。
『007 スカイフォール』の俯瞰のショットや引きの画を中心に組み立てられた無駄のない映像は美しいとすら言えますし、『007 スペクター』の冒頭のメキシコシティでの長回し演出はその1つの結晶でしょう。
また、『007 スカイフォール』は映像のクールなトーンが際立ち、一方の『007 スペクター』は上品さやエレガントさが際立っているという点で、やはり使い分けがなされています。
このようにダニエル=ボンドシリーズは、1つ1つの作品がボンドの置かれている状況や成熟度にリンクした映像のコンセプトを持っており、それが忠実に体現された映画になっているんですね。
では、『007 ノータイムトゥダイ』はどんな映像を追求したのでしょうか。
まず、大きな特徴の1つとして、前2作と比べて「寄りのショット」が増えた印象を受けました。
ボンドの置かれている状況や戦闘を、俯瞰や引きのショットで映し出すのではなく、表情や彼の周りの狭い範囲にフォーカスして捉えるショットを多用していました。
これに付け加えて、非常に「揺れ」が多い映像だったのも大きな特徴かもしれません。
例えば、ボンドが建物から建物へと飛び移って着地する様を映し出すショット1つにしても、『007 カジノロワイヤル』では固定されたカメラで撮っていましたが、『007 ノータイムトゥダイ』はボンドの着地に合わせてカメラが大きく揺れる手持ちカメラ風の仕上がりになっています。
同じ行動を映し出していても、そこに「揺れ」があるのかないのかでは、観客に与える印象は決定的に違ってきますよね。
『007 カジノロワイヤル』の映像は全体的にボンドの未熟さや若さを感じさせるために、アクションや映像が「軽く」見えるように撮られている節があります。
一方で『007 ノータイムトゥダイ』はボンドに寄ったショットが多く、それでいて彼のアクションに合わせて映像が揺れるので、すごく「重く」見えるんですよね。
この「重さ」はダニエル=ボンドの「円熟」を可視化していると言えます。
(C)2019 DANJAQ, LLC AND MGM. ALL RIGHTS RESERVED.
また映像のトーンとしても、過去2作品のようなクールさやエレガントさは抜け、ボンドの表情に寄ったショットが、彼の「温度」に焦点を当てていました。
これにより、ジェームズ・ボンドの「人間」的な部分が浮き彫りになり、映像全体がじわりと熱を帯びているのが伝わってきましたね。
キャリー・ジョージ・フクナガは、これまでのダニエル=ボンドとは決定的に違うコンセプトで作品を作り上げ、新しい一面を見せてくれました。
そして、そのコンセプトが物語とリンクし、若き未熟なボンドやクールで洗練されたスパイとしてのボンドではなく、1人の人間として円熟したボンド像を作り出すことに成功したのはお見事だったと言えるでしょう。
顔の見えない敵との戦いを作り出した日本的な感覚
『007』シリーズと言えば、もちろんそのアクションシーンは大きな見所の1つです。
今回の『007 ノータイムトゥダイ』が意識して作っていたように見えたのは、対峙する敵の「顔」を見せないつくりにしていた点だと思います。
作品冒頭のサフィンがマドレーヌの生家を襲撃するシーンで、彼は能面をつけていました。
監督のキャリー・ジョージ・フクナガは、能面を選んだ理由について「見る人によって表情が変わり、ミステリアスだから」とインタビューで答えています。
能面は、一見無表情に見えるのですが、あらゆる感情を表す表情の元を少しずつ取り込んでいるため、演者の表現によって様々な感情を表現することができるという特性を持っているのです。
監督は能面のこの特性を利用し、サフィンに多様な解釈をもたらしたと言えます。
また能面は「つける」ではなく、「かける」と表現され、「変身」や「憑依」といったニュアンスを強く感じさせますよね。
能面は、面 (オモテ) とも呼ばれ、演者は能面をかけることによって、自分自身の内面を裏側に隠すのです。
キャリー・ジョージ・フクナガは、能面に由来する顔を見せないことが生む、人間の本性を裏側に隠してしまうという効果を作品全体に上手く活かしていたと言えます。
例えば、冒頭の生物兵器の開発をしているラボをスペクターの一派が襲撃するシーンでは、潜入部隊が顔を隠しており、彼らの視線が赤いレーザーサイトだけで描写されていました。









このシーンでは、顔の見えない敵が車やバイクに乗って次々に襲い掛かってきました。
顔が隠されることにより、表情やその素性が見えない敵はどこまでも非常に不気味であり、見ている観客としては、その正体を知りたいという衝動に駆られ、不安を煽られます。
今回の『007 ノータイムトゥダイ』では、ブロフェルドやスペクターという組織を「能面」として、その背後に隠された謎の男や勢力からボンドが追われ、攻撃される様を描きました。
そうした構図を印象づけるために、敵ないし追っ手側の表情が見えないシーンを多用していたのは、面白い試みだと思います。
また、監督が日本にルーツを持っているということで、「らしさ」を感じたのが、このシーンですね。
(C)2019 DANJAQ, LLC AND MGM. ALL RIGHTS RESERVED.
能面をかけたサフィンの像がガラス越しにぼんやりと浮かび上がるショットなのですが、これ日本の襖ないし御簾の文化を想起させる演出ですよね。
向こう側に人間の存在があることは分かるけれども、その「顔」を見せない。
平安時代には、貴族の女性は男性に顔を見せてはならないという文化があり、御簾でその姿を隠し、対面する男性は透影からその姿を推しはかっていたのだそうです。
こういう日本的な感覚をライティングや演出の部分で上手く作品に持ち込み、物理的に顔を見せないような作りこみをしていたのも面白かったですね。









キャリー・ジョージ・フクナガが作り上げたサフィンというヴィランは、劇中でも言及されていましたが「ふわふわとしていてつかみどころがない」んですよ。
というのも、これまでの『007』シリーズの典型的な悪役のように高笑いをしたり、怨恨をむき出しにしたりといった「自分」を出す場面がほとんどないんです。
演じたラミ・マレックがひたすらに表情を変えないため、サフィン自身が「能面」をかけ、感情や内面を隠しているように見えるんですよ。
(C)2019 DANJAQ, LLC AND MGM. ALL RIGHTS RESERVED.
これが物理的ではなく、心理的な側面から指摘できる「顔の見えない敵」なんだと思います。
とりわけ『007 ノータイムトゥダイ』では、先ほども言及したようにボンドの内面や感情が暴かれ、表に出てきていましたから、それとは対照的に一定の表情で様々な感情を表現していたサフィンがどこか非人間的で、不気味に映ったのは当然ですし、これも計算されているのでしょう。
このように悪役側の「顔」を物理的ないし心理的に隠すことで、それを表にさらしているボンド側とのコントラストを際立たせていたのは、非常に巧かったと言えるでしょう。
ダニエル=ボンドは『007』の何を変えたのか?
では、ここからはダニエル=ボンド5作品を通して振り返りながら、その中で今回の『007 ノータイムトゥダイ』がどんな役割を果たしていたのかを考えてみようと思います。
ジェームズ・ボンド神話を解体する
(C)2019 DANJAQ, LLC AND MGM. ALL RIGHTS RESERVED.
ダニエル=ボンドはとにかく『007』シリーズの中でも異例に満ちた作品群であることは間違いありません。
それを象徴するのが『007 カジノロワイヤル』であり、その冒頭のパートで描かれたボンドの00昇格試験でしょう。
『007』シリーズは基本的に1作完結の趣が強く、これまでボンドを演じるキャストは何度も変わってきましたが、緩やかにつながっているという印象がありました。
そんな中で『007 カジノロワイヤル』は、ボンドが「007」になるまでのプロセスを描くことで、ダニエル=ボンドが辿るのは、これまでのボンドとは切り離された独立した物語になることを印象づけました。
さらに『007 慰めの報酬』はシリーズで初めて、前作の直接的な続編として制作され、これも当時としては異例中の異例でした。
こうして『007 カジノロワイヤル』からスタートしたダニエル=ボンド作品は、明確に物語がつながっており、その中でジェームズ・ボンドの人間としての成長と変化を描いてきました。
- 『007 カジノロワイヤル』⇒007「誕生」
- 『007 慰めの報酬』⇒スパイとしての「成長」
- 『007 スカイフォール』⇒Mとの「母離れ」
- 『007 スペクター』⇒最愛のマドレーヌとの「出会い」









つまり、ダニエル=ボンドがシリーズを通して追求してきたのは、不変の神話としての「ジェームズ・ボンド」像を打倒することだったのではないでしょうか。
ジェームズ・ボンドを酒を飲み、女を抱き、敵と戦う不変のアイコンとして描くのではなく、1人の人間として彼の物語に向き合う。
このコンセプトの下で一貫して作品を作り上げてきたわけです。
だからこそ、「誕生」で始まったダニエル=ボンドシリーズの最後は「死」でなくてはならなかったのです。これは当然の帰結だと思います。
もちろんジェームズ・ボンドの死はシリーズのタブーでもありますから、それを描けば、どんな反応が来るのかはある程度作り手の側も想定していたことでしょう。
それでも、彼らは自分たちが始めたダニエル=ボンドのコンセプトを最後まで貫き通しました。
本作『007 ノータイムトゥダイ』のラストシーンで、マドレーヌが自分の子どもであるマチルデに「昔、ジェームズ・ボンドという男がいてね…。」と語り始めます。
ジェームズ・ボンドという男は不変の神話であり、普遍的なアイコンでした。
そんなキャラクターが「死」を経て、愛する人たちの私的な思い出の中で語られる。
これこそがダニエル=ボンドが目指した「神話の解体」であり、ジェームズ・ボンドを人間として描くことのゴールだったのではないでしょうか。
時代に適応する物語や悪役を模索する
(C)2019 DANJAQ, LLC AND MGM. ALL RIGHTS RESERVED.
『007』というシリーズは一言で言ってしまえば『スーパーマリオ』のような趣があります。
スペクターという巨大な組織とその組織を支配するブロフェルド。さらに組織が差し向けてくる刺客。そんな状況で国と女性を守るために戦うボンド。
映画版はいろいろと権利の都合もあったりで、内容が変わっているのですが、イアン・フレミングの原作では、この構図が基本的にはシリーズを通底しています。
また、時代背景としても基本的には冷戦中となっており、これが大きく変化したのは、『007 ゴールデンアイ』以降でした。
ただ、スパイは元々は冷戦が生んだ産物であり、そんな時代のアイコンは「時代遅れ」ではないのか?という問いは常に付きまとうこととなります。
そこから脱却しようとして、あの手この手でいろいろな試みに挑戦したのが、実はピアース・ブロスナンの時代でした。
『007 ゴールデンアイ』~『007 ダイ・アナザー・デイ』までの4作品は、007から「冷戦」を取り除いたときに何ができるのか?を模索し続けていました。
香港映画界の大物ミシェル・ヨーをボンドガールに迎えて挑んだ『007 トゥモロー・ネバー・ダイ』なんかはアクション性を強めることで、これまでとの違いを印象づけようとしていましたね。
VFXやCGをふんだんに盛り込んで昔ながらの007を再現しようとした『007 ダイ・アナザー・デイ』なんかも試みとしては面白かったです。
『007 ゴールデンアイ』や『007 トゥモロー・ネバー・ダイ』は、大ヒットし、評価も高かったです。加えて何とか現代の世界で007を成立させようと苦心していたのが伝わってくる内容でした。
ただ、その最適解を見出せたとは言いづらく、007らしい荒唐無稽さや、女性に対する向き合い方、悪役の在り方が徐々に時代に適さなくなってきたことが作品を追うごとに浮かび上がってきました。
そんな中で、ダニエル・クレイグがボンドを演じることとなり、一度シリーズをリブートするという意味も込めて、『007 カジノロワイヤル』が作られました。
ここからダニエル=ボンドが始まるわけですが、以降の5作品は「ジェームズ・ボンドが登場するスパイ映画」というよりは、「ジェームズ・ボンドそのものについての映画」に舵を切ったように思います。
そのため、悪役のキャラクター造詣についても、世界の脅威でありながら、ボンドやその関係者に私的なつながりがあったり、怨恨があったりする人間が多く登場しました。
『007 スカイフォール』に登場するラウル・シルヴァはMI6のMに対して私怨を抱いており、その復讐を遂げることを目的に行動しています。
他にも『007 スペクター』は、原作シリーズではお馴染みのブロフェルド(フランツ・オーベルハウザー)を登場させ、ボンドとの私的な繋がりを描き、彼がボンドに執着する理由づけをしていました。
このようにダニエル=ボンドシリーズに登場する悪役は、旧来のような世界を股にかけた壮大な計画を持ってこそいるものの、そこはメインではなく、むしろボンドたちと極めてパーソナルな理由で戦おうとする人物が多かったんですね。
そんな中で作られた今回の『007 ノータイムトゥダイ』における悪役であるサフィンもまた、特殊なウイルス(ヘラクレス)を利用して世界を恐怖に陥れようとしていましたが、やはろそこは本質ではなく、もっと個人的な理由でボンドと対峙しようとしていました。
サフィンを演じたラミ・マレックは監督と「人がどんなところに恐怖を感じるのか」について話したとインタビューで明かしていましたが、その中でサフィンは「陰で高笑いをしている首謀者」ではないと語られていました。
つまり、今の世界において「世界中の人たちを死に陥れる」ような非現実的な野望を持っているだけの首謀者タイプの旧来的な悪役に、観客は「恐怖」を感じなくなっているのかもしれません。
冷戦の時代においては、いつ核戦争が起きてもおかしくない、いつ自分たちが住んでいる町が焦土と化すかもしれないという緊張感がありました。
だからこそ「みんな」を対象にした悪役が成立したわけです。
しかし、冷戦が終わり、そうした世界観が浮世離れする中で、ダニエル=ボンドは「みんな」ではなく、「あなた」や「わたし」を対象にした悪役に立ち向かってきました。
個人的な感情でボンドやボンドの周囲の人間を攻撃したり、世界中の人間の情報を手に入れようとしたり、個人や特定のグループに最適化されたウイルスを製造したり…。
悪役が世界に生きる「みんな」を攻撃しようとしているように見えて、実はその中に生きる「わたし」や「あなた」を狙っているという構造が確かに息づいているのです。
「公」だけではなく「私」を兼ね備え、「公」を攻撃しようとする一方で、「私」を狙う。
それは、ジェームズ・ボンドという「公」のために尽くす人間の「私」の部分を狙うブロフェルドやサフィンというヴィランの登場でもって、1つのゴールに達しました。
これが『007』が近年追求してきた、今の時代に適した悪とそれがもたらす「恐怖」だったのではないでしょうか?
常に時代に即した形で『007』という枠組みやそこに登場する悪をアップデートし続けてきたのがダニエル=ボンド5作品だったのです。
「お約束」との距離と007のアイデンティティ
ダニエル=ボンドが5つの作品の中で試みていた最大の挑戦は、「『007』とは何か?」というアイデンティティを模索することだったのではないかと思っています。
先ほどピアース・ブロスナンがボンドを演じていた時代の4つの作品を話題に挙げましたが、彼の時の作品は時代設定がガラッと変わったものの、『007』たる要素は基本的に継承されていました。
しかし、ダニエル=ボンドの5つの作品はそうではありません。
『007 カジノロワイヤル』がボンドが007になるまでの物語を描き、続く『007 慰めの報酬』は初の直接の続編に挑戦しました。
さらに、これらの作品では、007の名物である「夢のある秘密兵器」の類がほとんど登場せず、マニーペニーやQといったお馴染みのキャラクターも登場しないのです。
また、『007 カジノロワイヤル』に至ってはお約束ともいえる「カーチェイス」もほとんど描かれません。
続く『007 スカイフォール』はまさしく「007を脱構築する」という方向性の結実であり、「果たしこれは007なのか?」という意見もありましたが、それでも多くの人に受け入れられ、シリーズ最高傑作と評されました。
つまり、ある種の「お約束」から距離を置いた状態で、「007最高傑作」を作り上げるという偉業を成し遂げたわけです。
一方で、『007 スカイフォール』のラストでようやくマニーペニーやQ、Mといったお馴染みの面々が揃ったこともあり、その次の『007 スペクター』は急激に懐古色が強まります。
お馴染みの面々の活躍、過去作へのオマージュ、ボンドガール(ウーマン)の扱い、「夢のある秘密兵器」の登場、見ごたえのあるカーチェイス、そして何よりスペクターやブロフェルドの登場と一気に「お約束」を全面に押し出した作品になりました。









現代における「007」を探るために、「お約束」の一切を排した『007 スカイフォール』を作り、その反動として「お約束」をふんだんに盛り込んだ『007 スペクター』を作る。
元々ダニエル=ボンドはこの『007 スペクター』で終わると言われていました。
そう考えると、「お約束」がない状態でも「007」が成立することを見せつけた『007 スカイフォール』と、ダニエル=ボンドで「お約束」に満ちた往年の「007」を作るというある種のファンサービスともいえる『007 スペクター』とみるのが適切なのかもしれません。
ダニエル=ボンドとして追求してきた「007」とは何か?という問いかけは、おおよそ『007 スカイフォール』で完結していたと思います。
その上でダニエル=ボンドで往年の「007」をやるというエキシビションも含めて、『007 スペクター』がダニエル・クレイグの勇退に最適なタイミングだったと私はそう思っています。
しかし、プロデューサーのバーバラ・ブロッコリの強い要望もあり、ダニエル・クレイグがジェームズ・ボンドを演じる映画がもう1本作られる運びとなり、今作『007 ノータイムトゥダイ』が公開されました。
『007 ノータイムトゥダイ』は、いわゆる「ボンドガール(ウーマン)」を封印し、ジェームズ・ボンドから「007」をはく奪するなどして、依然としてこのシリーズのアイデンティティに問いを投げかけるような試みを内包しています。
一方で、『女王陛下の007』や『007は二度死ぬ』を強く思わせる演出や展開があったり、ボンドが振り向きざまに銃を撃つ演出を要所に置いてみたり、「夢のある秘密兵器」が登場したりといわゆる「お約束」が色濃く残っている部分もありました。
つまり『007 ノータイムトゥダイ』は、『007 スカイフォール』と『007 スペクター』とを融合させたようなトーンで作られていて、シリーズを脱構築していくような視点を保ちながら、「お約束」をほどほどに馴染ませているんですね。
ただ、今作は最後の最後で大きな爆弾を抱えていました。
それはMI6の存在意義を問う選択であり、ジェームズ・ボンドに子どもができるという展開であり、さらには不死身の男が命を落とすという展開です。
まず、MI6の存在意義を問うた点についてですが、そもそもスパイは秘密裏に国に降りかかる問題を解決し、それを表に出さないというのが至上命題なんですよね。
今作の終盤にMがミサイルを島に打ち込むのを躊躇っていたのはそういう理由で、これをやってしまうと島での一件が公になってしまいますし、何よりスパイの存在意義を問われます。
こういう展開をシリーズの最後の最後でやるというのも、ダニエル=ボンドの挑戦的な姿勢が垣間見えるところなのかなと感じました。









『007』シリーズは先ほども言及したように、演じるキャストが変わっても、キャラクターや物語に緩やかなつながりがあったのが1つの特徴でした。
だからこそ、今回のようにジェームズ・ボンドの「死」を描くと、そのキャストが演じたボンドは他のキャストが演じたボンドとは切り離され、独立した人間ということになってしまいます。
次のキャストがジェームズ・ボンドを演じるとき、その人物が演じるボンドはダニエル=ボンドとはつながりを持ちえないということがこの作品で明確になっているのです。
これは『007』というシリーズそのものが緩やかに作り上げてきたアイデンティティを一変させるような出来事であり、それだけにファンの方が受ける衝撃も大きいでしょう。
単体の作品で見た「らしさ」の話ではなく、シリーズが脈々と積み上げてきた暗黙のルールに反旗を翻しているのです。
しかし、これもダニエル=ボンドを終わらせるために必要な通過儀礼だったのかもしれません。
プロデューサーのバーバラ・ブロッコリは、インタビューで「ダニエル以外のボンドは考えられない」とまで言っています。
つまり、作り手の側にとっても、そして私たち観客の側にとっても、あまりにも「ダニエル=ボンド」のいうキャラクターは大きくなりすぎてしまったのではないでしょうか。
それは『007 スカイフォール』を通じて全く新しいボンド像を彼が確立してしまったことにも起因すると思います。
だからこそ、彼が演じたジェームズ・ボンドを「閉じた個人の思い出の中にしまい込む」という本作のラストも頷けます。
劇中のマドレーヌは「昔、ジェームズ・ボンドという男がいてね…」と言っていましたが、それは紛れもなく「ダニエル=ボンド」のことです。
ジェームズ・ボンドではなく、ダニエル=ボンドのことなんです。
ダニエル・クレイグが演じたボンドは「死」でもって、これまでの、そしてこれからのジェームズ・ボンドと切り離された独立した存在になりました。
だからこそ、私たちは「ジェームズ・ボンド」ではなく、「ダニエル・クレイグが演じたあのジェームズ・ボンド」について今後も語り続けることができるのです。
ジェームズ・ボンドは「いる」のではなく「いた」。
たった1文字の違いですが、シリーズにとっても、作り手にとっても、私たち観客にとっても大きな意味を持っています。
おわりに
いかがだったでしょうか。
今回は映画『007 ノータイムトゥダイ』についてお話してきました。









ダニエル・クレイグ版の『007』が追求してきた1人の人間としてのジェームズ・ボンドを描くというコンセプトは、おそらく今作まで描かれてこそのものだと思いますし、賛否あれどそれを貫いた製作陣には敬意を表したいです。
ただ、『007』を脱構築し、再定義するという意味では『007 スカイフォール』と『007 スペクター』があまりにも収まりが良すぎたんですよね。
そのため、作風がどっちつかずになっている今回の『007 ノータイムトゥダイ』はふわふわとしてしまっています。
しかし、先ほども書きましたが、ダニエル=ボンドがあまりにも「特別」だったという点を踏まえると、次回作以降のために、今作のラストが必要だったのかもしれません。
ダニエル・クレイグが演じたジェームズ・ボンドは、マドレーヌやマチルデたちの私的な思い出の中にしまわれ、次のジェームズ・ボンドが「帰ってくる」。
その方が、次世代のボンドがダニエル=ボンドというアイコンとの強い結びつきを担保する必要がないので、自由度が高くなると思います。
いろいろと話したいことは尽きませんが、ダニエル・クレイグにはありがとうと、そしてお疲れ様でしたを伝えたいです。
当初は批判もありながらも、その声を自らの実力でひっくり返し、21世紀に「007」が、そして「ジェームズ・ボンド」が存在できることを証明した、その仕事ぶりに敬意を表します。
今回も読んでくださった方、ありがとうございました。