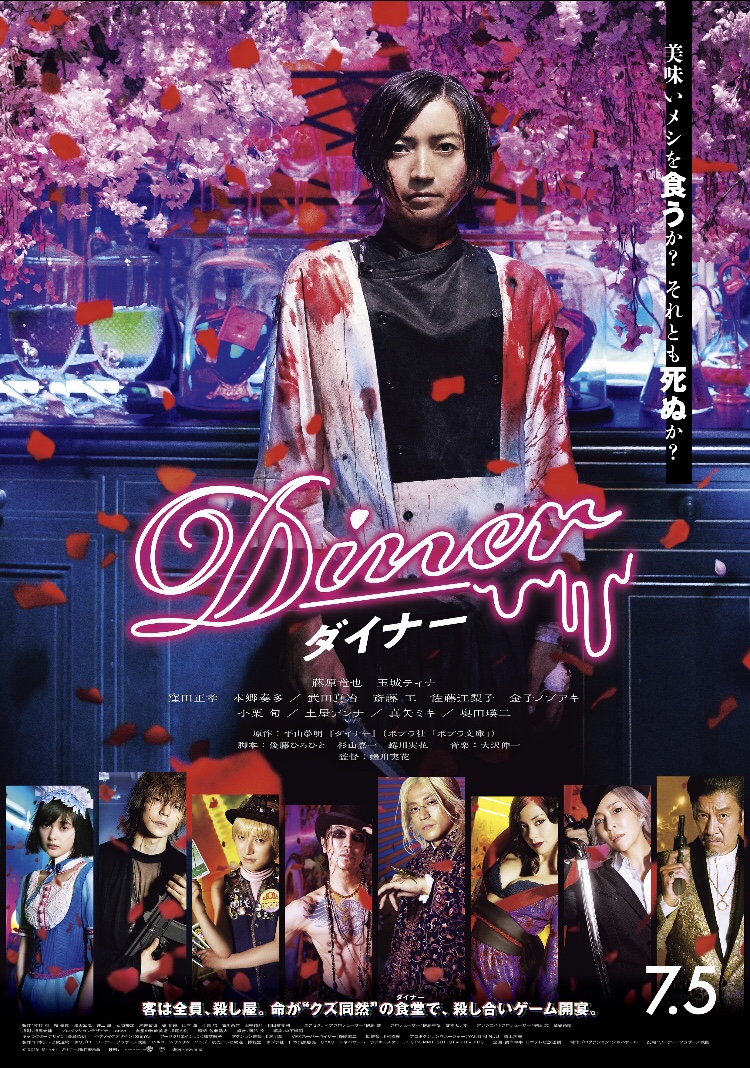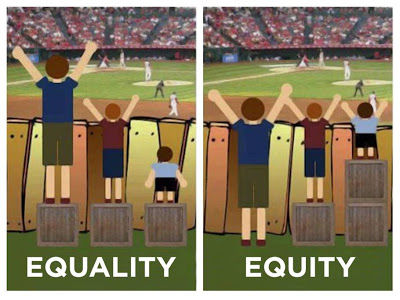みなさんこんにちは。ナガと申します。
今回はですね映画『アイの歌声を聴かせて』についてお話していこうと思います。

知らないよ!という方のために、簡単に吉浦康裕監督について説明させていただきます。
有名なのは、人間とAIが交流する小さなカフェの日常にスポットを当てた『イヴの時間』と重力の体系が異なる2つの世界におけるボーイミーツガールを描いた『サカサマのパテマ』ですね。
この2つの作品では、いずれも異なる価値観に裏打ちされた2つの主体(人間とAIあるいは人間と人間)がディスコネクトをコミュニケーションを通じて飛び越えようとする様が描かれています。
一方で、その原点にあるのは『ペイル・コクーン』という作品でして、これは監督が個人で完成させた20分ほどのショートアニメです。
後ほど詳しくお話しますが、この作品の舞台は地上に人類が居住できなくなった後の世界であり、そこにある「記録発掘局」という過去の記録を発見し、分析する機関の日常にスポットを当てています。
今回の『アイの歌声を聴かせて』の物語を裏打ちしているのは、まさしく吉浦監督の作品を通底するコミュニケーションにより断絶を乗り越えるという主題性です。
一方で、今作のキーである「歌う」という行為、そして「記録」というモチーフには、彼の原点である『ペイル・コクーン』とのリンクが見られます。
そう考えたときに、『アイの歌声を聴かせて』は単体の作品としても楽しめる一方で、吉浦監督作品の1つとして位置づけることでより深く味わえる可能性が見えてきますよね。
吉浦監督の過去作はどれも素晴らしいので、ぜひとも今回の新作とセットで鑑賞する人が増えてくれると嬉しいです。
ということで、今回の記事では自分なりにこれまでの吉浦監督作品を整理しながら、そのコンテクストにおける『アイの歌声を聴かせて』について考えてみようと思います。
本記事は作品のネタバレになるような内容を含む解説・考察記事です。
作品を未鑑賞の方はお気をつけください。
良かったら最後までお付き合いください。
目次
『アイの歌声を聴かせて』解説・考察(ネタバレあり)
「記憶」を通じて過去を、あるいは未来を見る
(C)吉浦康裕・BNArts/アイ歌製作委員会
『アイの歌声を聴かせて』において、物語の重要なキーになったのは「記憶」という明確な形を持たないモチーフです。
「記憶」とは私たちの頭の中に刻まれるものですが、人間の脳には限界があり、風化し、いつしか忘れ去られてしまう危機に晒され続けています。
そんな現在の一瞬を切り取り、半永久的に残すための映像や写真といった記録媒体は存在し、それらを通して私たちは遠い時間に思いを馳せることができるわけです。
本作の劇中において、主人公のサトミたちも自分たちの持っているスマートフォンで青春の1ページを切り取って「記録」に残そうと試みます。
それは何のためかと言うと、自分たちが過去を振り返るときの「足がかり」なんですよね。
人間はそんな「記録」を通じて、大抵は「過去」の方に目を向けます。
「過去」に自分が経験したこと、誰かが経験したこと。それらを見知る上で「記録」はその仲介役を果たすというわけです。
しかし、AIであるシオンにとって「記録」は少し違った意味合いを持っていることが『アイの歌声を聴かせて』を聴かせてを鑑賞していると見えてきます。
AIは膨大なビッグデータに基づいて、人間をはるかに超越するスピードで処理・演算できる能力を有しますが、これは将棋AIを考えるとイメージしやすいでしょうか。
将棋のAIは過去の膨大な棋譜を読み込ませてあり、その膨大なデータに基づいて、今現在の盤面を分析し、その次の最善手を導き出します。
つまり、AIにとっての「記録」は、「過去」を振り返るためというよりもむしろ「未来」を導き出すためのものであり、その点で人間のそれとは決定的にベクトルが違うという点が見えてくるのです。
こうした「記録」を巡る多様な認識についての原初は吉浦監督のデビュー作である『ペイルコクーン』の中にも描かれていました。
同作では、「記録発掘局」という機関が登場し、地球が環境破壊の影響で汚染されてしまった世界において、過去の記録を発掘し、分析する人間の姿にスポットを当てます。
しかし、「記録発掘局」に属する人間の中にも、「記録」というモチーフに対しての多様な認識が存在しているんですね。
例えば、主人公のウラの同僚であるリコは、「記録」は過去を振り返るためのものでしかないとし、それらの発掘、分析にこだわることには何の意味もないと断言します。
加えて、そうした「記録」が突きつけるのは、どこまでも非情な現実であり、彼女はそれを見ることにもう疲れてしまったのだとも語っていました。
このように、リコの持っている「記録」に対するイメージは「過去」志向であることが短い作品の中からも読み取れます。
しかし、主人公のウラはそれを現状を分析し、未来に向けた次の一手を導き出すための足がかりだと認識していました。
つまり、環境汚染によって地下に閉じ込められ、空を見ることすら叶わなくなった世界において、どうすれば再び青い空を見ることができるようになるのか?を考えるために「記録」の分析は重要な意義を持っていると考えたのです。
『ペイルコクーン』においては、リコとウラがすれ違う様を演出し、そのベクトルの違いを強調していました。
よって、こうした未来志向の「記憶」観と、過去志向の「記憶」観は、彼のデビュー作で既に打ち出されており、今回の『アイの歌声を聴かせて』では、それをAIという設定に上手くリンクさせたものだと理解することができるのです。
そして、吉浦監督の作品では、必ずその2つのベクトルが交わる様が描かれます。
『ペイルコクーン』においては、遥かな過去から未来に向けて歌を記録に残した女性の思いが、ウラへと届き、その交わりが文字通り世界に「風穴」を開けました。
『アイの歌声を聴かせて』においては、物語の後半にシオンがサトミを幸せにするためのデータベースとして蓄積してきた「記録」の数々を、サトミたちが垣間見るという形でその交わりが「演出」されました。
サトミたちはシオンの「記録」に触れ、過去へと、そして未来へと続く2つのベクトルを認識します。
過去を振り返り、シオンと過ごしたかけがえのない時間を思い、そして未来を見通してはシオンが幸せになるための道を模索するのです。
こうした吉浦監督ならではの「シンギュラリティ」が作品の中で演出されていたのが非常に面白かったですし、何よりそれがこれまでの作品から積み重ねられてきたものであるが故の強度が素晴らしかったと思います。
歌うこと、祈り、虚構
(C)吉浦康裕・BNArts/アイ歌製作委員会
もう1つ『アイの歌声を聴かせて』を語る上で欠かせないのは、その独特のミュージカル的な文法でしょうか。
吉浦監督の作品において「音楽」は物語を動かす原動力の根源とも言えるものです。
例えば『イヴの時間』において、主人公のリクオと彼の家で働くアンドロイドのサミィは過去の一件がきっかけですれ違い、それ以来微妙な関係のままになっています。
しかし、そんな2人の停滞した関係にブレイクスルーをもたらすのは、ピアノの演奏でした。
「音楽」は言語を超え、AIと人間という枠組みすらも超えて、お互いを理解するという途方もなく難しい進歩を支える原動力として機能するのです。
一方で『ペイルコクーン』においては、「音楽」が「歌うこと」として描写され、それが長い時間という断絶を飛び越える原動力として描写されています。
とりわけ『ペイルコクーン』で描かれた、YOKOという女性の歌うという行為は、祈りに近いものであり、荒廃した世界で在りし日の「青い地球」を思って為されました。
このように吉浦監督の過去の作品を見ていくと、「音楽」ないし「歌うこと」が描かれており、それが言語とは一線を画したパワーを持つものとして描かれ、劇中に設定されたディスコネクトを飛び越えていく原動力となっている様を見て取れます。
『アイの歌声を聴かせて』では、そうした過去作において端緒として見え隠れしていた「歌うこと」を前面に押し出し、ミュージカル映画の文法の中でそれを活かそうと試みていました。
アメリカ合衆国の哲学者・美学者として知られるケンダル・ウォルトン氏が自身の論文である『Fictionality and Imagination』の中で、ミュージカルについて興味深い指摘をしています。
ミュージカルでは、通常の台詞のパートと地続きで突然登場人物たちが歌い出すという独特の文法が存在しています。
1940年代半ばに公開された『オクラホマ!』は現在のミュージカルの在り方の原点とも言われる歴史的な作品です。
この『オクラホマ!』以来確立されたミュージカルの文法においては、登場人物の台詞と歌がシームレスにつながれています。
ケンダル・ウォルトン氏がこうしたミュージカル特有の文法について、「ミュージカルにおいて登場人物が歌を歌うとき、観客は登場人物が歌っていることを想像しなければならないが、彼らはストーリー上では歌っていないことになっている。」という二重構造を指摘しています。
つまり、「登場人物が歌っている想像の世界」と「登場人物が歌っていない想像の世界」が存在していると言っているわけですね。
実は、『アイの歌声を聴かせて』においては、まさしくこの言説が可視化されていて、それがシオンのミュージカルシーンでは、彼女の映像が監視カメラの映像などから消去されているという演出です。
彼女が歌っているミュージカルシーンというある種の虚構と、それを否定する想像としての現実が同居しており、その2つを劇中のデバイスを用いて上手く同居させていたんですね。
また、こうした「歌」を2つのレイヤーを結ぶものとして描く方向性は作品の序盤から一貫しています。
主人公のサトミは「ムーンプリンセス」というプリンセス映画に憧れているのですが、この劇中映画は明確に作品内虚構として確立されていました。
そして、冒頭の通学シーンですが、ここでサトミは持っている携帯型音楽プレーヤーで同じく「ムーンプリンセス」の楽曲を聞いているのですが、その音が作品世界に漏れ出すことはありません。
それは彼女がイヤホンをしているからというのもありますが、彼女の現実世界と「ムーンプリンセス」の世界が断絶されていることを表現する演出として機能していたとも指摘できます。
しかし、シオンという後に判明するように「ムーンプリンセス」に裏打ちされたAIは、サトミのために、彼女の現実世界に、歌を通じて「ムーンプリンセス」という虚構を持ち込もうとしました。
それは時に「ピンチの時に現れる王子様」という物語的な切り口からであり、それは時にミュージカルないし「歌」という演出的な切り口からでしたね。
こうして、シオンがサトミの世界に「ムーンプリンセス」ないし、それに裏打ちされたミュージカルの文法を持ち込むことによって、先ほども書いたように「登場人物が歌っている想像の世界」と「登場人物が歌っていない想像の世界」が生まれます。
そして、サトミはそのどちらかを自分の世界として選び取るチャンスを得たと考えて良いでしょう。
このように『アイの歌声を聴かせて』はミュージカルの文法にリンクさせる形で、主人公のサトミにコンフリクトを提示します。
当初、サトミはこうしたシオンの振る舞いを否定し、後者の世界を自分の現実として選択しようとしますが、徐々に彼女の周囲の人たちをも巻き込みながら、彼女もまた「登場人物が歌っている想像の世界」を受け入れようと変化していくのです。
その結実として描かれたのが、物語の「転」である夜のソーラーパネル区画でのミュージカルシーンであり、ここで劇中虚構である「ムーンプリンセス」とサトミの現実が明確にクロスしました。
(C)吉浦康裕・BNArts/アイ歌製作委員会
しかし、残酷にもシオンは機能を停止させられてしまい、サトミが望んだ世界は再び劇中虚構の世界へと引き戻されてしまうのです。
その後のサトミは「ムーンプリンセス」のアラーム音を拒絶し、自身に歌いかけてくる友人を拒絶するなど、明確に「ムーンプリンセス」ないし「登場人物が歌っている世界」を遠ざけようとしているのが見て取れます。
そんな中で、シオンが「歌う」ことの意味が明かされ、物語は再び大きく動き始めます。
シオンの「歌う」という行動の背後に見え隠れしていたのは、『ペイルコクーン』においてYOKOが青い地球を思って歌った時の心情に似たものであり、それをあえて言語化するのであれば「祈り」なのです。
「サトミに幸せになってほしい」という命令から始まった自我が彼女に宿り、その実現へのささやかな祈りを、彼女は「歌」という形で表現しています。
だからこそ、サトミは物語の終盤に、眠っているシオンを目覚めさせるために「歌う」わけですよ。
それは、彼女が「ムーンプリンセス」ないし「登場人物が歌っている世界」を自分の現実として受け入れた証左であり、同時に自分のために「祈って」くれたシオンに対して「祈り返す」ような行為なのです。
吉浦監督は、ミュージカルの文法が劇中に生じさせる2つの虚構のレイヤーを登場人物の物語における選択肢として位置づけるというメタ的な演出を施しました。
そして「歌う」という行為の主体を徐々に変化させていく過程で、サトミの変化や成長、選択や決断を描いたわけです。
また「歌う」という行為が『ペイルコクーン』でも描かれた「祈り」としての役割を果たすことで、それがサトミとシオンの双方向性を担保し、2人のディスコネクトを飛び越える「脚力」になりました。
単に映画的な「引き」として「歌う」という行為があるのではなく、それが物語と演出に丁寧に組み込まれているところに、吉浦監督の技量を垣間見ることができるでしょう。
『竜とそばかすの姫』にはできなかったこと
最後に偶然か必然か同じ年に公開された細田守監督の『竜とそばかすの姫』との比較の中で、『アイの歌声を聴かせて』について語ってみようと思います。
なぜ、この2つの作品を比較するのかというと、それは多くの点で2つの作品は共通しているからです。





- メインキャラクターが高校生である
- 私たちの世界にはまだ存在しない新しいテクノロジーが普及した世界を舞台にしている
- プリンセスが劇中で重要な役割を果たしている
- ミュージカル的な演出が劇中で登場する
- 物語のクライマックスに法や倫理を飛び越えるような演出がある
- 断絶を乗り越えることが物語の主題の一端を担っている
上記の点は、明確に2つの作品に共通していると思います。
そして、結論から先に行ってしまいますが、上記の軸で比較したときに、全てにおいて上手だったのは『アイの歌声を聴かせて』です。
まず、①については極めて表面的な部分ではありますので、それほど掘り下げて語る必要もないでしょう。主人公が冴えない女子高生という点も一致していました。
②ですが、『竜とそばかすの姫』で全く上手くいっていなかったのが、まさしくここでしたね。
というのも、『竜とそばかすの姫』では「U」という仮想空間を扱っているのですが、これが普及した世界を描写する解像度があまりにも粗いのです。
「U」の世界は本当に「仮想空間」として描かれているものに過ぎず、そこが何のために作られた空間なのかも分からず、どんな機能があって、人々が何を求めて利用しているのかすらも不明瞭です。
また、作中の現実世界において「U」が普及したことが社会に与えた影響が全くもって描写されておらず、設定を劇中世界に馴染ませるための描写や演出が決定的に欠落していたんですね。
その点で、吉浦監督は『イヴの時間』でもそうでしたが、今回の『アイの歌声を聴かせて』でもテクノロジーを劇中世界に融合させる描き込みがさりげなくも、抜群に巧いのです。
私が個人的に感動したのは、学校で掃除をするために使われているAIが生徒から「いじめ」に遭う光景を描いたシーンでした。





あのロボット型のAIが劇中世界の人間にとっても新しい技術であり、珍しいものなのだとしたら、それは畏怖と敬意を持って受け入れられているでしょう。
そういう状況で、あのロボットに「いじめ」をしてやろうという思考はまず働きません。
しかし、あのロボットが彼らの日常に溶け込み、当たり前のものになっていたとしたら、それは人間にとってもはや脅威でも、敬意の対象でもありません。
だからこそ「いじめ」の対象となり、彼らのおもちゃにされてしまう。
何気ない描写ですが、表面的な情報の背後にこれだけの作品世界の空気や人々の認識を読み解くだけのコンテクストが内包されていることが分かりますよね。
こうした細かな描写が『アイの歌声を聴かせて』において、主人公のサトミたちが暮らしている場所ないし時代の解像度を高めているのです。
他にも、彼女の通学シーンでは、道路にAIに関連した標識や看板があったり、農業用ロボットが作業をしていたり、バスに乗り込むと運転手がロボットだったりと矢継ぎ早にAIやロボットを映像に捉えていきます。
しかし、大切なのはそうしたAIやロボットの存在そのものというよりも、それらに対する人間のリアクションの方です。
劇中世界に生きる人たちはそうした私たちの目から見るともの珍しく見える事物を「当たり前の日常」の一部として受け入れ、特に気にも留めていないことが分かります。
これが、劇中世界にテクノロジーがどう馴染んでいるのかを観客に実感させる実に巧妙なテクニックなんですよね。
次に③「プリンセスが劇中で重要な役割を果たしている」について言及していきますが、これについては先ほどの章でも言及しました。
(C)吉浦康裕・BNArts/アイ歌製作委員会
『アイの歌声を聴かせて』においては、「ムーンプリンセス」という劇中フィクションがミュージカルの文法と連動し、物語の構造を生み出す重要な役割を果たしています。
一方の『竜とそばかすの姫』におけるプリンセス要素は基本的にビジュアルだけに留まる極めて表層的な情報であり、それが物語に大きな影響を及ぼすこともありません。
こうしたプリンセス要素1つを取り上げても、劇中で取り上げる必然性に雲泥の差があることが見て取れるのです。
続いて④「ミュージカル的な演出が劇中で登場する」ですが、これも『アイの歌声を聴かせて』と『竜とそばかすの姫』の明確な共通点ですよね。
どちらも主題歌ないし挿入歌そのものは素晴らしいのですし、物語の中で取り入れる必然性は共に認めることができます。
ただ、歌唱シーンのビジュアル的な見せ方も趣向が凝らされており、ミュージカルの文法まで汲んで、それを物語と演出に落としきった『アイの歌声を聴かせて』の方が、個人的には巧さを感じました。
演出としては、まずミュージカル特有の台詞と歌唱パートがシームレスであることにより生じる違和感に「シオンが試験中のAIだから」という理由づけが効いていた印象を受けました。
さらに、彼女がインターネットに接続することで、周辺の機器に働きかけ、これまたミュージカル特有のどこから流れているのか分からない挿入歌を、劇中世界に実際に生じている音として確立させることに成功していたんです。
こうしたSF設定があるからこそできるミュージカル演出が、全編にわたって抜群に巧く、作り手のミュージカルというジャンルそのものへの深い愛も感じることができる作りになっていたと言えるでしょう。
そして、⑤ですが、ここが『竜とそばかすの姫』と『アイの歌声を聴かせて』においてもう1つ大きな差が出たポイントだと思います。
ネタバレを防ぐため詳細な言及は避けますが、『竜とそばかすの姫』のクライマックスには法や倫理、社会制度を個人が超越していく描写がありました。
個人とその周囲の連帯によって事件を解決し、そこに当然介在するはずの社会や制度が存在しないという世界観は細田守監督作品ではお決まりですが、『竜とそばかすの姫』では、それが図らずも悪い方向に向いてしまったと思っています。
というのも、主人公が法や倫理、社会制度を超えていくような行動を取ることに対して何の必然性も動機も見て取ることができないんですよね。
『天気の子』の終盤にも、同様に主人公が法や倫理、社会制度を超えていく描写がありましたが、ここではあまり違和感を感じることはありませんでした。
なぜなら、同作の主人公の行動を裏づける動機と彼がその行動を取らなければならない必然性が圧倒的な強度で担保されていたからです。
この強度を観客に示すことができるかどうかで、こうした行動の印象が変わってくることは言うまでもありません。
上手くいかなければ、観客にはそれが「ノイズ」に感じられるでしょうし、上手くいけば登場人物の感情に自分を重ねて見ることができるはずです。
『アイの歌声を聴かせて』においても、終盤に企業ビルに侵入して、製品を盗み出すという紛うことなき法や倫理を超えた行動を主人公たちが取ります。
(C)吉浦康裕・BNArts/アイ歌製作委員会
当然、私たちの生きている現実世界であんなことをすれば、逮捕されてしまうことは容易に想像がつきますし、下手をするとノイズになりかねない展開なのですが、吉浦監督はそうはさせていません。
なぜなら、観客が主人公たちがそうした行動を取らざるを得ないことに納得し、共感できたからなんですよね。
というのも、『アイの歌声を聴かせて』という作品は中盤の夜のソーラーパネル区画でのミュージカルシーンを軸にして対になるような構造になっていました。
前半は、シオンというAIがそのぶっ飛んだ行動と歌でサトミとその周囲の人間模様を変化させていき、後半は対照的にサトミとその友人がぶっ飛んだ行動と歌でシオンを救い出そうとします。
シオンは、物語の前半部分で明確にAIに課せられた制約に違反していますが、そうしてでもなおサトミを「幸せにしたい」という願いに従うのです。
だからこそ、それと対になる後半パートで、自分たちが受けた恩恵をシオンへと今度は還元したいと考えるサトミたちが、「法や倫理に違反してでも」と考えるのはある意味で当然の成り行きなんですよね。
ここが同じ重さで描かれているからこそ、後半の展開に違和感を抱きづらくなっているわけです。
そして、もう1つ指摘できるのは、誰かを「幸せにしたい」というエゴにも似た願いの熱量がきちんと描かれていることでしょう。
『竜とそばかすの姫』では、あの行動を取るのが主人公でなければならないのかという疑念が常に付きまといます。そこをクリアするための根拠として現実世界の事例を持ち出したりもしているのですが、この認識が明確に誤っていたのも致命的でした。
一方で『アイの歌声を聴かせて』では、前半はシオンの「サトミを幸せにしたい」という願いが、後半はサトミの「シオンを幸せにしたい」という願いが物語を動かす原動力になっています。
そこに、あの行動を取るのがサトミでなければならないという必然性があり、同時に彼女自身の中に圧倒的な強度の動機が存在します。
こうした動機の描き込み、必然性の演出において『アイの歌声を聴かせて』は非常に優れており、それ故に彼らが法や倫理を超えて、シオンのために行動する展開が当然の帰結に思えたのでしょう。
最後に⑥「断絶を乗り越えることが物語の主題の一端を担っている」についてですが、これは若干方向性は違いますが、共通していることでした。
『竜とそばかすの姫』は、地域の共同体やセーフティーネットの崩壊により生じた断絶を個人の連帯とインターネットにより匿名の人間とのつながりが埋める可能性に、楽観的な希望を示す作品でもありました。
一方で『アイの歌声を聴かせて』は、人間とAIとの違いを「歌」と「記憶」という観点で描き出し、その断絶を飛び越えて通じ合っていく過程を描きました。
どちらも社会に根付いたテーマ性だと思いますし、これについてはどちらも優れていたと断言できます。
ここまで長短含めて2つの作品の共通点について比較してみました。
やはり私としては、物語や演出、世界観の描き込み、設定の活かし方、プリンセスという要素の持ち込み方などなど、どれをとっても『アイの歌声を聴かせて』が光っていたように思いました。
ただ、これほどまでに多くの共通点を抱えた日本のトップクリエイターによるアニメ作品が同じ年に公開されるというのも面白いですし、ぜひ2つを比較しながら鑑賞してみてください。
おわりに
いかがだったでしょうか。
今回は映画『アイの歌声を聴かせて』についてお話してきました。





彼の作り出す作品は今回取り上げた『ペイルコクーン』でも『イヴの時間』でもそうでしたが、断絶を飛び越えていく物語が共通しています。
もちろんそのプロセスを緻密に描写して、じっくりと「橋渡しをする」というアプローチもあるでしょうが、吉浦監督はあえてそこで「飛び越える」手法を取っているように思いました。
もちろんキャラクターの描写の積み重ねは丁寧なのですが、最後のところでは『アイの歌声を聴かせて』における「歌うこと」のように、ある種の力業が用いられます。
しかし、『イヴの時間』におけるマサキとロッティの断絶を越えるきっかけになったのが、「声をかけること」だったように、私たちが飛び越えられないと思っている断絶は、思ったよりもシンプルでかつ大胆な方法で、乗り越えられるのかもしれません。
描写や世界観の作りこみの細かさと、それとは対照的な大胆さと思い切りの良さを併せ持つ作家としての吉浦康裕監督。
だからこそ、私は彼の作品にこんなにも惹かれるのかもしれないと『アイの歌声を聴かせて』を鑑賞して、改めて感じました。
今回も読んでくださった方、ありがとうございました。