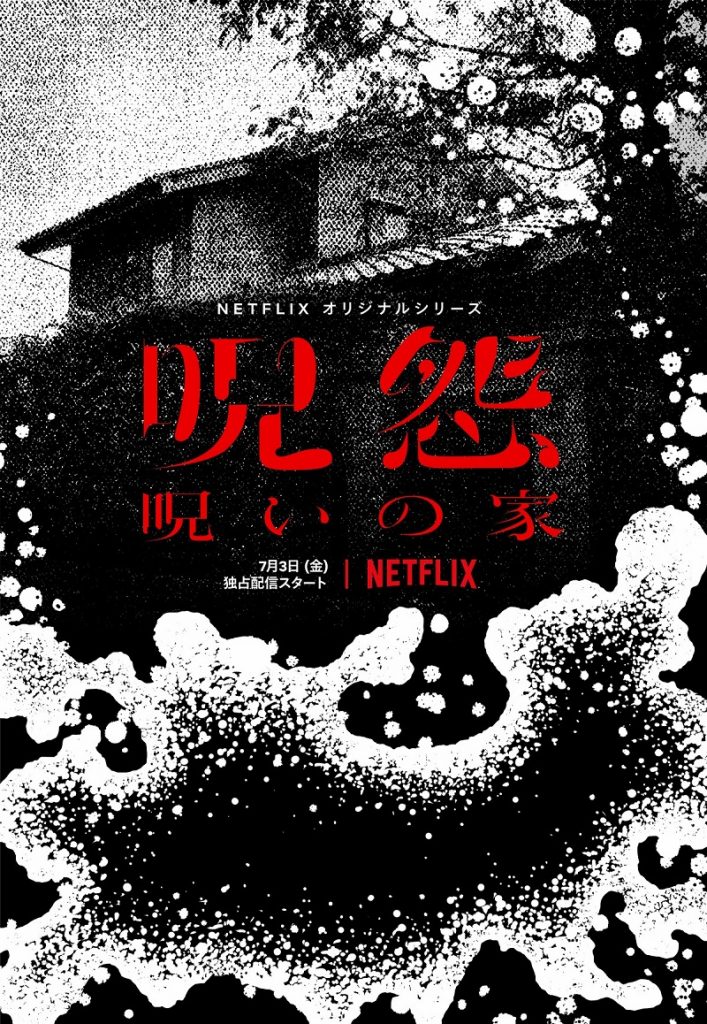みなさんこんにちは。ナガと申します。
今回はですね映画『ちょっと思い出しただけ』についてお話していこうと思います。

『花束みたいな恋をした』『明け方の若者たち』『ボクたちはみんな大人になれなかった』など、「シティムービー」とも呼ぶべき街と若者、そして記憶と別れを巡る映画が近年立て続けに公開されました。
そんな中で、『アズミハルコは行方不明』や『私たちのハァハァ』、『くれなずめ』など若者の独特の空気感を常に映像に収めてきた松居大悟監督が、今回このジャンルに挑戦する運びとなったようです。
この『ちょっと思い出しただけ』は個人差はありますが、「ちょっとで致死量」みたいな映画だと思っております。
作家のFさんが以前に著書『20代で得た知見』の中で恋愛の目的についてこう綴っておられました。
恋愛の目的とは、お相手に最高のトラウマを与えることだと思う。もう二度と素面では歩けない夜道を与えること、できればディズニーランドなんて二度と行きたくないと思わせること。
(F『20代で得た知見』より)
おそらくFさんの言うところの「素面で歩けない夜道」がある人にとって、この映画は「ちょっとで致死量」であり、おそらく本編上映中に死にます。





この映画を、映画好きに分かりやすく説明するとしたら、「『ラ・ラ・ランド』のラストシーンから始まり、『ラ・ラ・ランド』の本編を全て時系列を逆にして回想していく映画」となるでしょうか。
「回想劇」というジャンル自体はよくあるものですし、日付をトリガーにしてキャラクターの物語を描く手法も『ワン・デイ 23年のラブストーリー』なんかがあるので、珍しいものとは思いません。
では、『ちょっと思い出しただけ』の面白さはどこにあるのかと言うと、それは偶発性と作為性の絶妙なバランスにあるのです。
男女が出会い、恋をして、関係を深めていくも、徐々に覚めていき、最後は別れを選ぶ。
他人の失恋譚を描くためには、これだけのプロセスを描く必要があり、映画はストーリーテリングの都合上、彼らの重要な出来事にスポットを当てていく必要があります。
しかし、その切り口を「ある1日」に縛るとどうなるでしょうか。
「ある1日」で切り取るという定量的な観測により、映画という作為性の産物に偶発性が宿り、そこに血の通ったリアリティが生まれるのです。
『ちょっと思い出しただけ』とは、そんな作為性と偶発性のあわいに生まれた、何かが起きた瞬間、何かが起きそうな瞬間、そして何も起きなかった瞬間の連続を体験していく不思議なラブストーリーとなっています。
今回は、そんな本作について個人的に感じたことや考えたことを綴っていきます。
作品のネタバレになるような内容を含みますので、未鑑賞の方はお気をつけください。
良かったら最後までお付き合いください。
目次
『ちょっと思い出しただけ』
あらすじと概要
ロックバンド「クリープハイプ」の尾崎世界観が自身のオールタイムベストに挙げる、ジム・ジャームッシュ監督の代表作のひとつ「ナイト・オン・ザ・プラネット」に着想を得て書き上げた新曲「Night on the Planet」に触発された松居監督が執筆した、初めてのオリジナルのラブストーリー。怪我でダンサーの道を諦めた照生とタクシードライバーの葉を軸に、様々な登場人物たちとの会話を通じて都会の夜に無数に輝く人生の機微を、繊細かつユーモラスに描く。
(映画com.より)
『花束みたいな恋をした』では、Awesome City Clubの『勿忘』がインスパイアソングという位置づけになっていましたが、今回のクリープハイプの「Night on the Planet」もそれに近いようですね。
当ブログ管理人もジム・ジャームッシュ監督の『ストレンジャー・ザン・パラダイス』が大好きなので、今回の映画にジム・ジャームッシュ色が強く反映されていた点にはオタク心をくすぐられました。
スタッフ
- 監督:松居大悟
- 脚本:松居大悟
- 製作:太田和宏
- 撮影:塩谷大樹
- 照明:藤井勇
- 録音:竹内久史
- 美術:相馬直樹
- 編集:瀧田隆一
- 劇伴:森優太
- 主題歌:クリープハイプ





記事の冒頭にも書きましたが、松居監督は『くれなずめ』や『アズミハルコは行方不明』などの監督を務めたことでも知られています。
また、以前に彼の手がけた『私たちのハァハァ』もクリープハイプを題材にした青春映画でしたね。
松居監督の映画の面白さは、劇的なことを描くのではなく、それが起こりそうで起こらない空気を演出している点にあると思っています。
特に今回の『ちょっと思い出しただけ』はその良さが前面に押し出された作品で、ある1日で遡るというストーリーテリングの定量性により、何も起きない時間、あるいは何かが起こりそうな時間を確信犯的に作品の中に持ち込んでいました。
撮影には、『アイスと雨音』や『私たちのハァハァ』などこれまでの松居監督作品にも長く携わってきた塩谷大樹さん、照明には『万引き家族』などで印象的なライティングを施した藤井勇さんが起用されています。
また、劇伴音楽を、2021年末に公開の『明け方の若者たち』でも、徐々に関係が終わっていく男女の切ない人間模様を演出した森優太さんが手がけています。
キャスト
- 照生:池松壮亮
- 葉:伊藤沙莉
- 泉美:河合優実
- さつき:大関れいか
- 康太:屋敷裕政





まず、主人公カップルの2人を演じていたのが、池松壮亮さんと伊藤沙莉さんでした。
この2人は、もう当ブログ管理人が何かを言うまでもなく抜群に巧いですね。
『ボクたちはみんな大人になれなかった』でも思いましたが、伊藤沙莉さんは「別れた時はすぐに忘れるだろうと思っていたけど、2年経ってもふとした時瞬間に思い出してしまう女性」ってこんな人なんじゃないかなという妙な説得力があるのです。
また、本作には昨年『サマーフィルムにのって』でブレイクを果たした河合優実さんも出演しており、こちらも要注目です。
そして、個人的にかなり笑ってしまったのが、ニューヨークの屋敷さんですね。
下北沢的なエリアで若いころから遊びまくっていたけど、歳を重ねて、妙に落ち着いた人と結婚して家庭を持つ男性って、多分こんな人なんだろうというイメージをそのまま具現化したような、もはやそのイデアなんじゃないか?と思うようなリアリティでした。
というより、演技をしているというよりは、バラエティー番組などで見かける屋敷さんそのままだったので、それが逆に面白かったですね。
『ちょっと思い出しただけ』解説と考察(ネタバレあり)
作為性と偶発性の交錯を描く
(C)2022「ちょっと思い出しただけ」製作委員会
『ちょっと思い出しただけ』は主人公の照生の誕生日の1日だけを数年間にわたって遡っていく形式で物語を展開していきます。
記事の冒頭でも書いたように「失恋映画」を観客に理解できるものにするためには、ある程度描かなければならないパーツがノルマとして存在していますよね。
それは、出会いであり、恋の深まりであり、付き合い始めてからの日常であり、関係が徐々に冷めていくすれ違いであり、そして関係が終わるまさにその瞬間です。
2021年に大ヒットした『花束みたいな恋をした』も、このプロセスを時系列で丁寧に描くことで、ラストシーンの別れの決定的な瞬間を演出しました。
同作の脚本を手掛ける坂元裕二さんが文語的なセリフを好む傾向もあり、『花束みたいな恋をした』は自然体というよりは、意図をもって構築された失恋譚という印象を強めていたように思います。
一方で、『ちょっと思い出しただけ』は失恋譚という物語のジャンルこそ共通していますが、ストーリーテリングの観点で見ると、その対極にある作品と言えるのかもしれません。
失恋譚におけるパーツを回収しようとする物語の作為性と、ある1日で過去をさかのぼるというストーリーテリングの定量性によるせめぎ合いが劇中で生じているのです。
例えば、別れの瞬間を描きたければ、『花束みたいな恋をした』のファミレスのシーンのように2人が言葉を口にして、その関係を明確に終わらせる瞬間を描くのが一番分かりやすいですよね。
しかし、『ちょっと思い出しただけ』はある1日だけしか遡れないというフレームによって、その瞬間を描くことができません。
そのため、その瞬間が訪れる1週間前あるいは2週間前の、2人の関係が冷め切ってしまった空しい時間を切り取り、フィルムに焼きつけるに留まっているわけです。
これこそが松居監督の作り出す「空気」であり、彼の真骨頂とも言える描写なんですよね。
私たちの眼には盲点があり、そこに入った視覚情報は欠落してしまうのですが、それを脳が補うことで補完し、私たちに視覚情報の欠落を意識させないという機能があります。
『ちょっと思い出しただけ』の作劇にも同様の効果が見られます。
つまり、明確な別れの瞬間を描くのではなく、別れて数年が経った2人の姿と、別れる少し前の時間を見せることで、物語に必要なパーツを観客の脳内で補完させる仕組みになっているわけです。
物語には作為性が付きまとい、それは時に観客のノイズにもなるわけで、「ご都合主義」なんて揶揄はその典型ですよね。
失恋譚というジャンルも、ある程度必要なパーツは決まっているプラモデルのようなものであり、あとはそのパーツをどう加工し、どう色を付けるのかという細部の問題のような気がしています。
しかし、そのパーツ選びをある基準のもとで自分の意図を極限まで排して行ったらどうなるのか。それがこの映画の面白さなのです。
パーツは不揃いで、失恋譚の説明書通りに出来上がったとは、とても言えない映画ではあるのですが、私たちはその無作為に組み立てられたかに見える何かに、完成像をイメージすることができます。
こうした作為性と偶発性の交錯を作品の中で引き起こし、タイトルにもある「ちょっと」のニュアンスを表現した松居監督の手腕を手放しで賞賛したいと思いました。
ジム・ジャームッシュ映画のしらべ
『ちょっと思い出しただけ』には、何度も繰り返しジム・ジャームッシュ監督の『ナイトオンザプラネット』が登場します。
照生の部屋に飾られたポスター、2人が部屋で見ていたテレビ、そして2人がタクシーで演じた寸劇など細部に同作品が宿っているのです。
また、ジム・ジャームッシュ監督の作品ではおなじみの永瀬正敏さんが出演したことで、その印象はさらに強まっています。
彼は『ミステリートレイン』や『パターソン』などジム・ジャームッシュ監督のいくつかの作品に出演しており、その印象が強い俳優でもあります。
また、自宅と行きつけのスナック、職場を行き来するだけのシンプルな舞台設定や、タクシードライバーという設定、歩くシーンを横から撮影するショットのインサートなどジム・ジャームッシュ監督作品の影響は本作の至る所に見出すことができるのです。
では、なぜ松居監督は、今作を描くにあたって「ジム・ジャームッシュ」というクリエイターを持ち込んだのでしょうか。
その最大の理由は、ジム・ジャームッシュが「偶発性を愛する作家」であるからです。
彼はキャリア初期のインタビューでこう語っています。
僕が興味を惹かれたのは逆にちっぽけな出来事であって、それからそういうちっぽけな出来事同士をいかに関係づけられるかということだった。例えば、早朝に窓際でサックスを吹いている男が出てきて、次にサックスフォーンについてのジョークがあって、そして最後に朝のサックス吹きと主人公が再会する、と言った具合だ。
(ルドヴィク・ヘルツベリ『映画監督ジム・ジャームッシュの歴史』より)
また、偶発性については次のようにも語っています。
偶然の一致のほうが、観客の心を強く打つと思うんだ。ドラマチックな活劇、つまりカーチェイスとか、女と痴話喧嘩することなんかよりもね。
(ルドヴィク・ヘルツベリ『映画監督ジム・ジャームッシュの歴史』より)
こうしたキャリア初期の発言からも、そしてその後、彼が世に送り出した作品からも分かる通りで、彼の作品はいかに作為性を排除するかの戦いだったと思います。
例えば、『ダウンバイロー』は「脱獄劇」というジャンルでありながら、同ジャンルに必要なパーツのほとんどを描いていません。
脱獄計画が詳細に描かれないだけではなく、脱出するまさにその瞬間、同ジャンルの最大の見せ場でさえも外しているのです。
そして、『ちょっと思い出しただけ』でしきりに登場する『ナイトオンザプラネット』もそうした作品群の1つにあたります。
運転手がルートを選び、たまたまそのルートで車での移動を必要としていた他人が交わるタクシーという偶発性に裏打ちされた空間。
1つの夜にいくつ存在しているのかも分からないそんな偶然の空間を、さらに地球という惑星の中から無作為に5つ抽出するという『ナイトオンザプラネット』の試みは、ジム・ジャームッシュ監督の作家性が最も色濃く反映されたアプローチの1つでしょう。
そんなジム・ジャームッシュ監督の作品に触発された『ちょっと思い出しただけ』は、ある1日で時間を遡るという定量性により、映画の中から作為性を排除しようと試みました。
このアプローチにより、本作には本来の「失恋譚」であれば、編集段階でカットされてしまうようなシーンが当たり前のように残されています。
例えば、主人公の照生がただ仕事に行って帰って寝るだけの何も起きない時間があったり、主人公の部屋に以前に住んでいた夫婦の日常が映し出される時間があったりしましたよね。
これは「失恋譚」を描く上では、必要な時間とは言えませんが、ある1日を切り取るという定理によって、偶然映画に映りこんでしまったシーンたちと言えるでしょう。
しかし、その偶発性にこそ美学は宿るものなのです。
1つ1つの瞬間は確かに意味は宿らない「ちっぽけなもの」かもしれませんが、それらを関係づけると映画になる。
松居監督はジム・ジャームッシュ監督の『ナイトオンザプラネット』を引用することで、彼の偶発性の美学を作品に持ち込むことに成功しています。
作為と偶発が交錯する空間としての、自宅、ジェンガ
(C)2022「ちょっと思い出しただけ」製作委員会
『ちょっと思い出しただけ』は、そうした作為性と偶発性の交錯を体現するものとして、自宅という空間を採用しています。
自宅というのは、面白くて、引っ越した当初はあなたが明確に意図して購入したものや持ち込んだものに満たされた、極めて作為的な空間ですよね。
しかし、暮らしを続けていくと、自分が意図していないものが送られてきたり、家に遊びに来た誰かが忘れ物をしていったり、同棲し始めた恋人が私物を持ち込んだりといった形で、意図せぬものに侵食されていきます。
つまり、自宅は作為と偶発が交錯する空間であり、そのせめぎ合いが日常的に起きている場なんですね。
飼っている猫、トラの形をしたラグ、額縁に入れたポスター、窓際の観葉植物、毎朝体操を促すラジオ…。
時間を遡れば遡るほどに、照生の部屋からは偶発性の産物が排除されていき、自分が意図して持ち込んだものに満たされた、作為的な空間へと逆行していきます。
こうした自宅の描写は、私たちの現在が作為性と偶発性の上に成り立った極めて不安定なものであることを示唆しているように思えました。
現在の照生の自宅が、そうやって形作られたように、人間もまた作為性と偶発性の交錯の産物なのです。
『ちょっと思い出しただけ』に映し出される照生と葉の人間模様には、意図的なものと偶発的なものが混ざりあっています。
例えば、怪我をしたことを葉に伝えず関係性を険悪にしてしまったのは、照生の意図によるものですし、2人の関係性が発展した日に葉が照生のアルバイト先にまで会いに行ったのも意図的なものです。
一方で、葉が照生の舞台に出演しているダンサーの友人枠で打ち上げ会場にいて、その後オートロックで会場から締め出されたのは偶発的なものでしたよね。
私たちの自宅が作為と偶然に満ちているように、そこで暮らしている私たちの人生もまた作為と偶然に満ちており、その緻密なネットワークにより構築されているわけです。
先ほど引用したインタビューの一節にもありましたが、まさに「ちっぽけな出来事同士をいかに関係づけられるか」が重要なのであり、その関係性の結果が私たちの「現在」なんですよね。
そういう意味では、「失恋」はジェンガのようなものなのかもしれません。
ジェンガはプレーヤーの意図にさまざまな偶発的な要因が加わり、パーツを抜き、それを上に積み上げ続けられるかを競うゲームです。
私たちの意図で崩れる場合もあれば、意図せぬ偶然の出来事で崩れる場合もある。
しかし、ジェンガにおいてはその瞬間そのものは重要ではなく、むしろ積み重ねたプロセスがその決定的瞬間をもたらしているに過ぎません。
つまり、敗北を決定づける瞬間が意図したものであれ、意図せぬものであれ、そこに至るプロセスには作為性と偶発性が混在しているんです。
ジェンガがそのプロセスを味わうゲームであるように、自分の人生を恋愛をそんな風に振り返り、それが今の自分を形作るネットワークの一部なのだとして愛せるならば。
照生と葉は、映画のフィナーレで初めて「明日の朝日」を目撃することになります。
彼らが今、望んだ場所から、望んだ人とその朝日を眺めることができているのかどうかは分かりません。
それでも、過去をちょっと思い出し、そのつながりを愛することは、今自分が立っているこの場所を少しだけ愛せるようになるということでもあります。
舞台と観客、「演じる」が転じる構造
(C)2022「ちょっと思い出しただけ」製作委員会
もう1つ『ちょっと思い出しただけ』を語る上で欠かせないのが、舞台上の演者とサポートスタッフ(あるいは観客)によって構築される劇場という空間です。
通常、舞台の上にいる人間が「主」であり、サポートスタッフは「従」になり、物語の中心に立つことができるのは、舞台の上の前者になります。
そして、その構造はタクシーという空間にも見て取ることができます。
運転手は言わばサポートスタッフであり、目的地を決める主体ではありません。それを決めるのがお客様である以上、物語の主人公は彼らの方です。
照生と葉の関係性の変化は、こうした舞台と舞台袖の関係を意識しながら展開されています。
照生はダンサーであり、舞台上に立ち、演じる側にいた人間です。
一方の葉は、タクシー運転手であり、ずっと誰かの物語の目的地を追い続ける生活をしていました。また、その背景には演じることからの離脱があります。
(C)2022「ちょっと思い出しただけ」製作委員会
だからこそ、2人の出会いは舞台と観客席を介して実現される必要がありました。
演じる側とそれを支える側に属する他人同士の出会いが舞台と観客席という境界を隔てて実現したわけですね。
そうして、2人は出会い、夜の町の片隅で踊り始めるのですが、この瞬間、2人は自分たちだけの舞台に立ったと言っても過言ではないのかもしれません。
照生と葉は恋人関係を結ぶことで、2人だけの作品を構築し、他人同士でありながら恋人同士を演じるようになるわけです。
2人の関係性が発展する夜、照生は水族館のアルバイトをしており、そこにやってきた葉を抱きしめました。
しかし、2年後の誕生日には、2人は水族館に「お客様」の立場で忍び込み、空間を自分たちのものにしています。
他にもタクシー運転手とそのお客様という関係だった2人は、数年後にタクシー運転手とそのお客様という立場を演じる恋人同士という関係性に転じていました。
(C)2022「ちょっと思い出しただけ」製作委員会
このように舞台の袖にいる他人同士が、恋愛を通じて、2人だけの舞台を作り出し、その上で「演じる」という行為を始めるものとして、『ちょっと思い出しただけ』は恋愛の始まりを演出したのです。
では、恋愛の終わりとは一体何なのでしょうか。
それは、恋人同士が他人同士を演じるようになり、やがて他人同士に戻っていくプロセスなのではないでしょうか。
運転手とそのお客様という役割を演じていた恋人同士は、過ごした時間を経て、恋人同士を演じる運転手とそのお客様に転じていきます。
葉が照生に対して乗車料金を請求する一幕は、その決定的な瞬間であり、彼らが舞台の上で演じていた役割を脱ぎ捨てようとしていることを明確にしていたのです。
また、照生が足の怪我によって舞台から降りざるを得なくなったというのも印象的な出来事でしょう。
舞台の上でダンサーとして「演じる」ことを奪われた自分の人生の展望が見えない照生と、タクシー運転手を続けてきたことも相まって、舞台の下での生活をイメージできた葉と。
だからこそ、物語の冒頭とクライマックスで反芻される2人の視線が交錯しない形での再会は、照明スタッフになってもなお舞台の上から降りること受け入れきれない照生と、それを観客席の向こうから見つめる葉という形で実現するのです。
2人が、まだあの舞台に立って、「演じる」を続けていた未来があったのかもしません。
それでも、2人は意図的に、あるいは偶発的に、今この場所に立っているのです。
他人が恋人同士を演じるようになって恋愛が始まり、恋人同士が他人同士を演じるようになって恋愛が終わる。
そういう「演じる」が転じていくものとしての失恋を『ちょっと思い出しただけ』は描き出したのです。
おわりに:ジュンはなぜあのベンチを訪れるのか
いかがだったでしょうか。
今回は映画『ちょっと思い出しただけ』についてお話してきました。
最後に、永瀬正敏さんが演じたジュンがなぜあのベンチを訪れるのかについての自分なりの解釈をお話させてください!
(C)2022「ちょっと思い出しただけ」製作委員会
彼が見つめていたものは、抽象的に言うなれば「愛」です。それは揺らぎません。
では、それをもう少し言語化してみましょう。
ジュンは永瀬正敏さんが演じているという都合もあり、本作においてジム・ジャームッシュ監督の美学を体現する人物と見て良いと思います。
彼が妻と過ごした公園のベンチを訪れ続けるのは、単にもう来るはずのない彼女の亡霊を追っているからではないことは明白でしょう。
ジュンは、あの日この場所に自分が妻とやってきたという事実を裏打ちする、極めて作為的でかつ極めて偶発的な瞬間の連続とつながりへの賛美を表現しているのです。
ジム・ジャームッシュ監督の映画を見ていると、今自分がいるこの場所への愛おしさを無性に感じることがあります。
人生には、望んだことも望まなかったことも、意図したことも意図しなかったことも全てが混ざりあっていて、その関係性の上に私たちの今がある。
1つ1つは取るに足らない、本当に「ちょっとしたこと」なのかもしれません。
それでも、そのつながりがもたらす「今」を、私が立っている「ここ」を肯定できるようになることが「愛」なのではないでしょうか。
ジュンは妻の不在を引きずっているのではありません。妻の不在をも「今」「ここ」を形作る要素だと認識した上で、それらを肯定し、愛する達観した人間なのです。
表層的にジム・ジャームッシュ監督の作風を取り入れることは簡単かもしれません。
しかし、この作品は、彼の作品の美学や哲学を見事に取り入れ、松居監督なりの今の若者のための映画に翻訳しています。
その見事な手腕を讃えざるを得ない傑作であり、2022年必見の映画と言えるでしょう。
今回も読んでくださった方、ありがとうございました。