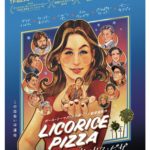2022年の春クールのアニメもその大半が放送終了を迎えようとしていますが、その中で事前の予測に反して、最も注目を集めた作品の1つが『パリピ孔明』ではないでしょうか。
四葉夕卜さんが原作を担当し、作画を小川亮さんが担当している同シリーズは、現在『週刊ヤングマガジン』にて連載中です。
とりわけ本作が注目されるきっかけになったのは、何と言っても中毒性のあるOP主題歌なのかもしれません。
ハンガリーの歌手JOLLYによる楽曲『Bulikirály』を日本語カバーした『チキチキバンバン』はその独特のダンスも相まって、盛大にバズったと言えます。
しかし、いくらそうした「飛び道具」的な部分で話題を集めたところで、作品そのものが面白くなければ、継続した視聴は望めません。
加えて『パリピ孔明』は、『三国志』の英雄である孔明が現代日本に転生するという、下手をすると「出オチ」になりかねない設定を根幹に据えています。
そんな中で、1クールしっかりと描き切り、それに視聴者もついてきたという事実は賞賛に値するものです。
ただ『パリピ孔明』は、個人的にもアニメ化が非常に難しい作品だったと感じています。
四次元ポケットと成長譚と1クールのジレンマ
© 四葉夕卜・小川亮・講談社/「パリピ孔明」製作委員会
その最大の理由は「四次元ポケット」「成長劇」「1クール」という3つの要素がかみ合わないことからくるジレンマなのです。
『パリピ孔明』は、国民的アニメシリーズの『ドラえもん』に似ています。
不甲斐ない主人公の前に何でも望みを叶えてくれるスーパーな存在が現れて助けてくれる、そのプロセスを楽しむという構造が非常に似ているのです。
もちろん『ドラえもん』も原作の方では、最終的にのび太が自立を獲得する成長劇には落ち着いています。
しかし、『ドラえもん』のアニメに関しては、1話完結方式で、ドラえもんがひみつ道具でのび太を助けるというお決まりの流れが半永久的に続いていますよね。
つまり、『ドラえもん』の場合はのび太という主人公の成長劇とドラえもんの「四次元ポケット」から出てくるひみつ道具のかみ合わせの悪さを内包しつつも、長寿シリーズであるが故に、成長劇の本筋に踏み込むことからある程度免除されているのです。
ただ、『パリピ孔明』の場合は、1クールで物語に1つの区切りをつけなければなりません。
誰がどう考えても、孔明がメインで登場して、英子を助けるというお決まりの流れを繰り返す方が面白いですし、それは「ひみつ道具」も「ドラえもん」も出てこない『ドラえもん』を視聴者が望んでいないのと同様です。
しかし、『パリピ孔明』は1クールで終わるという事情と、紛いなりにも「英子の成長劇」という側面を孕んでいる以上、『ドラえもん』のようにはいかないわけですよ。
現に、第7話付近から少しずつ孔明がメインで登場しないエピソードが続くと、SNSなどで「失速した」といった意見が目につくようになりました。
もちろん、そうした意見は理解できますし、私も『三国志』オタクですので、孔明がメインで出てきてくれる回の方が楽しめたのは事実です。
それでも、本作の制作陣は、こうしたジレンマの中で、英子の成長劇に真摯に向き合うという選択をし、最終回で特大のカタルシスをもたらしてくれました。
私は、この選択を賞賛したいのです。
刹那的な面白さに終始していたら、確かに失速はしなかったかもしれませんが、本作がのちにたくさんの人から思い出してもらえるような作品になっていたかどうかは分かりません。
下手をすると、その瞬間の楽しみとして短い時間で消費され、すぐに忘れてしまうような作品になっていた可能性もあります。
しかし、「英子の成長劇」という屋台骨をきちんと貫き通したことで、本作は1クールを通じて明確に1つの物語として固く結ばれました。
「孔明」という出オチめいた設定で1クールを駆け抜けるのではなく、ある程度その存在をコントロールし、あくまでも英子の成長譚、サクセスストーリーとして、彼女の「自立」を志向した点に、制作陣の勇気と気概を感じましたね。
眼を開くということ、誰かを救うこと
© 四葉夕卜・小川亮・講談社/「パリピ孔明」製作委員会
『パリピ孔明』は、ここまでも述べてきたように主人公である英子の成長劇、サクセスストーリーを描いています。
そこに孔明という『三国志』の英雄を絡ませることにより、ユニークで奇想天外な内容になっているわけですが、主軸そのものは王道です。
今作が巧いのは、『三国志』における孔明の物語と、現代における英子の物語をシンクロさせ、それを「眼」というモチーフでつないだことと言えます。
劇中でも何度か言及されていましたが、孔明はのちに主君となった劉備玄徳に「三顧の礼」で軍師として迎え入れられました。
逸話として面白いのは、三度目に劉備が訪れた際に、書斎で孔明は眠っており、劉備は彼が起きてくるのをじっと待っていたというものです。
劉備という人間の懐の深さが現れたものですし、そういう姿勢に孔明が魅力を感じたであろうことは言うまでもありません。
しかし、思えばここで「眠り」という状態が持ち出されており、孔明は劉備によって、眠りから覚め、ようやく眼を開いたと考えることもできます。
英子もまた高校生時代にメンタルに不調をきたし、修学旅行でやって来た渋谷の駅のホームで命を絶とうとしました。
そんな彼女を救い、眼を開かせてくれたのは、「アメリカの歌姫」と呼ばれる1人の女性シンガーでした。
『パリピ孔明』の第1話で描かれたこの回想シーンでは、英子の眼が「陰っている」様を映し出し、のちに歌を聴いた彼女の眼に光が戻る演出を施しています。
© 四葉夕卜・小川亮・講談社/「パリピ孔明」製作委員会
つまり、歌によって誰かを救うことを、本作はその眼に光を灯すこと、そして「眼を開かせること」だと第1話の時点で位置づけていたわけです。
そして、本作は英子の成長劇としてのゴールを、「救われた側」から「救う側」へと転じるプロセスを通じて描こうと試みました。
孔明は、劉備との出会いによって「眼」を開き、一方で、孔明はのちに北伐の際に、姜維という若者の「眼」を開かせ、自身の後継者に据えました。
『三国志』においても、この流れがあったからこそ、それに重ねる形で、英子の成長劇を演出することができたわけです。
『パリピ孔明』で英子が救うことになるのは、AZALEAというグループでベース&ボーカルを担当している七海という女性でした。
彼女は歌うことの楽しさを心の底から理解しつつも、アーティストとして成功するために、それを心の底に閉じ込めざるを得なくなってしまいました。
AZALEAのコスチュームにおいて、特に象徴的なのが、そのアイマスクではないでしょうか。
七海の「眼」を隠して、外から見えないようにしてしまうその装飾品は、彼女が歌うことの本質に眼を瞑らざるを得なくなった状況を視覚的に表現しています。
こんなコスチュームを身につけて音楽活動をしたくないと願いながらも、バンドとして売れるために、そうせざるを得ないジレンマが彼女の心を蝕んでいきました。
そんな七海の「眼」を開かせたのは誰か、彼女の心に光を取り戻させたのは誰か。それが他でもない英子だったわけです。
最終回(第12話)では、英子と七海がアーティストとして対峙するクライマックスが描かれましたが、その演出に改めて注目してみてください。
英子の心から歌うことを楽しむ姿勢と誰かを救いたい(あるいは過去の自分を救いたい)という強い願いが風となり、七海に音楽を純粋に楽しんでいたころの記憶を思い出させます。
そして、彼女のアイマスク越しに彼女の「眼」が見えるようになるのです。
© 四葉夕卜・小川亮・講談社/「パリピ孔明」製作委員会
ここで、アイマスクが外れるのではなくて、アイマスク越しに彼女の「眼」が見えるという演出を選択したことに、意味があると私は思います。
これまでアイマスク越しに眼が見えることはなかったわけですから、当然眼が見えているというのはフィクションがついた「嘘」に過ぎません。
実際に物理的に彼女の眼を開いたわけではなくて、彼女の心の眼を開かせたのだという事実が、この「嘘」によって明確になるわけですよ。
彼女にしか分からない、されど、彼女の中では確かに起きた革命的変化。
「眼を開く」という変化を、『三国志』に重ねる形で引用し、第1話の時点で演出として持ち込んだうえで、それを最終回の最も重要な局面の演出に還元するという構成はお見事という他ないものでしょう。
「たみくさ」を想う「エゴイスト」としての目覚め
最後になりますが、『パリピ孔明』が素晴らしかったのは、英子が「エゴイスト」に目覚めるところを成長の1つの落としどころに据えたことだと個人的には思っています。
「誰かを救う」なんて思いは、どこか自分本位で傲慢なものではないでしょうか。
現に、第9話で、英子は七海のためにスカイデッキで歌を披露したわけですが、この時彼女は七海に「私、歌うから。」と宣言していますよね。
© 四葉夕卜・小川亮・講談社/「パリピ孔明」製作委員会
この行動は七海を思ったものでありつつも、突き詰めると英子の「エゴ」なんです。
自分の歌で誰かを救うことができるなんて、思い上がりですし、そもそも誰かを救いたいなんて考えが傲慢さを孕んだものと言えます。
しかし、劉備玄徳がそうであったように、誰かを救うことができるのは、「誰かを救う」という思いが自分のエゴであると自覚しながらも、それが誰かのためになるのだと何の疑いもなく心から信じられる人だけなのではないでしょうか。
英子は『パリピ孔明』の序盤パートにおいて、「私の歌なんて…」が口癖で、自分の歌の力に何の自信も持っていませんでした。
それでも彼女は、あのスカイデッキのシーンで、確かに自分の歌に他者を救う力があるかもしれないと、心から信じられるようになったのです。
「たみくさを想うエゴイスト」としてのアーティストEIKOの覚醒を描く。
これこそが『パリピ孔明』が志向した英子の成長譚の核なのでしょう。
『六本木うどん屋(仮)』という謙遜にまみれた曲のタイトルが、全ての夢追い人を讃え、救わんと試みる『DREAMER』へと転じたように。