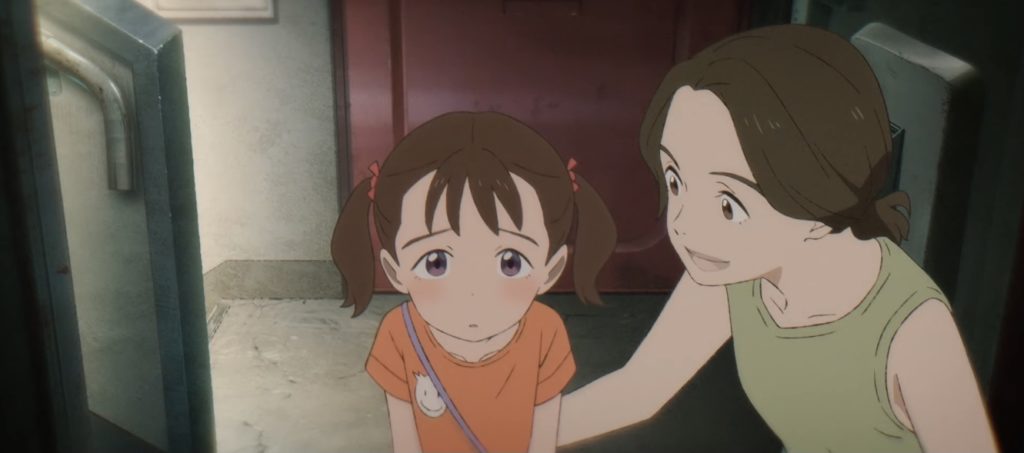『雨を告げる漂流団地』という作品を制作するにあたって、石田祐康監督は次のようなコメントを残した。
タイトルにしてしまうほど団地に思いを寄せた作品となりました。こういう類いのアニメ映画としては恐らく変わり者です。自分にとっても一つの挑戦となります。分かりやすく学校にするなどの意見もありました。苦しんで、悩んで、それでも信じるままに! 逆に皆で一緒になって知恵を絞りつつ!……団地を船出させることになりました。
(まんたんウェブ(2021年9月25日)より引用)
「子ども×漂流」は、古くは『十五少年漂流記』、日本では『漂流教室』、そして近年で言うと『Sonny Boy』など、多くの作品で用いられた普遍的な題材と言える。
そんな既に手垢のついているとも言える題材で、石田監督は2022年に新しい物語を作り出そうと試みたわけだ。
「漂流」を描いた作品において、学校という空間が用いられることは多く、『漂流教室』『学校の怪談』『Sonny Boy』などでは、学校とそこにいた生徒がセットで異空間、あるいは異時の空間へと飛ばされる。
とりわけこうした作品群に共通しているのは、学校という空間は舞台装置に過ぎず、あくまでも物語の主体は生徒であるという点だろう。
漂流ものの主眼は、子どもたちの成長やイニシエーション(通過儀礼)を描くことにある。そんな大人への過渡期にあるキャラクターを用意するにあたって学校という舞台が都合がよいわけだ。
一方で『雨を告げる漂流団地』は、子どもたちの成長を描きつつも、漂流の主体があくまでも団地という空間の側にあるように思わせるところがある。子どもたちが団地の漂流に巻き込まれたという体を取っているのだ。
なぜ、本作は団地という空間にこだわったのか、そして人間ではなく、空間(あるいは場)の漂流を描いたのか。
今回の記事では、この点に着目して、作品を掘り下げてみたいと思う。
『雨を告げる漂流団地』考察(ネタバレあり)
団地という空間を巡る言説
©コロリド・ツインエンジンパートナーズ
団地という空間は、これまでさまざまな日本のフィクションの舞台となってきた。
とりわけ団地を継続的に自分の作品の中に取り入れていた作家として、『リバーズエッジ』や『ジオラマボーイ パノラマガール』などで知られる岡崎京子さんが挙げられる。
彼女は自身のエッセイ「家の中には何かある」において次のように語っている。
家の中には何かある。家の中で起きてしまった惨事。それは人の目と気を引く。何故なら家の中にあるものは普通は愛や信頼や親密さであるはずだから。家の中で起こるドラマは本来はそういうやさしくあたたかいぬくもりのあるものでなければならないってわけ。ホーム・ドラマの筋立てを裏切るものは人の気もちを逆なでするってわけ。ホーム・ドラマの命題は人々を呪縛する。人々は家の中でドラマの役割を演じ続ける。ママはママの、パパはパパの、私は私の、妹は妹の、オトウトはオトウトの、犬のポチはポチの。ドラマにご奉仕する私達の生活。
(岡崎京子「家の中には何かある」より引用)
ここでいう「家」というのは、彼女の作品において頻繁に描かれた団地あるいは高層住宅などを含めた郊外の一般的な住宅地を指す。
『岡崎京子論 少女マンガ・都市・メディア』の著者としても知られる杉本 章吾氏は、この記述を引用しながら、当時の郊外の住宅地で起きた現象を次のように説明している。
「ホーム・ドラマ」の再演としての住宅地での家庭生活、あるいはイメージとしての「家族」を模倣する、シミュラークルとしての郊外の家庭生活。
(杉本 章吾「郊外化されたラブストーリー 岡崎京子『ジオラマボーイ・パノラマガール』論」より引用)
こうした記述から団地というものが、「ホーム・ドラマ」などの形でメディアで爆発的に拡散された理想の家族のイメージの受け皿として機能し、日本における核家族という家族形態の拡散に寄与したことが見て取れる。
また、石田祐康監督自身が本作を制作するにあたって影響を受けた作品として是枝裕和監督の『海よりもまだ深く』を挙げている。
同作に関するインタビューに応じた彼は、団地を舞台にした物語を作ったことについて次のように述べた。
そして、映画の主な舞台になる団地も、建設された当時とは、いろんな意味で違う着地にたどりつきつつある。そうした登場人物と団地の人生を重ねられたら面白いと思ったんです。
是枝監督は同作を制作するにあたり、脚本の最初の一行に「みんながなりたかった大人になれるわけじゃない」と綴ったそうだ。
今回取り上げた時代の異なる2つの団地への「まなざし」を合わせて考えてみよう。
団地が先ほど言及したように、メディアで拡散されたイメージとしての「家族」の受け皿としての役割を期待され、多大な貢献をしてきたと言える。
その一方で、徐々に家族、家庭生活、住宅の在り方が多様化したことにより、老朽化し、子どもが減り、高齢化も進んだことで、かつてのような役割や機能を担うことが難しくなっているわけだ。
こうした団地という空間が有するバックグラウンドやコンテクストを踏まえて、今作『雨を告げる漂流団地』について考えてみよう。
団地と人、せめぎ合う2つの引力
©コロリド・ツインエンジンパートナーズ
「漂流」ものにおいては、子どもたちの元の世界へと戻りたいという強い気持ちが物語の推進力となることが多い。記事の冒頭で挙げた作品群もそうであった。
ただ、帰りたいという思いが初期の登場人物の感情の大半を占める一方で、物語の中盤に差し掛かるにつれて、漂流世界に残りたいと考えるキャラクターが出てくる。
例えば『うる星やつら2 ビューティフルドリーマー』がそうであるし、記事の冒頭で紹介した『Sonny Boy』もそうである。
今作『雨を告げる漂流団地』では、兎内夏芽(以下、夏芽)という少女がその立ち位置のキャラクターとして描写されている。
彼女は、団地という空間に特別な思いを抱いている。といのも、自分の家族が壊れてしまったときに、団地にやって来て熊谷家に迎えられた夏芽はそこで初めて家族というものを知り、家族愛に触れたのだ。
そのため、彼女にとっての家族、あるいは親からの愛は、団地という空間と切っても切り離せないものとして存在してしまっている。
夏芽は、団地を失うことが、彼女にとっての家族、あるいは自分が触れた愛をを失うことと同義だと捉えており、それゆえに団地に固執する。
こうした人間の側が「漂流」先の世界に留まろうとする引力は、これまでの「漂流」ものでも描かれてきたものである。
その一方で、『雨を告げる漂流団地』が面白いのは、団地という空間そのものが、夏芽たち人間を引き留めようとする引力を無意識のうちに働かせている点ではないだろうか。
石田監督はあるインタビューにて、次のようにも発言している。
誰にでも、なかなか忘れられない思い出が詰まった場所ってあると思うんです。それに対する気持ちの折り合いがつかないことも、往々にしてあると思います。例えば、久しぶりに故郷へ戻ったら、お別れの合図も何もなくその場所やある建物がなくなっていたとか……。そんなことを考えながら、「もし団地側が、住んでくれていた少年少女から離れたくないと言ったらどうなるのだろう」と考えたんです。
ここで、監督も団地側が「住んでくれていた少年少女から離れたくない」という力を働かせていることを示唆している。
本作では、そんな団地側の意志や感情を可視化する存在として、のっぽくんという同年代の少年を登場させた。
彼は積極的に夏芽やその他の少年少女を団地に留めようと試みることはない。一方で、彼自身も意識しないところで、無意識のうちに彼らを引き留めようと試みる引力を働かせているのだ。
その原動力は、先ほど言及した団地の役割や機能に由来するものではないだろうか。
団地はかつて「人々の憧れや夢の象徴のような場所」だったのであり、メディアで拡散された理想の家族の受け皿としての役割を果たしていた。
時代が変わって、そうした役割を終えつつあるからこそ、団地は徐々に無くなったり、形を変えたりしているわけだが、この状況を団地の視点から見れば何とかしてこれからも自分たちの役割を全うしていきたいという感情になるのかもしれない。
のっぽくんは団地で暮らしてきたたくさんの家族を見届けてきたのであり、その幸せな家族の肖像を見つめることで満たされてきた。
だからこそ、これからも団地に住む幸せな家族を見続けていたい、そんな理想の受け皿であり続けたいと考えているのだ。
このように、『雨を告げる漂流団地』は劇中に2つの引力を忍ばせている。
役割を終えつつあることを悟りながらも、自身の役割を全うし続けたいと願う団地側の引力と、家族や愛が紐づいた団地という空間に固執する少女の引力と。
この2つの引力が同じ方向に働いてしまったことが、本作の漂流現象の原因とも言えるだろう。
ジュブナイルには別れが必要だ
©コロリド・ツインエンジンパートナーズ
本作の漂流現象を解決するために必要なのは、この2つの引力に折り合いをつけることだ。
団地は自らの役割を終えたことを認め、少年少女を解放しなければならないし、夏芽は団地が無くなっても、そこで過ごした家族の時間や愛が消えてしまうわけではないことに気づかなくてはならない。
彼らの物語に必要なのは、「バイバイ」である。
是枝監督が『海よりもまだ深く』の中で、団地に重ねたのは「みんながなりたかったものになれるわけじゃない」という思いだった。確かに理想や夢が現実になることなんてむしろ少ないのかもしれない。
私たちは生きていく中で、たくさんの「理想の残骸」や「夢のあと」を踏みしめて歩き続けなくてはならない。ときに「理想」や「夢」に別れを告げなければならないのだ。
でも、「理想」や「夢」に別れを告げることが、絶望に直結するわけでもなくて、その先にしかない希望や輝き、道はきっとあるはずだ。
是枝監督が『海よりもまだ深く』の結末で描こうとしたものについて、インタビューの中で次のように言及していた。
最初に団地の何を描こうと思ったかというと、子どもの頃、台風が過ぎ去った翌朝、学校へ行く時に見た芝生の光景なんです。
(中略)
だから、団地を舞台にしようとした時に、何ひとつうまくいってないし、何かが好転したわけじゃないんだけど、台風が来た翌朝の芝生はきれいだ、という話にしようと思いました。そこの感情に着地できればいいなと思っていましたね。(HOUYHNHNM「なりたかった大人になれなかったすべての人たちへ。『海よりもまだ深く』是枝裕和監督 Special Interview」より引用)
『雨を告げる漂流団地』が描こうとしたのも、まさしくここで言うところの「芝生のきらめき」ではないだろうか。
本作のラストには、大きな嵐と切ない「さよなら」が待ち受けている。それが夏芽たちの望んだものなのかと聞かれると、それは否かもしれない。
しかし、そんなほろ苦い別れの先にも「きらめき」は確かに存在している。
のっぽくんが辿り着いた漂流世界の終着点は、暗いものではなく、小さくも美しいきらめきに満たされている。
また、元の世界へと帰った夏芽たちがみた、雨が上がった団地の屋上からの景色は言葉にできないほどに美しい。
©コロリド・ツインエンジンパートナーズ
夏芽にとって、何かが解決したのかどうかは分からない。何かが好転したのかどうかも分からない。
彼女は「理想の残骸」あるいは「夢のあと」となった団地に別れを告げ、母親との生活へと帰っていく。それでも、その先で彼女はきっと彼女なりの「芝生のきらめき」を見つけられることだろう。
『雨を告げる漂流団地』が漂流世界の旅を通じて描いたのは、ほろ苦い別れとその先にある「きらめき」である。
少年少女は「バイバイ」を重ねて、少しずつ大人になっていくのだ。