この記事は一部作品のネタバレになるような内容を含みます。作品鑑賞後に読んでいただくことを推奨します。
目次
作品情報

映画『くれなずめ』感想
①バイバイって言いたい人に、バイバイを言えない僕らは。
②今を生きる私たちにとって、最もリアルな「死」を描く
③「つまらない結婚式の余興」で涙が止まらなくなるような
①バイバイって言いたい人に、バイバイを言えない僕らは。

松居大悟監督は、本作あるいはこの映画の原作に当たる舞台が制作されたきっかけについて、次のように語っている。
生きるとか死ぬとか、僕らなりの死生観を描きたくて。演劇仲間の友だちと突然会えなくなったことが大きな要素となりました。
(fan’s voice「【単独インタビュー】『くれなずめ』松居大悟監督」)
監督が「吉尾のモデルとなった人物に送る手紙のような映画」とも形容する『くれなずめ』という作品は、何とも人生のあるいは人の営みの無情さを感じさせる。
生きることは死に向かって前進することであり、死による別れというものからは逃れがたい。
もちろん、前もって死の訪れが分かっているのであれば、私たちはちゃんとバイバイを言うことができるだろうし、別れに対する心の準備ができるというものだろう。
しかし、得てして私たちはバイバイと言いたい人に、バイバイを言うことはできない。
それゆえに、私たちは、死したその人がまだどこかで生きているのではないかという感覚をぼんやりと抱きながら、生活を続けていく。
facebookに誕生日の通知が来ると、何事もなかったかのようにその人が1つ歳を重ねているのだろうと思わずにはいられない。
よく、死した人の魂が成仏できずにこの世界に留まり続けるなんてことが言われるが、死した人の魂を成仏させないのは、生きている私たちの方なのかもしれないとも思う。
『くれなずめ』は、そういう繊細な感覚を上手くすくい取っている。
というのも、これはバイバイを言えなかった人に、バイバイを言うための映画なのだ。
また会って酒を交わす日が来ることを信じて違わなかった、ありふれた一時の別れ。しかし、その別れは、吉尾がふわっと消えてしまったことにより、永遠のものとなってしまう。
あの日、あの時、言いたかったバイバイは、通夜に出て、棺の中に収められた彼の姿を見ても、もう届けることができない。言えなかったバイバイが、胸の奥に沈殿し、別れあるいは死という感覚を麻痺させ、ひどく曖昧なものにしていく。
『くれなずめ』はそんな状況に、フィクションならではの魔法で終止符を打つ。
バイバイを言いたかったあの日に、あの夜に、あの時間に、あの瞬間へ。
登場人物たちの抱え続けていたバイバイが溢れ出す瞬間には、ただただ涙が止まらない。
またどこかで会える日を望みながらも、それが永遠の別れになることを受け入れる、彼らの涙交じりの笑顔は本作のハイライトだ。
②今を生きる私たちにとって、最もリアルな「死」を描く

先ほども述べたように本作『くれなずめ』は親友の「死」を巡る物語である。
世の中に「死」を巡る物語は、数えきれないほどある。それくらい「死」というのは、言ってしまえばありふれた題材なのだ。
そんな中で、本作の「死」は妙に肉感があるというか、リアルな手触りがある。
「死」の瞬間を生々しく描いているだとか、そういうことではない。
ただ、スクリーンの向こう側にある「死」がどうも他人事に思えないのだ。そしてその感触というか手触りは作品を見進めるほどに増していく。
沖田修一監督の『横道世之介』を見ていた時に、おおよそこれに似たような感触を感じたような気がする。
今まさに自分自身のテリトリーで「死」が起きるのだとしたら、きっとこんな感じなのだろうとイメージさせてしまう不思議な力があるのだ。
劇中で前田敦子演じるミキエの発言がその感触を上手く言語化してくれていた気がする。
てか、アカウント消して欲しいんだけど。FacebookとかTwitter。こっちからは何となく外せないのよ。電話帳だって消せないし。今日は吉尾の誕生日ですって、忘れかけたころに毎年出てきて、もう「いいね」も押せないから、「んーっ」ってなんの!
どんなに描写が緻密な「死」も、どんなに劇的な「死」も、どんなに悲劇的な「死」も、きっと今を生きる私たちはそれが自分の身に起こる、あるいは自分の周囲の人に起こるなどとイメージすることは難しいのだと思う。
しかし、今作のミキエの発言が言い表す、吉尾の「死」は何だかすごくイメージができてしまう。物語の中の「死」が自分事のように思えてくる。
そうなのだ。きっと「死」というのは、その人について思いを馳せるときに直面するものなのだ。きっとそうなのだ。
いなくなったその人の痕跡や匂いは、この世界の至るところに残存し続ける。そして、ふとした瞬間(例えば、お菓子を手を滑らせて地面に落としてしまった瞬間のような)に、それに触れてしまう。
その度に、その人のことを思い出し、そして、その人がもういないことを思い知る。
この繰り返しが生者にとってのリアルな「死」の感覚なのではないかと、そう思わされた。
③「つまらない結婚式の余興」で涙が止まらなくなるような

最後に本作の構成面の良さについて語っておきたい。
とは言え、『くれなずめ』の構成は、かなり賛否が分かれると思うし、人によってはまったくハマらないというか、面白く感じない危うさも孕んでいる。
一言でいえば、良くも悪くも作為性を感じさせないのである。
本作は結婚式と二次会の間の数時間に焦点を当てた作品だが、ダラダラと何も起きない一種のモラトリアムと登場人物たちの何気ない一幕の回想を交互に展開していく。
物語の比較的序盤に吉尾が死んでいるということが分かるため、観客の興味は当然、その死の背景や理由の方へと引き寄せられるのだが、本作の構成は、そうした観客の興味に一切応える作りになっていない。
登場人物たちのダラダラとした何も起きない時間は続いていくし、時折インサートされる回想もそうした観客の興味に応えるものではない。
ゆえに、物語の推進力が恐ろしく弱いし、停滞感が強く、この映画への興味を保てなくなる観客が出てくるのも無理はない。
各レビューサイトで、本作がそれほど高く評価されていないのも納得できる。
しかし、私は『くれなずめ』があえてこうした構成にした意味が理解できるし、むしろそこを高く評価したい。
登場人物たちの回想が、吉尾の死を暴くという作り手や観客の都合に縛られていないのが、本作の独特の空気感につながっているのである。
彼らは何気ない瞬間をトリガーにして、吉尾との些細な思い出を回想する。そのどれもが本当に何でもないものばかりだ。
でも、私たちが誰かについて、あるいは何かについて思い出すときに浮かんでくるのは、こういう何でもない瞬間ばかりなんじゃないかと思う。
当時は何とも思っていなかったようなことが、思い出になってみて、初めて価値を持つなんてことはしばしばあるものだ。
『くれなずめ』は、数ある思い出の中から無作為に抽出した1つを取り上げているかのように、作為性を感じさせない構成になっている。
それが、この映画が作られた物語であるということを忘れさせ、登場人物たちの独特の「空気」の中に観客を巻き込んでいく。いつの間にか、登場人物たちの隣に自分も立っているような気がしてくる。
すると、その「つまらない結婚式の余興」のような時間が突然、愛おしく思えてくるのだ。
それが無性に面白くて、笑えて、そして泣けてくる。
本作が素晴らしいのは、作為性を排除することにより、この「空気」を作り出したことだと思う。
『くれなずめ』は友だちと過ごす時間のような映画だ。
爆発的に面白いとか、劇的だとかじゃない。居心地がよくて、ホッとするんだ。



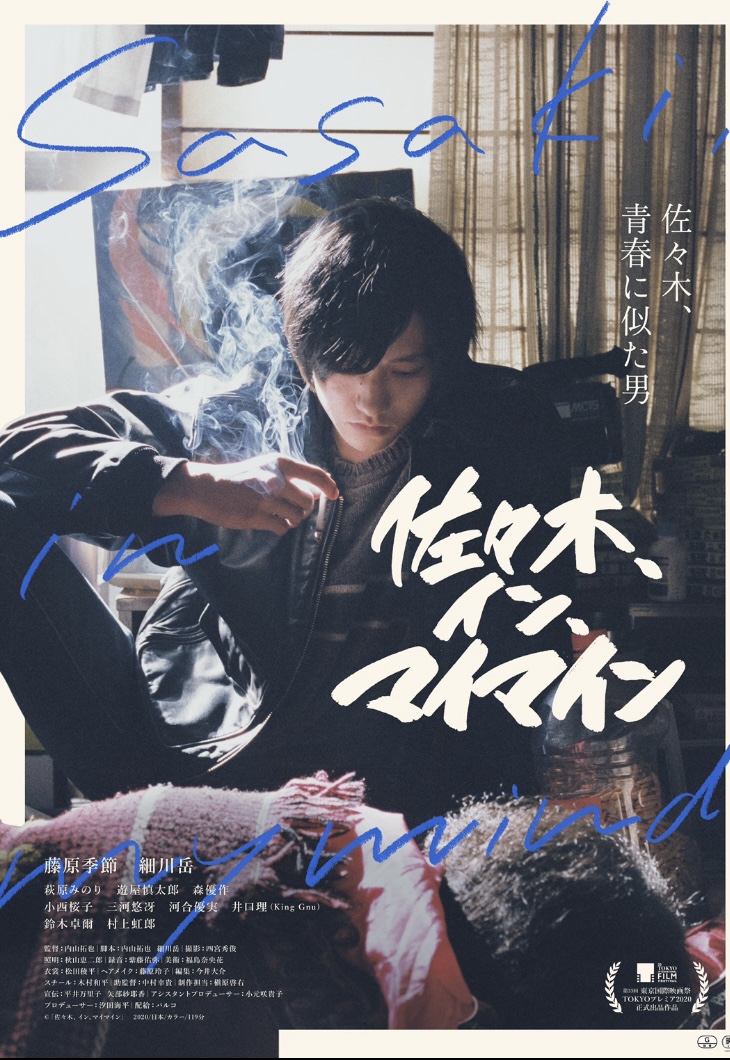











<キャスト>