本記事は一部、作品のネタバレになるような内容を含みますので、鑑賞後に読んでいただくことを推奨します。
作品情報

映画『窓ぎわのトットちゃん』感想と考察

第2次世界大戦前後の日本を舞台にした近年のアニメ作品と言えば、片渕監督の『この世界の片隅に』が真っ先に話題に挙がるだろうか。
今作『窓ぎわのトットちゃん』はそれに匹敵する傑作であるとまずは断言したい。
近年、テレビアニメ、アニメ映画の数はどんどんと増えてきている。
ただ、物語が面白い作品は山ほどあるが、アニメーションそのものを楽しめる作品に出会う機会はそう多くない。
『窓ぎわのトットちゃん』は、そんな中で、純粋にアニメーションとして楽しませてくれる映像作品に仕上がっていたように思う。
例えば、冒頭のトットちゃんが初めてトモエ学園を訪れたシーンで、彼女は校庭に電車が設置されていることに気づき、猛然と走り出す。
その時に、彼女は砂場を通過するのだが、それを追いかける彼女のママの動き1つにも注目して欲しい。
彼女は、砂場に足を取られたために、ヒールを脱いで、ヒールの中に入りこんだ砂を外に出すのである。
何気ないほんの数秒のカットだが、このようなちょっとした観客の予想を裏切る動きのカットが作品の中の至るところに散りばめられている。
私たちは劇中のキャラクターがどのように動くか、どのように行動するかをある程度予測し、無意識のうちに軌道を描きながら見ている。ゆえに、その軌道に沿って登場人物が動くと、描写がすんなりと入ってきやすい。
しかし、自分の想定した軌道の範疇でしか動かないキャラクターというのも味気ない。
アニメーションを見る面白さのひとつは、クリエイターの想像力が観客の思い描く軌道を超えたり、裏切ったりする瞬間にあると思っている。
他にも今作の映画のアニメーションとしての面白さはたくさんある。
トットちゃんの空想世界は、クレヨンで描いたような温かみのある柔らかいタッチで描写されたり、逆に終盤にはケルト・アニメを思わせるような少し不気味さを帯びたタッチで描写されたりしていたが、これも面白い。
エンドロールを見るに、それぞれの空想のシーンに、個別の制作チームが存在していたようで、実に面白い試みだったように思う。
他にも、戦争が始まり、豊かさや色が失われた町の中でトットちゃんと泰明ちゃんが歌を歌うシーンでは、ミュージカル的な演出が炸裂していた。
本来は存在しない色で世界を彩り、建物や看板などが音に合わせて跳ねるように変形していく。まさにアニメーションにしかつけない「嘘」である。
見ていて楽しいと何度も感じさせてくれた時点で、本作はアニメーション作品として既に成功していると言っても過言ではないだろう。
その上で、『窓ぎわのトットちゃん』が素晴らしかったのは、トットちゃんという1人の少女が成長していく過程に、日本が戦争へと向かっていく過程を重ねたことだ。
今作は、トットちゃんの成長を言葉で説明したりはしない。映像でもって彼女の見える世界の広がりという形で語らんと試みていた。
職員室で校長先生に叱責される女性の先生、いつも改札口に立っていたのに突然いなくなった男性の駅員、泰明ちゃんの葬儀の場から学校へと向かう途中の家で遺骨を抱えて泣いている女性。
見えなかったものが少しずつ見えていく。気づかなかったことに気づいていく。そうやって見える世界が広がっていくことがそのまま彼女の成長だったのである。
しかし、見える世界が広がれば広がるほど、自由になるのではないかと思うものだが、逆に視界が広がるほどに世界が窮屈で不自由に思えてくるというのは、なんと残酷なことだろうか。
彼女が成長し、大人に近づけば近づくほどに、日本の戦争は激化していき、どんどんと暮らしは貧しくなり、町は活気や色を失っていく。
まるで、「大人になる」ということは、子どもの頃は確かに持っていた無限の想像力や豊かな感性を失うことだと言わんばかりの残酷さである。
そう、『窓ぎわのトットちゃん』は「大人になる」ということについて描いた作品でもあると私は思うのだ。
物語の冒頭では、窓から身を乗り出してちんどん屋に大声で呼びかけていたトットちゃんは、物語のラストには、身を乗り出そうとするのを抑え、自分の弟を抱えて「ちんどん屋さん…」とボソッとつぶやくのみになっている。
この変化に私たちはトットちゃんが大人になったと感じるのだが、その成長にはどこか寂しさと申し訳なさのような感情を抱かずにはいられない。
今作は、子どもたちに対する戦争と大人の責任を浮かび上がらせている。

それらはいずれも子どもたちに「いい子」であることを強いるものだった。
戦争は子どもたちに貧しい生活を強い、町で楽しく歌を歌うことすら卑しい行為だとして断罪した。大人は学校で型にはまらず、集団の中で輪を乱す子どもを嫌い、矯正を試みた。
大人が決めた「いい子」を、国が決めた「いい子」を子どもに押しつけ、大人になることを促すことが教育だったのだ。
しかし、それは無限の想像力や好奇心、豊かな感性を奪うものだ。
本作の終盤に、校長先生がトットちゃんに「君は本当に『いい子』だねえ。」と告げるシーンがあるのだが、このときの校長先生はトットちゃんに対して、罪悪感を抱いているようなニュアンスが感じ取れる。
これは、戦時中に大人や国が求める「いい子」にならざるを得なかったトットちゃんに対しての、1人の大人として、あるいは教育者としての罪悪感なのではないかと思う。
一方で、本作には確かに希望は描かれていた。
それは、泰明ちゃんの葬儀のシーンである。

戦争に突入し、町が色を失っていく中で、泰明ちゃんの葬儀が行われた教会はステンドグラスや飾られた花々によって、実にカラフルな色彩感覚で描写されている。
ゆえに、彼との別れ、あるいはあの色とりどりの教会を後にすることが、トットちゃんにとっての子ども時代の終わりとして演出されているように感じられた。
それでも、トットちゃんが教会を後にするときに振り返って告げた言葉を思い出して欲しい。
「わたしも忘れない。」
この言葉には、大人になってしまったとしても、いつかまた泰明ちゃんと過ごした色とりどりの豊かで自由な世界へと戻ってくるんだというトットちゃんの覚悟を感じられた。
話は変わるが、本作公開を記念したイベントの中で、次のような一幕があったそうだ。
妹は「お母さんから徹子さんは『頭に飴が入ってる』って聞いたんですけど、今も入っているんですか」と直撃。無言のまま、おもむろに頭をいじりはじめた黒柳をみて「え…あるの?」と動揺。黒柳が取り出した飴を手わたされると「うれしいです」と笑顔がこぼれた。
(オリコンニュースより)
こういうエピソードを聞くと、黒柳徹子さんは今でも、子どもの頃に一度は別れを告げたあの世界と今でもつながっているんだろうなと思わずにはいられない。
大人が見るのと、子どもが見るのでは、全く受け取り方が違う作品なのだが、だからこそ世代を超えて、この物語は普遍的に愛されてきたのだと思う。
そして、令和の世になった今でも少しも色褪せてなどいないのだ。






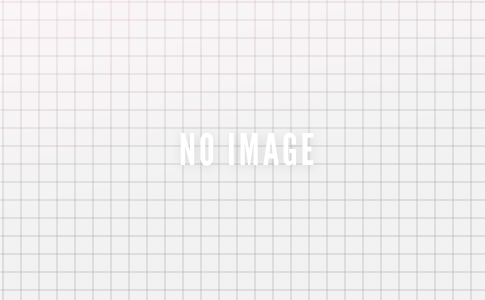







<スタッフ>
<キャスト>