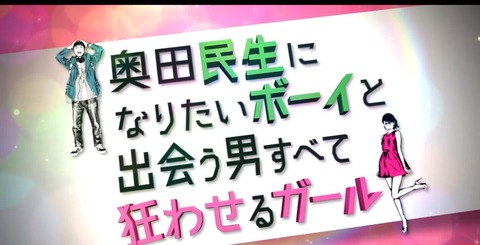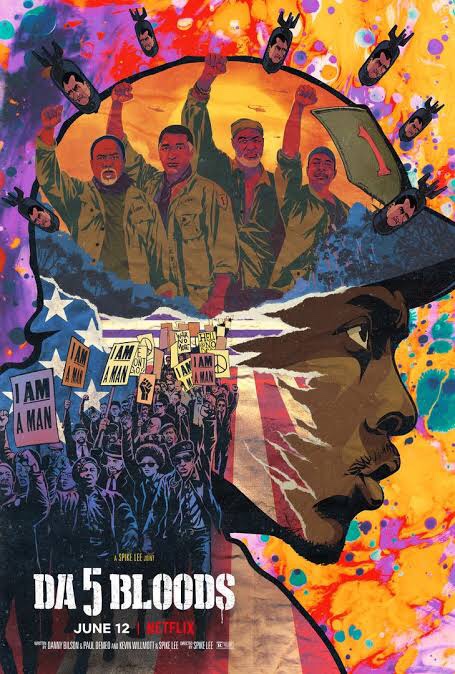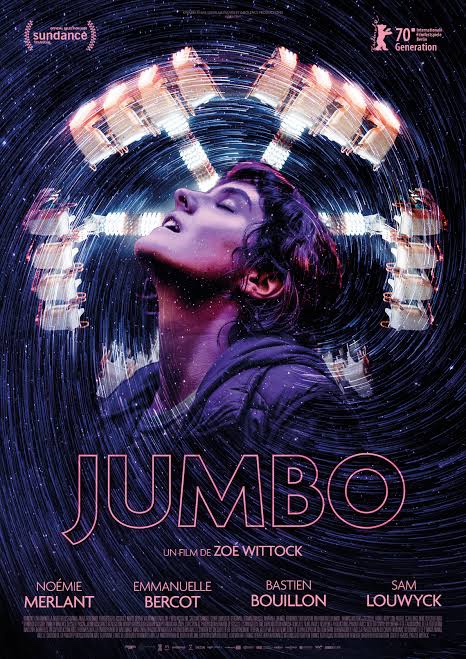わたしたちは「光」に手を伸ばす生き物だ。
しかし、「光」というものは手に入れたと思ったその瞬間から、その手から溢れ、こぼれ落ちていく。
感じたはずの温もりもその温度が失われていく。
わたしたちはその瞬間の寂寥を知りながらも、なぜ手を伸ばさずにはいられないのだろうか?
映画『余命10年』が描いた高林茉莉(以下、茉莉)と真部和人(以下、和人)の物語もそんな「光」を巡る映像作品だったと言える。
映像作品を作る上で光は、光源をどこに配置するか、どんな色温度にするか、何をフィルターにするかといった技術的な側面でも重要なものだ。
邦画を追いかけている人であれば、名前を知らない人はいないであろう撮影監督の今村圭佑さんと照明監督の平山達弥さんのタッグは、今作でも圧巻の映像を作り上げてくれた。
一方で、今作においては「光」そのものが物語上、重要な役割をもって映像の中に配置されていることが多い。
この記事では、「あなたとわたしの間」という空間に注目して、劇中の「光」の主題系を紐解いていきたいと思う。
『余命10年』考察(ネタバレあり)
積み重ねていく「光」の主題系
映画『余命10年』は、「肺動脈性肺高血圧症」という難病を患う茉莉と人生に行き詰まった和人が心を通わせていく過程にスポットを当てた物語だ。
そのため、映像の中に2人が同時に収められているカットは当然多いわけだが、今作が大切にしているのは、2人の間に生じる空間に何を描くかだったのではないかと思う。
茉莉と和人の関係性が大きく変わり始めたあの夜。桜が幻想的に咲き誇っていたあの美しい夜。2人の関係性の変化がもたらす未来を暗示する象徴的なカットがあった。
風が強く吹いて、桜の花びらが宙を舞う。
その瞬間、世界はスローモーションのように短い時間をそれが永遠に続くかのようにゆっくりと刻む。
そして、茉莉と和人は見つめ合う。
©2022映画「余命10年」製作委員会
このとき、2人の間に何が映し出されているかに注目してほしい。
街灯、つまり「光」なのである。
このカットは、茉莉と和人が関わることで、その先の未来に「光」が待っていることを視覚的に暗示する役割を果たしている。
そして、この構図は「光」がその形を変えながら、作品の中で何度も反芻される。
和人の自宅で友人たちと鍋を囲んだ夜のキッチンでの一幕。和人が茉莉に自分の思いを伝えようとするが、このとき2人の間にはキッチンの白色照明が配置されている。
©2022映画「余命10年」製作委員会
冒頭のシーンよりも照明の色温度が高くなり、暖色系から白色系に変化することで、少し冷たい印象を与えるように演出されているのも特筆すべき点だろうか。その冷たさには、茉莉のためらいが投影されている。
ここまでは「光」を単に街灯や電灯といった光源のモチーフとして捉えてきたが、「光」とは2人にとっての未来であるとも言い換えられるわけだから、必ずしも直接的である必要はない。
茉莉と和人の関係は一度壊れてしまうが、自暴自棄になった彼女のところに和人が駆けつける夜のシーンで、その関係は以前よりも強く結び直されることとなる。
このときの2人の間に描かれていたものは何だったかと思い見てみると、線路であった。
線路は運命性を強調する残酷なモチーフという側面もあるが、ここでの2人にとっては未来へと続く道という意味合いが強いのではないだろうか。
行き場のない街の中で2人の間に、2人が関係を結び直した先に、新しい道が生まれるという未来を暗示している。これも「光」のひとつの形に思えた。
淡くなり、失われる「光」
「光」はさらにその形を変えていく。
ベランダから見える朝日。線香花火。ケーキ用の花火ろうそく。
©2022映画「余命10年」製作委員会
どれも「光」ではあるのだが、そのモチーフが徐々に刹那性を帯びていくところに、2人の関係性の行く末が仄めかされているようで胸を締めつけられる。
少しずつ「光」が淡く、弱く、脆くなっていくのである。
それを決定的づけたのが茉莉と和人がスキー場に旅行に行った夜のシーンだ。
2人はコテージのベッドで肌を重ねるのだが、このシーンにおける「光」の演出は天才的という他ない。
このシーンは間接照明を背後にした茉莉と和人をクローズアップショットで捉えている。そのため、照明の手前にいる2人の姿はもはや影のようになっているのだ。
©2022映画「余命10年」製作委員会
少しずつ2人の影が近づいていく。すると、背後にある間接照明、つまり「光」を2人の影が覆い隠してしまう。
©2022映画「余命10年」製作委員会
これまでのシーンでは、茉莉と和人の間には常に「光=未来」が存在していた。
しかし、このシーンでは、近づけば近づくほどに、彼らの間にあった「光=未来」が失われていくというジレンマを生じさせている。
だからこそ、このシーンは見ているだけで苦しい。この夜が2人にとっての「終わり」なのだろうという空気をひしひしと感じさせるからだ。
計算されているのかどうかは不明だが、それに続く夜明けのカットにおける「光」も実に示唆的に用いられている。
©2022映画「余命10年」製作委員会
2人の間には、今にも消えてしまいそうな仄かなコテージの灯が配置されているのだが、シークエンスの中で少しずつカメラの方向を変えることで、その灯を和人の背後に隠してしまう。
©2022映画「余命10年」製作委員会
その瞬間、茉莉と和人の間に確かに存在していた「光」が完全に失われ、2人が歩む「未来」が閉ざされてしまったことを強烈に印象づけられる。
光源が映像から失われたことに伴う視覚的な冷たさと寂しさが、見事にそれを演出している。
「光」に手を伸ばすこと、生きること
物語の前半には「光」を手に掴んだときの温もりや喜びを描いていた。
そして、後半にかけては、それが手から零れ落ちていくときの寂しさや空虚さを描いてきた。
そのコントラストが視覚的に演出されているからこそ、見る者の心に訴えかけるものがあるのだ。
その上で、『余命10年』は茉莉は、あるいは和人はそれでも「光」に手を伸ばすのか?という問いに対するアンサーを物語のクライマックスに描こうと試みていたように思う。
病室で目を閉じる茉莉。彼女の頭の中に広がる光景のすべてに和人がいて、2人の間にはいつだって「光」が描かれている。
やがてその「光」は形を変え、2人のかけがえのない子どもになる。子どもは言うまでもなく「未来」の象徴だ。
©2022映画「余命10年」製作委員会
その「光」や「未来」は手をどんなに伸ばしてももう手に入らないものなのかもしれない。
あるいは手にした瞬間にさらさらとその手から零れ落ちていくものなのかもしれない。
それでも。それでも、その「光」に手を伸ばすことが、伸ばし続けることが「生きる」ということなのではないかと、強く思わせてくれる。信じさせてくれる。
自転車を必死に走らせて病院を目指す和人の前には太陽が、「光」がある。
©2022映画「余命10年」製作委員会
そして、頭の中に広がる光景が内包する「光」を掴みたいと願う茉莉は懸命に生きようとしている。
一度は諦めた2人が、また「光」を追い求め、手を伸ばすところで物語は幕を閉じる。
どうしても人の死というのものは弱さを感じさせるが、『余命10年』における茉莉の死はそうした弱さを感じさせない。
今敏監督の『千年女優』で描かれた藤原千代子のように、まだ何かを手に入れたいと、どこかに辿り着きたいと渇望する者の力強い「旅立ち」として描かれていたように思う。
そして、その力強さに、私は冒頭に投げかけた問いに対する答えを見たような気がした。
頬につたふ
なみだのごはず
一握の砂を示しし人を忘れず
(石川啄木『一握の砂』より)
手にした「光」は零れ落ちれど、それを掴んだという感触は手に残って消えない。
そんな消えない何かを私たちは追い求めているのだ。
和人を演じた坂口健太郎さんが、インタビューの中でラストシーンについてこう語っている。
今まで茉莉が生き抜いた証明を和人の顔でしなきゃいけない。
この言葉を聞いて、ラストシーンの和人の表情がそんな「消えない何か」を体現していたことに改めて気づかされる。
「間違ってなかったよね。これで良かったよね。」
その問いかけに応えるのに言葉はいらない。