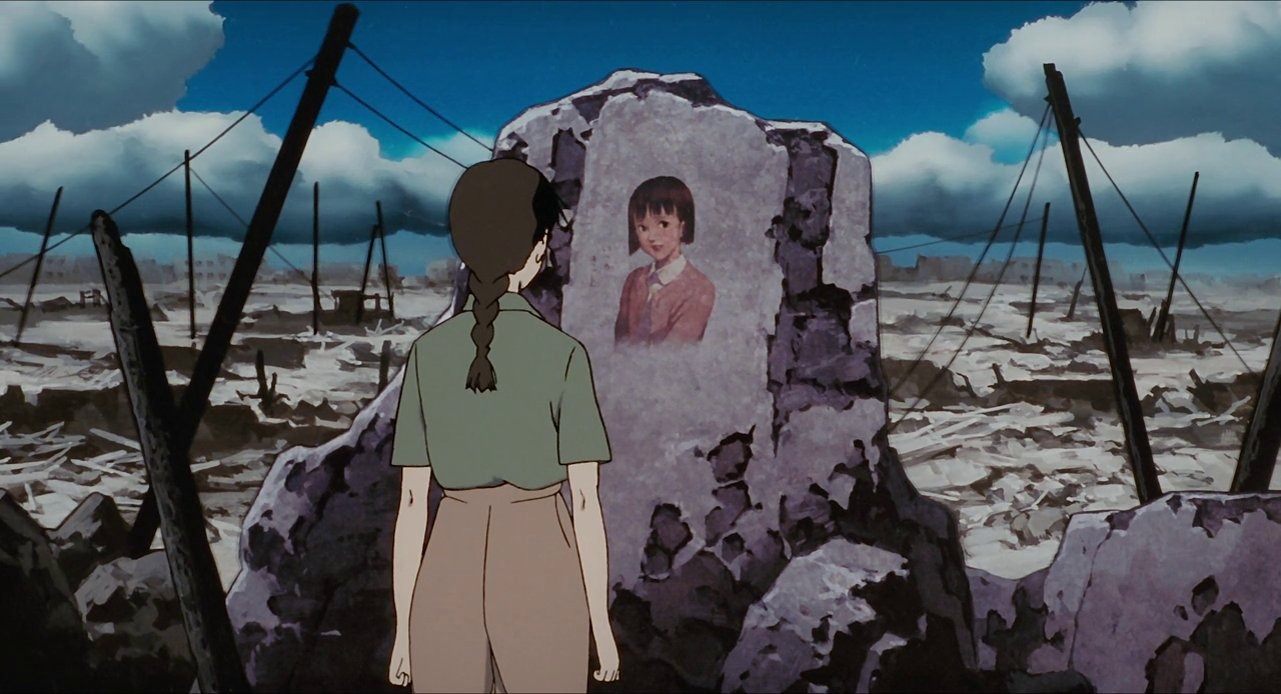安藤サクラ演じる、本作の主要キャラクターの1人である早織が、職員室の一幕でこう告げた。
©2023「怪物」製作委員会
「わたしが話してるのは人間?」
それは、自分の息子である湊が学校でいじめを受けているのではないかという懸念を伝えたことに対し、何も対応しようとしない死んだ目をした教員たちに向けられたものだった。
映画を見ていた私たち観客もまた、あの瞬間、早織と同じ感覚を確かに共有していたのではないか。
いじめという重大な問題が起きているにも関わらず、積極的に介入しようとせず、事なかれ主義で済ませようとする発言や態度、そして何よりその死んだ目を見て、彼らが「機械」あるいは「怪物」のようであると思ってしまうのは自然なことなのだろう。
そして、新聞や週刊誌に掲載された一連の顛末に関する記事は、永山瑛太演じる教師の保利や学校そのものに「怪物」というレッテルを貼りつける決定的な免罪符となり得る。
©2023「怪物」製作委員会
ここまでで1つの物語として完結していると言えばしているのだが、『怪物』という作品は、3つの視点から成る『羅生門』的な3幕構成になっており、ここまでの出来事をさらに2人の人物の視点から再構築していく。
すると、不思議なことに、今度は安藤サクラ演じる早織が「怪物」に見えたり、彼女の息子である湊が「怪物」に見えたりする。
その結果として、私たちはあることにハタと気づかされる。
この映画の中に「怪物」は初めからいない。誰もが血の通った「人間」なのだ。
それぞれの視点から切り取られた物語だけで考えるならば、そこに「怪物」は確かに存在する。しかし、3つの視点を束にすると、全員が「人間」に見える。
これこそが『怪物』という作品の面白さの根幹なのではないかと思うのだ。
視点を変えて1つの出来事を捉えなおしていく手法はミステリ的であり、それゆえに伏線の回収や謎の解明にどうしても観客の興味や関心が集まりがちである。
現に今作のレビューを見ていても「伏線の回収がすごい!」といった意見は散見されるし、本作にその側面からの面白さがあるのは事実だ。
「謎解き」的な要素を物語を進めていくための推進力として間借り的に利用していたし、点と点が結びついていくある種のアハ体験が観客の視線をスクリーンから逸らさせないために一役買っていた。
しかし、そこが本質ではなかったことに本作の素晴らしさがある。
『怪物』は、3つの視点から成る3幕構成があくまでも「手段」であり、「目的」ではないということをはっきりと示していた。
それは、3幕構成の最後に何かが解決したり、謎の全貌が解き明かされるわけではないことからも明らかである。そこが、この作品のゴールではない。
是枝監督は、自身の作品で、あまり明示的な答えのようなものを提示しない傾向がある。それは『海よりもまだ深く』でもそうだったし、『万引き家族』でもそうだった。そして、今作でもそうだ。
ただ、坂元裕二脚本がもたらした3つの視点から成る3幕構成というトリッキーな語り口ゆえに、いつも通りの観客に答えを委ねる幕切れに「描写不足」「説明不足」という印象を与えているのかもしれない。
それでも、是枝監督がやりたかったことは変わっていないのだと思う。
今作がしたのは、あくまでも3つの視点を提示すること、ただそれだけであり、この物語の輪郭を最終的に描いていくのは、それを受け取った観客一人ひとりだ。
映画館を出て、今作を一緒に見に行った人と、近くの喫茶店でアイスコーヒーを飲みながら、作品について少しの間、語り合った。
話題の中心は、やはり3幕構成の面白さや、物語の謎めいた部分が徐々に明らかになっていくストーリーテリングにあった。
3幕構成によって、劇中の何気ない登場人物たちのセリフやテレビ番組などが孕む無意識の加害性が暴き出されていく様についての議論には特に熱が入ったものだ。
しかし、少し多めに入れられた氷が溶けだして、コーヒーが薄まった頃、「何かあのラストシーンすごく良かったよね。」という素朴で何気ない一言をきっかけにして、話題の中心はラストシーンの映像の持つ力強さへと移っていった。
©2023「怪物」製作委員会
子どもたちの純真さ、無邪気さ、力強さ。
陽光に包まれたどこまでも自由で広大な風景。
この映画を包み込む停滞感や閉塞感を突き破るような躍動感。
それまでの何もかもが吹き飛んでいくような感覚があったし、「このシーンを見せたかったんだな…。」と納得させられた気がした。
1か月後、半年後、1年後、5年後、10年後…。
長い時間を経て、私たちがある一つの映画について思い返すとき、一体どれだけのことを覚えていられるだろうか、思い出すことができるだろうか。
そう考えたときに、きっと3幕構成の細かなディテールの中身はほとんど覚えていないだろうなと思った。
同時に、目に強烈に焼きついたあの美しい光景だけは、子どもたちが駆け出していく力強さだけは真っ先に思い出すんだろうなとも思った。
そんな瞬間との出会いこそが視覚志向の芸術媒体としての「映画」の醍醐味だ。
脚本的な面白さが前面に押し出されてもおかしくない作品でありながら、ラストシーンの短い映像がそれらよりもずっと力強いことに、『怪物』の映画としての矜持を感じる。
複雑ですぐには言語化できないことが、この映画にはたくさん描かれている。
だからこそ「何かあのラストシーンすごく良かったよね。」という素朴で純粋な思いを大切にしたいし、みなさんにも大切にして欲しいと思う。
きっとあの光景は、この作品に、あるいはそこに描かれたさまざまなことに再び思いを馳せるための「栞」のような役割を果たしてくれるだろう。