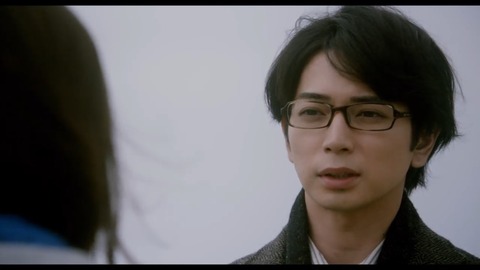本記事は一部、作品のネタバレになるような内容を含みますので、鑑賞後に読んでいただくことを推奨します。
作品情報

- 監督:濱口竜介
- 脚本:濱口竜介
- 企画:濱口竜介/石橋英子
- プロデューサー:高田聡
- エグゼクティブプロデューサー:原田将/徳山勝巳
- 撮影:北川喜雄
- 編集:濱口竜介 山崎梓
- 音楽:石橋英子
『悪は存在しない』をめぐる3つの視点と考察
①対話と分かり合えなさ
②被虐のバランス
③因果とシステム~水は高い方から低い方へ流れる~
①対話と分かり合えなさ

本作のあらすじに目を通すとこんなことが書いてある。
自然豊かな高原に位置する長野県水挽町は、東京からも近いため近年移住者が増加傾向にあり、ごく緩やかに発展している。代々その地に暮らす巧は、娘の花とともに自然のサイクルに合わせた慎ましい生活を送っているが、ある時、家の近くでグランピング場の設営計画が持ち上がる。
なるほど、これは住民とグランピング場の計画を持ち込んだ企業の争いあるいはそこからの融和を描く物語になるのだろうと何となく想像がつく。
しかし、『悪は存在しない』は、そんな誰しもが想像する物語のレールには全く乗る気がない。
対話を尽くすなどという次元には達することなく、言葉と感情はただただ空疎にすれ違いを続ける。その連続を淡々と見せる。
特に主人公の巧と芸能事務所の高橋のすれ違いは面白い。
巧が「タバコは吸われますか?」と尋ねると、高橋はライターを差し出す。しかし、巧が求めていたのは、タバコそのものだったという些細なやり取りがあった。
これに似た小さな言葉のすれ違い、感情のズレが作品の中で幾度となく描かれる。
住民説明会の中で女性が「都会の人はここにストレスを投げ捨てに来る」と発言していたにもかかわらず薪割りが気持ちよかったと巧に言ってしまう。
あるいは、同じく住民説明会の中で女性が「水にこだわって作っている」と述べたそばを食べて、温度についての感想のみを述べてしまう。
もちろん高橋には何の悪意はないし、むしろ自分は相手に喜んでもらえる、あるいは自分は相手に対して歩み寄っているんだという意識の下で発言しているのだろう。
しかし、それを受け取る側がその言葉をどのように受け取り、ラベリングするかは分からない。彼の無神経な正義は、受け手にとっては悪意になる可能性がある。
では、劇中に登場したコンサル会社の社長の発言はどうだろうか、あるいは芸能事務所の社長の発言はどうだろうか。
レビューサイトで、彼らの言動は疑いようのない「絶対悪」だと言っている人を見かけたが、それは一面的な見方に過ぎないと思う。
社長には従業員のために会社の収入を作らないといけないという責任があるし、その正義感から無謀にも思えるグランピング場の計画に乗ることを決めたのかもしれない。
コンサル会社の人間にとっては、クライアントに利益を出させることが正義である。であれば、住民に不都合になるとしても、利益を最大化できるようにアドバイスをすることは、決して悪意からではない。
このように、私たちは自分たちの言動が相手にどのように受け取られるかに対して無自覚なことが多いし、特にそれが純粋な善意や正義感に裏打ちされていればいるほど、相手に悪意として受け取られる可能性に鈍感になってしまう。
例えば、あなたがある人に対してスキンケア用品をプレゼントするとする。心からの善意だし、喜んでもらいたいと思っている行為だ。そこに何の嘘偽りもないだろう。
しかし、相手がそのスキンケア用品を見て、暗に自分の肌が汚いと言われていると感じ、プレゼントを悪意を持ったものとして受け取る可能性はないだろうか。
では、劇中の別の例で考えてみよう。
猟師が猟銃で鹿を撃つとする。この行為を撃たれる鹿の視点から見たら、それは正義だろうか悪だろうか?
きっと、悪だと答える人が多いだろうと思う。
一方で、次の場合はどうか。
小さな女の子は傷ついた鹿に対して、何とかしてあげたいと思い、自分の被っていたニット帽子を差し出そうとしている。この行為を鹿の視点から見たら、それは正義だろうか悪だろうか?
その答えは映画のクライマックスで描かれている。
そして、これこそが『悪は存在しない』が描かんとした対話不可能性なのだ。
対話でもって分かり合えるなどという甘い幻想は、この映画のどこを探しても見当たらない。それでも、本作は対話不可能性に対する1つのアンサーを提示している。
それは「バランス」である。
②被虐のバランス

『悪は存在しない』は、対話不可能性を観客につきつけつつも、人と人、人と動物、人と自然の共生の可能性を完全に否定しているわけではない。
現に、水挽町は、グランピング場の建設の話が持ち上がるまでは大きな問題はなく、住民たちの生活が続いていたわけで、そこには共生が成立していたという見方ができる。
それを支えていたのが、住民説明会での巧のセリフの中にもあった「バランス」だ。
コンサル会社の社員がオンラインミーティングの中で「ガス抜き」という言葉を使ったが、これもある種「バランス」に関わっている。
住民は、芸能事務所からグランピング場の話を一方的に持ちかけられ、自分たちの生活にとってメリットになることもありつつも、デメリットも押しつけられる形となっている。
だからこそ、住民たちも芸能事務所の懐事情や社員の生活などは一切顧みることなく、自分たちの意見や要望を一方的に押しつける。
水挽町と芸能事務所は全く異なるように見えて、同種の構造をしている。
それは、住民への説明を2人の社員に任せて自分は表に出てこない芸能事務所の社長と、芸能事務所への対応を町民の巧に任せて、自分は身を引こうとする区長の男性を重ねることによって、明確に示唆されていると言える。
そんな2つの共同体ないしその構成員が完全に分かり合えるなんてのは幻想である。コンサル会社の社員はその点をシビアに理解しているのだと思う。
共生において、大切なのは、「ガス抜き」であり、双方が得るメリットと背負うデメリットの「バランス」である。
相手も自分もメリットを享受するというのは大前提でありつつ、それ以上に相手と自分が背負うデメリットが釣り合っているのかというのも大切な視点だ。
相手にネガティブなことを押しつけられたとしても、相手が自分と同じだけのデメリットを背負っていると分かれば、それを抱えたままで共生することができる。分かり合って、それを乗り越えるというプロセスを踏まなくとも可能なのである。
そして、人間と自然の関係にも同種のバランスが存在する。
水挽町の住民は、生活を続けるために、湧水をくみ取り、陸ワサビを摘み取り、木を伐採して暖をとる。
本作は、こうした行為を映し出す際に、水や陸ワサビ、あるいは伐採される木材の視点から人を見つけるようなカットをインサートするが、これは一連の行為が自然の側からどのように映るのかを描こうとしているように思える。
パンフレットの中で『悪は存在しない』と同じ映像群をベースに作られたもう1つの映像作品である『GIFT』について、文筆家の五所純子氏が次のように述べている。
人物の視点ショットに切り返されて地に生えたワサビが、そして人物がワサビを採って食べる姿が映された。そのとき、青銅を思わせるような光沢のある体鳴楽器がきゃらきゃらと音階を飛び跳ねて奏でられた。人物が植物を噛む音だろうか、それとも植物が人物に噛まれる音だろうか。
彼女は、ここに加虐と被虐の同居を感じ取っており、それらを切り分けることの困難さを指摘しているのだ。
私たちは加虐と被虐を切り分けることが難しいにもかかわらず、都合よく切り分けて解釈している。つまり、加虐には鈍感であり、被虐には敏感であるということである。
日常生活の中で木を伐採し、それを薪にし、生活をしている。この行為が木々に対する加虐であることに人は鈍感だ。しかし、森を歩いている最中に、木々の刺によってつけられた手のひらの傷には敏感だ。
同様に、住民たちはグランピング場の建設により自分たちが受ける加虐に対しては過敏なまでに反応するが、自分たちの要求や意見による芸能事務所への加虐を考慮しない。
対話をして、分かり合って、お互いが加虐をすることを止めましょうというのは、確かに目指すべき目標なのだが、それは難しいし、綺麗事にも思える。なぜなら、ここまでに述べたように人は加虐に対しては鈍感だからだ。
ならば、対話不可能性を前提とした共生の在り方は、被虐を平等に引き受けることにならざるを得ないのではないか。
それは、具体的に言えば、鹿を猟銃で撃ち殺すのであれば、それと同じだけの人間の命が奪われることを受け入れるということでもある。
まさしく、本作のクライマックスの描写だ。
③因果とシステム~水は高い方から低い方へ流れる~

本作のクライマックス、あれはどうすれば防ぐことができたのだろうか?少し考えてみよう。
花の母親が存命だったら?
巧が花のお迎えを忘れていなければ?
蕎麦屋を経営する女性が街にやって来ていなければ?
巧が蕎麦屋のための水くみを引き受けていなければ?
芸能会社がグランピング場の計画を水挽町に持ち込んでいなければ?
先生と呼ばれる男性がチェンバロのために鳥の羽根を集めていなければ?
花が巧の言いつけを守って、あの草地に赴かなければ?
猟師が鹿猟をやっていなければ?あるいは鹿をちゃんと仕留めていれば?
高橋が鹿に向かって大声を出さなければ?
きっと、劇中の描写だけでも挙げていけばキリがないだろう。そして、すべてが正解なのだと思う。
どれか1つでも欠けていたら、クライマックスのあの出来事は起きなかった。
すべての偶然が揃ったことにより、あの出来事は必然的にもたらされたのだ。
「水は高い方から低い方へ」という区長の男性の言葉があったが、これは、私たちの世界を取り巻くシステムと因果律を表現した言葉のように聞こえる。
一つ一つは些細なことであり、その言動の主に花ちゃんに危害を加えたいなどという悪意を持っている人間は1人もいないはずだ。
しかし、1つ1つの言動が時間の流れの中で徐々につながっていき、下流でついに1つに交わる。その交点こそが、クライマックスのあの出来事だったというわけだ。
高度に複雑化した私たちの社会において、もはや単体の絶対悪は存在しえない。
現代における悪とはシステムである。
冒頭とラストにインサートされた木々の映像は、システムを可視化したもののように見えた。
個々の枝葉が単体で何か影響力をもつものでなくとも、それがつながり合うことによって、空を覆う影になるかもしれない。言い換えれば、正義や善に思える言動も、悪意のシステムの一端を担っている可能性があるということだ。
システムはあまりにも巨大で、私たちはその全容を認識することは不可能である。
つまり、認識できないものは存在しないという私たちの世界観の原理原則に則るのであれば、確かに「悪は存在しない」と言えるのだ。
社会に生きている存在である限り、共生する存在である限り、私たちはシステムから逸脱することはできない。
そして、システムの中で私たちは無意識のうちに加虐する側に回っている可能性がある。一方で、システムに加虐される側に回ることもある。
前者に鈍感で、後者に敏感な私たちが共生するためには、対話によって前者を可能な限り減らすか、後者を平等に引き受けるしかない。
『悪は存在しない』は、前者の実現可能性に対してドライであり、後者を現実的なものとして冷静にとらえているような気がする。
しかし、被虐を平等に引き受けると言っても、それが自分や自分の大切な人に降りかかることを私たちは簡単に肯定できるだろうか?
クライマックスで巧がとった行動は、私の個人的な解釈としては、この問いに対する1つのアンサーとして受け取った。
「バランス」を保つために誰かが被虐を引き受ける側に回らなければならないとして、それを高橋が引き受ければ、花は助かるのではないか。巧が首を絞める動作はそういう祈りにも似た感情を秘めた儀式のようにも見えた。
バランスが大切だと発言した彼自身が、この行動を取ってしまうところに、人間の感情の非合理さを感じずにはいられないし、それによって、また物語は出口のない迷路へと迷い込む。
巧が花を抱えて夜の森を走っていくシーンで映画は突然終わりを迎える。
何だかこの森が出口もなくただ永遠に続くような感覚だけが残され、その余韻が消えない。