本記事は一部、作品のネタバレになるような内容を含みますので、鑑賞後に読んでいただくことを推奨します。
『違国日記』は特別だった

ヤマシタトモコ先生の『違国日記』を読んだときに感じた、あの「特別さ」の正体は何だったのだろう?
瀬田なつき監督が手掛けた映画『違国日記』を見たときに、原作から感じた「特別さ」が決定的に欠けていることに気づいた。
それは単なるキャラクター描写の稚拙さや物語の多くがカットされた消化不良感とは、もっと別の次元の作品の本質に関わるようなものだった気がする。
その正体を探ろうと、原作を読み返していると、ハッと気づいた。
砂漠だ。あるいは浜辺、オアシス、森林、クラブだ。
登場人物たちの「こころの中の風景」、すなわち心象風景が欠けていたのだ。
『違国日記』では、登場人物たちのとりわけ主人公の朝の心象風景としての砂漠がたびたび描かれる。
かつて文化人類学者の岩田 慶治氏が自身の著書の書き出しにこんな言葉を綴った。
そこに不思議の場所がある。 眼を閉じておのれの内部を凝視すると、そこに淡い灰色の空間がひろがっているのを感ずるが、その空間の背後に、不思議の場所があるように思われるのである。不用意にそこに近づいてそれを見ようとすると、その場所は急ぎ足に遠ざかってしまう。しかし、おのれを忘れ、その場所の存在をも忘れていると、それが意外に近いところにやってきて何事かを告げる。
(岩田 慶治『カミの人類学:不思議の場所をめぐって』より引用)
彼はさらにこう続けている。
その場所にたどり着いてみると、この世界が違って見える。おのれ自身が違って見える。そういう予感がしたのである。
(岩田 慶治『カミの人類学: 不思議の場所をめぐって』より引用)
彼の言うところの「不思議の場所」と『違国日記』における心象風景には重なる部分があるように思える。
岩田氏が瞼を閉じると広がる「不思議の場所」を探ろうと試みたように、『違国日記』では朝が砂漠という心象風景に向き合う。
両者に共通しているのは、「不思議の場所」も砂漠も己の内に広がる風景である点、さらに彼らが己の中から探り当てようと試みていたのが、自分自身であるという点だ。
教育学者のシュプランガーは青年期を「自我の発見」の時期と呼び、心理学者の久世敏雄氏は高校生の時期を「内面的世界の獲得、 発見と展開の時期」と呼んだ。
青年期にある朝が砂漠の心象風景と直面するのは、彼女が自分の内なる世界を手に入れ、それを豊かにする過程で自己を見つけ出していくためなのだ。
砂漠と海、オアシス
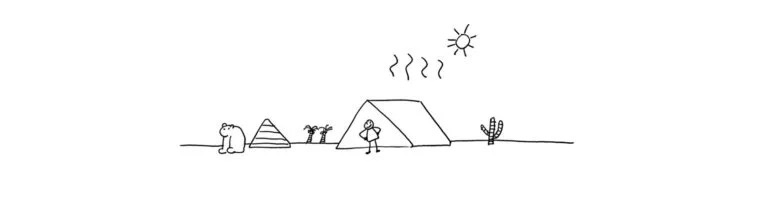
なぜ朝の心象風景は砂漠として描かれるのだろうか?
そこには、水との対比関係があるように思う。
水は羊水を想起させるし、母なる海ともつながることから、亡くなった彼女の母親とのリンクが強いモチーフとして描かれる。
あるいは、水に浮かんでいれば、自分を違う場所に連れて行ってくれることもある。これは彼女が人生における選択の多くを母親に依存していたことにも重なる。
ゆえに、砂漠は水がないことから母の不在性を際立たせるし、自分の足で歩かなければどこにもいけない、孤独な空間なのである。
そして、水というモチーフとの隔絶が作品の中で何度か表現されていた。
砂漠のオアシスの水は、私をどんなに慰めても、私の体とは決して融け合わないのだった。
(『違国日記』第3巻より)
このモノローグは、海とオアシスを対比している。
海の水が母、オアシスの水が槙生を表していると解釈すると、母を失ったことで得難くなったものを槙生に求めることは難しいのだと朝が悟っている描写にも思える。
同じ水だとしても、全くの別物であり、オアシスの水は海の水の代わりにはならない。その逆もまた然りだ。
また、第5巻では、朝が両親の死を初めて実感する瞬間が訪れるが、そのトリガーとなったのは、槙生の小説だった。そしてその小説にはこう綴られていた。
悲しみは果てのない長い長い浜辺を歩くようなものだった。
(『違国日記』第5巻より)
浜辺とは砂と水の境界であり、朝にとっては、両親がいたころの自分の世界(海)と両親を失った今の自分の世界(砂漠)の交点のような空間なのだろう。
しかし、彼女はもう海に戻ることはできない。今の彼女にできるのは、海を見つめながらも、ただ永遠に続くような浜辺を歩くことだけなのだ。
この対比が、強烈に両親のとりわけ母の喪失を色濃く際立たせるのは、ここに至るまでの心象風景の積み重ねがあるからこそである。
『違国日記』はこのように朝の感情の揺れ動きを直接的に表現するのではなく、その心象風景をもって、よりぼんやりと曖昧に可視化しようと試みた。
言葉にした途端に、指の隙間からさらさらとこぼれ落ちていくような、繊細で細かな何かをイメージに託すことで、物語に留めることに成功している。これは奇跡的だ。
心象風景の広がりと他者

そして、物語が進むにつれて、少しずつ彼女の砂漠は変化していく。
例えば、砂漠の中にビルのような建物ができていたり、水をあげているうちに大きなサボテンが育ったりするし、そして何より他者の存在を内包していくのは面白い。
槙生や彼女の元恋人の笠町が朝の心象風景の中に登場するのだが、前者は砂漠のオアシスを謳歌しており、一方で後者は森林から彼女の姿を眺めている。
朝はそんな2人の距離感や関係性に「さびしくない…?」と疑問を呈するのだが、独立した人間同士がお互いの世界を保ったままで共存するには、そうする他ないのかもしれないとも思う。
槙生のモノローグにこんな言葉があった。
あの頃わたしたちの孤独はそれぞれかたちが違っていて、わたしだけがひとりで、わたしだけが誰からも愛されなく、わたしだけがほんとうの恋を知らず、わたしだけが、と、わたしたちの多分誰もが思っていた。
(『違国日記』第3巻より引用)
溝上慎一氏が「他者の森をかけ抜けて自己になる」と述べたように、私たちが自己を確立する上で、他者の存在は欠かせない。
朝は、両親を失った自分だけが孤独で、そして、自分だけに何もないと思い込んでいるが、他者もまた違った孤独を抱えているし、たくさんのものを持っているように見える他者も何も持っていないことに悩んでいるのだと知っていく。
そして、物語の終盤には、朝視点ではない、他の人物視点の心象風景も描かれる。
例えば、えみりの恋人のしょうこにとっての静寂や孤独を表す心象風景は「ミラーボールが光って、爆音が鳴っているクラブ」だそうだ。
私たちの多くがそれは静寂や孤独とは正反対ではないかと反論したくなるだろうが、それが彼女にとっての心象風景なのだ。
あるいは、えみりにとっての孤独を表す心象風景は浜辺だった。
彼女が立っている浜辺は身体的な性と心の性がせめぎ合う境界線であり、そのどちらにも明確に帰属することができない揺らぎが孤独なのだと読み取れる。
第8巻で朝に対し、えみりが自分にガールフレンドがいることを打ち明けるシーンがあるが、ここでの心象風景の描写はあまりにも印象的だ。

足元が浜辺になっており、2人の間に陸と海の境界線、つまり波打ち際が存在する。
朝にとっての砂漠とえみりにとっての浜辺という2つの心象風景がつながった描写にも見える一方で、同時に波打ち際が完全には交わらない2人の世界を表現しているようにも感じられる。
この優しさと残酷さが同居するような不思議な感覚こそ『違国日記』らしさなのだと思う。
浜辺という「あわい」に

思えば、浜辺という心象風景は劇中で幾度となく登場するし、第11巻の終盤の槙生が朝に宛てた詩が綴られたページの背景にもなっている。
浜辺は本作のテーマを体現する最も重要な視覚的表現ではないだろうか。
私たちの喜びも、悲しみも、苦しみも、寂しさは1人1人違う風景をしている。それらが完全に重なったり、融けあったりすることはない。
その様をまるで「私たちは1人1人違う国に生きている」ようであると評してもよいだろう。
それでも人と人が関わろうとするとき、対話を試みるとき、そこには波打ち際が生まれる。
波打ち際というのは、完全な境界線ではない。そこでは、波が寄せては返すことで、その境界が緩やかに変動する。
その「あわい」にこそ、私たち人間が理解し合い、共生できる可能性が残されているのではないかと思う。
『違国日記』は、さまざまな人と人の関わりを描く中で、当人同士にとっての心地よい「あわい」を模索していく作品なのである。
客観的に見ると、それは少し奇妙で歪に見えるかもしれない。
砂漠のオアシスで孤独を謳歌しているように見えた槙生とそれを双眼鏡で遠くから見つめる笠松に対し、朝は思わず「さびしくない…?」という感想をこぼす。
しかし、それが2人の関係の心地のよい落としどころなのであれば、それでいいではないか。
そして、この記事の冒頭でも述べたように、最終的には朝が自己を見つける物語というところに収束していく。
他者との境界を見出すことが、ひいては自己の輪郭を見出すことにつながるという描き方をしているのは、本作の大きな特徴だろう。
『違国日記』が私にとって特別だったのは、言葉ではなく、風景やイメージの描写によって、私たちの心の断絶や重なりを描いた作品だったからなのだと思う。
言葉よりもずっと曖昧で解釈の余地を多分に残したそれらは、言葉よりもずっと多くを私に語りかけ、心の渇いた部分へ沁み込んでいった。
映画版の『違国日記』が原作を彩った心象風景の数々を何とかすくい取ろうとした痕跡は確かに見て取れる。
朝が日記に砂漠のイラストを描く描写は原作のまま残されていたし、彼女が自宅で歌う歌が歌詞に砂漠と海が登場する『怪獣のバラード』だったのも意図的だろう。
そして、何より朝と槙生が対話するクライマックスのシーンの舞台に海辺を選んだのは、原作を意識してのことなのだと思う。
ただ、原作では幾度となく浜辺の描写が登場するが、浜辺に実際に赴いているシーンは存在しないということを強調しておかなくてはならない。
本作のタイトルにおける「国」とは、1人1人の心が映し出す風景ないし空間のことだと考えられるし、そこをカットしてしまった時点で、私にとって、映画版は少なくとも『違国日記』ではなくなってしまった。
ちなみに朝の制作した楽曲のキーになった「エコー」という言葉だが、朝の友人の千世が「反響で周囲が見える」と言っていた。
それはつまり、他者に自分の言葉や感情が届き、はね返ってくることで、自分の輪郭がクリアになっていくということであり、そのまま前述の本作のテーマに直結する言葉だったのだ。
映画版はここの「エコー」という言葉の掘り下げも甘く、それ故に物語のクライマックスに流れる「あさのうた」も楽曲そのものは素晴らしいのに、肝心のキラーフレーズに深みがないというジレンマに陥っていたように思える。
とは言え、映画版をきっかけにこの作品の存在が広まったのであれば、それは喜ばしい。
これを機に原作も手に取っていただけたら、作品のファンの1人として嬉しい限りだ。
「余地」を巡る余談
完全に余談だが、「あわい」という言葉で、TOMOOの『あわいに』という曲を思い出した。その最後のサビにこんな歌詞がある。
ああ、まばたいた 先に誰かがいる
味わう余地ばかりのこの世界で
楽しくなる余地ばかりだ 今から
(TOMOO『あわいに』より)
この「余地」という語感が私はとても好きだ。
『違国日記』という作品は、槙生の言葉の節々からも伝わってくるが、人と人が完全に分かり合うことはできないという視座に裏打ちされている。
しかし、人と人が関わることで生まれる波打ち際という「あわい」を、TOMOOが言うようなポジティブな「余地」として描いてくれているような気がするのだ。
その「余地」は私たちの息苦しさや閉塞感を少しだけ和らげてくれる。
劇中の醍醐の手紙の言葉を借りよう。
『違国日記』という作品がなかったら、私は息ができなかった。
私にとってこの作品は、そういう作品だ。
そして、あなたにとっても、そうなるかもしれない。
そう感じたあなたと話がしたい。














