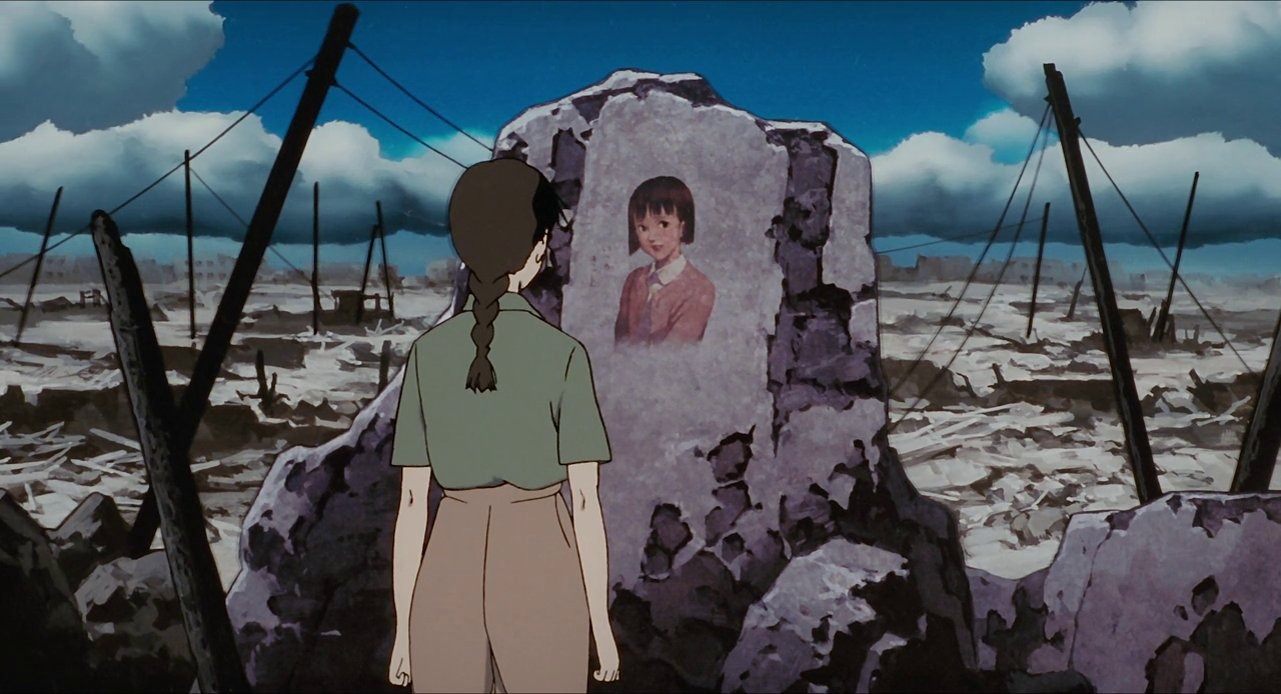本記事は一部、下記の作品のネタバレになるような内容を含みますので、鑑賞後に読んでいただくことを推奨します。
目次
作品情報

- 監督:山田尚子
- 脚本:吉田玲子
- キャラクターデザイン原案:ダイスケリチャード
- キャラクターデザイン:小島崇史
- 作画監督:小島崇史
- 音楽:牛尾憲輔
- 音楽監督:牛尾憲輔
- 主題歌:Mr.Children
- 制作:サイエンスSARU
『きみの色』をめぐる3つの視点と考察
①さらに先鋭化したオミットと『エコール』の影響
②窓と見守るまなざし
③揺れの表象としての色、それを増幅させる装置としての楽器
①さらに先鋭化したオミットと『エコール』の影響

創作物であれば、どんなものでもそうだが、何を描くかよりも、何を描かないかを選択する方が圧倒的に難しいと思う。
私自身、こんなブログを書いているわけだが、基本的に自分の媒体の中では思ったことを思ったままに書くようにしているため、毎度毎度、文字数がとんでもないことになっており、読む人にとっては冗長な文章に仕上がっていることだろう。大いに反省している。
そんな私でも、外部のメディアで記事を書かせていただく機会がいただくことがあるが、その際はある程度文字数の制約が課される。そうなると、何を書くかではなくて、何を書かないかを決めていかなくてはならない。
頭の中にあることのありったけを10000字で表現するよりも、それを取捨選択して、1500字のアウトプットにする方が圧倒的に難しいのだ。
閑話休題。
山田尚子監督は、映像表現の面においても、物語の面においても、何を描かないか、つまり何を自分の作品から「オミット」するかにこだわってきた映像作家である。
『リズと青い鳥』はそれが顕著に現れた作品だと思う。吹奏楽部にスポットを当てた物語である以上、ふつうは組織の総体の在り様を描くべきだ。
しかし、『劇場版 響け!ユーフォニアム~誓いのフィナーレ~』という並行して制作された作品があるのをいいことに、『リズと青い鳥』はふつうは描くべきものの大半をオミットし、徹底的に2人の少女の行動や感情の機微、関係性の変化にだけフォーカスした。
この作品を鑑賞したときに、衝撃を受けたのを覚えているが、とは言え、原作やオミットした部分を補完する別作品が存在するからこそ成立した作品だろうとやや高を括っていたのは事実だ。
『きみの色』を鑑賞して、いかにその見立てが甘かったかを思い知らされた。
1本で完結するオリジナル作品であるにも関わらず、『リズと青い鳥』よりもさらに、その「オミット」が先鋭化していたからである。
川村元気氏は、新海誠監督をうまくハンドリングし、その作家性を残しつつも、マス向けに上手くチューニングし、国民的アニメ作家への転身をアシストした。
おそらく、彼は山田尚子監督を同じレールに乗せたかったのではないだろうかと、今作のマーケティングを見ていて感じたところはある。
あからさまに『君の名は。』以降の新海誠監督作品を意識したポスターやタイトルロゴもそうだし、作品のコンセプトからして明らかに浮いているにも関わらず、Mr.Childrenを主題歌に選んだのもそうだ。
しかし、山田尚子監督は肝が据わっているというか、マス向けにチューニングするどころか、自分の作家性をさらに純化させた作品で勝負してきた。
彼女が『キネマ旬報 2024年8月号』におけるインタビューで次のように発言していたことが話題になったのは記憶に新しい。
彼ら・彼女らの尊厳を踏みにじらない。見られたくないと思うような瞬間に、わざわざ正面に回ってアップにするようなことはしない。興味本位で撮らない。でも、そこは人が見たいと思う部分でもあるので、ちゃんと香らせるような演出をする。
(『キネマ旬報 2024年8月号』より)
『きみの色』では、徹底して「決定的な出来事」をフレームの中に収めないということをやっていたように思う。
例えば、影平ルイが母親と2人で暮らしている家には、母親とルイと彼の兄と思しき人物の3人で撮った写真がリビングの一角に飾られている。
しかし、2人の何気ない会話の中で、母親は自分の診療所を継いでくれる人はルイしかいないことに言及し、それを受けたルイの表情が切り取られるに留まっていた。
登場人物のバックグラウンドはもっと掘り下げて描くのがふつうだが、『きみの色』はそれ以降、ルイの母親以外の家族については一切描かないのである。
他にも、きみのルイに対する淡い恋愛感情についても香らせつつも掘り下げようとはしないし、きみとルイが自身の保護者に秘密を打ち明ける重要なシーンもそれぞれワンカットで処理しており、その顛末は全くもって描かれない。
こういう本来なら物語に構成面や感情面での起伏をもたらしてくれそうなシーンを徹底してオミットしているため、『きみの色』は表面的にはすごく凪いだ作劇に見えるのだ。
とは言え、この作品から読み取れないというわけではなく、これについては後述するが、登場人物の「揺れ」ないし、その表象としての「色」という形で表現されている。
彼女のこうした作品を歪にしてしまうほどの大胆なオミットの背景には、ルシール・アザリロヴィック監督の映画『エコール』の影響もあるのではないかと思う。
山田尚子監督は『キネマ旬報 2011年12月上旬号』の中で、映画『エコール』について言及しており、自身の作品に影響を与えていることを明確にしていた。
『きみの色』の舞台が少女だけの寄宿学校を舞台にしていたり、バレエや噴水というモチーフを描いていたりするのは、同作への直接的なオマージュと言っても差し支えない。
その上で、『エコール』という作品の特徴は、不穏な空気が全体を通底しながらも、決定的な出来事がフレームの中に収まることはなく、断片的あるいは象徴的にしか描かれない点にある。
例えば、ある雪の日に寄宿学校から1人の少女が逃亡を試みる描写があるのだが、その結果として彼女がどうなったのかは明確に描かれない。しかし、その直前に凍った池で絶命し、水面に浮いている蛙の亡骸のショットがインサートされており、彼女の行く末を暗示しているようにも読み取れる。
しかし、『エコール』と決定的に異なるのは、次の項で触れようと思っている「まなざし」の部分ではないだろうか。
②窓と見守るまなざし

『きみの色』の中で、最も印象的な舞台装置を1つ挙げるとするならば、それは窓ではないだろうかと思う。
エンドロールで、スタッフロールの脇に映し出されていたアニメーションが窓を意識した映像になっていたのも偶然ではないだろう。
窓は、物理的に隔たれた空間から向こう側の空間に「まなざし」を向けるための舞台装置であると捉えることができる。
前述の『エコール』でも、窓が何度も登場する。

ただ、『エコール』における窓を介して少女たちに向けられる「まなざし」はネガティブな意味合いが強かったように思う。
少女たちを監視するものであり、もっと言うなれば、外の世界の男性が彼女たちを性的な視点で品定めする「まなざし」であったと表現しても過言ではない。
つまり、少女たちだけの閉鎖空間というユートピアから隔てられた空間から注がれる消費し、搾取する者たちの「まなざし」を表現するために、窓という舞台装置が用いられたのだ。
一方で、『きみの色』は窓という舞台装置を少年少女をやさしく見守る人たちの「まなざし」を可視化するものとして作品に取り入れていたように思う。
「午後LIVE ニュースーン」の「トクシュ-ン」で、山田尚子監督と新海誠監督の対談の模様が放送されたが、その中で彼女はこんな発言をしていた。
悩みを持っている人を「気にかけているよ」という心の動き、「自分がしんどくても、ちゃんと見ているよ。」という目線をすごく大切にしたい。
例えば、「水金地火木土天アーメン」と口ずさみながら、学校の廊下で踊るトツ子に同校のシスターである日吉子が向ける「まなざし」がそうだろう。
雪の夜の合宿のシーンで、教会の外で母親と電話をするルイを見つめるトツ子ときみのショットがあったが、これもそうだろうか。
そして、ミッションスクールを舞台にしたこともここに重なってくるのだろうが、教会や講堂という空間において窓あるいはそれを装飾するステンドグラスが描かれている。
とりわけクライマックスで、3人がライブをしているその背後にステンドグラスが大きく映し出されているのは、象徴的だ。

『ヨハネの第一の手紙』の中に次のような一節がある。
神は光であって、神のうちには暗いところが少しもない。これが、私たちがキリストから聞いて、あなたがたに伝える知らせです。
(『ヨハネの第一の手紙』1-5)
これを踏まえると、教会などの施設において、ステンドグラスを介して教会の中に差しこむ光は神そのものあるいは神が私たちに向ける「まなざし」を表しているという側面もあると言える。
そして、私たち観客もまたスクリーンという一種の「窓」を介して彼らに「まなざし」を向ける当事者になっているという指摘もできる。
このように窓を介して表現された様々な「まなざし」が、心のうちに行き場のない悩みや葛藤、孤独を抱えた少年少女たちをやさしく見守っている。
山田尚子監督は、自身の作品に影響を与えた『エコール』を多くの点で意識しつつ、同作を通底する邪悪な大人の「まなざし」を、やさしく見守る温かな「まなざし」に塗り替えたと言える。
それは彼女が青春を描く作品を作り続ける理由でもあり、彼女自身が少年少女に向けた「まなざし」に重なるものでもあるのだろう。
③揺れの表象としての色、それを増幅させる装置としての楽器

山田尚子監督は、『けいおん!』『たまこまーけっと』『聲の形』『リズと青い鳥』など、高校生を主体に据えた作品を多く手掛けている。
彼女は、前述の新海誠監督との対談の中で、高校生を描く理由について問われ、「子どもと大人のどちらでもないでこぼこした感じが美しい」と回答していた。
つまり、子どもと大人の境界で「揺れる」存在としての高校生に彼女は創作意欲を掻き立てられているのだろうと推察される。
そして、彼女は「揺れ」を登場人物の感情表現として、これまでにも明確に作品の中に取り入れてきた。
例えば、私が個人的に選出したオールタイムベスト映画TOP10の中に入れている映画『たまこラブストーリー』では、もち蔵がたまこに告白するシーンで、2人を捉える「カメラ」そのものが「揺れる」演出を取り入れている。
幼馴染というこれまでの関係が大きく変化していく瞬間の戸惑いや動揺が「カメラ」に伝わり、それが「揺れ」という形で観客に可視化されているのだ。
『リズと青い鳥』でも見られた登場人物の瞳孔やまつ毛が感情に呼応して「揺れる」演出は、今作『きみの色』でも多く見られた。
一方で、『きみの色』では、映画の冒頭で「色は光の波のようなもの」とモノローグで明言したことにはじまり、「波(=揺れ)」が作品の中に散りばめられている印象を受けた。
コップの中で揺れる牛乳。
ドッジボール中の軽い脳震盪(脳が揺れた衝撃がもたらす)。
噴水の水面。
ルイの暮らす島へと向かうための船、あるいはその揺れに伴う船酔い。
ニュートンのゆりかご。
光が炎のように揺れるフィラメント電球。
冷たい冬の教会を温めるろうそくの火の揺らぎ。
こうしたフレームに映りこむさまざまなモチーフの「波(=揺れ)」が登場人物の揺れ動く感情を繊細に表現していると言えるだろう。
何より本作のタイトルにもある「色」は、「波(=揺れ)」の表象でもあり、登場人物の心の揺れは、一貫して「色」という形で可視化される。

顕著だったのは、雪の日の夜に、トツ子ときみがルイにプレゼントするためのスノードームを購入するシーンで、きみがルイへの好意を思わず香らせてしまうシーンだ。
彼女の内に秘めた思いを明確に描写することはないが、その心の内に生じた「波」が「色」の変化という形で、トツ子のフィルターを介して観客にも可視化される。
そして、今作の中心には、音楽がある。
面白いのは、3人が音楽で何かを成し遂げたい、あるいは音楽で成功したいといった目的で音楽に関わっていないことなのだと思う。
もちろんルイは音楽が大好きなので、そういう感情が背後にあるのかもしれないが、トツ子やきみにとっては音楽であることはそれほど重要な意味を持っていないように見えた。
トツ子が音楽に関わるきっかけになったのは、きみに近づきたいという思いだったし、きみにとってのそれは家を出ていった兄や気になっている異性であるルイへの感情からだろう。
大切なのは、音楽でなくてもいいが、音楽を選んだことだ。
「色は光の波のようなもの」と表現されているが、音もまた「波」によって生み出される。
音楽とは本質的に「波(=揺れ)」とその重なりなのである。
そう考えると、楽器は「揺れ」を増幅させるための装置であると捉えられる。(テルミンはその顕著な例だろう)
3人に必要だったのは、音楽そのものというよりは、自分の心の中の「揺れ」を増幅し、解放し、昇華させるための手段としての音楽だったのではないか。
そして、増幅し、「波」が重なり合うことで生まれた音楽は、空間を振動させ、その「揺れ」を伝播させていく。
本作のクライマックスのライブシーンは、彼らが制作した3つの楽曲を立て続けに演奏するという、尺の使い方的にもかなり尖ったものであった。
しかし、長い時間をかけて描写したことで、小石が落ちた水面に少しずつ波紋が広がっていくかのように、演奏者から観客に、そして映画を見ている私たち自身にその「揺れ」が伝播していく様を演出することに成功したのだ。
ポストクレジット映像で、彼女たちの楽曲がカセットテープに収められている様が描かれていたが、これは『けいおん!』を見ていた人にはお馴染みだ。
彼女たちの青春時代の「揺れ」を閉じ込めたカセットテープは、時間を超えて、大人になったいつかの彼らにもその「揺れ」を伝えてくれるだろう。
物語の最後、彼女たちが走る堤防の1本道は、未来への滑走路だ。
飛び立ったその先で、きっと青春時代の「揺れ」が過去のものとなり、何だか微笑ましいものに思える瞬間がきっと訪れる。
山田尚子監督は、そんな希望を届けたかったのだと思う。
揺れるは美しい。
揺れている君も美しい。