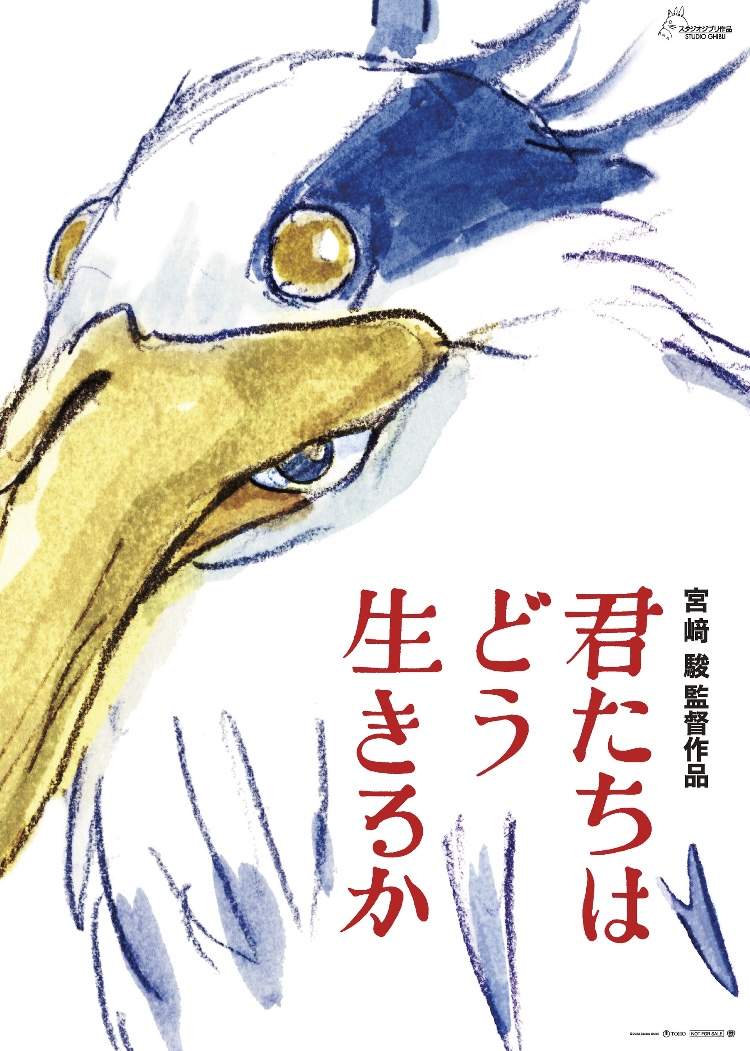本記事は一部、下記の作品のネタバレになるような内容を含みますので、鑑賞後に読んでいただくことを推奨します。
作品情報

- 監督・脚本・撮影:奥山大史
- 照明:西ヶ谷弘樹
- 録音:柳田耕佑
- 美術:安宅紀史
- 装飾:松井今日子
- 衣装:纐纈春樹
- 編集:奥山大史&ティナ・バス
- 音楽:佐藤良成
- 主題歌:ハンバート ハンバート
『ぼくのお日さま』をめぐる3つの視点と考察
①強い光、濃い影
②吃音、靴、車、ガソリンスタンド、船
③滞留するもの、流れゆくもの
①強い光、濃い影

『僕はイエス様が嫌い』で高い評価を獲得し、近年は米津玄師の『地球儀』のMVも手掛けた奥山大史監督の映像作品の特徴の1つはその光の使い方だろう。
画面全体が明るく、色の彩度も高いので、映像そのものが少し「作りもの」っぽさがある。また、強い光源を被写体の背後に配置し、逆光で撮影し、白飛びしたような映像を自身の作品の中に取り入れるのも面白い。
しかし、彼の作品において白眉なのは、そのやや強すぎるかに思える光が作り出す影を登場人物の痛みや葛藤の表現として応用している点だろう。
被写体の背後に強い光源を配置すると、当然、被写体がその光を遮り、影を生むことになる。
例えば、アイスダンスのバッチテストの会場にさくらが現れず、タクヤがポツンと1人でスケートリンクを見つめるシーンを思い返してほしい。
スケートリンクは強い白色光を放っており、その光がリンクの傍らに佇むタクヤが生み出す影を濃くしている。彼の抱える痛みや悲しみが強く印象づけられる。
奥山大史監督の映像に心惹かれるのは、強い光をフレームの中に取り入れながらも、むしろそれによって登場人物や近景に生じる影に寄り添っているからなのだと思う。
それは、優しさや希望を提示しながらも、登場人物の抱える痛みや葛藤をちゃんと描く、彼の物語と協調している。
この重なりとシナジーこそが彼のフィルムの圧倒的なまでの強度を裏打ちしていると言える。
②靴、車、ガソリンスタンド、船

映画においては、ちょっとしたモチーフにも、そしてそれを誰が誰に渡したり、もたらしたりするのかにも意味がある。
例えば、この映画で主人公のタクヤは誰からフィギュアスケート用の靴を貰ったかを思い返して見て欲しい。
タクヤは、男だからという理由で、アイスホッケーをしているが上手くスケートリンクを滑ることもできないし、キーパーの役割を押しつけられており、楽しみを見出せていない。
そんなときに、リンクの上で美しく自分を表現するさくらを見惚れ、自分もあんな風に自分を表現してみたいという淡い憧れを抱くようになる。
しかし、アイスホッケー用の靴という「自分に合わない靴」では、スピンをすることはできず、自分の思い描いたようにリンクを滑ることもできない。
そんな彼にフィギュアスケート用の靴を手渡すのは、池松壮亮演じる荒川だった。
これは、言い換えれば荒川がタクヤに自分自身を表現するためのツールを授けたということでもあるわけだ。
主人公の言葉に詰まってしまう吃音という特性もそこにリンクし、スケートの技術が上達し、氷の上を滑らかに滑れるようになっていく過程と、彼の中で滞留していた感情が少しずつ流れ出していく様が重なって描かれているのは巧みである。
そんな「靴」が、最後に借り物から、彼自身のものになるという演出も憎い。
荒川は、自身の抱える閉塞感から、まっすぐで純粋なタクヤに希望を見出し、自己投影をしているように見えた。だからこそ、この時点では靴は借り物だった。
しかし、物語の終盤に荒川はその靴をタクヤに譲り渡す。
それは、タクヤに自分の作為の上ではなく、自分自身の思いのままに氷の上での表現を追求して欲しいという願いの表れであると同時に、自己投影から脱却し、自分の足で前に進むという荒川の決意の表れにもなっている。
「靴」以外にも、もう1つ本作においては移動を司る重要なモチーフがある。
それは、荒川を象徴する「車」だ。
車は第一に移動手段である。
そんな荒川の交際相手である五十嵐はガソリンスタンドで働いている。
車とガソリンスタンドの関係は、そのまま今作における2人の人間関係を表現していた。
車にとってガソリンスタンドは欠かせない。しかし、車はずっとガソリンスタンドに留まることはない。
五十嵐は、愛情だけでなく、たくさんのものを都会で疲弊した荒川に与えた。そして、荒川は五十嵐からもらったたくさんのものを胸に、彼のもとを去っていく宿命なのだ。
ラストシーンで、彼は車を降り、船に乗る。
移動手段の変更という形で、彼の新しい物語の幕開けを予感させる演出はこれまた巧みだ。
車は第二に心的空間の表象だ。
物語の冒頭で、荒川は1人で車に乗っている。
しかし、タクヤとの関わりを深めるうちに、彼を車に乗せ、やがてはさくらをも車に乗せることになる。
車に乗り、車内の空間を共有するという形で、人が人に心をゆるしていく様を表現しているわけだ。
ただ、この演出の積み重ねが、物語のターニングポイントにおいて、車の内と外の対比という形で極めて残酷な形で効いてくる。
さくらは、スーパーの駐車場で車内で荒川と五十嵐が仲睦まじくじゃれ合っている様子を偶然見かける。
あの日、自分が座っていた彼の車の助手席。そこには、自分ではない男性。
当然共有のものだと思っていた親密さが自分の独りよがりであったこと、自分がいられると思った居場所を突然誰かに奪われたような疎外感。
その裏切りが、彼女の感情を反転させ、強烈な拒絶へとつながっていく。
『ぼくのお日さま』は多くを語る映画ではない。
しかし、こうしたモチーフの使い方によって、観客に多くを語りかける。
その巧さに、圧倒される。
③滞留するもの、流れゆくもの

『ぼくのお日さま』は冬の始まりから春の訪れまでを描いたミニマルなフィルムだ。
その季節性に重ねて、これは「雪解けの映画」だと評しても、よいだろう。
水が滞留して、固まって、厚い氷になる。
私たち人間が生きていく中でも同様の現象が起きる。
言葉も、人間関係も、感情も、キャリアも。いろんなものが滞留して、固まって、動けなくなってしまう。
それでも、「お日さま」はずっと僕らを背後から照らしてくれている。
「お日さま」をフレームに収めるとき、光という視覚的な記号に焦点が当たりがちだが、この映画はむしろ「お日さま」の温度を意識させてくれるような気がした。
それは、口から吐き出される白い息、授業中の水を沸騰させる実験など、温度を表現する描写がいくつも取り入れられていたことによっても裏打ちされている。
「お日さま」がくれる温もりよって、登場人物たちの固まった感情や関係が、やさしく融かされ、また流れていく。
そして、春が訪れ、いろいろなものが再び流れ始める予感とともに本作は幕を閉じる。
荒川がこれからどんなキャリアを歩んでいくのか。
タクヤとさくらの人間関係はどんな風に変わっていくのか。
描かれない彼らのこれからに思いを馳せながら、エンドロールを見ていると、映画を見ている間にじわじわと自分の中に溜まっていた感情が余韻とともに溢れて、涙の形になって流れていく。
素晴らしい映画体験。2024年のベストフィルムの1つであると断言できる。