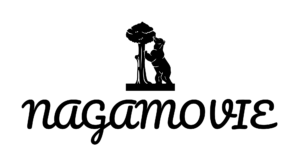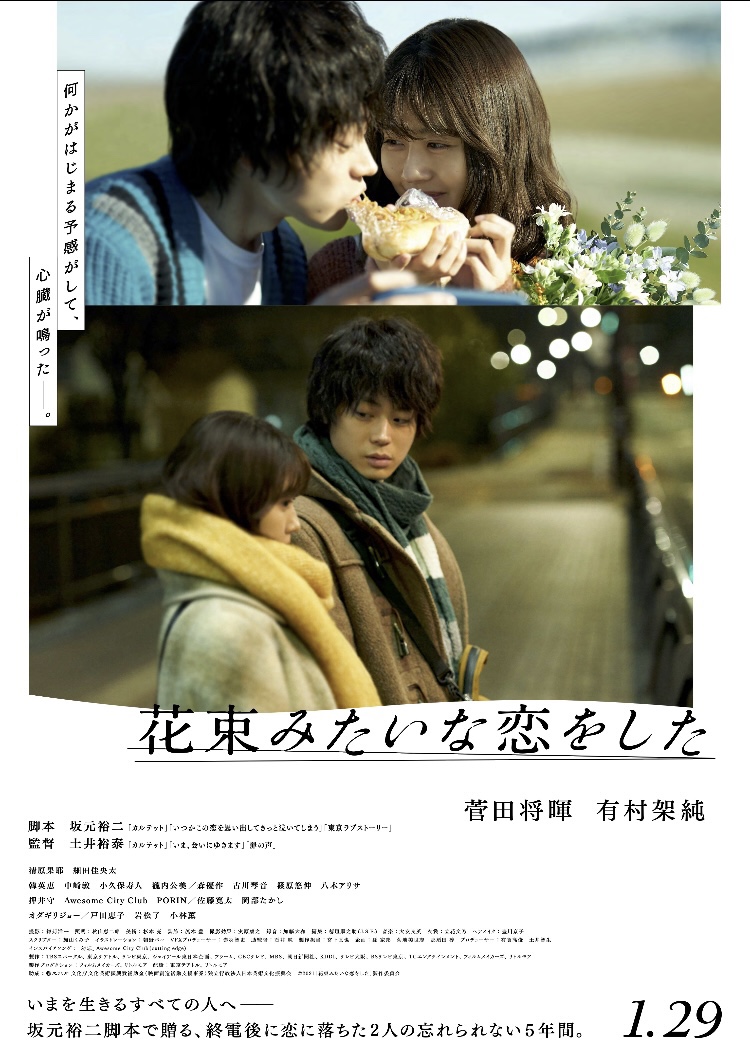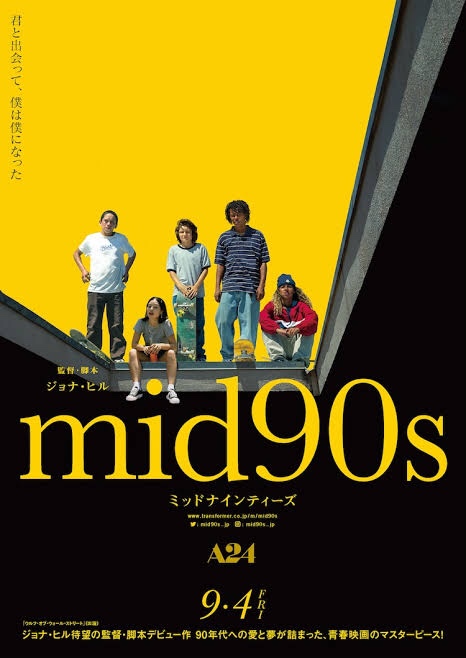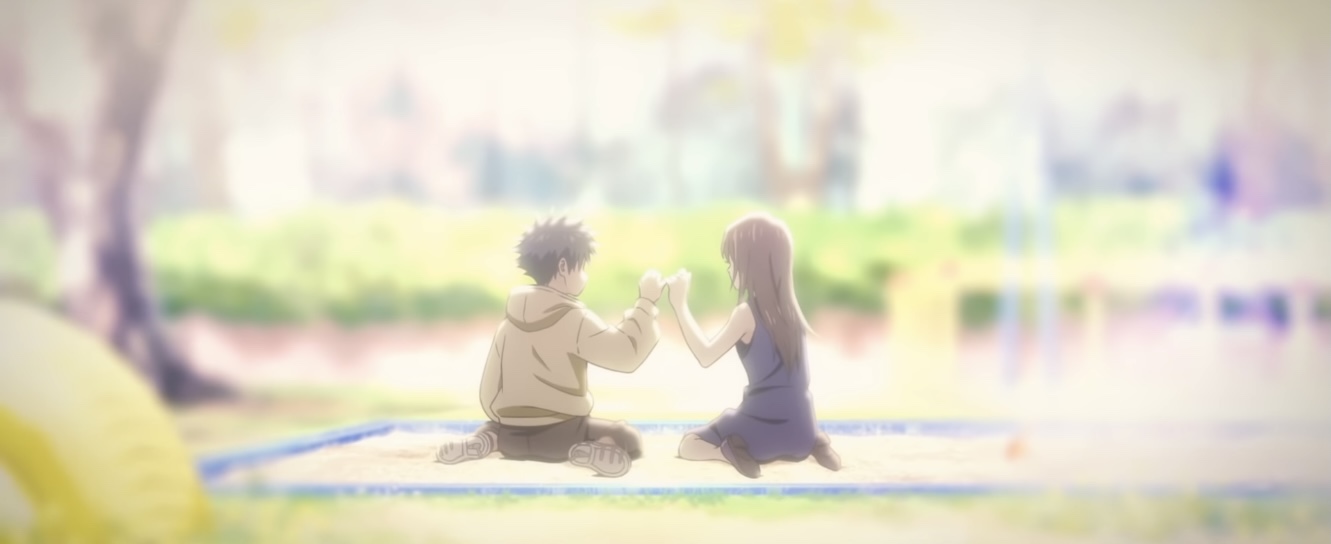本記事は一部、下記の作品のネタバレになるような内容を含みますので、鑑賞後に読んでいただくことを推奨します。
作品情報

- 監督:土井裕泰
- 脚本:坂元裕二
- 撮影:鎌苅洋一&小林拓
- 照明:秋山恵二郎
- 編集:穗垣順之助
- 音楽:鈴木慶一
『片思い世界』をめぐる2つの視点と考察
①「ままならなさ」を抱えて生きていくということ
②あなたを「かき抱き」、癒す物語にならんことを
①「ままならなさ」を抱えて生きていくということ

傷や喪失といかに向き合うかというのは、物語にとって今も昔も重要なテーマであり続けていると思う。
しかし、現実において私たちが、あるいは私たちの社会が抱える傷や喪失に対して物語は無力であるとする見方も多い。
物語は、傷口の縁をなぞり、ただその周囲を語って回ることしかできない。言葉は痛みの生々しさをほのめかすものの、傷はまさに身体のものとしてあり、その屈辱と不安を言葉は決してとらえることができない。
(アーサー・W・フランク『傷ついた物語の語り手』より)
映画『片思い世界』に登場する人物の多くが傷や喪失を抱えており、傷は様々な形でアレゴリー化され、スクリーンの中に息づいている。
主人公たち3人が暮らす家の写真立てに飾られた不自然な集合写真。
事件が起きた施設の片隅に作られた、被害者を追悼する石碑。
被害が起きたときに偶然現場を離れてしまっていた少年にとってのピアノ。
1人娘を失った母親にとっての夕焼けチャイムの放送、あるいは三日月型のクッキー。
これらはただそこにあるだけで痛みを内包している。そのままにしていても痛いし、触れると痛みが増す。ゆえに本作の登場人物たちもまた、触れないように、傷口の縁をなぞるようにして生きている。
主人公たち3人は飾られた集合写真を顧みることはないし、少年はピアノを弾くことを遠ざけている。また、石碑の前で偶然足を止めた家族は、そこで命を落とした子どもたちを「かわいそうな子」として、自分たちから切り離そうとしているようにも見えた。
そんな本作だが、主人公たち3人が、自分や周囲の人たちが負った傷を限りなく無かったことにできる1つの可能性を知り、そのために行動を開始したことで物語が動き始める。
ただ、それは同時に自分たちの傷に触れることであり、劇中で美咲が言及したように痛みやさらなる傷を伴うものでもある。
だか、その過程で浮き彫りになるのは、癒しや救いというよりもむしろ「ままならなさ」だったように思う。3人は目的を達成することはできなかったし、娘を失った母は事件の犯人と対峙したが、その男から欲しかった言葉が発されることはなかった。
社会学者の天田城介氏が前述のアーサー・W・フランクの著書『傷ついた物語の語り手』について分析した記述の中で、次のように述べている。
病者は自らの病いとともに生きる身体のままならなさにこそ価値を見いだすことで、自らの生を立て直すことが可能であり、またそれは病者にとってよきことである
(天田城介「病い・1」(世界の感受の只中で・15)『看護学雑誌』より)
傷に背を向けることはできる。あるいは見ないふりをすることもできる。あるいは何かで隠してしまうこともできるかもしれない。
しかし、傷を無かったことにはできない。だからこそ、自分が負った傷の「ままならなさ」を受け入れ、傷とともにその後を生きていくことにこそ、その歩みにこそ、癒しや救いがあるのだと思う。
その点で『片思い世界』は実に誠実な映画だったと言える。
それは、安易な癒しや救いを提示するわけではなく、ラストシーンで傷とともに力強く前に歩いていく登場人物たちの姿に、いつか彼らに癒しや救いがもたらされるよう祈る切実さが強く感じ取れるからだろう。
②あなたを「かき抱き」、癒す物語にならんことを

一方で、事件をきっかけにピアノを遠ざけた高杉典真という青年の事の成り行きには、作り手が「物語」そのものの力や可能性を仮託しているように感じた。
作り手は物語に何らか自分の思いや考え、信念のようなものをしばしば託すし、それによって受け手の感情にどんな波を立て、どんな影響を与えられるのかを考えていたりする。もちろん物語に限った話ではなく、創作には少なからずそうした側面がある。
ただ、作り手が物語に託したものが、作り手の想定していた通りに受け取られることはむしろ少ないだろう。
それは、受け手が置かれている状況やバックグラウンドによって、あるいは社会や時代の変化によって、絶えず変化していくからだ。
『片思い世界』において、相良美咲がノートに綴った音楽劇の脚本は、典真のことを思って書いたものではないような気もするし、当時は事件が起きるなんて知らなかったわけだから、そのコンテクストを織り込んでいるはずもない。
それでも、時間を超えて典真に届いたそのノートは、彼を包み込み、その傷を少しばかり癒してくれる救いの書となった。いや、正確には彼がそう解釈したとするのが正しいだろう。
作り手が考えたことや思っていることをそのまま受け手に届けたいのであれば、物語の形をとる必要はないし、ナンセンスである。
受け手との関わりの中で、作り手が託したものがさまざまな受け取られ方をし、さまざまな感情を生むことこそ、物語の力や可能性ではないかと思うのだ。
『片思い世界』という映画にも受け手の数だけ、解釈や受け取り方が存在するだろう。
物語に世界や社会を動かす力はないかもしれない。受け取った全員の心を動かしたり、救いになったりするような作品を作ることは不可能かもしれない。
それでも、たった一人、あなたを「かき抱き」、その傷をわずかばかりでも癒すことができるならば。傷を抱えて生きていく支えになれるならば。
そんな作り手のささやかなる「片思い」がいつか必要とする誰かに届くことを祈りつつ、本作への私の短い論考を締めくくることとしたい。