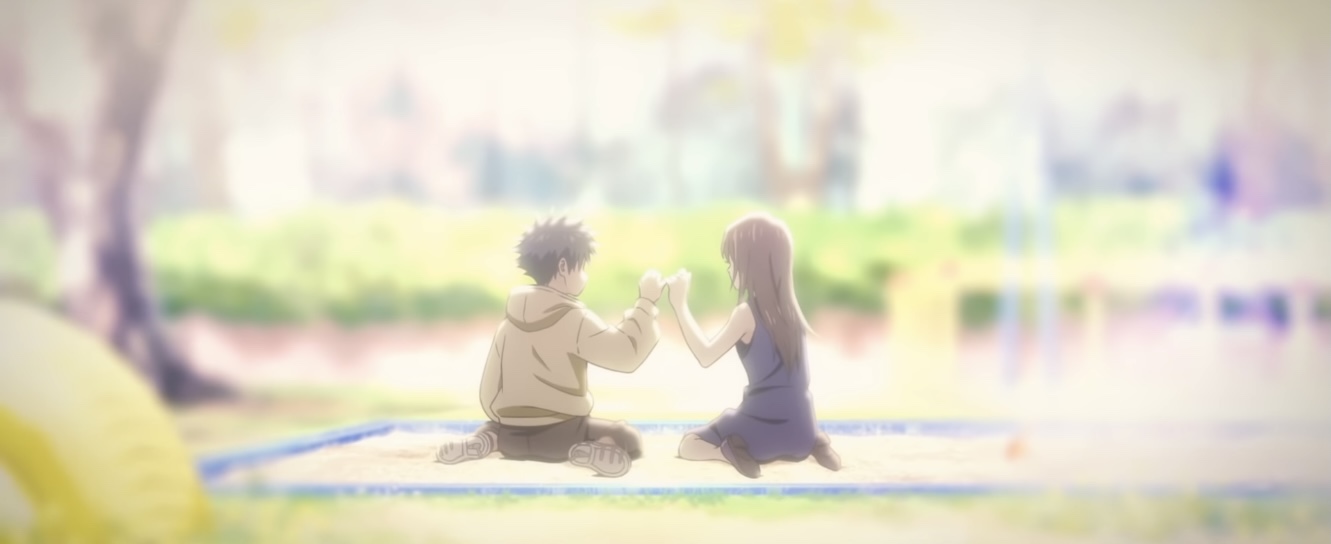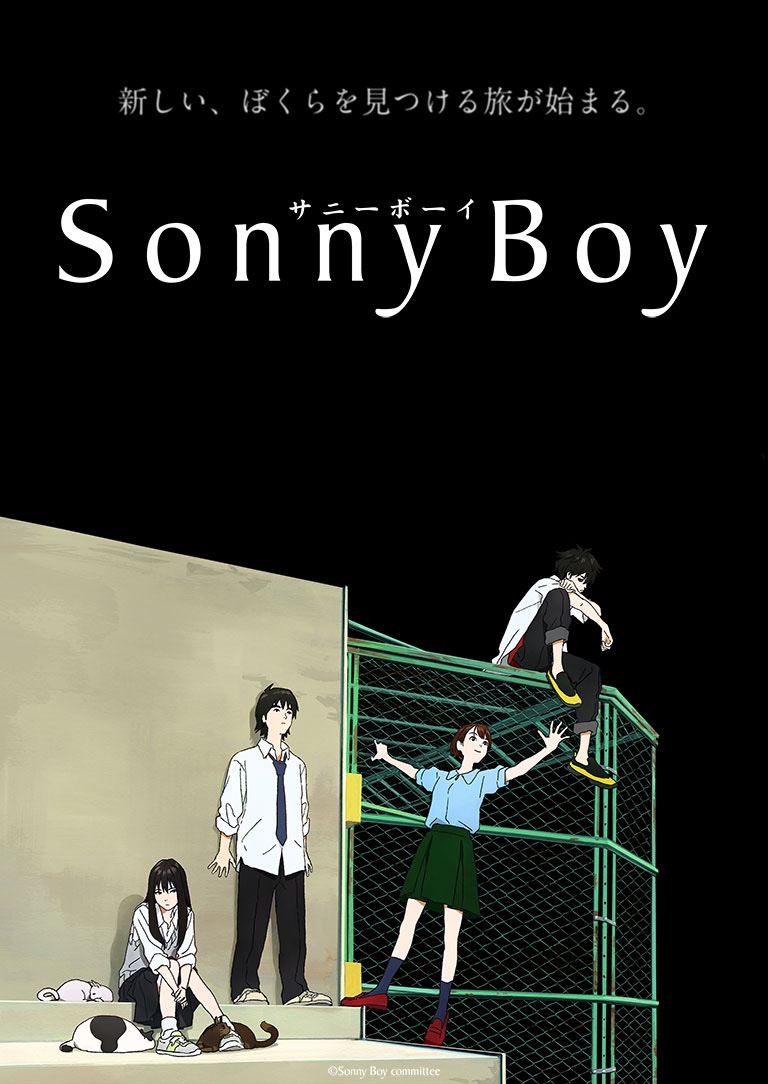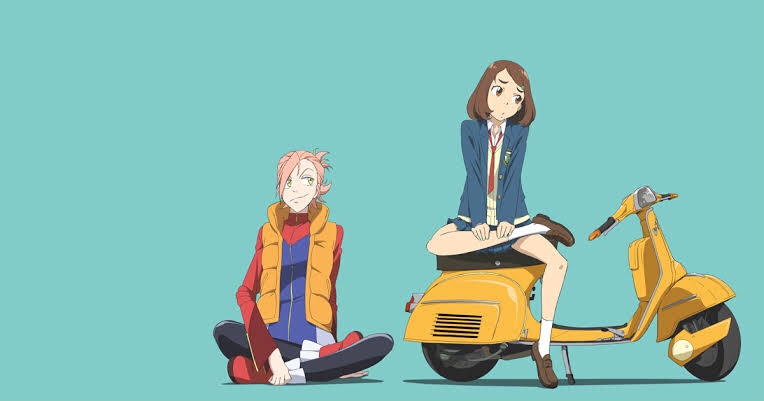アイキャッチ画像:©Project Itoh/GENOCIDAL ORGAN 映画「虐殺器官」PVより引用
目次
はじめに
みなさんこんにちは。ナガと申します。
夭折の作家伊藤計劃のSF小説の3作品の映画版が2015年から公開の運びとなり、その最後を締めくくる作品として「虐殺器官」が公開された。
今回はそんな映画『虐殺器官』についてお話していく。
概要的な部分は以下の記事でも触れましたので、今回の記事では割愛させていただくこととする。
【ネタバレなし・解説】「虐殺器官」の意義と今見るべき理由とは?
映画『虐殺器官』の感想
伊藤計劃の映画化された3部作は本来、「虐殺器官」、「ハーモニー」、「屍者の帝国」の順番で鑑賞することが望ましいとされる。しかし、映画版の公開順はなんとその真逆で、「屍者の帝国」、「ハーモニー」、「虐殺器官」となってしまった。
まず、「屍者の帝国」が1番目という時点で疑問を感じていたが、「虐殺器官」の大幅な公開時期のズレは仕方のない部分も大きい。当初製作予定だった製作会社であるマングローブが倒産してしまったのである。
結果的に、「虐殺器官」のチーフプロデューサーである山本幸治氏が「ジェノスタジオ」を設立し、今作品の制作を引き継ぐこととなった。結果的に2015年10月公開予定であった今作は2017年2月にまで上映延期となってしまったのである。
そしてようやく公開の運びとなった映画「虐殺器官」だが、やはりスタッフ陣の思い入れの強さなのであろうか?その圧倒的なミリタリー作画・演出には驚かされるばかりであった。
客観的視点と一人称視点を織り交ぜることで、より高い臨場感を演出し、R15指定になりながらも原作でも鮮烈に描かれていた、戦闘シーンの描写を映像メディアという媒体で妥協無く描いたことで、よりその鮮烈さを増していたように思う。
日本最高峰のミリタリーアニメ作品としてだけでもこの映像を劇場で見る意義は十分にあると思う。
しかし、この作品の最大の問題点はやはり映画の尺であり、脚本である。まず400ページ弱ものボリュームがある本原作を2時間弱という尺で映像化しようというのが無茶な話である。
そんな無茶をしたがために、作品中には原作を読んでいないと、理解できない、補足のしようもない描写や演出、展開が多く登場する羽目になっている。
今回の記事ではそんな映画「虐殺器官」のわかりにくかったいくつかのポイントに解説と補足を加えていきたいと思う。
スポンサードリンク
映画『虐殺器官』の興味深い5つのポイントを考察
シェパードらの部隊が使っていた「ポッド」とは一体?
映画版ではインドへの降下作戦で初登場した、主人公たちが上空から急降下、着陸するために使用していたポッド。劇中であまり説明がなく、あれはいったい何なんだ?と疑問に思われた方もいるかもしれない。
物語の中盤で、主人公のクラヴィスはルーシャスによって拘束されます。そしてクラブで彼が「計数されざる者」であることを告げるシーンで、ルーシャスは、クラブで給仕用のロボットを指さし、ここに使われている人工筋肉はヴィクトリア湖で遺伝子操作され、養殖された鯨やイルカの筋肉であることが述べられている。
このロボットと同様に、主人公たちが登場していた降下用ポッドにもその人工筋肉が使われているのである。搭乗者の衝撃を吸収するために内部には人工筋肉が敷き詰められ、目標地点に着陸できるよう制御する翼のような部位にも人工筋肉が使われている。
そして、このポッドが着陸ないし着水すると、自動的に消滅していくシーンが映画にあったように思う。これは人工筋肉が酸素の供給を受けていない、壊死して消滅するという性質を利用したもので、ポッドは役目を終えると、その痕跡隠滅のために酸素の供給が停止され、消滅しているのである。つまり、映画版でのそのポッド消滅シーンからも分かる通り、あのポッドのほとんどは人工筋肉から作られていて、その骨組みの一部分に金属や電子部品が使われているのである。そして、そのわずかなパーツも酸によって自動的に消失するように設計されているのである。
つまり、あのポッドは目的地への正確かつ迅速な着陸を可能にしただけではなく、その痕跡までも自動的に消してしまうという優れものなのである。
小説版では、このポッドは「2001年宇宙の旅」の冷凍睡眠ポッドや棺に例えられており、このポッドに入ることは他人の死を追体験しているかのようであるとも表現されており、物語を理解していく上で一つ重要な要素となっているのだが、この点に関しては映画版を理解する上では必要がない知識なので、気になった方は原作を手に取ってみてください。
インドでのジョン・ポール奪還作戦を決行した院内総務ないしユージン&クルップス
まず、映画「虐殺器官」の冒頭の作戦は、ジョン・ポールと元准将の2人を殺害することが目的だった。その作戦をアメリカ本土の指令本部から見守っている大統領たちであったが、そこに院内総務が現れる。大統領の口ぶりから推測するに、指令本部は院内総務に作戦の決行に際して招集をかけなかったようである。そして、大統領の怪訝そうな表情。何かあると思わせる表情である。
クラヴィスたちの部隊はこれまでにも多くの作戦を遂行してきていて、ジョン・ポールは何度もその対象になっていたのだ。しかし、何度作戦を重ねても一向に彼にたどり着くことができないのである。そこで、情報軍内部の極秘捜査チームが動き出して、軍内部にジョン・ポールの協力者がいるのではないかと調査を始める。そして、その結果、院内総務が一人の容疑者として浮上、作戦を重ねていくうちに少しずつ疑いを強めていく。
そして、その容疑が固まったのが、インドでのジョン・ポール奪還作戦である。奪還作戦に登用されたのは、院内総務自身が役員を務めるユージン&クロップスの傭兵であったことが判明し、芋づる式に彼の容疑が固まったのである。
映画版ではカットされていたが、小説の方で、クラヴィスと捕らえられたジョン・ポールの会話のシーンで、自分が支援者を失うことを予期する発言をしており、彼は自分を助けるために院内総務が墓穴を掘るところまで見通していたように思われる。
クラヴィスはなぜルツィアに執着したのか?
これを語るには、映画版「虐殺器官」にはあまりにも大きな欠陥があるのですが、原作での要素の補足をくわえながら話していきたいと思う。
まず、クラヴィスがルツィアに執着する理由は大きく分けて2つあると私は解釈している。
一つ目は映画版でも少し匂わせてはいるが、ルツィアに対する愛と呼ばれる感情だろう。では、なぜ、クラヴィスがこれほどまでにルツィアに惹かれたのかと言う事であるが、それを語るにはクラヴィス自身の背景を語っておく必要がある。
原作においてクラヴィスは父親の死、脳死状態になった母親の生命維持装置を自分の一言で停止させた、つまり自分の手でもたらした母親の死、そして職業軍人として自らが殺めてきた人の死に囚われた存在なのである。ゆえに物語の一番冒頭に、クラヴィスはまだ死んでいないにもかかわらず、死者の国で母親や自分が見てきた死者たちと共に歩いていくという描写が登場する。これは紛れもなく、クラヴィス自身が「死者の国」の住人であると言う事を示しているのである。
そして、原作の135ページに非常に重要な一節があるので引用させていただく。
「ブライアン・イーノも『パルプ・フィクション』を観てこう言っていた。カリフォルニアの女性は、生き生きした女性にはなれても、運命の女にはなれない、と。ルツィア・シュクロウプはカリフォルニアの女ではなかった。」
この一節はクラヴィスがルツィアに惹かれた理由を考えるうえで非常に重要な一節なのである。「生き生きとした」という表現はまさに「死」と対比的な表現である。「死」というのは、間違いなくクラヴィスにつきまとっているものだが、同時にルツィアにもつきまとっているものであることは特筆すべき点である。
ルツィアは映画の冒頭でも描写されていたように、ジョン・ポールが自分の妻子をサラエボの核爆発で亡くした時、彼と性的な関係を結んでいた女性である。この時彼女は、ジョン・ポールの妻子が死んだことを自分の「罪」であるかのように背負ったのである。この時その妻子の「死」が彼女の背中にのしかかったのである。
ゆえに先ほど挙げた一節の「ルツィア・シュクロウプはカリフォルニアの女ではなかった。」という部分は単に、ルツィアがアメリカないしカリフォルニア出身の女性ではなく、チェコの女性であると言う事を指しているのではなく、彼女が生き生きとした女性ではなく、「死」がつきまとっている女性であったと言う事を指しているのである。
映画版では、クラヴィスはPTSDにより混乱した同胞のアレックスを「合理的な判断」でもって射殺する。彼は軍の管理により平静を保っていたが、心はその痛みを確実に感じていたように思うし、自分が殺してきた多くの人の死にも痛みとしては感じない「痛み」を蓄積していったのである。
原作と映画版で大きくクラヴィスのバックグラウンドは異なるが、彼の心に刷り込まれた「死」というものが、同じく「死」を背負ったルツィアへの好意に無意識的に作用したことは間違いないと思う。
もう一つの理由は「罪と赦し」の考え方に起因する。彼は、職業軍人として多くの人を手にかけてきた。彼はその殺害をアメリカ政府からの命令であったからということで納得しようとしてきた、納得してきたのである。自分が殺してきた人の死は無意味ではなかったと、原作の言葉を借りるならば、彼らは「平和のための殉教者」であると自分の中で規定し続けてきたのである。
映画版では、カットされてしまったのだが、ここで、彼の考え方を大きく揺るがす「死」に直面する。それが彼自身の母の死なのである。彼は自分の母親の生命維持装置を自らの意志で止めたのだが、この母親の「死」に際して、彼は自分の母親の生涯の記録たるライフグラフというものを見ようとしなかっったのである。これはまさしく彼が母親を自分の意志で殺すという事実から目を背けようとしたことの表れなのである。
しかし、クラヴィスはルツィアとの会話の中で、救われたような思いになるのである。原作208ページに以下のような記述がある。
「ただ、自分がそれらを選んできたということを、誰かに罪を背負わされたのではなく、自ら罪を背負うことを選んだのだ、ということを、ルツィアが教えてくれたからだった。」
つまり、ルツィアとの対話を通して、彼は自分が母親を殺すという罪を自分がちゃんと背負えているんだということを実感したのである。
そして、彼はルツィアに母親とは違う何か感じるのである。それは「瞳」である。原作では、彼が母親と目が合った時に冷たいものが背筋を走った、と記述してある。一方で、ルツィアの記述にはその「ヨーロッパ的な大きな瞳」、「物憂げな瞳」に惹かれた点が記されている。この2つの瞳ないし視線は非常に対照的に表現されていることがうかがえる。つまり、クラヴィスはそんなルツィアの瞳に、視線に、自分自身の母親からの赦しを求めていたのである。原作の第3部の冒頭にクラヴィスの頭の中で起こった葛藤を表す、母親の幻影とのやり取りで、次のような記述がある。
母親「お前はよくやったわ。私のためにつらい決断をしてくれた。・・・・省略。」
クラヴィス「本当に・・・母さん。」
母親「いいえ。」
母はそう冷たく言い放ち、「そう言ってほしかったんでしょ。・・・省略。」
そうである。結局のところ、クラヴィスは母親からの赦しが欲しかったのである。そして、その母親はもう死んでしまって、彼女自身から赦しを得ることはもうできなくなってしまったのである。ゆえに彼はルツィアにその赦しを求めるのである。ルツィアが持つ物憂げで大きな瞳は、おそらく母親の冷たい瞳と対比的に表されていて、まさしく母親の赦しの象徴であったのだろう。原作280ページに次のような記述がある。
「ぼくはルツィアに赦すと言ってもらいたい。
ぼくはルツィアに赦すと言ってもらえればそれでいい。」
ここまで述べてきたように、クラヴィスがルツィアに執着した理由は、同じ「死」を背負う人間として感じた愛情と彼女が母親の赦しの代弁者であったことの2点であったというのが私の結論である。
映画版で、クラヴィスの母親の要素がごっそり抜け落ちた、ごっそりカットされた点がいかに大きなダメージであったのかもお分かりいただけたかと思う。
スポンサードリンク
最後のアフリカ編で水の中を泳いでいたイルカたち
これは察しの良い方は映画版だけでも理解できたかとは思いますが、少し説明が省略されていてわかりにくかったので解説を加えておきます。
ルーシャスがクラヴィスを捉えてナイトクラブで<計数されざる者>の話をしているとき、彼は人工筋肉の話に触れたのを覚えているだろうか?その時にヴィクトリア湖という湖の名称が出てきたと思う。
そして降下作戦の手前でアフリカの湖が大きく映し出された地図が画面に挿入されていたと思うが、クラヴィスたちが最後の作戦で着水したのはまさしくヴィクトリア湖なのである。ゆえに人工筋肉生産のために養殖されているイルカが水中を泳いでいたというのが結論である。
と、ここまでは良いのだが、このヴィクトリア湖の背景に関する説明が映画版からはごっそりと抜け落ちていたので、そこを捕捉させていただく。
ヴィクトリア湖周辺の住民たちは、漁業で生計を立てていました。しかし、湖にナイルパーチという外来種が放流され、従来の生態系が完全に崩壊してしまったのです。
さらにナイルパーチは非常に高級魚であったため、ほとんどが輸出され、住民たちが食べられる魚はほとんど残っていませんでした。このためヴィクトリア湖周辺の住民たちは没落していきました。
しかし、次に、小魚類が絶滅したことでその餌であった藻類が繁殖し、水中の酸素が減少。結局ナイルパーチも絶滅してしまいました。そしてそんなヴィクトリア湖に目を付けた業者が、藻類を一掃し、イルカの養殖を始めたのです。
そして人工筋肉生産がヴィクトリア湖沿岸部の最大の産業となり、沿岸部の住人たちは、ケニア、ウガンダ、タンザニアからの独立を求めて戦いに挑む決断をするのです。この決断を手引きしたのがジョン・ポールというわけですね。
後のシーンで、クラヴィスがジョン・ポールに対峙した時、「虐殺の文法は、食糧不足に対する適応だった、というのか」というセリフが登場しましたが、これはクラヴィスが戦闘前にヴィクトリア湖のこのような背景を聞いていたがゆえに導き出された言葉だったんですね。
結局ラストはどうなったの??
映画版では、クラヴィスが自分の経験を、ジョン・ポールに関する事実を公衆の面前で語ったところで幕切れとなる。
さすがにそれはどうなんだ?製作スタッフさん?
確かにクラヴィスが自室で、ジョン・ポールの虐殺の文法を解読し、その文法に基づいてアメリカ国民に対する発信をしたという点が推測できないわけではない。しかし、「虐殺器官」という映画を締めくくるにおいて、クラヴィスの決断は最重要項目であり、その決断がアメリカにどういう影響を与えたのか?つまりエフェクトの部分までをきちんと描くべきだったのではないでしょうか?
虐殺の文法でもってアメリカを陥れる、つまりアメリカを内戦状態に陥れることで、アメリカ以外の世界を守ろうと決断したクラヴィスの決断を。アメリカ国民の死を自分が背負うと決めたクラヴィスの決断を。
肝心のラストが描写不足というかクラヴィスの語りのみによって結論付けられたために、映画の結論としては非常に弱く、説得力に欠けるものとなってしまったのである。
私が、明確にアメリカでの内戦状態の様子まで映像化すべきだっったと感じているのは、やはり前回の記事でも述べたように「虐殺器官」というのは「気づき」を与える文学作品だと考えているからである。
虐殺の文法が使われてきたのは、もはやメディアでも大きく取り上げられることがないような名もなき紛争地域である。人々は無意識にそういった情報から目をそらす。世界は自分の欲している情報にしか興味がないのであって、あまりにも数の多い虐殺や内戦はもはやこの「虐殺器官」の世界では刺激を失い、人々の興味からは外れたものとなってしまったのである。
人々の関心は虐殺や紛争よりもデリバリーピザにあるのである。
つまり、「虐殺器官」のラストにおいて、主人公が虐殺の文法をアメリカにばらまくのは、そんなデリバリーピザが普遍性を獲得した、かりそめの平和に甘んじてきたアメリカに、いままで国民が目を背けてきた現実を突きつけたかったのではないだろうか?
スポンサードリンク
おわりに:総評
映画版「虐殺器官」を称賛することはできない。ミリタリーアニメとしては間違いなく一流の仕上がりであったが、「虐殺器官」という作品として大切な本質を完全に見落としてしまっている。
伊藤計劃作品が3作品がこれですべて劇場公開されたわけだが、結局のところ称賛できる出来のものは一つもなかったように思う。原作の理解度が低いというよりも、単純にあのボリュームの小説を丁寧に描き切れるだけの尺が無かったのが最大の問題点であると思う。また、語りが主体でそのまま映像化してしまうとスペクタクルに書けてしまう点も映像化の最大の壁だったのではないでしょうか?
伊藤計劃の世界観を映像メディアに落とし込むのがいかに難しいのかを痛感させられた3部作だったと思う。
しかし、今作品で見せてくれた素晴らしいミリタリーアニメの技術を生かして、ジェノスタジオのスタッフさんたちには次の作品に取り組んでいただきたいと思う。決して今作のアプローチが間違っていたとは思わない。
当初の予定から1年と4か月。なんとか劇場公開まで漕ぎつけてくれたスタッフの方々に感謝を述べるとともに締めさせていただくこととする。
*ぜひ原作をお手に取ってみてください。この記事で解説したことはほんの一部にすぎません。全貌は自分の目で確かめてみてください。
また虐殺器官の世界感を継承した「The indifference engine」という短編が掲載された短編集もありますので、そちらも読んでみるとより理解が深まるかもしれません。

今回も読んでくださった方ありがとうございました。