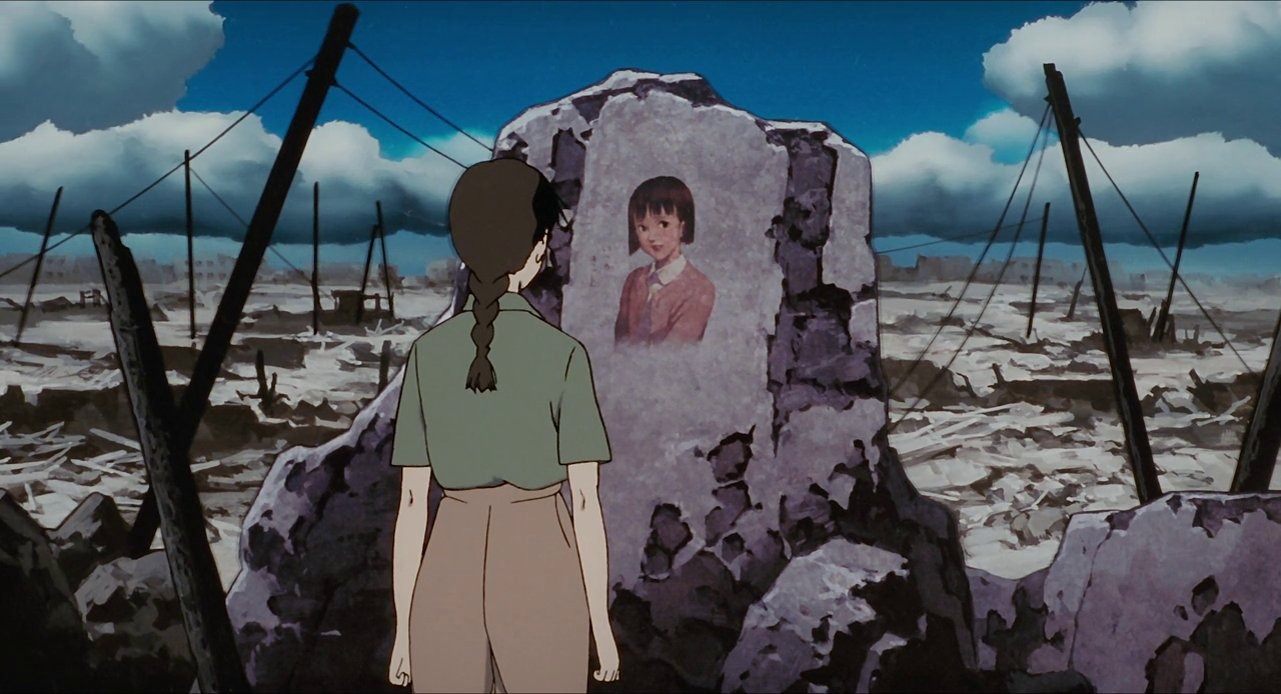目次
はじめに
みなさんこんにちは。ナガです。
今回はですね本日から公開の映画『バトルオブザセクシーズ』についてお話していこうと思います。
ネタバレを含む考察を書いていくことになるとは思いますが、その点はご了承いただけたらと思います。
作品を未鑑賞の方はお気をつけください。
良かったら最後までお付き合いください。
『バトルオブセクシーズ』
あらすじ・概要
「ラ・ラ・ランド」のエマ・ストーンが実在のテニスの女王を演じ、1970年代に全世界がその行方を見守った世紀のテニスマッチ「Battle of the Sexes(性差を超えた戦い)」を映画化。
73年、女子テニスの世界チャンピオンであるビリー・ジーン・キングは、女子の優勝賞金が男子の8分の1であるなど男女格差の激しいテニス界の現状に異議を唱え、仲間とともにテニス協会を脱退して「女子テニス協会」を立ち上げる。
そんな彼女に、元男子世界チャンピオンのボビー・リッグスが男性優位主義の代表として挑戦状を叩きつける。
ギャンブル癖のせいで妻から別れを告げられたボビーは、この試合に人生の一発逆転をかけていた。一度は挑戦を拒否したビリー・ジーンだったが、ある理由から試合に臨むことを決意する。
ビリー・ジーン役をエマ・ストーン、ボビー役を「フォックスキャッチャー」のスティーブ・カレルが演じた。監督は「リトル・ミス・サンシャイン」のジョナサン・デイトン&バレリー・ファリス。「スラムドッグ$ミリオネア」のダニー・ボイルが製作、サイモン・ビューフォイが脚本。
エマストーンは前回のアカデミー賞にて『ララランド』で主演女優賞を受賞しています。まさに今最も勢いのあるハリウッド女優の1人と言えるでしょう。
そしてスティーブカレルもまた実力派の俳優の1人で、やはり彼の作品の中でも有名なのが、自身が脚本と制作指揮をも担当した『40歳の童貞男』でしょうか。
また『フォックスキャッチャー』では、その圧倒的な存在感と演技力でアカデミー賞、ゴールデングローブ賞の2大タイトルで主演男優賞にノミネートしました。
映画『バイス』では、ドナルド・ラムズフェルドという実在の政治家を熱演していました。
監督を務めた、ジョナサン・デイトン&バレリー・ファリスはやはり『リトルミスサンシャイン』が圧倒的に有名でしょう。
その物語性やメッセージ性だけに留まらず、映画としても素晴らしい出来の1作なので、ぜひとも併せて鑑賞してほしい作品です。
またこのジョナサン・デイトン&バレリー・ファリスのコンビの映画の中では『ルビースパークス』という作品もおすすめなので、こちらも良かったらチェックしてみてください。
『バトルオブザセクシーズ』感想・考察(ネタバレあり)
性差ではなくこれは人と人との関わり方を描いた映画である
(C)2017 Twentieth Century Fox
タイトルからしても、ビリー・ジーン・キングという女性の権利を主張したテニスプレイヤーを題材に扱っていることからも、この映画が「フェニミズム映画」であるという視点で見られることはもはや避けがたいことでしょう。
しかし、私個人としてはそういう言葉で片づけられて欲しくないのがこの映画です。というのもこの映画を見ている人はお分かりかと思いますが、劇中でエマストーン演じるビリー・ジーンは自身はフェミニストではないときっぱり否定しているんですよ。
そしてこう付け加えています。自分はただのテニス選手で、そして女であると。
そうなんです。この映画は、もうこのセリフからも分かる通りでフェミニズムを全面に押し出した映画ではないんです。
大切なところはそこではなくて、もっとシンプルなことなんだと気がつきませんでしたか?
ビリージーンはただ「女性テニス選手」として、1人の人間として生きたいだけなんです。
しかし、そこには社会の柵があって、どうしても変えられない。では自分が自分らしく生きるにはどうしたら良いのでしょうか。
『バトルオブセクシーズ』という映画はそんな性差を超えたところにある、人間の「自分」を見つける物語として非常に完成されています。
そしてそれは女性だけが見つけるものではなくて、男性もまた見つけていくべきものです。だからこそ『バトルオブザセクシーズ』というタイトルの「セックス(性、性別)」という単語は複数形になっているわけです。

そう考えてみると『バトルオブザセクシーズ』というタイトルは男女がお互いに住みやすい世界を作るための「努力」という意味にも解釈できるわけです。
近年のフェミニズム活動はあまりにも行き過ぎた思想に傾倒し、本来の意味を見失っているのではないかとすら感じてしまうことがあります。それは「女性の権利が認められるためなら、男性が虐げられても仕方ない」というものです。
近年の一部の過激なフェミニズム思想にこういう類の考えが見え隠れしているのは悲しい事実ですよね。
そういう考え方に対してもエマストーン演じるビリー・ジーンは、女性が男性より上だと主張したいわけではなくて、あくまでも対等だと認めて欲しいだけなんだと述べています。
つまり、どちらかがどちらかを虐げ合う社会ではなくて、お互いに自分らしく生きられる社会を作ろうというのが、この映画のスタンスでもあると考えています。
だからこそ近年も大きな議論を巻き起こしている「性差」の問題は「戦い」ではなく、あくまでも「努力」であるべきなんです。さらに言うなれば、それは双方の「性」の努力によってしか成し遂げられないことです。
劇中で食い入るようにテレビを見つめるアメリカ国民たち。そして少し古臭いざらざらとした質感の『バトルオブザセクシーズ』という名の映像を映画館で見ている我々。時代を超えて、我々はまた同じものを見ているわけです。
あの頃と比べて我々は少しでも歩み出ることが出来たのでしょうか。映画は我々に問いかけます。
『バトルオブザセクシーズ』を読み解くための”2つの部屋”
さてここからはみなさんも一体どういう意味なんだろうか?と気になっていたであろうタイトルの「666号室」と「237号室」について解説していこうと思います。
「666号室」映画とテレビの戦い
666号室とは何ですかと聞かれると、それは1982年に公開されたヴィムヴェンダース監督が数々の映画監督にテレビメディアの台頭や映画は消えゆくメディアなのかということについて問うたドキュメンタリー映画です。
なぜこの映画を『バトルオブザセクシーズ』という作品の考察に取り上げるのかと言うと、映画(フィルム映画)に携わる人たちにとってテレビメディアの登場というのは、映画館のアイデンティティーを奪われることの連続であったわけですよ。
だからこそ70年代・80年代には映画とテレビはある種の対立するものだと考えられていました。とりわけ映画陣営はテレビの台頭を好ましく思っていません。それでいて映画の方が優位であるという思想に憑りつかれていたりします。
この『666号室』という映画を撮影しているヴェンダース自身もテレビメディアに対しての危機感と対決意識を強く持っていて、テレビから映画を守ろうとする姿勢を作品の中でも伺わせています。
例えば『女は女である』といった映画で知られるジャンリュックゴダール監督はこの『666号室』の中で、テレビと映画についてこう語っています。
テレビに対して不安を抱く必要はありません。何故ならテレビはあんなにも小さいし、人は画面に近づいていかなければならないからです。それに対して映画の映像は大きく、畏怖の念さえ抱かせるほどです。
そして観客はある程度の距離を置いて眺めます。しかし今日では、人々は、大きな映像を離れて見るよりも小さな画面を近くから見る方を好んでいるように思えます。
テレビは、主に米国で生み出されたせいもあって。非常に早く世に出回りました。しかしそれは、そもそもの資金源であるコマーシャルと共に生み出されたものです。そういうわけで、テレビというものは最初から広告の世界だったのです。
(映画『666号室』より引用)
このように彼はテレビなど恐るに足らない存在であると軽視していたような印象があります。
他にも『アギーレ神の怒り』などで知られるニュージャーマンシネマを代表する映画監督の1人ヴェルナーヘルツォークはこう述べています。
私たちはそれほどテレビに従属してしまってはいませんし、また、映画美学も完全な独自性を持っています。テレビは一種のジュークボックスのようなものに過ぎません。
つまり、テレビをつけても人は映画館の空間、その映画自体の空間の中にいるわけではなく、視聴者のポジションも不安定なものです。それに、スイッチを切って消してしまうこともできます。―それに対して映画は、スイッチを切ることはできません。
(映画『666号室』より引用)
こういった思想が語られた一方で、この映画を撮影したヴェンダース監督はテレビの力の強大さを感じていて、そんな画一的で均質な映像をあまねく届けられるテレビの台頭がドイツの地方映画館を衰退させていくことへの不安を『さすらい』という映画に込めたりもしています。
つまり映画を作る人たちにとって、テレビというメディアはある種の「敵」のような存在だったわけです。だからこそ映画の中でテレビの力を評価するなんてことは当然しないわけですよ。
ヴェンダース監督は『パリ、テキサス』の中でフィルム映像を家族の再生物語のキーアイテムに据えたりしていますからね。映画監督の主眼はあくまでも映画の力を如何に訴えるかにあったわけです。
しかし『バトルオブザセクシーズ』という作品は1970年代というまさにテレビ台頭の時期を切り取った映画でありながら、映画の力というよりもテレビの力を訴えかける作品になっているのがお分かりでしょうか。
テレビに映し出されたボビー (C)2017 Twentieth Century Fox
ビリージーンの試合を会場で見た人はわずか3万人。それでもその試合が大きなムーブメントになったのは、テレビというメディアがあったからに他ならないのです。これは映画にはどうしても成し得られなかった芸当でしょう。
ただ『バトルオブザセクシーズ』という映画を見ることで、我々はビリージーンが感じていた70年代アメリカの空気感と社会を追体験できるわけです。
これは他でもない映画本来の意義です。そしてそこにテレビの持つ力や魅力というものが込められています。
つまりこの作品は男女の「戦い」を主軸に据えつつも、映画とテレビの「戦い」をも映し出しているように思えるんです。
映画らしさとテレビの良さ。2つが合わさることでしか表現できない何かがある。そしてかつて対立を深めていた2つのメディアが1つの作品の中でそれぞれの良さを出し、融和しているという状態に、私は男女の関係性の理想を見たような気がします。
「237号室」鏡が隔てる空想と現実
映画が好きな方は「237号室」と聞いただけでパッとこのスタンリーキューブリック監督の『シャイニング』が頭を過ったことでしょう。ご名答です。
私はこの「シャイニング」という映画を鏡というモチーフに注目して読み解き、フィクションと現実世界を対比させながら描いている作品だと見ています。詳細はネタバレにもなりますので、以下のリンクから読んでください。
さて、その『シャイニング』という作品の中で印象的なのが先ほども述べました通りで「鏡」というモチーフなんです。鏡は多くの映画の中で登場するアイテムです。この使い方が上手いのは、ロシアの巨匠アンドレイタルコフスキーですとか、ドイツのライナーヴェルナーファスビンダーでしょうか。
『バトルオブザセクシーズ』の鏡の使い方に近いのは、個人的にはこの『シャイニング』だと思ったので取り上げてみました。この作品の中で鏡というモチーフは現実と空想を隔てる存在として君臨しているんです。
『シャイニング』の冒頭で、男の子が鏡を見つめているシーンがあるんですが、この時カメラはひたすら少年の実体ではなく、鏡に映し出された少年の像にフォーカスしていくんです。私はこの瞬間に『シャイニング』という映画は鏡の中の世界へとシフトし、鏡の中のフィクションを描いた作品へと変化したと考えました。
では『バトルオブセクシーズ』に話を戻してみましょう。この映画では至るところに印象的に鏡のシーンが取り入れられています。
まずは美容室でビリージーンとマリリンが初めて出会ったシーンです。このシーンで2人は施術される側とする側の関係性ですから、基本的にはお互いに鏡に正対している構図になります。
つまり実際のところ2人は同じ方向を向かい合っていないんですが、鏡に映るマリリンとビリージーンは向かい合っているんです。そして鏡に映るビリージーンとマリリンは向かい合っています。
鏡に映る2人が向かい合う (C)2017 Twentieth Century Fox
鏡の中に写る「もう1人の自分」という存在をシャイニング的に理想や空想であると解釈したならば、このワンシーンというのは、お互いがお互いにもっと自分のことを見て欲しい、知ってほしい、愛してほしいと思い始めながらも、それを受け入れきれない現実の自分という視覚的な演出が完成しているんですよ。
次に宿泊先のホテルで2人がすれ違ってしまう夜のシーンです。
この時マリリンとビリージーンは2人とも相手と一緒にいるビジョンが見えなくなってしまっているんですよね。特にビリージーンは夫がいるという制約やファンを裏切れないという社会的な体面のためにマリリンと一緒にいることが難しいわけです。
そのため鏡の中の世界と現実の世界、その両方に1人項垂れ、思い悩むマリリンとビリージーンが時間差で、しかもほとんど同じ構図で撮られているんです。
そしてボビーとの戦いに臨む直前にマリリンはビリージーンの美容師として帰ってきます。そして2人は再び美容師と選手の関係に戻るわけですが、このシーンではまだ2人は冒頭のヘアサロンの時のままです。
施術を終えて、ビリージーンが会場に向かおうとするときですよ。その一瞬の鏡の中の映像を見逃してはいけません。何と鏡の中でも、そして現実でもビリージーンとマリリンが向き合っているという映像が成立しているんですよ。何と言う映像の魔法・・・。
つまりこのシーンでようやく2人は自分を縛る様々な束縛から解き放たれて、自分が「生きたいと思う」生き方で生きることを決心できたわけですよ。
鏡の中の世界と現実の世界の一致という視覚的なマジックが描き出した2人の思いの結実にぜひ注目してほしいところです。
おわりに
いかがだったでしょうか。
今回は映画『バトルオブザセクシーズ』についてお話してきました。
かなり前評判も高い映画でしたし、『リトルミスサンシャイン』や『ルビースパークス』の監督の映画が面白くないわけがないだろうと、かなり期待して見にいきましたが、その期待に違わぬ傑作でした。
一見「フェミニズム」的な題材ではあるんですが、男性の方からの側面もしっかりと忘れずに描いている映画でして、だからこそ『バトルオブザセクシー”ズ”』なんだと考えさせられました。
自分たちが「自分らしく」生きるために必要なのは「バトル」です。しかし、それは「戦い」ではなくて「努力」です。お互いがお互いのために努力する。
当たり前のことですが、難しいことを改めて思い出させてくれる大切な映画だったと思います。
今回も読んでくださった方ありがとうございました。