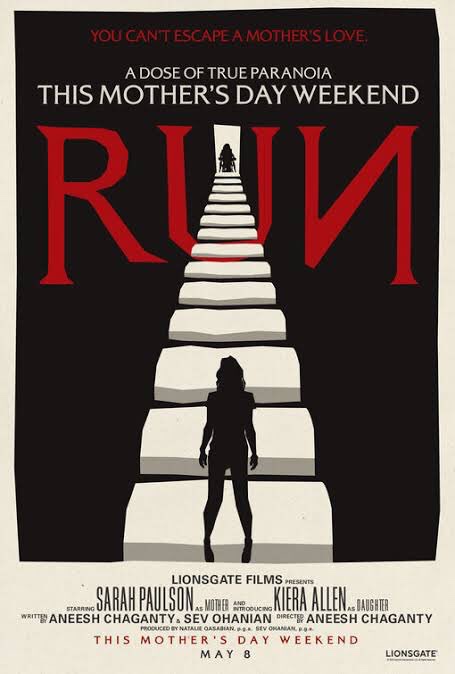(C)2018 NORDISK FILM PRODUCTION A/S
目次
はじめに
みなさんこんにちは。ナガと申します。
今回はですね映画『THE GUILTY ギルティ』についてお話していこうと思います。
本記事は作品のネタバレになるような内容を含む解説・考察記事となっております。
作品を未鑑賞の方はお気をつけください。
良かったら最後までお付き合いください。
映画『THE GUILTY ギルティ』
あらすじ
過去のとある事件がきっかけで、警察官として一線に立つことができなくなったアスガー。
彼は緊急通報指令室のオペレーターとして働いていて、パトカーや救急車を遠隔手配するなどの業務を担当していた。
電話越しに市民の小さないざこざや事故に対応する日々。
しかし、裁判では「正当防衛」であることを認められる裏付けが進んでおり、彼の無実が確定し、現場復帰になる日も近づいていた。
そんな裁判を翌日に控えた夜、誘拐されているという女性からの通報を受ける。
アスガーは電話の音声だけを頼りに、事件の真相を解き明かしていくことになるのだが・・・。
作品情報
本作『THE GUILTY ギルティ』は、実験的な映画が多く集まるサンダンス映画祭にて観客賞を受賞した作品です。
また北米の大手批評家レビューサイトのRotten Tomatoesでも批評家・オーディエンス双方から絶賛されています。
- 批評家支持率:99%
- オーディエンス支持率:89%

特に批評家支持率なんかは70%を超えることですら、かなり難しいと言われる中で99%というとんでもない支持を獲得しています。
監督を務めたのは、グスタフ・モーラーというスウェーデン出身の新進気鋭の映画監督です。
今作が長編デビュー作でありながら、いきなり世界中の注目を集めることとなりました。
ちなみに「電話だけのワンシチュエーション映画」という試みは別段革新的なものではありません。




当ブログ管理人はこの作品をその年のベスト5にも選出していたほどなので、それだけにどうしても比較してしまう部分はあります。
個人的に好きなのは、圧倒的に『オン・ザ・ハイウェイ』です。
ジャンルとしてもサスペンスではなく、描かれるのが主人公のただのプライベートな問題なんですが、それ故に「人間臭さ」が引き立てられ、ワンキャラクター映画として秀逸でした。
一方で完成度が高いのは圧倒的に本作『THE GUILTY ギルティ』だと思います。
1つの映画として演出や脚本のシャープネスが高くて、隙のない作りになっていました。
ぜひぜひ2つの作品を併せて鑑賞してみてください。
より詳しい作品情報を知りたい方は映画公式サイトへどうぞ!!




スポンサードリンク
映画『THE GUILTY ギルティ』解説・考察
映画と物語
映画とは常に他人の物語に「途中から」参加することである。
エンターテイメントは長らく、映画にしてもアニメにしても、あるいは小説にしても音楽にしても、基本的に「他人の物語」への感情移入だった。
文化史的には、おそらく活版印刷から映像の世紀に至るまでの時代の現象になると思うのだが、「他人の物語」を享受することによって個人の内面が醸成され、そこから生まれた共同幻想から社会というものが形成されていった時代があった。
(宇野常寛「母性のディストピア」より引用)
宇野氏も自身の著書の中でこれまでの映画や小説などのメディアを上記のように位置づけている。
我々が映画を見始める時、あるいは小説を読み始める時。それは登場人物たちの人生(物語)の始まりではない。
我々が映画や小説といったメディアを通じて観測し始める前に、既に彼らには物語が存在しているのであり、それ故に「途中から」参画することしかできないのだ。
さらに言えば、我々が観測できるのは、映画が終わるまでのほんの1時間から2時間程度の時間であり、その中で描かれていない登場人物の「以後の物語」を知ることもできない。
『THE GUILTY ギルティ』という作品は、そういったクラシカルな映画と物語の在り方を体現しており、肝心の主人公アスガーが「ギルティ」である理由は映画が始まる前に存在している。
つまり本作をアスガーの物語として捉えるならば、やはり我々は彼の人生に「途中から」参加する存在にすぎないのである。
一方で本作のミステリーとして捉えていくならば、アスガーと我々の「物語」はほとんど一致しているように思われる。
というのも本作で起きる事件は映画が開始してから起こるものであり、アスガーが知り得る情報は音声のみということで、映画を見ている鑑賞者と完全にフェアなのだ。
この時点で本作にはアスガーの物語、鑑賞者とアスガーが共有する物語という2つのレイヤーが存在していることに気がつかされる。
しかし、『THE GUILTY ギルティ』という映画はそれだけには留まらないのである。
なぜならここまでの2つのレイヤーを構築したいだけであれば、この作品が映画である必要は無くなる。
むしろラジオドラマか何かの媒体を活用した方が臨場感が高まることだろう。
ここで本作が映画という媒体でなくてはならなかった3つ目のレイヤーの存在を指摘していこう。
この映画を見ている間、我々はアスガーと同等の聴覚情報を手に入れているわけだが、その一方でアスガーには見えてないものを見ている。
それは何かというとその聴覚情報を取り入れている際のアスガーの表情である。
つまり『THE GUILTY ギルティ』という作品を見ている間、我々はメインプロットとなる事件の捜索という物語をアスガーと同質に共有しつつ、その一方で独立して、アスガーの「罪」を探る探偵活動を続けていることとなる。
故にこの映画には3つのレイヤーが存在していると指摘できるだろう。
- 我々には知り得ないアスガーの物語
- 我々とアスガーが共有する聴覚情報に基づくミステリ物語
- 我々がアスガーの表情と行動を見ながら彼の「罪」を推理していく物語
「他人の物語」への参加を主軸とする映画というメディアでありながら、見ている我々が「自分の物語」を構築できるというところに、本作の面白さがあると私は思う。
再程引用した宇野常寛氏の「母性のディストピア」から別の一節を引用しよう。
でも僕の考えは少し違っていて、やはり「自分の物語」を求めて遊んでいるうちに事故的に「他人の物語」に出会えるような仕掛けにしておくほうが面白いと思う。だからこうやって「他人の物語」の時代の遺産のうち、何が有効かを検証する仕事に人生を費やしているわけだ。
(宇野常寛氏「母性のディストピア」より引用)
映画『THE GUILTY ギルティ』の面白さは、まさしくここにあると感じる。
我々は旧来、映画を見ている間、「他人の物語」に途中参加し、その一部を見届ける。
そうして、そこで知り得た内容を自分の知見に変え、「自分の物語」へと還元していく。
これが1つの映画メディアの在り方であったように思う。
しかし、この『THE GUILTY ギルティ』という映画は、我々が「自分の物語」を主軸にして、その過程で「他人の物語」に出会うという面白さを体感することを可能にしているのだ。
我々が見ている視覚情報を元にして、アスガーの犯した「罪」を探っていく中で、隠されていた「アスガーの物語」に出会うこととなる。
本作が斬新であり、革新的なのは電話による音声情報だけで物語を展開するというシチュエーションを採用したからではない。
多層的な物語をシンプルな作品の中に構築し、映画を見ている人間を作品の中に取り込み、映画と観客のコンテクストを覆さんとしたところにあるのだと思う。
スポンサードリンク
本作のタイトル「ギルティ」の意味を探る
本作のタイトルは『THE GUILTY ギルティ』である。
タイトルの意味を単純に日本語で表現するとするなれば、「罪人」「加害者」という表現が当てはまるだろう。
確かにこの映画は、アスガーが事件の真相を探ろうとする中で、自身が犯した罪を告白するという流れになっている。
それ故に我々のフォーカスは当然彼が犯した「罪」の内容に当たることとなる。
しかし、この映画を紐解いていくに当たって、彼が犯した罪の内容はさして重要ではないと私は考えている。
では、何が大切なのか?というと、それはいつ彼が罪を背負い、罪人になったのか?という部分なのではないだろうか。
確かに本作の物語の開始以前にアスガーは「罪」を犯しているし、その事実は変わらないだろう。
しかし、それはあくまでも客観的に見た事実に過ぎないし、アスガーがその主観的な感覚で「罪」を感じているかとは全くの別問題である。
これを考えた時に当然浮上してくるのはドストエフスキーの『罪と罰』である。
ラスコーリニコフとスヴィドリガイロフという2人の主人公が印象的な作品だが、この作品における「罪と罰」の考え方は非常に興味深いものがあります。
確かにラスコーリニコフという人物は、最終的に自分の罪を受け入れ、ソーニャに歩み寄り、罰を受けながら生きていくという選択をすることとなる。
その一方でスヴィドリガイロフという人物は自分の罪を認めることなく、死んでいくこととなる。
これについて三田氏は自身の論評の中で以下のように記述している。
スヴィドリガイロフの自殺が、ドゥーニャの拒否によるものであることは明らかだが、そのことがスヴィドリガイロフの価値観を全否定したわけではない。
気に入っていた女の子に嫌われたという、ほとんど石につまずいたようなアクシデントによって彼は自殺したのであって、資産家の妻を殺したことや、示唆されているようにもっと以前の妻を殺したことについては、彼はまったく罪の意識を感じていない。
(三田誠広「『罪と罰』を読み解く/小説によるドストエフスキー論」より引用)
つまりドストエフスキーが『罪と罰』の中で描いたのは、客観的な罪と罰、そして主観的な罪と罰の間に存在する途方もない距離なのだと思う。
確かに現代社会においても、人は法を犯せば社会的に、客観的に「罪人」として扱われることになるだろう。
しかし、客観的に「罪人」になることと主観的に「罪人」になることは全く異質なものであることを理解しておく必要があるはずだ。
多くの映画は、人を殺害するシーンを物語の中で描き、人が客観的に、社会的に、法的に「罪人」になる瞬間を描く。
一方で『THE GUILTY ギルティ』という作品は、人が自らの罪を認め、主観的に「罪人」になることを選ぶ瞬間を切り取った映画なのである。
アスガーという人物は確かに「殺人」という「罪」をこの映画の開始以前の時間軸で犯している。
しかし、彼はそれを「正当防衛」であると装っており、それを自ら「罪」であると認めている様子は見受けられない。
つまりアスガーは客観的には罪人であるが、主観的には罪人ではないという状況が成立しているし、「正当防衛」が認められたならば彼は法的、社会的にも罪人ではなくなるのだ。
そんな時に彼が直面するのが、イーベンという女性に纏わる事件である。
イーベンは誘拐されたと語っていたが、実際にはそうではなく、自分の息子を殺害していた。
さらに精神疾患を患っており、自分は息子を殺したのではなく、救ったのだと信じている。
そう考えるとイーベンという女性は、まさにアスガーの写し鏡のようであると指摘することができる。
この2人は、互いに「罪」の意識を感じておらず、殺人という罪を犯しているにもかかわらず、自分が「罪人」だとは微塵も感じていないのだ。
そしてイーベンは終盤、気が動転し、自らその命を絶とうとする。
この姿がドストエフスキーの『罪と罰』において自殺したスヴィドリガイロフの姿に重なるのは偶然ではないだろう。
彼女は罪の意識を感じることなく、命を絶とうとしているのである。
またこの状況が、自ら罪の意識を感じることなく「正当防衛」により罪人ではなくなるアスガーの置かれている立場に重なることも指摘するまでもないだろう。
そんな中で2人が下す決断はラスコーリニコフ的であったと言える。
自らの罪を告白し、主観的に「罪人」であることを受け入れたのである。
映画『THE GUILTY ギルティ』において重要なのは、アスガーがどんな罪を犯したのかではない。
彼がいつ「罪人」になったのか?である。
その罪を背負う決断をした瞬間を描いたという点で、主観的な「罪人」の誕生を描いたという革新性があるとも言えるのではないだろうか。
それこそが本作のタイトルの本質と言えるのではないかと考えている。
スポンサードリンク
おわりに
いかがだったでしょうか?
今回は映画『THE GUILTY ギルティ』についてお話してきました。
全編が電話の音声のみで展開されるというワンシチュエーションスリラーであるという点に加え、そこに物語構造やドストエフスキーの『罪と罰』的な主題を持ち込み、秀逸な作品に仕上がっていました。
ぜひぜひ映画館で体験してほしい映画ですね。
今回も読んでくださった方ありがとうございました。
関連記事
・全編パソコン画面の映画?『search サーチ』