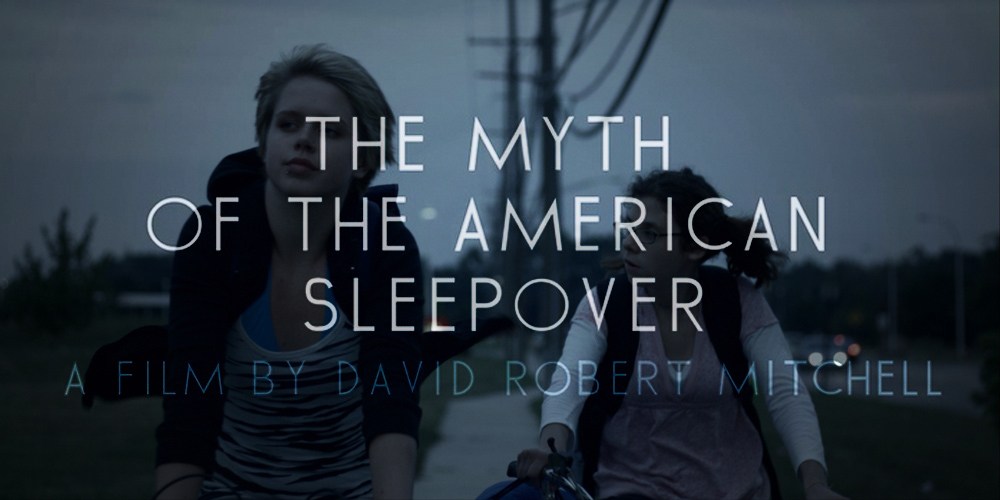Copyright (C) 2018 Paradox
目次
はじめに
みなさんこんにちは。ナガと申します。
今回はですね映画『ウトヤ島、7月22日』についてお話していこうと思います。
本記事は作品のネタバレになるような内容を含む感想・解説記事となっております。
作品を未鑑賞の方はお気をつけください。(とは言っても実話ベースの映画なので、ネタバレも何もないとは思いますが)
良かったら最後までお付き合いください。
『ウトヤ島、7月22日』
ノルウェー連続テロ事件
映画『ウトヤ島、7月22日』は2011年7月22日にノルウェーで起きた連続テロ事件を題材にして作られた映画となっております。
この連続テロ事件は首都のオスロで起きた車両爆破事件と、そしてそこから少し離れたウトヤ島で起きた銃乱射事件から成ります。
本作は冒頭で少し前者の事件を扱ってはいますが、基本的には後者のウトヤ島でのノルウェー労働党青年部の惨殺がメインに扱われています。
映画を見ていると、混乱した青年たちが「犯人は複数いる!」と言っていましたが、実際は単独犯で、犯人のアンネシュ・ブレイビクは短時間で最も人の命を奪った殺人犯ではないかと言われています。
この犯人はアルカイーダのようなテロ組織に属していたわけではなく、ノルウェー政府の移民受け入れ政策に強く反対していた極右思想、キリスト教原理主義的思想を持った男性でした。
彼は事件前の犯行声明で、かつてイスラム教徒の手から、聖地をキリスト教権益に取り戻すために活動した「テンプル騎士団」を自称していました。
イスラム過激派のテロが世界中で起こる中で、ブレイビクは反イスラム過激派でかつホームグロウンテロリストとして蛮行に及びました。
この事件による死亡者は77人とされていて、負傷者は100人を優に超え、心的外傷を負った人の数は数え切れないとも言われています。
そんなノルウェー史上最も残酷なテロ事件が今回映画化されました。
キャスト・スタッフ
- 監督:エリック・ポッベ
- 脚本:シブ・ラジェンドラム・エリアセン&アンナ・バッヘ=ビーク

監督を務めたのは、『ヒトラーに屈しなかった国王』や『おやすみなさいを言いたくて』などの作品でも知られているエリック・ポッベですね。
戦地で報道写真家として働く女性の姿を切り取った『おやすみなさいを言いたくて』、ナチスドイツに懸命に抵抗したノルウェーの国王ホーコン7世の姿を描いた『ヒトラーに屈しなかった国王』。
どちらも社会派リアリズム映画ですし、そんな彼だからこそ事件から約7年が経過したノルウェーの連続テロ事件を映画化に踏み切ったのも頷けます。
- アンドレア・バーンツェン:カヤ
- エリ・リアノン・ミュラー・オズボーン:エミリエ
- ジェニ・スベネビク:オーダ
- アレクサンデル・ホルメン:マグヌス









彼らのフィルモグラフィを見ても、ほとんど作品が掲載されていないことからも、経験の少ない若手俳優を集め、その可能性に賭けたという見方もできますね。
本作は72分ワンカットということで演じる側も非常に苦労したのではないかと思われますが、全員が迫真の演技を披露していて、その緊迫感がスクリーン越しにひしひしと伝わってきました。
より詳しい作品情報を知りたい方は映画公式サイトへどうぞ!!
スポンサードリンク
『ウトヤ島、7月22日』感想・解説
あまりの恐怖と緊張感でボミット寸前
当ブログ管理人、乗り物酔いとかってこれまでしたことがないですし、POV視点の映画を見ても気持ち悪くなるってことは基本的にはありませんでした。
ただ『ウトヤ島、7月22日』を見ていて、私は終盤20分はスクリーンを直視できないくらいに気分が悪くなって、お腹の底の方がもやもやとする感覚に襲われ、今にもボミットしてしまいそうでした。









確かにこの映画は、全編にわたって手持ちカメラで撮影されており、映像はブレブレで安定しませんし、かなりグルグルとアングルが変化するので、「酔いやすい映画」ではあると思います。
ただそれにしても『ブレアウィッチ』シリーズや『ハードコア』の様なPOV視点のグルグルアングル映画をこれまでたくさん映画館で見て、気分が悪くなったことってないんですよ。









いろいろと調べていると、どうやら不安や緊張感、強迫観念といった心理的な要因が「酔い」を加速させるという原因があることが判明しました。
つまり私は『ウトヤ島、7月22日』を見ている間、常に心理的に追い詰められており、そこに手持ちカメラのブレブレ映像という外的要因が重なったことでボミット寸前にまで至ってしまったということです。
結局のところ、何をお伝えしたいのかというと、それくらいに緊張感と恐怖が押し寄せてくる映画なのだということです。
もちろんこの映画よりも怖い映画も、グロテスクな映画も、緊迫感のある映画もこの世界にはたくさん存在しているとは思います。
しかし、『ウトヤ島、7月22日』という作品が私たちに与える「そこにいる」という感覚は、他のどんな映画よりもリアリティをもって我々に迫り、精神的に追い詰めてきます。
2017年公開の映画にクリストファー・ノーラン監督の『ダンケルク』というものがありました。
ダンケルクにて、祖国からの救援を待つ孤立した兵士たちのリアルをこれでもかという映像と音響で表現した映画です。









『ダンケルク』を見ていた時に、自分も戦場にいるかのような感覚を強く感じさせられ、だからこそ映画の終盤に兵士たちが帰国できた時の安堵を我々も観客として共有することができました。
ただ、どうしても兵士や戦場に馴染みがないものですから、没入感は感じれど、自分がそこにいるというイメージってなかなか湧いてこないんですね。
それ故に『ウトヤ島、7月22日』という作品は恐ろしくて、普通に生きていた少年少女が突然の銃声と共に「非日常」へと突き落とされる様を描いたことで、観客が「そこにいる」というイメージを持ててしまうんです。
確かにこの映画にはカヤという主人公が存在してはいますが、それ以上に我々観客は『ウトヤ島、7月22日』を自分の映画として知覚しています。
どこからともなく聞こえてくる銃声。
地面に転がる死体。
さっきまで生きていた人間が冷たくなっていく感触。
自分が何もできないことへの無力感。
助けが来ないことへの絶望。
これらの感覚を作中の人物と共有できてしまうことで、自分もどんどんと追い詰められていき、そして気分が悪くなっていく・・・。
映画とは言ってしまえば、たかが映像です。
それでも映画には、観客の心理にダイレクトに訴えかける力があります。それを『ウトヤ島、7月22日』という作品はまさに体現しています。
72分間ノーカットという特異な演出が、私たちに緊張から解放されることを許してくれず、ひたすらにあの日あの島で起きたことを追体験させてきます。
吐き気をもたらすほどのリアリティにこそ、この映画の存在意義はあるのだと言えるでしょう。
ドキュメンタリーではなくフィクションとして
この映画がドキュメンタリー映画ではなく、フィクションであることは映画本編でも、そして監督の言葉の中でも繰り返し触れられています。
これはドキュメンタリーではない。しかし架空の物語にするために、ウトヤ島で起こったことを基にして作られている。それは非常に大変な作業で、関係者全員が熟練の技を最大限に生かすことが必要だった。そして、必要以上に感傷的になることなく、物語を伝えたいと思った。映画に登場する若者たちの感傷的な気持ちはいいのだが、映画自体が感傷的にならないように気をつけた。
(『ウトヤ島、7月22日』公式サイトより引用)
つまりこの作品に登場している人物は、あくまでも架空の人物であって、劇中で成されていた会話なんかも全て創作されているということです。
事件に直面した若者から事実を聴き、それを作品に取り入れながらも脚色を施し、ドキュメンタリーに徹さないように配慮しています。
「実際の事件と同じ72分間がノーカットで進行」「銃声は実際の事件と同じ540発」といった事実に即した要素は作品のリアリティを高めています。
その一方で監督は、本作をドキュメンタリーにしない意義としてこう語っています。
実話に基づく映画の場合、目撃者の証言によって物語を構成するのは自然なことだが、その内容を現実に思い出してしまう人がいることを忘れてはならない。亡くなった方や事件の影響に今でも立ち向かっている人たちに対する敬意をこめて、私は脚色ができないドキュメンタリーではなく、架空の物語にすることで、この事件をより鮮明に描けると考えた。
(『ウトヤ島、7月22日』公式サイトより引用)









ドキュメンタリーとは、現実をそのまま映し出す行為であり、もし本作がそれを追い求めるのであれば、生存者の証言や実際の映像を繋いでいく構成になるでしょう。
ただ、事件が起きた2011年からまだ10年も経過していない残酷なテロ事件であり、その心的外傷に苦しみ、今もその傷と向き合って生きている人がノルウェーにいるんだということを考えると、そのアプローチは難しいですよね。
だからこそあくまでもフィクションであるというスタンスで、このテロ事件に直面した人たちに敬意を払い、この映画は製作されています。
私は、日本で東日本大震災を題材にした映画を作ることも同じことだとは思いますが、フィクションが社会に対して貢献できることの1つとして「風化させないこと」という役割があると思っています。
どんなに残酷で、凄惨な事件が起きたとしても時の流れとは残酷なもので、時間と共に人々はその記憶を徐々に風化させていきます。
映画が人々が目を背けたくなるような凄惨な出来事に立ち向かうのは、そんな時と共に風化していく人の記憶を色褪せさせない意義を全うするためなのです。
それ故に、事件からもうすぐ10年が経過しようとしている今、この出来事を忘れさせないために、そしてテロに立ち向かった行くという毅然とした姿勢を示すために、ノルウェーはこの映画を製作したのでしょう。
スポンサードリンク
テロに立ち向かう映画として
カヤとマグヌス Copyright (C) 2018 Paradox
この映画を今を生きる私たちが見ておく意義は非常に大きいと思います。
監督のエリック・ポッベは次のように述べています。
外国人への嫌悪、潜在的な恐怖や絶望が世界を取り巻くこの時代において、この映画は現実味を帯びた作品だと思う。事件の内容だけでなく、映画の中の若者たちが見せる思いや行動は、今こそ我々が思い出すべき人間の善良な面ではないだろうか。今だからこそ人間らしさは不可欠であり、大切なのだ。
(『ウトヤ島、7月22日』公式サイトより引用)
この映画の冒頭で、主人公のカヤたちが、オスロで起きた爆破事件の犯人について考察を巡らせていましたよね。
この時に、「犯人はまだわからないよ」とか「ガス管の破裂だろう」といった意見の他にマグヌスが「アルカイーダの仕業だろう」という旨を仄めかしていました。
何気ないワンシーンかもしれませんが、このセリフは『ウトヤ島、7月22日』という作品の本質を突いているとも言えます。
日本では、やはり居住しているイスラム教徒の数がヨーロッパ諸国よりも1桁小さいということで、まだまだ顕在化していませんが、ヨーロッパやアメリカなどで移民・難民としてやって来たイスラム教徒の問題は深刻です。
やはりテロリストとイスラム教徒が結び付けられて考えられてしまうことが多く、移民・難民のイスラム教徒というだけで不安や恐怖と対象とされ、地域コミュニティから排除されてしまうケースは珍しくありません。
ドイツで右派のAfDが勢力を伸ばしていることやアメリカでドナルド・トランプが大統領に当選したこと、イギリスでEU離脱の決断が下されたのも、そういった人々の潜在的不安や恐怖が1つの原因です。
『ウトヤ島、7月22日』において犯人のアンネシュ・ブレイビクはほとんど姿を見せることなく、ただただ銃声と悲鳴が若者たちを追い詰めていくような映像に仕上げていたのも実にメタ的だったと言えます。
私たちは結局、見えない何かに帯びえ、仮想敵を創り出し、異質な他人を排除することで、結果的に現実に敵を生み出してしまっているんです。
善良なイスラム教徒たちがヨーロッパで地域コミュニティから排除され、その疎外感がテロリズムの過激思想へと傾倒させる要因になっていることも事実です。
つまり「見えない敵」を疑い、恐れ、排除することで、私たちは敵を創り出しているという何とも皮肉な事態が今の世界では起こっているのです。
クリント・イーストウッド監督は『15時17分、パリ行き』という自身の作品で、極めてマッチョなテロリズムとの立ち向かい方を表現しました。









でも、あれって確かに事実ではありますし、そういう若者がいたことは讃えられるべきなんですが、テロリズムに対して英雄的に立ち振る舞うのは、やっぱり難しいんですよ。
それを『ウトヤ島、7月22日』という作品は嫌という程に教えてくれますよね。テロリストに対して我々はもはやどうすることもできないし、ただただ逃げ惑うことしかできません。
では、我々はどうすれば良いのか。その答えを監督は、1つの形として描こうとしたのではないでしょうか。
人種も生まれも異なる、話したこともない人と手を取り、助け合う。極限の状態でも他者のことを想うこと。
見えない恐怖と不安ゆえに、他者を排除するのではなく、受け入れ、共に生きようとする姿勢こそテロリストに立ち向かうための有効な手段なのかもしれません。
彼が『ウトヤ島、7月22日』という作品を今作ったのは、決してテロに対する恐怖を煽るためではありません。
実在のテロ事件を題材にし、そこに脚色を加えて創り出された物語には、今を生きる我々への指針が確かに示されています。
作品の終盤でカヤが口ずさんでいたシンディ・ローパーの『True Colors』。
私たちには自分の色があります。そして他人には他人の色があります。
自分と異なる色を排除し、自分の色を保とうとするのではなく、他人を受け入れ、共生することで美しい世界が実現されるという監督の思いがこの歌にも込められていたのかもしれません。
おわりに
いかがでしたか?
今回は映画『ウトヤ島、7月22日』という作品についてお話してきました。









これは冗談抜きなので、注意してください。ただそれをネガティブにネガティブに解釈するのではなく、それだけ作品の臨場感と緊迫感がすごいという風に考えていただけると幸いです。
テロ事件がたびたび話題になり、移民や難民の問題が世界中で取り沙汰され、日本にもその波が迫ろうとしている中で、この映画を見ておくことは重要な意義があるはずです。
すごく見ていてしんどい映画なんですが、それでも勇気をもって映画館に足を運んでみて欲しいですね。
今回も読んでくださった方ありがとうございました。